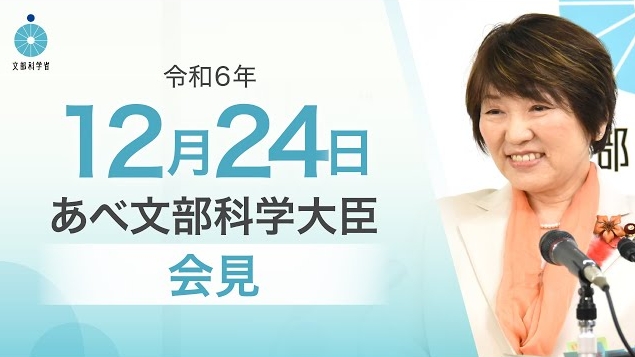- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和6年12月24日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和6年12月24日)
令和6年12月24日(火曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
福島原子力発電所の廃炉現場の視察等について、大臣の年末年始の海外出張(中国・米国)、「D-EST」構築の最終まとめと今後の取組、学習指導要領の改訂に向けた子供への意見聴取について、国際卓越研究大学に係る東北大学の体制強化計画の認可と第2期公募開始、「宇宙基本計画工程表」の改訂、教職員の精神疾患による休職者数の増加への対応について、教員の働き方改革と処遇改善に関する公明党文部科学部会の緊急提言
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和6年12月24日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和6年12月24日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から6件もございまして申し訳ありません。まず、先週末の21日土曜日、福島県内の原子力関連施設を視察をさせていただきました。廃炉創造ロボコンに出席をいたしましたので、御報告をいたします。東電の福島第一原発及び日本原子力研究開発機構におきまして、廃炉の進捗状況を確認させていただきまして、廃炉研究の重要性を再認識をさせていただいたところでございます。また、廃炉創造ロボコンを観戦いたしまして、福島高専の学生とも意見交換をしました。小学生の頃から廃炉に興味を持ち、将来は廃炉に関わりたいという学生さんがいらっしゃいまして、小さい頃からその志の高さに私は大変感動いたしました。困難な課題に立ち向かう高専生の姿、大変素晴らしく、今後廃炉を支える人材になっていただけることをまさに期待をさせていただきます。今回の訪問を踏まえまして、引き続き、東電の福島第一原発の廃炉現場を支える取組への支援を進めまして、福島の復興にしっかりと取り組んでまいります。
2件目でございます。明日12月25日水曜日から26日木曜日まで、「第2回日中ハイレベル人的・文化交流対話」に、議長となる岩屋外務大臣と御一緒に出席するため、中華人民共和国を訪問させていただきます。本対話におきましては、両国間におけます青少年の交流、また教育・文化・スポーツ交流、コンテンツ交流などについて議論する予定でございます。そして、1月2日から8日まで、米国国立科学財団長官や米国航空宇宙局NASA長官と会談などを行うために、アメリカ合衆国を訪問いたします。本出張では他にも、現地の日本人研究者、また美術館関係者、またアフリカ開発会議TICADも見据えたアフリカ連携に関する関係者との意見交換なども予定をさせていただいています。
3件目でございます。まもなく能登半島地震発生から1年が経過いたしますが、文部科学省といたしましては、被災地での学びを支援する派遣等枠組みの「D-EST」、この構築に向けまして検討してきたところでございまして、本日、その最終まとめを取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。災害が頻発化・激甚化する中、災害時に子供たちの学びを確保するためには、平時からの備えを強化していくことがますます重要でございまして、そこで、「D-EST」では、被災地で速やかに子供たちの学びを確保するために、文部科学省職員の派遣によるニーズの把握、これに基づく支援、全国の学校支援チームの派遣、また被災地のニーズに応じた応援の教職員、スクールカウンセラーの派遣調整などに取り組むことにしているところでございます。このために、文部科学省だけではなく、教育委員会相互の協力も重要となってまいりますので、引き続き、関係の皆様と連携・協力しながら、「D-EST」の実質化を図ってまいります。
4件目でございます。明日、中央教育審議会総会におきまして、今後の学習指導要領の在り方について諮問を行う予定でございます。諮問後の審議にあたりましては、こども基本法の趣旨も踏まえまして、これから社会を担う子供たちの思いや願いを生かしていくことがまさに重要でございます。そこで、1月下旬から、子供たちの意見を直接聞く取組を実施することにいたしまして、明日、参加者の募集を開始させていただきます。この取組は、子供や若者から意見を聞いて政策に反映する仕組みである「こども若者いけんぷらす」を活用させていただきながら、こども家庭庁と連携して、協力をして開催します。多くの子供たちから積極的な意見を出していただき、受け止めていきたいというふうに考えているところでございます。
冒頭の5件目でございます。国際卓越研究大学に関わる東北大学の体制強化の計画の認可と第2期公募の開始について、お知らせをいたします。本日、12月24日、国際卓越研究大学である東北大学の体制強化計画を認可いたしました。今後、東北大学におかれましては、若手研究者が独立した環境で自由な発想による多様な研究活動を行うための研究体制の確立など、体制強化計画に盛り込まれた内容の着実な実行を通じまして、我が国全体の研究力をけん引していただくことを期待をしております。また、大学ファンドの支援対象となります国際卓越研究大学の第2期の公募に関しましては、本日、12月24日から開始いたしますので、各大学から意欲的な提案がなされることを期待しているところでございます。
6件目、最後になりますが、本日24日でございますが、宇宙開発戦略本部におきまして、「宇宙基本計画工程表」が改訂されたところでございます。会合の中におきましては、私から、JAXAを中核機関といたしまして、基幹ロケットの開発・高度化及び衛星・探査機の開発・運用を進めていくこと、日本人宇宙飛行士2名の月面着陸の実現等に向けまして、有人の与圧ローバ開発等を本格化していくこと、また、宇宙戦略基金によりまして、民間企業・大学等の更なる宇宙分野への関与やいわゆる裾野拡大を推進していくことなどについて申し上げまして、石破総理からも各府省が連携して取り組みを進めていくよう指示がございました。文部科学省といたしましては、宇宙分野における人材育成・確保も含め、関係府省と連携をしていきながら、この工程表の内容を着実に進めてまいります。私からは以上でございます。
記者)
精神疾患で休職した教職員が3年連続で増えて過去最多となりました。文科省で様々な対策を講じているのは承知しておりますが、なかなか効果が見られません。有識者からは、現行の学習指導要領の時数が多すぎるのではないかというような指摘をする声もございます。それも含め、新たな対策を講じるお考えがあるか御意見をお伺いできればと思います。
大臣)
御指摘のように、令和5年度調査の結果におきまして、教育職員の精神疾患による病気休職者数が、前回調査に引き続きまして、過去最多となりました。文部科学省といたしましては、今回の結果も踏まえ、新たに、令和6年度補正予算を活用させていただきまして、医療の専門家と連携した公立学校教員のメンタルヘルス対策、この強化等に取り組んでいくとともに、中教審の答申を踏まえた働き方改革、この一層の推進や教職員定数の改善など、教師を取り巻く環境整備の一層の充実に取り組んでまいります。また、現行の標準授業の時数がただちに病気休職の要因になるとは考えてもいないところでもございますが、いずれにいたしましても、標準の授業時数を大幅に上回って教育課程を編成している場合には、私ども指導体制に見合った計画とするように求めているところでございまして、今後とも更なる改善を促してまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
昨日、公明党文科科学部会のほうから大臣に宛てて教員の働き方改革と処遇改善に関する緊急提言を受け取られたかと思います。提言で新たな手当について創設するということが盛り込まれていましたが、文部科学省として今後どのように御対応なさるか、計画をお聞かせください。
大臣)
現在、来年度予算につきまして、予算編成に向けた財政当局との最終調整を鋭意行っている段階でございまして、文部科学省といたしましては、学校が対応する課題、複雑化・困難化をしていく中、教師という職責の重要性を踏まえた給与になるように、また本給相当である教職調整額の引上げに加えまして、まずは学校担任の手当の加算、また若手教師のサポートを行う新たな教師の職の設置と新たな級の創設など、真に頑張っている先生方に報いる職務、また勤務の状況に応じた処遇改善となるように努めてまいりたいというふうに思っております。また、昨日いただいた提言も踏まえまして、職務や勤務の状況に応じた処遇改善など、教師の処遇の在り方について、引き続き、しっかりと検討してまいります。以上です。
記者)
卓越大の関連でお伺いをさせていただきます。2回目の公募では公募期間が長く設定されているですとか、あるいは現地視察をなるべく多くの大学で行うといったりするようなことがあると思うのですが、その狙いというのはどこにあるのか、それを教えていただければと思います。
大臣)
おっしゃるように、第2期の公募に関しては、初回の審査を行った有識者会議の意見が様々出た、それを踏まえつつ、大学からの御意見を丁寧に伺いながら、例えば、検討する期間を十分に確保する観点から、先ほどおっしゃってくださったように、公募期間を長く設定、今回5カ月弱になります、また、大学との対話の機会を多く設けるという観点から、なるべく多くの大学を現地視察する対象とすること、また大学の負担を軽減する観点から、一部の書類などの提出を不要とすることについて変更させていただいています。このような取組を通じまして、世界最高水準の研究大学の実現にふさわしい提案を選定していきたいというふうに考えているところであります。以上です。
記者)
同じく卓越大の関連で伺います。既に2回目の公募に意欲を示している大学もありますが、今後申請する大学に向けての期待をお願いします。
大臣)
国際卓越研究大学を目指すものは、世界のトップクラス、この研究者が集まり相互に触発し活躍することでございまして、次世代の一流の研究者集団を育成し若手研究者に独立して存分に研究できる環境を提供することでございます。これを通じまして世界最高水準の研究大学となること、これを私どもが目指しておりまして、これに加えまして、第2期の公募に申請する大学におかれましては、各大学が世界最高水準の研究大学を実現するという強い意思に基づき、明確なビジョン、これを持った意欲的な提案をしていただくことを期待しているところでございます。以上です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室