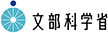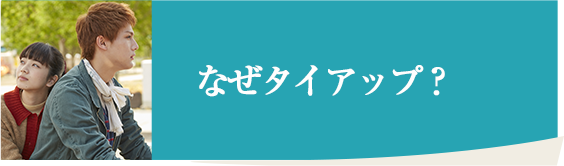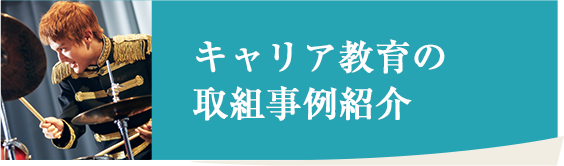監督インタビュー

監督
三木孝浩
知らないけど飛び込んでみようとか、わくわくしたいなって思うことを大事にしてほしいって思います。
中学時代から将来の夢を発表するときに、卒業文集とかに映画監督になりたいとは書いていました。当時も映画が好きだったので、ある種かっこつけではありますけど、映画監督って言えば「おお」って思われるみたいな。本当になりたかったかどうかは定かじゃないです。
作るのが楽しいなって思い始めたのは、高校時代ですね。映画同好会に入っていて、家庭用のビデオカメラで、ミュージックビデオの真似事をやってたんですよ。いろいろな友達のちょっとした何気ないお芝居を撮って音楽にのせてみたら、何かかっこいいなって思って、それを見て友達が喜んでくれるのが本当にうれしかったんですよね。映像を作って人を喜ばせて笑顔にするとか、人に楽しんでもらうとか、これは自分にとって本当にやりがいのあるものになるなって、漠然と映像を仕事にしたいなと思っていましたね。
それで、大学を選択するときに、映像の仕事をするなら東京でと思って、映像のサークルがたくさんある大学を選んで、段々と自分の将来の仕事として何をするのか考えて、3年生のときに1回休学して専門学校に通ったんです。
僕にとってラッキーだったのは、専門学校でミュージックビデオ制作実習があったんですが、ソニー・ミュージックで映像制作をされていた方が講師としてミュージックビデオの面白さを教えてくれたことですね。
映画監督になりたいという思いはあったんですけども、映画監督じゃなくても映像の仕事をしたいなと思ったときに、音楽でこんなに楽しくて面白い映像が作れるんだって教えてもらえたのが専門学校のときです。
それもあって、就職活動するときには、レコード会社の採用試験を受けました。
こういうふうに生きたいとか、こうなりたいと思ったものをそのままストレートに実現できる人の方が少ないと思うんですよね。
でも、自分の知らないところでいっぱい道筋があって。例えば律ちゃんも、薫に「先生似合うと思うよ」って言われて初めて、先生っていう職業に気付いたりとか。薫にしたって、ある種家庭環境でそうならざるを得ないと思っていたものが、見方を変えれば自分にとってすごくやりがいのある仕事だと気付く瞬間がどこかにあっただろうし。
外的要素で自分の目指す道が決められたとしても、そこでやりがいを感じるかどうかは本人次第だったりいろいろなケースがあると思うし、自分には向いてないよって思うことが実はすごく自分の才能を開花させる場所だった、ていうこともあるじゃないですか。自分の意識だけに凝り固まらずに広げていくっていうのはすごく人生が豊かになる気もしますし、素敵だなって思いますね。
僕自身もたぶん専門学校に行ってなかったらミュージックビデオに意識がいってなかったと思うし。映画やりたいな、監督になる方法ないかなってずっと思っていたけど、こんなにも面白い世界があるんだと、ふとしたタイミングで教えられたことで、たぶんそのままストレートに映画監督目指すより、今の作品にその経験が活かされている部分ってものすごく大きいと思っています。
そうなんですよ、だからそこはやっぱり自分にとってすごく大切な時間だったなって思いますね。
率直な友人、本当は音楽がなかったらつながらなかった3人が、10年後にいろんな道で再会する。目指している一つの道だなと共感をさせていただきました。
半分半分ですね。リサーチはきちんとした上で、物語が豊かになる感覚も大事にしたいなって思っているので。
職業ものとかはまずリサーチして現場の人の話をお伺いします。「こんなことはないよ」って突っ込まれるところもあると思うんですけどそれがなるべくないように、というのは意識していますね。
映画業界の人じゃない人たちともコミュニケーションをとるようにはしています。一般のお客さんが観たときにどういうふうに感じるかっていうフレッシュな感覚を失わないためにですね。
努力というよりは、そういうのが楽しいなと。
大事なのは聞く力だと思っていて。例えば自分の意見と全く違うとか、キャラクター的にはあんまり好きじゃない人の話す言葉を拾えるかどうか。嫌いだからとか、自分には関係ない世界だからっていうふうにシャッターを下ろすともったいないなあって思うんですよね。全然関係ない人が言った何気ない一言が人生を決めたり、ヒントになる瞬間がたくさんあるので。
特にこういう映画作品を作るときに、一人の想像力では限界があって。いろいろな人の言葉や意見が新鮮に感じることっていっぱいあるんですね。
例えば自分とは全然真逆の見方をする人が、どういうところを面白いと思うのだろうと聞いてみると、意外なところを面白がってくれたり、自分はすごくいいと思ってこだわっていたところがあんまり伝わってなかったり発見が多いんです。そういうことを気付かせてくれる人の考えをちゃんと拾えるかどうかがすごく大事だなと思っています。
僕も、今回は特にアナログな手触り、時代感が気に入ってます。
今回の設定は1966年ですが、もしかしたら現代の設定で撮っても、熱量を同じように表現するのは難しいのかなって思ったりします。
情報も何もなかったり、電話もすぐできなかったり、ということが逆に相手のことを自分の中で想像したり相手を思いやる時間になったり、不都合とか不便が多いからこそ、あの熱量があの時代にはあったのかなって思います。
僕が作る映画って若いお客さんが見る作品が多いんですけど、未来にわくわくしてほしいなって思うんですよね。映画の中でも知らない世界に飛び込んだり、知らなかったジャズ音楽に触れるとかを、知らないからシャットアウトするんじゃなくて、知らないけど飛び込んでみようとか、わくわくしたいなって思うことを大事にしてほしいって思います。
今回は特に、作ってる自分がわくわくできたっていうのが大きいですし、それをお客さんにも感じてもらえたらすごくいい作品になるんじゃないかな、って思いましたね。
なかなかやりたいことが見つからない、自分には何ができるんだろうって迷ったとき、そこで立ち止まるんじゃなくて、寄り道してでも絶対最後にはたどり着けるポイントっていうのがきっとあるんですよね。
それでいうと僕自身もそうですけど、寄り道したことで新たな発見があって、今の自分に生かされていたりすることもあるので、映画の中で薫が千太郎に飛び込んでこいよ、って言われて飛び込んだみたいに、間違ってるかもしれないって思ってても、飛び込んでみる勇気っていうのを是非持ってもらいたいですね。
「ムリムリ」って思ってても、入ってみると意外と楽しいって思うことって本当にたくさんあるので。
それで、もしそこから違う道へ行ったとしても、絶対その時間って人生にとって糧になると思うので、是非知らない場所へわくわくしながら飛び込んでほしいなと思います。
是非全国の子供たち、中高生に見ていただきたいと思っています。
本日は本当にありがとうございました。
(聞き手 初等中等教育局 坪田児童生徒課長)