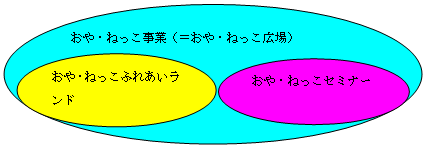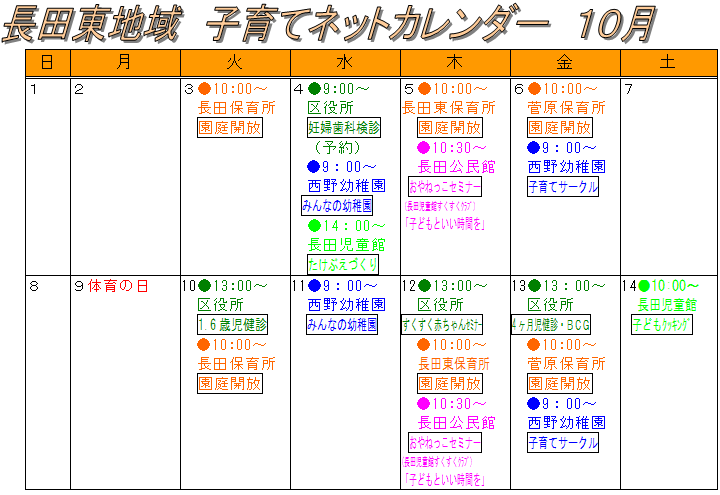- 現在位置
- トップ > 教育 > 社会教育 > 家庭教育支援のための連携事例集 > おや・ねっこ事業を通じた子育て支援団体との連携(神戸市)
おや・ねっこ事業を通じた子育て支援団体との連携(神戸市)
おや・ねっこ事業を通じた子育て支援団体との連携
| 1 | 自治体・団体名: | 神戸市,長田公民館 |
| 2 | 自治体・団体の概要 海,山,まち,田園‥神戸の街にはさまざまな顔がある。六甲山の緑と船が行き交う港。エキゾチックな異人館街や旧居留地。そして1,000万ドルの夜景。 多様な都市環境を有するこの街は,歴史的には国際港湾都市として発展してきた。温暖な瀬戸内海に面する神戸の街は,古くは奈良時代に「大和田泊」と呼ばれた港が中国など諸外国との貿易拠点として栄えた。江戸時代に入り鎖国によって外国貿易は途絶えたが,1868年(慶応3年)の兵庫開港により再び活気を取り戻した。 戦後の高度成長期には造船,鉄鋼,機械などの基幹産業が集積する都市として発展したが,現在ではファッション,ケミカルシューズ,洋菓子などでも有名である。 昨年2月には空港が開港し人・物・情報が行き交う観光交流都市を目指している。 1995年(平成7年)に発生した阪神淡路大震災は,わが国で初めての都市直下型大地震であり,本市だけでも約4,600名の尊い人命が失われるなど未曾有の被害をもたらした。 特に長田区では大規模な火災が相次ぎ,既成市街地の中でも被害は甚大であった。震災により神戸市の人口は約10万人減少したが,さまざまな震災復興事業に取り組むことによって次第に回復し,平成18年12月現在の人口は約153万人,世帯数は約65万,面積は約552平方キロメートルである。 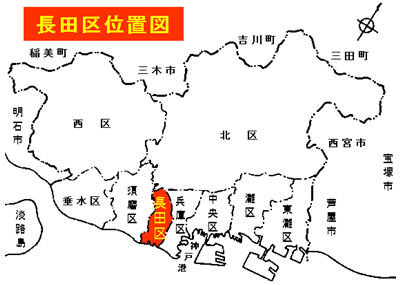 |
||||||||||||
| 3 | 地域の特徴 長田区は市の中央部よりやや西に位置し,北の高取山,南の長田港に挟まれた南北に細長い形をした区域で,平成18年12月現在,人口約103千人,面積約11.5平方キロメートルである。長田区では,戦後にゴム工業やマッチ,金属機械工業などが盛んになったが,とくにケミカルシューズ産業など労働集約型産業が発達しており,神戸でも下町的な雰囲気が残る地域である。 現在,市内には7つの公民館があるが,長田公民館のある地域は「番町地区」と呼ばれている。この地区は長田区内でも東部に位置し,周囲は高層の市営住宅等が林立する住宅地であるが,都市計画道路の山手幹線に面しており,市営地下鉄西神山手線「長田駅」から徒歩で5分という交通至便のところにある。 また,公民館には長田児童館が併設しており,近くには長田・長田東・菅原の3保育所がある。さらにこの地区は室内・御蔵・水木の3小学校の校区と,丸山・長田・兵庫の3中学校の校区にもまたがっている。 したがって,公民館を中心に半径約500メートル以内に児童館や幼稚園,3保育所,3小学校があるため,行政機関や児童支援 施設・団体が非常に集まりやすいという利点がある。 一方で,長田区内の65歳以上の人が人口に占める割合(高齢化率)は市全体の約20パーセントに比べて,約25パーセントと非常に高く,館の利用者も高齢者が多い。児童数の減少とあわせて,少子高齢化へ対応が急務である。 公民館は本来,公的な教育施設として社会教育や生涯学習の「場」と「機会」を提供するという役割があるが,全市的に子育て支援に取り組む中で,今日では他の行政機関や学校園,団体との中継(ハブ)機能を果たす事が求められている。  |
||||||||||||
| 4 | 連携の取組状況
|
||||||||||||
| 5 | 今後の方向性や展望 今日では核家族化や少子高齢化の急速な進展などにより,次第に家庭や地域の養育力が弱まりつつあるように思われる。 しかし子育てや子どもの健全育成の主体はあくまでも家庭やそれを取り巻く地域であり,保育所や学校,行政はそれを補完し,側面的に支援するものである。 子育て支援に関わる団体や行政は,たえず成長過程にある子どもたちを中・長期的な視点でとらえ,相互に情報交換や連携をしながら支援を行うことが重要である。 また高齢者といえどもまだまだ元気なお年寄りも多いので,このような人の生きがいづくりと子育て支援への活用も必要である。 したがって,今後の公民館は子育て支援という分野において,自ら事業を行うだけでなく,事業所や団体,ボランティアとのコーディネート,情報提供,事業所間の中継機能などの役割を果たすべきと考える。 |
||||||||||||
| 6 | 担当者連絡先 神戸市立長田公民館 館長 吉山 幸男 〒653-0004 兵庫県神戸市長田区四番町4丁目51
|
| 前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --