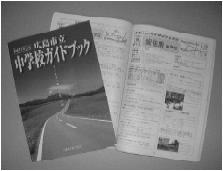| 1 |
本制度の概要 |
| |
本市が、「就学区域の弾力的運用(新入学児童生徒及び他市町村からの転入生について、保護者が市教育委員会に申し出ることにより、就学区域にとらわれることなく、瑞穂市立7小学校及び3中学校から就学する学校を自由に選択することができる)」制度を導入したねらいは、次のとおりである。 |
| |
| ○ |
保護者の住所地により就学すべき学校が指定される仕組から、保護者(児童生徒)が行かせたい(行きたい)学校が選択できる仕組にすることによって、保護者(児童生徒)の選択幅を拡大し、より公平性・平等性に応える。 |
| ○ |
この制度が「特色ある(魅力ある)学校づくり」「開かれた学校づくり」を推進することになり、総じて瑞穂市の教育の活性化につながる。 |
| ○ |
学校選択制を通して、児童生徒が自己を確立しながら多様な価値を認め合い、目標に向かってゆとりの中で「生きる力」を身に付け、その子にあった自主的な生き方・個性を伸長する魅力ある教育風土を醸成していく。 |
|
|
| |
制度導入後の各小中学校では、児童生徒及び保護者の選択に応じる学校をつくるため、子どもたちの実態や地域の特質を十分に理解したうえで、子どもたちの実態に応じ、地域のよさを生かして、一人一人の子どもに「確かな学力」と「豊かな心」を育てるべく特色ある(魅力ある)教育活動を展開している。(本市では「魅力ある学校づくり」と称している。)
市教育委員会としても、児童生徒及び保護者に制度の主旨を理解していただき、また、各学校の特色ある(魅力ある)教育活動に共感・理解した上で学校を選択してもらいたいと考えており、そのための情報提供を次の方法で行っている。
|
| 2 |
情報提供(広報)の方法や内容 |
| |
| (1) |
市広報誌への掲載 |
| |
市教育委員会は、市広報「広報みずほ10月号」で新1年生の入学準備から入学式までの流れを特集するなど、市民に広く本制度を紹介している。(広報誌は瑞穂市HPにも掲載)
|
| (2) |
就学時健康診断の際に小学校新1年生の保護者へ説明 |
| |
市教育委員会は、各小学校長へ10月から11月にかけて実施している就学時健康診断の際に、制度についての具体的な説明を保護者にするよう依頼している。受診日に各小学校長は、市教育委員会作成の資料を配付のうえ保護者に説明をしている。
|
| (3) |
中学校新1年生の保護者に資料を配付 |
| |
市教育委員会は、制度についての詳細な資料を作成し、10月に各小学校を通じて現小学校6年生の保護者に配付している。
|
| (4) |
自由参観日の設定 |
| |
保護者が実際の教育活動を参観することができるよう全市一斉に各学校で自由参観日を設定している。
|
| (5) |
その他 |
| |
市外からの転入生については、転入の際、市教育委員会から保護者に説明をしている。
|
| |
以上の情報提供の方法で特筆されることは、次の2点である。 |
| |
 |
冊子『まちの学校』の刊行 |
| |
市教育委員会は、毎年冊子『まちの学校』を刊行し新入学児童生徒の保護者へ配付をしている。内容は、市教育の方針と重点、就学区域の弾力的運用の説明並びに各学校の魅力づくりの取組の具体的内容(学校規模、教育目標、指導方法、教育活動等)で、各内容A4判2ページずつで紹介している。 |
 |
学校自由参観日の設定 |
| |
児童生徒の姿や学校の様子及び特色ある(魅力ある)教育活動を実際に保護者が参観できるよう参観日を12月上旬に1週間程度設けて実施している。 |
|
| |
市教育委員会は、このような方法で学校選択のための情報提供を行っており、保護者には制度及び各学校の特色(魅力)についてを概ね理解していただいているものと考えている。 |
|
| 3 |
実績と傾向 |
| |
| 年度 |
児童生徒総数 |
新入学児童生徒数(A) |
就学区域の弾力的運用利用者数(B) |
利用率(B A) A) |
| (注1)12年度 |
(小学校)2,134人
(中学校)1,026人 |
(小学校)356人
(中学校)354人 |
(小学校)3人
(中学校)1人 |
(小学校)0.8パーセント
(中学校)0.3パーセント |
| (注1)13年度 |
(小学校)2,155人
(中学校)1,035人 |
(小学校)382人
(中学校)347人 |
(小学校)5人
(中学校)1人 |
(小学校)1.3パーセント
(中学校)0.3パーセント |
| (注1)14年度 |
(小学校)2,151人
(中学校)1,035人 |
(小学校)336人
(中学校)333人 |
(小学校)2人
(中学校)0人 |
(小学校)0.6パーセント
(中学校)0.0パーセント |
| (注1)15年度 |
(小学校)2,188人
(中学校)1,019人 |
(小学校)385人
(中学校)332人 |
(小学校)3人
(中学校)4人 |
(小学校)0.8パーセント
(中学校)1.2パーセント |
| (注2)16年度 |
(小学校)3,059人
(中学校)1,447人 |
(小学校)547人
(中学校)493人 |
(小学校)27人うち新入学12人
(中学校)11人うち新入学4人 |
(小学校)0.9パーセントうち新入学2.2パーセント
(中学校)0.8パーセントうち新入学0.8パーセント |
| 17年度 |
(小学校)3,141人
(中学校)1,454人 |
(小学校)573人
(中学校)492人 |
(小学校)12人
(中学校)5人 |
(小学校)2.1パーセント
(中学校)1.0パーセント |
|
| |
| (注1) |
穂積町が平成12年度に制度を導入した。平成12年度から15年度までは、穂積町(小学校4校、中学校2校)の実績。平成15年5月1日に穂積町と巣南町(小学校3校、中学校1校)が合併して瑞穂市となった。平成16年度以降は、瑞穂市一円で実施している。 |
| (注2) |
平成16年度に限っては、合併のメリットを生かすための特例として、新入学児童生徒及び他市町村からの転入生だけでなく、市内全小中学校全学年の児童生徒も対象として実施したため利用者数が多くなっている。
|
|
| 4 |
評価等 |
| |
上の表から、制度利用者数はやや増加傾向であることが分かる。しかし、児童生徒の全体数からすれば利用者数は少なく、ほとんどの児童生徒は保護者の住所地によって指定された学校に通学している。制度導入以前は、学校間に児童生徒数の大きな偏りが生じることも心配されたが、導入して6年が経過した時点でそれほど大きな動きは見られない。保護者に対し、広く学校選択のための情報提供を行っている中で利用者が少ないのは、通学の利便性や地域社会における交友関係といった理由もあるが、特色ある(魅力ある)学校づくりの努力の結果、住所地の学校への教育に対する信頼が大きいことの現れであると市教育委員会ではとらえている。
また、各学校も自校を選んだ保護者の期待に応えるべく、子どもをよりよく成長させなければという意識を持ち、特色ある(魅力ある)教育活動の充実に努めている。
市教育委員会では、制度利用者数が増加することよりもむしろこうした各学校の意識の高まりこそが大きな成果であるととらえ、今後も市の教育がより活力のあるものとなるよう「就学区域の弾力的運用」を推進するとともに、保護者だけでなく広く市民にも情報を提供していきたいと考えている。 |