| ア |
状況の確認 |
| |
都道府県福祉相談所より、裁判所の保護命令及び、居住地情報の写しをいただき、これを状況確認のための資料とした。
|
| イ |
申請書の提出 |
| |
教育委員会窓口にて、母親に今回の事情を確認し、就学希望の申請書を記入していただいた。その際、福祉相談所担当相談員に同行を依頼し、現在の状況を母親・相談員の両方の立場から聞き取り確認を行った。
|
| ウ |
受入れ学校への状況報告 |
| |
同時に、受入れ先小学校へ状況報告を行い、児童相談所担当者が同行の上、学校と保護者との面談の場を設けるよう学校へ依頼した。 |
| |
| ※ |
学校側には、現状を十分に理解できるよう、保護者・相談員、学校側との面談を必ず依頼している。また、学校側に就学拒否権がないため、あえて所見等の提出は求めていない。 |
|
| エ |
住民票登録地との協議 |
| |
本来、区域外就学は、住民票登録地への協議をもって就学許可を行なわなければならない。転出先学校や教育委員会の心情を考えても、また、子供の教育指導上重要な指導要録等のやり取りを行うためにも、協議は必要である。
しかし、今回の事例では、保護者・相談員との状況確認の折、転出先の地域性や、周囲の人間関係上、情報漏洩の可能性が非常に高い状況にあった。別の案件ではあるが、他市にて区域外就学中に居住地情報が加害者に漏洩し、居場所を突き止められたがため当市町村へ逃亡してきたといった事例も実際生じている。
よって、この相談についてはDV被害者救済のため、相手先教育委員会に、学校に対する情報の制限を行った上で協議を行うこととした。 |
| |
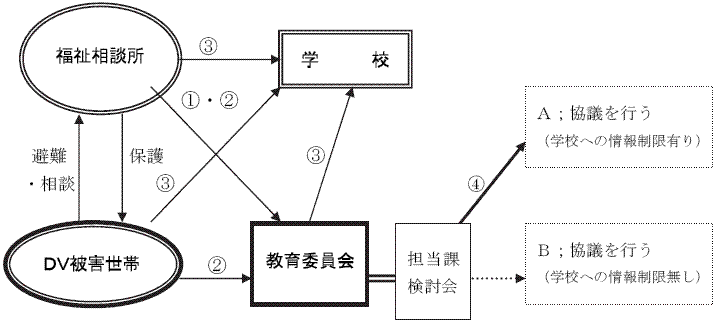
|
| ※ |
丸数字は手続きの順番を示す。 |
| |
| A; |
協議を行う… |
協議を行うが、転出学校へは転出のみを知らせるよう依頼。指導要録等児童の情報は、教育委員会間でやり取りを行なう。 |
| B; |
協議を行う… |
通常通りの協議、情報のやり取りを行う。 |
|