- 現在位置
- トップ > 政策関連情報 > 政策評価 > 文部科学省の政策評価制度について > 重要対象分野に関する評価書—若年者雇用対策— > 3.各事業の評価
3.各事業の評価
(b)高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究
1.事業の概要
(1)高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究
近年,若者が職業について考えたり進路を選択・決定したりすることを先送りする傾向,いわゆるモラトリアム傾向や進路意識や目的意識が希薄なまま進学する者の増加が指摘されている。特に,この傾向は,高等学校の普通科において強いともいわれている。
また,若者自立・挑戦戦略会議をはじめ,各種会議・提言等において,総合人材育成施策としてのキャリア教育の推進が重要である等と盛り込まれているところである。
このような状況を踏まえ,平成19年度から,高等学校,特に普通科高校におけるキャリア教育を充実するため,![]() 高等学校段階におけるキャリア教育の充実,
高等学校段階におけるキャリア教育の充実,![]() キャリア教育に専門的知識を有する人材の活用方法,
キャリア教育に専門的知識を有する人材の活用方法,![]() 高等学校卒業者及び中退者への支援方策,などを調査研究課題とした調査研究を実施している。
高等学校卒業者及び中退者への支援方策,などを調査研究課題とした調査研究を実施している。
具体的には,![]() 小・中学校や大学等と連携・協力や,就業体験(インターンシップ)の効果の検証,
小・中学校や大学等と連携・協力や,就業体験(インターンシップ)の効果の検証,![]() 産業や雇用等の状況を理解し,就職・進学等を選択・決定させる能力を身に付けさせるため,その活動を補助する人材の養成・配置方法の検討,
産業や雇用等の状況を理解し,就職・進学等を選択・決定させる能力を身に付けさせるため,その活動を補助する人材の養成・配置方法の検討,![]() 関係行政機関や地域若者サポートステーション等との連携により,中退者や卒業者の進路,就職等の動向把握及びその要因を分析し,必要に応じ,キャリア教育の改善・充実に活かすための方法などについて全国119の高等学校で調査研究を行っている。(平成19年度予算額208百万円,平成19年度事業対象生徒数66,266人)
関係行政機関や地域若者サポートステーション等との連携により,中退者や卒業者の進路,就職等の動向把握及びその要因を分析し,必要に応じ,キャリア教育の改善・充実に活かすための方法などについて全国119の高等学校で調査研究を行っている。(平成19年度予算額208百万円,平成19年度事業対象生徒数66,266人)
2.必要性,有効性,効率性
(1)必要性
近年の産業・経済の構造的変化や,雇用の多様化・流動化等を背景として,就職・進学を問わず児童生徒の進路をめぐる環境は大きく変化している。学校から職業への移行のプロセスが複雑化し,多くの若者にとって,その移行が極めて困難な状況になっている。
また,職業の選択や決定を先送りし,進路意識や目的意識が希薄なまま「とりあえず」進学したり,せっかく就職しても長続きせず,早期に離職したり,安易にフリーターを選択したりする若者が,結果として,ニートやフリーターなどの増加の要因になっているのではないかと懸念されている。今後,少子高齢化社会を迎え,「日本の将来推計人口」によれば生産年齢人口(15歳〜64歳まで)は2050年には2004年よりも約3千万人減少による,社会全体の活力の低下が予想される中,ニート62万人,フリーター181万人(2007年現在)は,減少傾向にあるものの,今後,これ以上増大させないための予防策としても,キャリア教育を実施する必要がある。
(参考)
- ニート,フリーターの問題については,P.14を参照。
このような背景にあって,キャリア教育は学校教育において,高等学校,特に普通科におけるキャリア教育の取組については十分であるとはいえない状況である。
そのため,高等学校段階でどのように生徒に勤労観・職業観を身に付けさせ,進学・就職を問わず進路を選択・決定できるように指導できるのかなど,キャリア教育の在り方について調査研究を行うことは,効果的な学習方法や指導につながるものであり,その必要性は高いと考える。
こうしたことから,高等学校,とりわけ高等学校の7割を占める普通科におけるキャリア教育の在り方について調査研究を行うこととしたところである。具体的には,普通科におけるキャリア教育を推進するため,![]() 外部人材の配置・活用の在り方に関する検討,
外部人材の配置・活用の在り方に関する検討,![]() 高等学校卒業者及び中退者への支援の在り方等について検討を行うことなどにより,キャリア教育の一層の推進を図る。
高等学校卒業者及び中退者への支援の在り方等について検討を行うことなどにより,キャリア教育の一層の推進を図る。
(2)有効性
高等学校におけるキャリア教育の実施については,卒業年次の指導に力を入れる,いわゆる出口指導に偏りがちな進路指導の状態を改善させることが必要不可欠であるが,本事業が効果をあげることにより,各高等学校において,進路指導が中核ではあるが,発達段階に応じたより幅広い意味でのキャリア教育の向上に寄与すると考えられる。このことから本事業の施策目標の達成に対する貢献度は高く,本事業を実施することが有効と考えられる。
また,高等学校におけるキャリア教育の推進に関する調査研究協力者会議において指摘されているとおり,将来の進路選択の幅を広げる観点から,就業体験(インターンシップ)などの多種多様な体験機会を与えることによって,勤労観や職業観,さらには進路を主体的に選択する能力を育成することが可能となる。
(3)効率性
本事業は,進学者の多い高等学校,就職者の多い高等学校,双方が混在する高等学校で調査研究を行っており,このような条件,環境の異なる高等学校での調査研究の成果と課題を整理し,情報提供することで,高等学校におけるキャリア教育を充実するための方策を提示することになり,高等学校におけるキャリア教育を一層推進するための手段として適切であると考える。
3.施策の効果及び貢献度(ロジック・モデルとの関係)
(1)高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究
表2−1.高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究の指定学校数
| 調査研究期間(予定) | 都道府県数 | 指定学校数 |
|---|---|---|
| 平成19、20、21年度 | 37(地域) | 119(校) |
(2)就業体験(インターンシップ)の実施状況等(国立教育政策研究所生徒指導研究センター調)
図2−1.公立高等学校(全日制)の学科別インターンシップ実施率
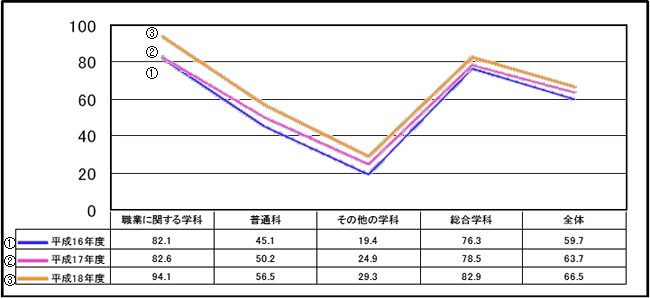
- その他の学科:理数科,英語科,工芸科,体育科など
図2−2.公立高等学校(全日制)の学科別インターンシップ体験生徒数
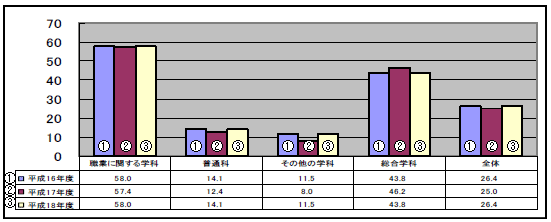
(3)事業評価を実施するに当たってのアンケート調査結果等
本事業の実施校を対象に,平成20年6月に,学校,教師,生徒,保護者,卒業生の区分でアンケート調査を実施した。
[内訳:学校119,教師240,生徒480,保護者480,卒業生240]
(未実施校を対象とした調査項目については,比較・検証を行った)
○学校アンケート(回答数:110)
〈調査結果1〉学校が考える成果(図2−3)
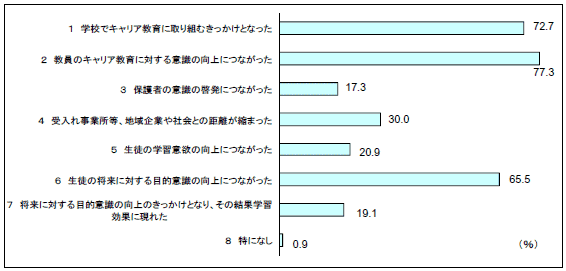
本事業の指定を受けることにより,「1 学校でキャリア教育に取り組むきっかけになる」とともに,「2 教員のキャリア教育に対する意識の向上」,「6 生徒の将来に対する目的意識の向上」等の効果につながっていることが伺える。今後,引き続き,本事業における調査研究を通じて,有効性,効率性の向上を目指す必要がある。
○教師アンケート(回答数:234)
〈調査結果2〉教師が考える成果(図2−4)
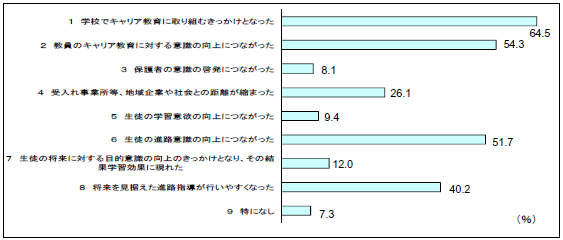
〈調査結果1〉の学校に対するアンケート結果と傾向が類似しているが,効果が認められる一方,「生徒の学習意欲の向上」や「将来に対する目的意識の向上」等については,成果として認められない状況にあることが伺える。この観点について,本事業を実施し引き続き調査研究を行い,教師は,生徒の学習意欲向上に努める必要がある。
○生徒アンケート(回答数:471)
〈調査結果3〉将来の職業選択において,重視すること(図2−5)
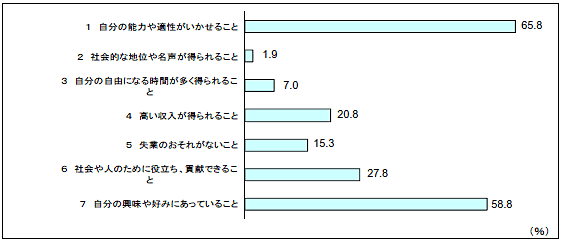
将来の職業選択に関しては,自由やお金ではなく,「自分の能力や適性をいかせること」,「興味や好みにあっていること」に重点が置かれていることが伺える。こうした指導を重視するためにも,本事業は重要な役割を担っており,今後,より一層,学校・教師が生徒の個性の伸張や興味・関心を理解したキャリア教育の充実に努める必要がある。
〈調査結果4〉将来の生き方や進路について考えるため,ホームルーム活動の時間などで,どのようなことを指導してほしかったか。(図2−6)
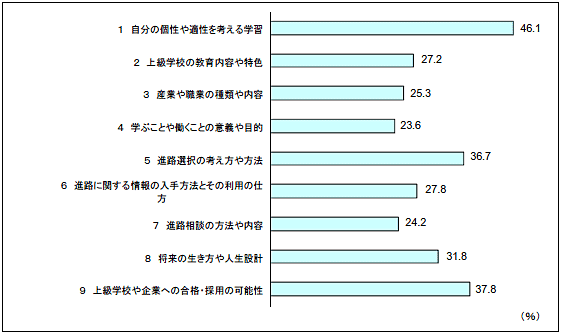
調査結果から,「1 自分の個性や適性を考える学習」や,「5 進路選択の考え方や方法」について,生徒は指導を望んでいることが伺える。他方,進路・就職についての具体的な問題として,「9 上級学校や企業への合格・採用の可能性」についての要望も高い。
○生徒アンケート(回答数:実施校(普通科のみ)427,未実施校(同)325)
〈調査結果5〉ホームルーム活動の時間における,将来の生き方や進路に関する学習の状況について調査した結果
〈調査結果5—1〉産業や職業の種類や内容
(表2−2−1)
(図2−7−1)実施校(普通科のみ)427
| よく学習した | ある程度学習した | あまり学習しなかった | 学習しなかった | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 42 | 208 | 159 | 16 | 2 |
| 割合 | 9.8 | 48.7 | 37.2 | 3.7 | 0.5 |
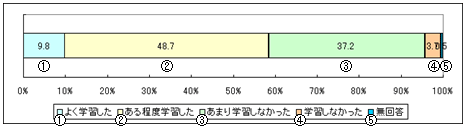
(表2−2−2)
(図2−7−2)未実施校(普通科のみ)325
| よく学習した | ある程度学習した | あまり学習しなかった | 学習しなかった | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 15 | 178 | 120 | 10 | 2 |
| 割合 | 4.6 | 54.8 | 36.9 | 3.1 | 0.6 |
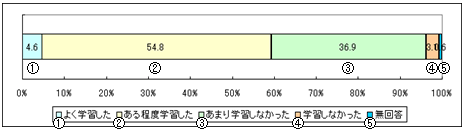
〈調査結果5—2〉学ぶことや働くことの意義
(表2−3−1)
(図2−8−1)実施校(普通科のみ)427
| よく学習した | ある程度学習した | あまり学習しなかった | 学習しなかった | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 104 | 229 | 84 | 9 | 1 |
| 割合 | 24.4 | 53.6 | 19.7 | 2.1 | 0.2 |
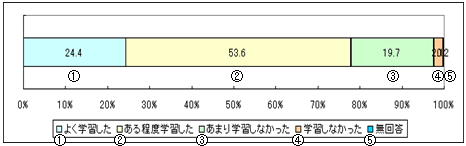
(表2−3−2)
(図2−8−2)未実施校(普通科のみ)325
| よく学習した | ある程度学習した | あまり学習しなかった | 学習しなかった | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 67 | 172 | 76 | 6 | 4 |
| 割合 | 20.6 | 52.9 | 23.4 | 1.8 | 1.2 |
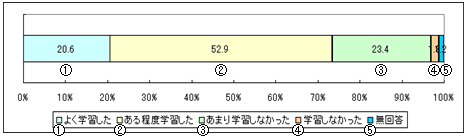
〈調査結果5—3〉希望する進路の実現可能性
(表2−4−1)
(図2−9−1)実施校(普通科のみ)427
| よく学習した | ある程度学習した | あまり学習しなかった | 学習しなかった | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 62 | 241 | 108 | 13 | 3 |
| 割合 | 14.5 | 56.4 | 25.3 | 3.0 | 0.7 |
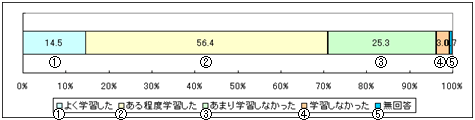
(表2−4−2)
(図2−9−2)未実施校(普通科のみ)325
| よく学習した | ある程度学習した | あまり学習しなかった | 学習しなかった | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 49 | 183 | 84 | 8 | 1 |
| 割合 | 15.1 | 56.3 | 25.8 | 2.5 | 0.3 |
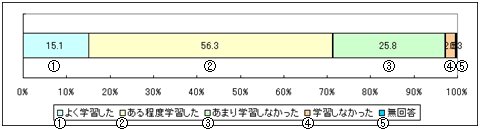
〈調査結果5−1〉「産業や職業の種類や内容」,〈調査結果5−2〉「学ぶことや働くことの意義」に関しては,未実施校に比べて実施校が「よく学習した」という割合が高かった。一方,〈調査結果5−3〉「希望する進路の実現可能性」など卒業直後の進路選択に関わる指導に関しては差が見られず,卒業後の進路保証に係る指導が従来通りなされていることが推測される。
これらのことから,本事業指定1年目でありながらも,本事業を通じて,キャリアに関してより長期的な視野に立った指導実践が充実し,かつ,それらが生徒によっても認識されるレベルに至っていることが伺い知ることができる。
○生徒アンケート(回答数:実施校(普通科のみ)427,未実施校(同)325)
〈調査結果6〉将来の生き方や進路にかかわる体験活動として,これまでの活動について
(表2−5−1)
(図2−10−1)実施校(普通科のみ)427
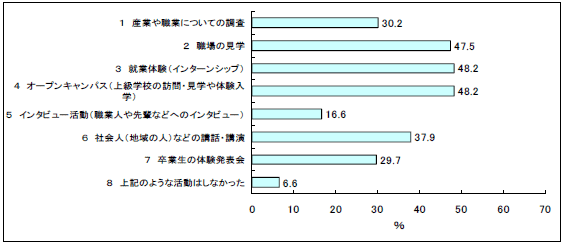
(表2−5−2)
(図2−10−2)未実施校(普通科のみ)325
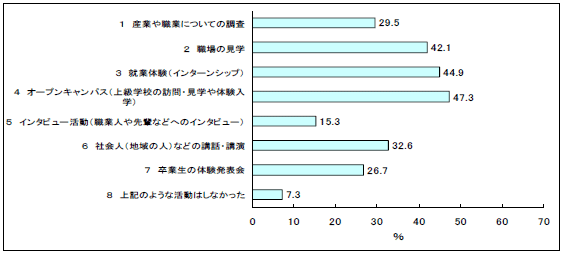
「1 産業や職業についての調査」から「7 卒業生の体験発表会」までにおいて,実施校の生徒の割合が,未実施校の生徒のそれに比べて,上回っている。
このことから,本事業を実施することにより,キャリア教育に関する体験的な活動も,本事業指定後1年目ではあるが活性化していることが伺い知ることができる。
○教師アンケート(回答数:234)
〈調査結果7〉教師が抱える課題(図2−11)
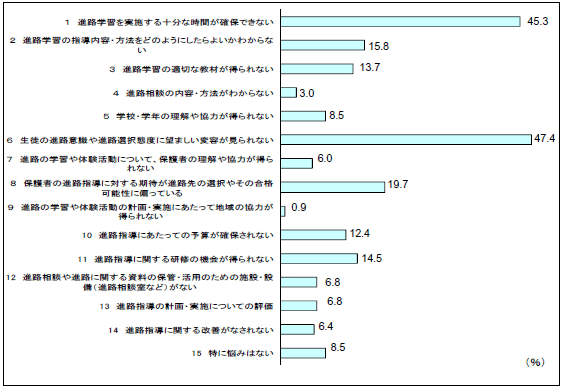
「1 進路学習を実施する十分な時間の確保」(45.3パーセント)や,「6 生徒の進路意識や進路選択態度に望ましい変容が見られない」(47.4パーセント)との課題が大きな数字を示している。また,15.8パーセントの教師が「2 進路学習の指導内容・方法をどのようにしたらよいかわからない」と回答している。このことから,教師の資質・能力の向上のための研修の充実を図るとともに,本事業を通じて,これらの課題を克服しキャリア教育の改善・充実につなげる必要がある。
○保護者アンケート(回答数:464)
〈調査結果8〉学校の進路指導に期待すること(図2−12)
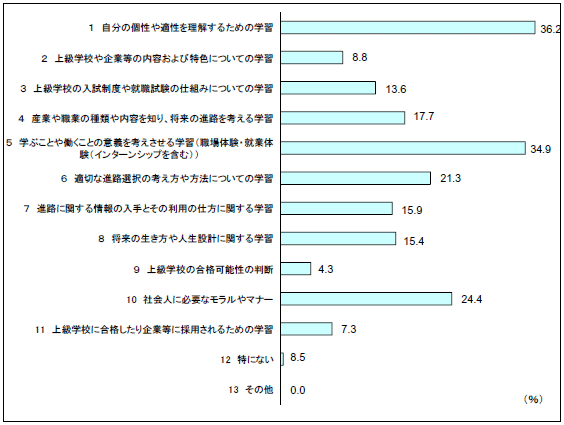
「1 自分の個性や適性を理解するための学習」(36.2パーセント),「5 学ぶことや働くことの意義を考えさせる学習(職場体験・就業体験(インターンシップを含む))」(34.9パーセント)について期待すると回答した保護者が多い結果となった。
また,「10 社会人に必要なモラルやマナー」についても24.4パーセントの保護者が期待すると回答している。
このことから,キャリア教育が目指す方向性は,保護者のニーズや期待に十分応えうるものであることがわかる。
○卒業生アンケート(回答数:232)
〈調査結果9〉高校在籍時に指導して欲しかったこと(図2−13)
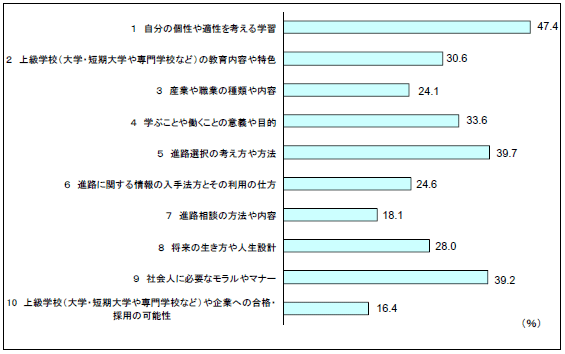
卒業生も在籍生同様,「1 自分の個性や適性を考える学習」と,「5 進路の考え方や方法」についての指導を望んでいたが,本事業実施校では既に,その効果的な指導内容・方法について調査研究に取り組んでいる。このことからも,必要性に基づいた調査研究であり,今後は,その成果と課題を整理・改善し,生徒の進路指導の充実に資することとしている。
4.成果事例
【事例:奈良県立平城高等学校】(平成19年度報告書より)
- (研究課題)
- 生徒に将来の目標をもたせるためのキャリアカウンセラーの活用について
- (活動内容)
-
- 生徒へのキャリアカウンセリングの実施
- キャリアの視点から,生徒が大学や職業を選択する際に参考となる情報提供
- クラスごとでのワークショップ実施(1年生6クラス,2年生9クラス)
- キャリア教育内容の計画立案
- (本事業を実施したことによる生徒の意識の変容)
-
- 自分の将来の目標を見つけることに関して,満足度[かなり満足している
 まあ満足している]が上昇した。
まあ満足している]が上昇した。
- 自分の将来の目標を見つけることに関して,満足度[かなり満足している
- (数字)3年 86.8パーセント(2年生時74パーセント)/2年 71.5パーセント(1年生時57パーセント)
-
- 生徒に次のような意識の高まりが見られた。(数字は「とてもそう思う」と答えた者の率)
- (1)たいへんでもやりがいのある仕事がしたい
- (数字)3年 56.9パーセント(2年生時48.5パーセント)/2年 45.4パーセント(1年生時42.7パーセント)
- (2)世の中を良くすることや,人のために役立つ仕事をしたい
- (数字)3年 38.8パーセント(2年生時27.4パーセント)/2年 24.6パーセント(1年生時22.7パーセント)
- (3)学校を卒業すれば,働くことは社会の一員として当然のことだ
- (数字)3年 39.8パーセント(2年生時28.2パーセント)/2年 34.8パーセント(1年生時26.2パーセント)
- (4)希望の職種でなくとも正社員として働きたい
- (数字)3年 19.6パーセント(2年生時12.1パーセント)/2年 18.1パーセント(1年生時13.1パーセント)
- (5)多少つらくても転職せず,できるだけ1つの職場で働き続けた方がよい
- (数字)3年 26.8パーセント(2年生時21.5パーセント)/2年 28.8パーセント(1年生時22.4パーセント)
- (6)私生活より仕事を優先するのは当然のことだ
- (数字)3年 10.3パーセント(2年生時5.4パーセント)/2年 8.4パーセント(1年生時4.6パーセント)
- 生徒に次のような意識の高まりが見られた。(数字は「とてもそう思う」と答えた者の率)
5.まとめ
(1)評価のまとめ
本事業の目的は,若者が職業について考えたり,進路の選択・決定を先送りしたりする傾向,いわゆるモラトリアム傾向や,進路意識や目的意識が希薄なまま進学する者の増加が指摘される中,高等学校,特に普通科高校でキャリア教育に取り組むことにより,キャリア教育を充実することにある。
上述の各評価結果などから,本事業の指定をキャリア教育に取り組む契機とし,事業の目的に向けて推進しているといえる。
(2)今後の課題等について
普通科高校も他の学科同様,学校規模,在籍生の興味・関心・進路意識等が多様であり,地域における学校の役割もまた,学校ごとに異なっている。よって,普通科高校における望ましいキャリア教育の在り方は一様ではない。今後,それらの多様な課題を検証し,具体的なキャリア教育の方法を模索することが大きな課題である。
また,「教師が抱える課題」(調査結果7)として,「進路学習の指導内容・指導方法をどのようにしたらよいかわからない」等があげられており,教員の資質・能力を向上させることも課題である。
普通科の生徒であっても将来は職に就くことから,勤労観・職業観を身に付けさせ,主体的に進学・就職を含め進路を選択・決定する能力を育成しなければならない。このため,生徒の勤労観・職業観に対する意識や将来に対する目的意識等がどのように変容したか等,本事業による生徒への効果をどのように把握・活用するかについても課題である。
本事業の成果と課題を整理し,今後のキャリア教育の改善に生かすためにも,本事業実施校においては,引き続き,調査研究を実施し,その成果を生徒に還元する必要がある。
-- 登録:平成21年以前 --