- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 文化資源の保存、活用及び創造を支える科学技術の振興 > 第4章 科学技術による新たな文化資源の創造 2 メディア表現のための研究開発
第4章 科学技術による新たな文化資源の創造 2 メディア表現のための研究開発
東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授 浜野 保樹
2-1 文化資源としてのコンテンツ
世界的な景気低迷にあって、各国で成長が続き、環境問題など地球規模の問題にも無縁なコンテンツ産業は、21世紀に基幹産業としての認識されるようになっている。世界の工場である中国の台頭で、20世紀末から各国は先のアメリカと同じ問題に直面し、産業構造を転換せざるをえないという事情もある。またこれまでの労働中心から、自己実現や「楽しみ」といったことに価値が移行しつつある状況で、コンテンツ産業はそれらを充足される産業であるだけでなく、コンテンツ製作そのものが自己実現や自己表現であるため、魅力ある雇用を創出できる産業としても注目されている。
20世紀、アメリカ合衆国は長引く冷戦構造によって、軍事や航空宇宙などの巨大技術に特化しすぎた結果、民生品の製造で国際競争力を失った。しかし冷戦構造の崩壊とともに、産業の国際競争力をとりもどす処方箋を求めて、1983年にレーガン政権は「産業競争力委員会」を設立し、1985年に報告書を公表した。委員長名から通称「ヤング・レポート」と呼ばれるこの報告書には、国際競争力を保持するために、商業化に適する科学技術の基盤構築、新知識の商品化や製造法への実用化といった提案とともに、知的財産権の保護強化が提案されている。レーガン政権は報告書の勧告に準じた政策を推進したわけではないが、報告書が示した通り、その後、著作権産業はアメリカにおいて成長が最もめざましい産業となった。
2001年、アメリカにおける著作権産業はGDP(Gross Domestic Product 国内総生産)の5.24パーセントを占め、著作権産業にかかわる流通や販売業などの周辺ビジネスまで含むと、GDPの7.75パーセントにのぼり、800万人の雇用を生み出している。1977年から2001年の間に、年平均7.01パーセントの増加を示している。アメリカ国内の売り上げよりも輸出額の方が大きく、商務省の推計では、化学産業、自動産業や航空産業を抜いて、アメリカ最大の輸出産業となっている(※1)。
アジアでは「コンテンツ(コンテント)産業(content industry)」という言葉が使用されるが、アメリカでは「著作権産業(copyright industry)」、イギリスでは「クリエーティブ産業(creative industry)」、フランスでは「文化産業(industrie culturelle)」と呼ばれことが多い。著作権産業は、コンテンツ産業にコンピューター・ソフトウェアや情報処理サービスなどを加えたものである。クリエーティブ産業や文化産業は、コンテンツ産業にデザインや伝統的な表現活動を加えたものである。
わが国のコンテンツ産業は、筆者が試算したところ、2000年には12兆5246億円(※2)であった。同年のわが国のGDPが513兆3768億円(※3)であるため、コンテンツ産業の比率は2パーセント強にすぎない。このようにアメリカに比べて、わが国のコンテンツ産業が大きく立ち遅れている理由の一つが、コンテンツ制作にかかわる研究開発の立ち後れにあることを、黒澤 明は映画を例にとって次のように述べている。
「アメリカ映画のバックボーンには、アメリカ映画芸術科学アカデミイという組織があり、映画は科学と密接に結びついた芸術である、という確固たる認識の上に立っているからだ。テレビという新興勢力と闘うためには、映画もまたテレビに負けぬ科学的武装が必要である」(※4)
コンテンツが研究をもとにした科学的成果の上にあることと、わが国にその認識が欠けていることを、黒澤は指摘している。黒澤の言葉は、「確立した映画産業を持つ国はたいてい、全国的な映画の研究組織がある」(※5)と言い換えることもできる。それが正しいのであれば、「全国的な映画の研究組織」がないわが国には、「確立した映画産業」を持つことなどはできないことになる。
2-2 コンテンツ研究
(1)研究分野
20世紀に入って複製技術が普及すると、作家が一つずつ制作していたそれまでの芸術作品と異なる、録音音楽や映画などの「複製芸術」が生まれ、放送のように不特定多数の人々にまで享受できるメディア表現技法も開発されるようになった。このように新しい表現内容は技術革新の産物であって、新しい表現内容も文化資源であるとすれば、文化資源の創造は技術開発に大きく依存するようになったのである。わが国では、メディア技術に依存する芸術をメディア芸術(media art)と呼んでいる。
複製による商用利用を前提として制作される表現内容は、1980年代中期からパーソナル・コンピューターによって、文字、図像、音声、映像などの表現形式を一元的に、かつ安価に制作できるようになった。デジタル技術で、表現形式毎に分割されていたメディア産業が融合することをデジタル融合(digital convergence)と呼ぶが、文化資源の研究開発においても、デジタル融合に似た現象が起こった。
表現内容毎に流通や公開の方法が存在していた時には、表現内容毎に新聞研究、映画研究、放送研究、マスメディア研究など、個別の研究領域が存在していた。しかし映像や音声といった最終形態は何であっても、デジタル・データとして制作されるようになったため、表現内容を文字や映像といったように区分せず、コンテンツ(あるいはコンテンツ)と一元的に扱い、それを総合的に研究するようになある。技術は工学、産業は経済学や経営学、政策は法学と、分散していた研究分野をコンテンツでたばねた研究領域をコンテンツ研究と呼ぶようになりつつある。
これまでのコンテンツ研究は以下の6つに大別され、コンテンツ制作そのものに関する研究はほとんど見られなかった。
- コンテンツの流通、利用と保存(アーカイブ)
- コンテンツの個人や社会への影響
- コンテンツの基盤技術
- コンテンツ産業(歴史を含む)
- コンテンツ政策(規制、人材育成を含む)
- コンテンツ批評
しかしコンテンツの制作そのものに関する研究は極めて少なく、これまでの研究は作られたコンテンツに関する研究が中心であった。「小説の書き方」や「絵の描き方」など、映画や音楽、小説などコンテンツ制作の経験則やハウツー本は古今東西無数にあるが、学術研究はほとんどなされなかった。
(2)コンテンツ研究が必要な理由
ブロードバンド時代と到来によって、コンテンツは国境を越えて行き交うことが現実のものとなりつつある。コンテンツ制作の研究状況からすると、文化資源を生み出す研究は放置されたままで、道を造ったけれど、その道を使う車のことは考慮されていないということになる。一生懸命道を造ってみて、気が付くと走っているのは外車ばかりという状況にもなりかねない。
わが国のコンテンツの共通基盤たるメディア技術の研究開発は、NHK放送技術研究所とNTTの研究所の、放送と通信の二大研究機関に依存してきた。しかし、テレビ受像技術としてNTSCが開発されていたにもかかわらず、ヨーロッパでPALやSECAMが開発され普及したように、単に技術的水準や機能の優劣だけでは、メディア技術は評価されない。コンテンツにかかわるハードウェア技術は文化資源を扱う技術であり、国家の独自性にかかわる技術でもあるため、政治的存在とみなされる。こういった教訓が生かされなかったため、わが国のハイビジョン(※6)や携帯電話の規格は海外に普及する機会を活かしきれなかった。
またハードウェア技術は、映画の規格をハリウッドが実質的に握っていることが示しているように、人々を引き付けるコンテンツを握っているところが決定することになる。ハードウェア技術の普及のためにもコンテンツ制作の研究開発が不可欠となる。
(3)制作研究が行われなかった理由
モノ作りでは 製作過程やロジスティックスの研究開発は不可欠であるが、コンテンツでは制作に関する研究がほとんど行われることはなかった。多くのコンテンツ研究が存在するのにもかかわらず、制作に関する研究がなされなかったのには、以下の理由が考えられる。
- 研究の客観性:作品は主観の固まりのようなものであり、芸術に代表される創作活動は研究対象にはなりにくいという先入観が根強い。研究成果は、特定作品の事例研究から脱することができないと考えられていた。
- 研究の再現性:主観的創作物であるコンテンツは一過性のものであり、同じものは二度と生まれないため、研究の再現性が保証しにくい。
- 研究の応用性:もの作りは、製品が市場に出てからも繰り返し改善でき、他で行った工夫が試されたり、研究結果を実社会に応用できる。しかしコンテンツは、バーションを変えて市場に出すということはあり得ないし、市場の結果から修正して、作品を出し直すということもありえない。スニーク・プレビュー(sneak preview)という手法はハリウッド映画では使われているが、世界的には一般的な手法ではない。作ってしまえば終わりであって、研究の応用性が極めて低いと考えられていた。
- 研究対象の不在:作品制作はたった一度だけの機会であるため、研究実施はその二度とない機会をだいなしにする可能性がある。納期が決まっている創作活動に従事している人々は、作品制作に集中できる環境を作ることに腐心しているため、研究などはじゃまものでしかない。また創造的活動である制作現場と、論理性を追求する学会は、本来的に異質であり、両立しがたい性質を内包しており、関係が希薄で、研究協力を依頼することが困難であったことも関係している。
これらの理由から、制作そのものではなく、コンテンツ周辺の事象に既存の分析手法を当てはめるという研究が大半であった。
2-3 アメリカの優位
(1)アメリカの研究
コンテンツの制作手法を学術的に研究とした数少ない系譜として、第2次世界大戦から開始された教育工学(educational technology)の教授設計(instructional design)モデルを応用した軍人訓練や教育用の映画やテレビ番組の制作研究があるが、研究の蓋然性についての批判が少なくない(※7)。
制作技術に関する研究系譜としては、コンテンツのデジタル化、そしてそれに伴うコンテンツ制作のダウンサイジング、制作技術の開放をもたらした研究群がある。具体的には、J・C・R・リックライダー(J.C.R.Lilider 1915~1990)が触媒となって、今日のデジタル・コンテンツ制作の基礎技術の大半を開発に導いた事例である。ヴァニヴァー・ブッシュ(Vannevar Bush)(※8)の知的活動を支援するための機械のビジョンに端を発して、リックライダーが指揮した1960年代の研究開発がパーソナル・コンピューターやインターネット、コンピューター・グラフィックス(Computer Graphics)、バーチャルリアリティ(Virtual Reality)を生み出すことになったことはよく知られている(※9)。既に述べたように、パーソナル・コンピューターがコンテンツ制作の主要手段であり、かつインターネットがコンテンツの主要な流通手段となりつつあることからして、リックライダーが指揮した研究開発は、実はコンテンツ技術の研究でもあったことになる。
それも偶然ではなく、リックライダーはコンピューターを「コミュニケーションの道具」(※10)と考えており、彼の支援を受けて、パーソナル・コンピューターの概念を作るアラン・ケイ(Alan Kay)は、パーソナル・コンピューターを「コミュニケーションの増幅器」であるとともに「ファンタジーの増幅器」(※11)とみなし、パーソナル・コンピューターの原型であるALTOで子どもたちに表現活動の実験を行っている。
ケイのビジョンを継承し、マサチューセッツ工科大学(MIT)のニコラス・ネグロポンテ(Nicholas Negroponte)は1980年、論文「日曜画家の復活」(※12)の中で、コンピューターが表現活動を支援するものであることを説き、この考えの実践として、1985年MITメディアラボ(※13)を設立した。
コンテント制作が技術革新の産物である以上、これまで遊離していた芸術と工学の融合、あるいはエンターテインメントと工学の融合が必要となるが、MITメディアラボは、その先鞭をつけた。
(2)民間企業研究所
表現技術やエンターテインメント技術の研究開発は、最近になるまで民間企業で行われていた。特にウォルト・ディズニー社とルーカス・フィルム社が果たした役割は大きかった。
ウォルト・ディズニー(Walt Disney)は、「映画産業の技術革新があれば他社に先駆けて取り入れるべきだ」(※14)というのが持論だった。トーキー、カラー、70ミリフィルム(※15)、新しい音響システムなど、ディズニーはいち早く試みている。テーマパークのためにオーディオ・アニマトロクス(Audio-Animatronics)(※16)を開発し、CAPS(Computer Animation Production System)(※17)によってどのスタジオよりも早くCGアニメーションに挑戦している。
テーマパークを開発する会社(※18)を設立し、ウォルト・ディズニーは、テーマパークのアトラクション開発に従事するスタッフを、イメージのエンジニアという意味でイマジニア(Imagineer)と命名し、その社名をウォルト・ディズニー・イマジニアリング社(Walt Disney Imagineering)とした(※19)。のちに同社はアラン・ケイを副社長に迎え、一九九六年に、ディズニー社はという制度を作り、ダニー・ヒリス(Danny Hillis)、マーヴィン・ミンスキー(Marvin Minsky)、シーモア・パパート(Seymour A. Papert)などの研究者をディズニー・フェローズ(※20)に任命したが、2001年にディズニー・フェローズは解散した。フランシス・コッポラ(Francis Coppola)のゾーエチロープ社も研究機能を持っていたが、会社更生法を申請した後、ルーカス・フィルムのILM(Industrial Light & Magic)が研究機能を引き継ぐことになった。ルーカス・フィルムはサンフランシスコに、デジタル映像制作研究の核都市Letterman Digital Arts Center(※21)を建設中である。アニメーション工房の一つに過ぎなかったディズニー社は世界最大のメディア企業の一つとなり、ILMが世界最大の特撮工房になったのも、研究開発機能を有していたからに他ならない。
(3)アメリカの大学の研究所
アメリカには芸術系と工学系が融合した大学の付置研究所としては以下のようなものがある。
- MITメディアラボ
- カーネギー・メロン大学エンターテインメント工学センター(Entertainment Technology Center):芸術学部とコンピューター・サイエンス学部が共同で運営
- 南カリフォルニア大学エンターテインメント工学センター(Entertainment Technology Center)(※22)、
- 南カリフォルニア大学統合メディア・システムズ・センター(Integrated Media Systems Center)(※23)
- 南カリフォルニア大学ロバート・ゼメキス・デジタル芸術センター(Robert Zemeckis Center for Digital Arts)
- カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)ゲーム・カルチャー&テクノロジー・ラボ(Game Culture & Technology Lab):開設準備中。2003年夏、グレイ・デイビス知事が先頭に立って進めてきた州の科学・技術革新イニシアチブである『Cal-(IT)2』プログラムの一環として、研究開発施設である本センターの承認を得ている(※24)。
2-4 わが国の研究の劣勢
(1)わが国の研究
アメリカの、ACM SIGGRAPHのようにCGを中核としたデジタル・コンテンツ制作に関する学会がわが国に存在しない。テレビジョン学会、映像情報メディア学会(1933年設立)、日本出版学会(1969年設立)(※25)や日本映像学会(1974年設立)(※26)が既にあり、20世紀後半から表現形式毎の学会、例えば日本アニメーション学会(1998年設立)(※27)、日本漫画学会(2001年設立)(※28)ゲーム学会(2002年設立)(※29)、コンテンツクリエーション・アンド・コミュニケーション学会(2003年設立)(※30)などが設立されたが、批評と工学系の研究発表がほとんどである。
わが国で制作システムに関する研究開発として注目されているものとして、カーネギー・メロン大学に移籍した金出武雄教授のVirtualized Realityがある。複数のカメラで同じ被写体を撮影し、視差を使用してコンピューターに3D映像をとり込むシステムであり、動く被写体を取り込むことが可能だ。従来の撮影だと、撮影した際のカメラ・アングルを変えることはできないが、Virtualized Realityのシステムでは、コンピューター内に撮影した空間がそっくり写し取られているため、後でカメラ・アングルを決定したり、映像の修正加工も可能になる。
かつて金出教授の共同研修者であり、東京大学に移った池内克史教授は、視差を利用して3D映像を取り込む技術を利用して、大仏などの文化財のデジタル・コンテンツ研究を行っている。一方、南カリフォルニア大学のポール・デベヴェック(Paul Debevec)は、Virtualized Realityよりも簡便な写真機を利用して景観を取り込むimage-based modeling/renderingを開発し、映画『The Matrix:Reloaded』(2003年)などで使われている。研究があっても、実際の作品で利用できる環境がわが国には整っていない。
東京大学大学院新領域創成科学研究科メディア環境学研究室では、映像制作の工程管理ソフトウェア「EizoWorks」を2002年に開発し、これまで勘に頼っていた制作方法を、明示的な根拠のもとに組み立て、進捗状況をだれもが把握できようにするとともに、制作のノウハウを蓄積できるようにした。さらに、デジタル化によって映像制作の中での重要度が増しているポストプロダクションの工程管理ソフトウェアV-TOOLsも開発した。このようにソフトウェアにするということは、制作の暗黙知を顕在化して共有できるようになる。
EizoWorks
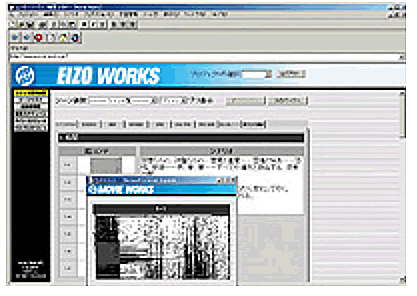
(2)教育研究機関の日米比較
コンテンツ制作に関する学術研究の実勢を示す定量的なデータは存在しないが、わが国のコンテンツ研究体制の相対的脆弱さは、アメリカとの比較において間接的には示すことができる。高等教育機関は人材育成機関であるとともに研究機能を有する主たる機関の一つであるため、機関数は研究者数をある程度反映している。
表1は日米の映像関係の大学数を比較したものである。研究者育成を主たる目的にしている大学院の博士課程の数が研究の量的格差を反映している。表2には北米で映画テレビについて教えている大学教官の数である。大学教官がすべて研究者というわけでなく、アメリカでは特にその傾向は強いが、大学を本務にしている研究者数を推測することはできる。しかし日本にはこの種のデータすら存在しない。
表1 日米映画・映像教育関連大学比較
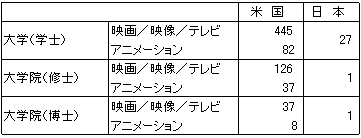
注1:数値は該当する講座を設けている大学等の数を示す。
注2:学士はB.A.、修士はM.A.、博士はPh.D.の数を示す。
出所:日本「1998年度全国マスコミ関係講座一覧」(総合ジャーナリズム研究165号)
米国「The Complete Guide to American Film Schools and Cinema and Television Courses 1994」「Animation School Directory 1999 Winter」
表2 北米における映画テレビの高等教育機関
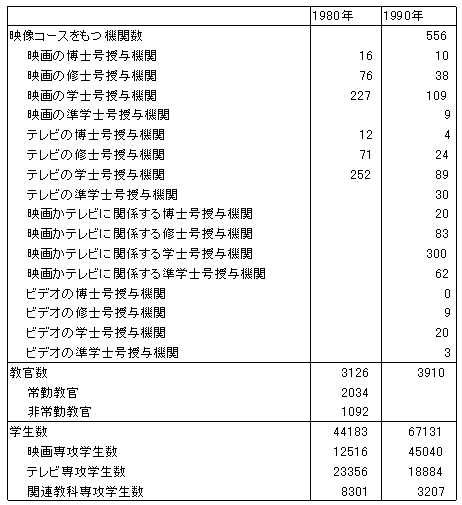
出典:American Film Institute. The American Film Institute Guide to College Courses in Film and Television, 7th Edition. New York: Prentice-Hall, 1980.
American Film Institute. The American Film Institute Guide to college courses in film and Television, 8th Edition. New York: ARCO, 1990.
わが国のデータとしては、毎年、季刊誌『総合ジャーナリズム研究』が「全国マスコミ講座一覧」を掲載しているが、映画や映像に関する学部学科を設けている大学は10に満たない。国際競争力があると言われているわが国のアニメーションやビデオゲームではあるが、アニメーション学科は東京工芸大学芸術学部に2003年4月に設置されたのが、わが国で最初のものであり、ゲームに関しても大阪電気通信大総合情報学部にデジタルゲーム学科が2003年4月設置されたのが最初である。もともと、わが国の表現活動は家元制という、全権を与える変わりに、教育機能を特定の家族に委任してきた文化資源の継承制度があり、誰もが学べるように暗黙知を顕在化したりする努力は希薄だった。世阿弥の『風姿花傳』も一子相伝の書だった。
上記の2つの表にはゲームのデータが含まれていないが、南カリフォルニア大学(USC)では、美術学部、映画・テレビ学部、コンピューター・サイエンス学部が、ゲームを学際的な副専攻課程2004年秋学期に開講し、大規模な総合大学としては初めての試みになる。これまで、ゲームを教育プログラムとして認定しているのは、シアトルのディジペン・インスティテュート・テクノロジーや、ゲームアート/デザインに学位を与えているサンフランシスコのアート・インスティテュート・オブ・カリフォルニアなどの、より専門的な学校に限られていた。ニューヨーク大学(NYU)、ワシントン大学は、ビデオゲームをプログラムとして認定しており、マサチューセッツ工科大学(MIT)では、メディア研究の科目でゲームを学べる。カーネギー・メロン大学は、エンターテインメント・テクノロジーで修士号がとれる唯一の大学である。
2-5 各国のコンテンツ制作に関する研究開発への支援政策
(1)アメリカ
高等教育機関の少なさは人材の供給面での深刻な問題をひきおこすだけでなく、研究の質と量、および研究の蓄積においても影響がないわけはない。アメリカにおいてコンテンツの研究開発が盛んなのには別の理由もある。宇宙開発が以前ほどの勢いがなく、冷戦構造が崩れた今日では、莫大な費用をかけて研究開発した技術を使用して、試行錯誤や失敗を許容できる分野はエンターテイメントだけだと言われているからだ。
(2)イギリス
イギリス政府は「クール・ブリタニア・プロジェクト」でクリエーティブ産業支援を集中的に行っていたが、1999年12月デジタル・コンテンツ産業の育英を目指す、報告書『UK Digital Content:An Action Plan for Growth』を発表し、デジタル・コンテンツ産業支援の姿勢を明確にした。
(3)フランス
文化は国家で管理するという施政を貫いてきたフランスは、文化と産業の両面からあらゆる手段を駆使してコンテンツ産業を支援している。研究支援はフランス国立視聴覚研究所(INA)を中心に行われてきたが、それ以外にも研究機関が設置されるようになっている。
フランス南部アングレーム(Angouleme)市は、映像核都市構想ポール・イマージュ(Pole Image)には、デジタル映像研究所(LIN)が設置されている他、映像に関する高等教育機関三つ、高校が二つ、国立アニメーション・映像センターの国立研究所が、アニメーション映画学校(Ecole des Metiers du Cinema d'Animation d'Angouleme)なども設置されている。
(4)ドイツ
ドイツ南西部のバーデン・ヴュルテンベルク州・カールスルーエ市は、1977年に開所したZKM(カールスルーエ芸術・メディア技術センター)を中核として、メディア芸術の最先端をめざしている。メディア・ミュージアム、現代美術館、メディア・テークとともに、映像メディア研究所、音楽・音響研究所が設置されている。
(5)韓国
韓国では金大中前大統領は、国家予算の1パーセントを文化に支出することを大統領選挙の公約とし、当選後公約通り実施し、ゲーム総合サポートセンター(後に「韓国ゲーム産業開発院」に名称変更)や韓国文化コンテンツ振興院を設立するなど、コンテンツ産業を積極的に支援しており、こうした中で、ソウル・アニメーション・センター、映画博物館(済州シンヨン)、韓国漫画博物館(プチョン市)なども矢継ぎ早に設立されている。2002年1月には「オンライン・デジタル・コンテンツ産業発展法」を制定し、世界のコンテンツ市場を占有する上位五ヵ国に食い込むことを目標としている。こういった施策が功を奏し、韓国のポップカルチャーがアジア諸国で浸透しつつある。2003年2月「第1次オンライン・デジタル・コンテンツ産業発展計画」を策定し、その中でオンライン・デジタル・コンテンツに関する研究開発に関して、以下の3つの具体的施策を打ち出している。
- 映像コンテンツ技術開発センターの設立:
CG等のデジタル・コンテンツ関連の核心技術を持つため、電子通信研究院(ETRI)を中心とした「映像コンテンツ技術開発センター」(仮称)を設立する。 - オンライン実感型ゲーム・エンジン技術・特殊映像合成技術等の開発:
デジタル・コンテンツ製作、管理、流通に必要なオンライン実感型ゲーム・エンジン技術・特殊映像合成技術等の開発を集中支援する。 - 『デジタル・コンテンツ技術協力フォーラムの結成:
大学がデジタル・コンテンツ基礎技術研究を活発にするよう、デジタル・コンテンツ関連大学IT研究センター(ITRC)を増やし、民官共同『デジタル・コンテンツ技術協力フォーラム』を構成し、汎国家的レベルの体系的な研究開発と標準化活動を推進する。
(6)台湾
台湾は2002年8月、「デジタル・コンテンツ産業振興オフィス(DCIPO)」を設置した。
(7)中国
中国は、北京オリンピックや上海万博を目指して、放送と映画のデジタル化をどこの国よりも早くなしとげようとしている。
高度なデジタル技術を駆使したアニメやゲームの制作技術者を育成するため、中国・上海の名門、上海交通大学が2003年秋から「デジタルメディア芸術・技術」を看板に掲げた大学院修士課程を創設する。従来の教育システムでは、芸術系と技術系が別々だったが、この課程では海外企業などとも協力し、「芸術とコンピューターの両方がわかる」専門家を育てる。第1期生は50~60人を募集する)(※31)。
(8)マレーシア
20世紀末より、マルチメディア・スーパー・コリドー計画を実施し、マルチメディア大学を設置して人材育成を努めている。
(9)シンガポール
これまで海外に通用するコンテンツを持っていなかったシンガポールは、デジタル・コンテンツ制作のハブを目指す「メディア21」)(※32)ビジョンを2002年に発表し、「Global Media City」への転換を標榜している。GDPに占めるコンテンツの比率を、1.56パーセントからここ10年の内に3パーセントに引き上げ、38,000人の雇用を50,000人に引き上げるという目標を掲げ、研究施設であるコンテンツ・クリエーション・センター(CCC)を設置している。
(10)日本
わが国にはNHK放送技術研究所という、わが国のみならず世界の放送技術を先導してきた研究所がある。しかしは、NHKという組織体の研究所であるため、大学の付置研究所のような開放性を望むことはできないし、放送に限定されている。
このようにみてくると、わが国にはコンテンツ制作に関する研究機関が皆無であることが分かってくる。こういった状況について、国が支援の姿勢をみせつつも、研究開発機関が存在しないことについて、関連業界からも批判の声が上がっている。東映社長である岡田 剛は次のように述べている。
「映像や音楽などのコンテンツがブロードバンド時代の有力産業と目されるなか、コンテンツ産業の様々な支援策が検討されている。関係者から『大規模なスタジオ建設』や『制作費の資金援助』などの政策案を相談されることも多いが、『日本映画をこれからどうしていきたいのか』という本質的な視点に欠けている。今後、邦画の成長にとってカギとなるのはコンピューター・グラフィックス技術だ。制作費が少ない日本の映画でも米ハリウッドの大作に比する作品を作ることはできる。だが、民間各社が最先端の技術と人材を維持していくことは難しい。邦画の国際競争力を引き上げるには民間がCG加工を委託できる世界最先端の研究機関を設立する策も有効だ」)(※33)
2-6 文化の多元性
わが国でも近年になって、文化資源だけでなく経済資源としても、また外交資源、観光資源としても、コンテンツの重要性が認識されつつある。2002年に文化芸術振興基本法が制定され、2003年に入って経済産業省がコンテンツ産業国際戦略研究会を、総務省が情報通信ソフト懇談会を設置した。内閣知的財産戦略会議が2003年7月に発表した日本版「ヤング・レポート」ともいえる報告書「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」を受けて、コンテンツ専門調査会を設置が設置され、「コンテンツビジネス振興法(仮)」の制定などが検討されている。
しかし、クリエーターの人材育成だけでなく、研究機関を設立し、研究開発を急いでいるアジアやヨーロッパ諸国は、わが国が得意としていたアニメーションやゲームで目覚ましい成果を上げつつある。
先に紹介した黒澤明の言葉にあったように科学という認識をもち、研究開発を継続して行ってきたアメリカのコンテンツは、どの国のコンテンツ市場においても強い支配力を持っている。文化の多元性を維持するためにも、文化資源を生み出すための、制作現場と連携できる研究開発は不可欠であり、そのための研究者育成を急がなければならない。
参考文献
※1 Stephen E. Siwek. Copyright Industry in the U. S. Economy: The 2002 Report. Washington D. C.:International Intellectual Property Alliance, 2003.
※2 浜野 保樹『表現のビジネス』東京大学出版会、2002年、192頁。
※3 総務省統計局『世界の統計』総務省統計局、2002年。
※4 黒澤 明『蝦蟇の油』岩波書店、1984年、361頁。
※5 エマニュエル・レヴィ『アカデミー賞全史』濱口 幸一訳、文藝春秋、1992年、53頁。
※6 ジョエル・ブリンクリー『デジタルテレビ日米戦争』浜野 保樹・服部 桂訳、アスキー、2001年。
※7 浜野 保樹「セサミ・ストリートの過誤」、浜野 保樹『マルチメディア・マインド』BNN、1993年、257~268頁。
※8 G. Pascal Zachary. Endless Frontier:Vannevar Bush, Engineer of the American Century. New York;The Free Press, 1997.
※9 ハワード・ラインゴールド『思考のための道具 異端の天才たちはコンピュータに何を求めたか?』青木 真美訳、パーソナルメディア、1987年。
浜野 保樹『極端に短いインターネットの歴史』晶文社、1999年。
※10 J.C.R. Licklider & Robert Taylor, The Computer as a Communication Device, Science & Technology, April 1968.
※11 浜野 保樹監修『アラン・ケイ』鶴岡 雄二訳、アスキー、1992年、133頁。
※12 ニコラス・P・ネグロポンテ「日曜画家の復活」、月尾 嘉男訳、『コンピュータ・個人・生活・新情報社会への展望』コンピュータ・エージ社、1980年、59~62頁。
※13 スチュアート・ブランド『メディアラボ』室 謙二・麻生 九美訳、福武書店、1988年。
※14 グローヴァー、ロン『ディズニー・タッチ』仙名 紀訳、ダイヤモンド社、1992年、11頁。
※15 ジョン・テイラー『ディズニー王国を乗っ取れ』矢沢 聖子訳、文藝春秋、218頁。
※16 フランク・トーマス、オーリー・ジョンストン『The Illusion of Life 生命を吹き込む魔法』スタジオジブリ訳、徳間書店、2002年、532頁。
※17 マイケル・アイズナー『ディズニー・ドリームの発想 上』布施 由紀子訳、徳間書店、2000年、295頁。
※18 The Imagineers. Walt Disney Imagineering: A Behind the Dream Look at Magic Real. New York: Welcome Enterprises, 1996.
※19 マーク・エリオット『闇の王子ディズニー 下』古賀 林幸訳、草思社、1994年、143~144頁。
※20 「『魔法の王国』を支える天才たち」、『ニューズウィーク日本版』1997年8月13日、34~37頁。
マイケル・アイズナー『ディズニー・ドリームの発想 下』布施 由紀子訳、徳間書店、2000年、302頁。
※21 Letterman Digital Arts Center
※22 南カリフォルニア大学エンターテインメント工学センター(Entertainment Technology Center)
※23 南カリフォルニア大学統合メディア・システムズ・センター(Integrated Media Systems Center)
※24 Hotwired Japan 『南カリフォルニア大学がゲームを副専攻課程として認定』
※25 日本出版学会
※26 日本映像学会
※27 日本アニメーション学会
※28 日本漫画学会
※29 ゲーム学会
※30 コンテンツクリエーション・アンド・コミュニケーション学会
※31 http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20030822ij81.htm
※32 www.mda.gov.sg/MDA/documents/media21.pdf
※33 『日経新聞』2002年11月4日。
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課