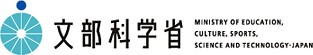| 1. |
保護期間は過去、延長をくり返されて来た
| イギリス: |
1709年[公表から14年原則]から2001年[生前全期間(平均寿命74歳)プラス70年] ※生前保護を30年と見るならば、300年で約6倍以上に長期化
|
| アメリカ: |
20世紀の100年間で、保護期間の原則は[公表後28年(更新で42年)]から[公表後95年(更新不要)又は死後70年]へと、約3倍前後に長期化 |
| 他の創作保護制度との比較: |
特許登録から20年(最大で5年のみ延長可) |
|
私たちの文化の数千年の歴史の中で、かつて一度も生前プラス死後70年もの期間、作家の遺族に作品の法的独占を認めた時代はない。著作権が作品という情報の独占を認める制度であるならば、社会はかつてない情報の長期独占時代に入ることになる。その影響を予測する試みは大変重要だが、究極的には影響は立証困難というほかない。
ただ、ひとつ確実にいえることは、保護期間はいったん延長されたら短縮は極めて難しいということである。そのため、いま期間が延長されれば、その影響は私たちの子孫に半永続的に及ぶ。また、「一億総ユーザー、一億総クリエイター」といわれる時代、延長の影響は社会のすべての領域に及ぶ。よって、誰がどのような根拠で延長に賛成し、反対し、あるいは沈黙したのか、歴史の検証に耐える議論を望み、注視したい。
|
| 2. |
保護延長によって作品流通や文化活動が停滞しないか
著作権は相続人全員の共有が原則で、権利者全員の同意がないと利用できない。70年も前に亡くなった創作者の相続人全員を特定し、連絡をとり、利用の許可を得るのは難しく、「各種エンタテインメント産業活動」、「図書館・博物館やアーカイブ活動」、「福祉・教育・研究目的での利用」、「オーケストラ・合唱・劇団その他の文化活動」が停滞し、埋もれた作品が増えるおそれがある。発表者の経験をいえば、これまで現場ではしばしばアバウトな権利処理も見られた。しかし、今後は、権利意識の高まりから厳密な処理が求められる場面は確実に増える。本当に社会は、「死後70年」の負担に耐えられるのだろうか。
「許可のとりにくさは、全著作者を網羅するデータベースや、簡易裁定などで解消できる」との意見もある(日本文藝家協会意見)。いずれも意義ある取り組みだが、第一にデータベースはデータベースであって、許可をとれるかはまったく別論である。第二に、延長の問題点を解消できるほど網羅的な、海外作品まで含めたシステムの構築は極めて困難な作業だ。図書だけに限っても、国立国会図書館に所蔵された和図書の著者は約79万人で、日本文藝家協会への管理委託者(部分委託を含む)の250倍に迫る。海外の著者は優に10倍するだろう。死後70年もの過去への情報追跡は、データベース構築の費用と時間を飛躍的に増大させるだろうが、その負担を国民に負わせるのだろうか。第三に、文化庁長官の裁定制度は、対象が「権利者不明の場合」など限られている上(法67条ほか)、すべての利用者が日常・広汎に使えるほど簡易にできるとはとても思えない。そもそも、延長が必要なのかという議論が先決だろう。
|
| 3. |
保護延長は創作活動への制約を増やさないか
「作家は骨身を削って創作している。残された配偶者が気の毒だ」との意見がある。しかし、自然に考えれば、死後50年から70年にかけての受益者は創作者の孫・ひ孫以降の世代が中心だろう。社会のさまざまなデメリットを無視してまで孫以降の世代の収入を守るべきかは疑問である。よしんば、レアケースにおける創作者の配偶者や子の生活保障をはかりたいとしても、数千万を超える作品の保護期間を一律に延ばす必要があるだろうか。
また、「保護が死後70年に延びると創作意欲が高まる」と議論されることがある。しかし、すでに作られた作品について創作の意欲が高まるということはないので、既存作品について保護を延ばす理由にならない。将来の創造についても意欲が高まるかは疑問で、延長はむしろ創作者の手足を縛り、新たな創造に決定的な悪影響を及ぼす危険性がある。下記は、作品が公表後およそ50年から120年の期間中に翻案によって再創造された例だ。「アイディアが借用された」といったレベルではなく、現在なら、遺族の許諾が得られなければ封印されざるを得ない作品が大半である。
公表後50年から120年程度の作品を翻案・下敷きにして新しい作品が創作された例
「ロミアスとジュリエットの悲劇物語」→シェイクスピア「ロミオとジュリエット」/ゴーリキー「どん底」→黒澤明「どん底」/ドストエフスキー「白痴」→黒沢明「白痴」/芥川龍之介「藪の中」→黒澤明「羅生門」/森鴎外「山椒太夫」→溝口健二「山椒太夫」/ユーゴー「レ・ミゼラブル」→ミュージカル「レ・ミゼラブル」ほか/ガストン・ルルー「オペラ座の怪人」→ミュージカル「オペラ座の怪人」/ディケンズ「クリスマスキャロル」「オリバー・トゥイスト」→ミュージカル・映画/小説「ボヘミアン生活の情景」→オペラ「ラ・ボエーム」・・・ミュージカル「レント」/ブラム・ストーカー「ドラキュラ」→「魔人ドラキュラ」はじめ無数のドラキュラ映画/ルイス・キャロルなど童話→数々のディズニー映画/宮澤賢治「銀河鉄道の夜」→杉井ギサブロー・アニメ版「銀河鉄道の夜」/ドストエフスキー「罪と罰」→手塚治虫「罪と罰」、大島弓子「ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ」ほか多数/夏目漱石の諸作品→無数/キャンベル缶などのデザイン(著作物性は微妙)→アンディ・ウォーホールの代表作/落語「長屋の花見」(大阪落語→二代目馬楽版→四代目小さん版など)/落語「居残り左平次」「品川心中」→映画「幕末太陽伝」/三遊亭圓朝「芝浜」「文七元結」→歌舞伎「芝浜革財布」「人情噺文七元結」/チャイコフスキー「白鳥の湖」→プティパ版以降翻案多数/ホフマン「くるみ割り人形とねずみの王様」→チャイコフスキー「くるみ割り人形」/ホルスト「木星」→平原綾香「ジュピター」/パガニーニのバイオリン曲→ラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲」ほか多数/エルガー「威風堂々」→平山綾「来て来てあたしンち」/ボロディン「ダッタン人の踊り」→トニー・ベネット「ストレンジャー・イン・パラダイス」/サン・サーンス「白鳥」→さだまさし「セロ弾きのゴーシュ」/ほか |
上記はほんの一例だが、これらは「創作を軽視した、商業主義の所産」だろうか。発表者はそうは思わない。期間延長がくり返されると、社会はこうした重要な創造の源泉を失うのではなかろうか。多くの創作者は、素晴らしい作品の創造に生命を賭けている。そこに私たちの文化のゆくえも、作品の死後の生命もかかっている。創造の制約を必要以上に増やすことが賢明な選択だとはとても思えない。
|
| 4. |
保護延長で「知財立国」は決定的に害されないか
著作権をめぐる国際収支は年々赤字幅を拡大しており、年間6,000億円に迫る(注1)。周辺波及効果はさらに大きい。戦前の欧米作品を延命させ続ければ、こうした輸入超過や国際的な知財の偏在を固定化するおそれがある。特に、古い作品に基づいて二次的作品が創られた場合、旧作品の著作権者の許可がなければ二次的作品は利用できない(法28条)。そのため、古い作品の保護延長は、想像以上の影響を及ぼす。著作権と比べ、保護期間が短い特許使用料の収支は改善を続け、近年黒字に転化した。仮に欧米の基本特許がすべて100年存続していたら、日本はこのような独自性を発揮できただろうか。
他方、「日本も延長しないと『相互主義』の結果、欧米への日本作品の輸出が害される」と主張されることがある。しかし、アメリカは相互主義をとっていないので、これは誤りだ(注2)。そのため問題はヨーロッパに絞られるが、今延長しないと海外で損をする日本作品とは具体的に何か。「村上春樹やアニメ、漫画」が例に挙げられることがあるが、そうした作品の保護が切れるのは30年から50年以上も先である。30年後の国民が、その時点での国際的な知財状況を見て判断すべきことを、私たちが決める権利があるのか。今延長して、戦前の欧米作品の延命を日本が後押しする理由は何だろうか。
上記のような危惧があるのだから、延長を議論するなら明確な延長のメリットが示されることがスタートになるはずである。過去の作品の利用や収集・保存の円滑化方策にしても、死後50年以後の作品に関する限りは、(延長のメリットがないなら)保護期間を延長しないことが最大の円滑化策であることを忘れてはならない。
延長のメリットを考えるとき、「期間が短いと欧米の権利者に恥ずかしい」との意見や、作品への敬意・評価と死後の独占管理との混同、著作権侵害の多発を延長の理由にする混同は、いずれも論評に値するとは思えない。そこで、以下、「死後70年は国際標準であり、期間を調和させないとコンテンツの流通が害される」という意見に絞って、国際ライセンス及び国際交渉の実務家として意見を述べる。
|
| 5. |
「著作者の死後70年」は本当に世界標準か
誤った情報が流布されているが、アメリカは現在問題になっているような古い作品については死後70年の保護は採用していない。下記の通り公表時起算であり、まったく異なる期間である。この結果、アメリカで保護が終わっていて、日本で保護が続いている作品も少なくない(注3)。このように日・米・欧で期間が不統一なのに、「死後70年が国際標準」と述べる前提が誤っている。
 |
1922年以前の作品はすべて保護消滅 |
|
 |
1963年以前の作品は公表後28年で、登録・更新があれば同95年 |
 |
1964年から1977年までの作品は公表後95年 |
 |
1978年以降の作品は死後70年 |
が原則(注4) |
|
昨年12月の時点で確認できた限りでは、死後70年を採用しているのは世界でもベルヌ条約加盟国の3分の1程度であったが、よしんば死後70年が今後多数になったとしても、日本はベルヌ条約の基準を充たしている。なぜ慌てて多数派に追随する必要があるのか。欧米のやり方には理由を問わず追随するという姿勢こそ、知財立国・文化立国の最大の障害であり、私たちが克服すべき課題ではなかろうか。
付言すれば、今世紀に入ってECやイギリス政府が著作隣接権延長を断念するなど、そもそも期間長期化が現在の世界潮流といえるかは疑問がある。むしろ、世界に先駆けて日本モデルを示すチャンスともいえる。
|
| 6. |
期間を調和させないと作品の国際流通を害するのか
発表者は漫画・映画・イベントなどの契約が業務の中心で、国際契約だけでも年間100を超える交渉に携わるが、保護期間が不統一なことがネックになってビジネスがつぶれた例や、目立った悪影響を受けた例は知らない。経済合理性から考えても、期間不統一でビジネスをやめるという事態は想像しづらい。たとえば、保護期間が異なるために、日本では出せた書籍が欧米ではそのまま流通できないということはあり得る。しかし、「では日本の保護期間を延ばして日本でも出せないようにしよう」という発想はあり得ない。逆に、欧米では権利処理が必要だった作品が、日本では自由に複製頒布できるという場面もあり得る。しかし、それをもって流通が害されていると呼ぶだろうか。おそらく呼ばない。
発表者が実務家として日々直面する課題は、それとはまったく異なる。現場で深刻なのは、欧米のビジネス相手の強固な、時に過剰な主張に押され、対等な交渉ができないままに権利の海外流出を招いたり、不公平な負担を負わされるケースの多発である(注5)。今回の期間延長問題も、それと極めて同根であるように思える。なぜ、相手が欧米だと要求を受けた途端に譲歩するタイミングをはかりはじめるのか。経験上、アメリカが日本に特定の政策を強く迫って来るのは、それが自国の利得になる場合である。日本は落ち着いて、日本自身と世界全体のために立場をしっかり主張できてこそ、国際社会でも国際交渉でも一目置かれるのだということを、強調したい。
なお、「死後70年に延長することで『戦時加算』を撤廃できる」という意見があるが、同調できない。戦時加算はサンフランシスコ講和条約上の義務で一方的に撤廃などはできないのはもちろんだが、そもそも、「一部作品が10年長いのが嫌なので全体を20年延ばす」などという交渉は、聞いたことがない。それ以前に、戦時加算の対象になるのは講和条約以前に公表された作品のみであって、現在でも、戦時加算を加えてすら年々保護期間は終了している。つまり、時の経過と共に問題としては縮小を続ける性質のものである。なぜいま持ち出すのか、との印象をぬぐえない。
|
| 7. |
結びにかえて
以上のように、保護期間のこれ以上の延長は、私たちの文化や知財立国に深刻な悪影響を与え、創作活動そのものを制約する危険を伴う。これに対して、そもそも延長すべきメリットはまったく客観的に示されていない。文化を愛し次世代の社会に対して責任を持つひとりとして、そのようなあやふやな理由での延長には決して賛同できない。
創作者の正当な利益は守られるべきである。そのために議論すべき改善点は、まだまだ多い。しかし、必要性も合理性もない期間延長を無理押しすれば、権利者や著作権制度は社会の信頼を失うだろう。発表者は、その点をこそ危惧する。
|
| 以上 |