現在、著作権等の権利を侵害する物品(以下「海賊版」という。)を販売するために、インターネットオークション等を利用して当該物品の譲渡の申出(以下「譲渡告知行為」という。)が行われ、その行為が海賊版の取引を助長しているとの指摘がある。
現行の著作権法第113条第1項第2号においては、
を、権利を侵害する行為とみなしているが、頒布の前段階の行為である海賊版の譲渡告知行為については侵害行為とはみなされていない。
しかし、インターネットを活用した譲渡告知行為は、告知される情報の伝達範囲の広さや取引の迅速さなどの面で、チラシやカタログの配付、ダイレクトメール等の従来の一般的な広告手法と比べて権利侵害を助長する程度が高く、対策の必要性が指摘されている。
プロバイダ責任制限法(注2)においては、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定めているが、その規定の適用には「特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合」であることが必要となる。しかし、著作権法においては譲渡告知行為それ自体は権利侵害に当たらないため、プロバイダ責任制限法の「情報の流通によって権利の侵害があった場合」に該当せず、同法による情報の削除請求や発信者情報の開示請求を行うことができず、海賊版の流通を防止することが困難になっているという実情がある。
以上の観点から、海賊版の譲渡告知行為を権利侵害と位置付ける法的措置を検討する必要がある(注3)。
| 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 (上半期) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 著作権法違反(海賊版事犯等) | 計 | 70 | 109 | 145 | 163 | 81 |
| うちネットワーク利用 | 41 | 82 | 67 | 87 | 49 | |
| (出典) | |
| 「平成19年度上半期における主な生活経済事犯の検挙状況について」 | (平成19年8月、警察庁生活安全局生活環境課) |
| 「平成18年中における生活経済事犯の検挙状況について」 | (平成19年2月、同上) |
| 「平成17年中における生活経済事犯の検挙状況について」 | (平成18年2月、同上) |
| 「平成16年中における生活経済事犯の検挙状況について」 | (平成17年2月、同上) |
海賊版の譲渡告知行為として想定される行為を類型化すると、次のような場合が考えられ(その他、これらの組み合わせの形態も考えられる。)、それぞれ、現行の著作権法第113条第1項第2号の規定による対応の可否については、立証の問題を別とすれば、次のように考えられる。
この類型は、譲渡告知行為を行っている者が同時に「頒布を目的として所持する行為」を行っている者でもあるため、権利侵害を構成することができる。
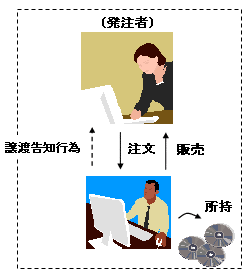
この類型は、譲渡告知行為を行っている者は侵害品を所持していないため、譲渡告知行為をしただけでは、権利侵害を構成することができない。ただし、譲渡告知行為を行っている者が受注して海賊版所持者が販売していることから、譲渡告知行為を行っている者と海賊版所持者とを共同行為者として構成して権利侵害を追及できる可能性がある。
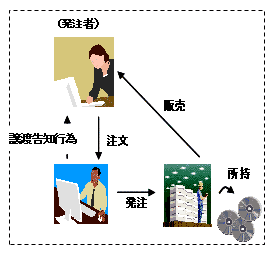
この類型は、譲渡告知行為を行っている者は侵害品を所持していないため、譲渡告知行為だけでは、権利侵害を構成することができない。また、譲渡告知行為を行っている者は、告知情報の掲載の依頼を受けて告知を行っているだけであるから、販売の共同行為を行っている者としても、せいぜい幇助の可能性があるにとどまるのではないかと考えられる。
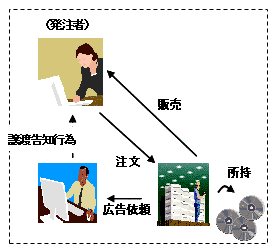
この類型は、譲渡告知行為を行っている者は侵害品を所持していないため、譲渡告知行為だけでは、権利侵害を構成することができない。ただし、譲渡告知行為を行っている者と海賊版所持者が親会社・子会社のように共同して販売行為を行っているととらえられる場合には、譲渡告知行為を行っている者を共同行為者として構成し、又は同一人格と構成して、権利侵害を追及できる可能性がある。
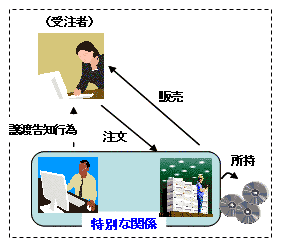
この類型は、譲渡告知行為を行っている者は、譲渡告知行為をした時点では侵害品を所持しておらず、「頒布を目的として所持する行為」ということができないため、権利侵害を構成することができないと考えられる。
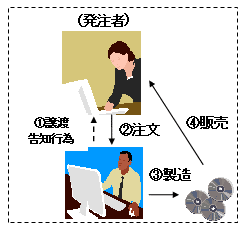
他の知的財産権法においては、侵害物品の譲渡の申出や譲渡のための展示行為を侵害行為として規定している例がある。
| 第2条 | |||
| 3 | この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
|
| 第2条 | |
| 3 | この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。 |
| 第2条 | |
| 3 | この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。 |
| 第2条 | |||
| 5 | この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
|
| 第2条 | |||||
| 3 | この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
|
著作権法における親告罪の在り方については、過去にも特許権等侵害罪の非親告罪化に伴い、著作権審議会や文化審議会著作権分科会において審議が行われたことがあるが、非親告罪化に積極的な意見と消極的な意見の双方があり、引き続き検討を行うこととされていたところである(注7)。
近時、いわゆる海賊版の製造、販売行為など重大かつ悪質な著作権等侵害事犯の存在等から、我が国の著作権法において親告罪とされているものについて、見直しが必要との指摘がある(注8)。
また、デジタル化・ネットーワーク化の進展といった急速な技術革新の中で大量かつ高品質の著作物の複製物が容易に作成・流通できるようになっていることから、これまで我が国の著作権法においては、侵害の抑止と著作権の適切な保護を図るため、累次の法改正により著作権法の罰則を強化してきており(平成18年法改正において、著作権侵害罪の法定刑は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に引き上げられている。)、著作権を取り巻く状況は、制定当時と比べて大きく異なっている。
このように、現在の我が国において、知的財産創造立国を実現する上で、著作権保護の必要性が強く認識されている状況に鑑み、著作権等の侵害の罪を親告罪とすることを維持することが適当か否か再検討する必要がある。
現行著作権法上、親告罪とされているのは以下のとおりである。
これらの罪が親告罪とされた制定趣旨は、次のとおりといわれている(注9)。
ア〜カについての保護法益は、著作権、著作者人格権、出版権、実演家人格権及び著作隣接権という私権であって、その侵害について刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当であり、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切であるためである。
キについての保護法益は、レコード製造業者がレコード製作者との契約によって得べかりし経済的利益であり、その侵害に対する刑事的責任の追及も、第一義的には、無断複製された商業用レコードの原製作者であり被害者であるレコード製造業者の判断に委ねることが相当であるためである。
クについては、秘密保持命令が、営業秘密を保護するための制度であるにもかかわらず、秘密保持命令違反の罪の審理は、憲法上の要請から公開せざるを得ないことから、その対象となった営業秘密の内容が審理に現れ、漏洩するリスクが想定される。このため、その起訴を営業秘密の保有者の意思に委ねているものである。
なお、非親告罪となっているのは、死後の人格的利益の保護侵害(第120条)、技術的保護手段を回避する装置・プログラムの公衆譲渡等の罪(第120条の2第1号及び第2号)、出所明示の義務違反(第122条)、著作者名を偽る罪(第121条)である。
親告罪の場合の捜査・訴追の手続(非親告罪の場合との差異)は、次のとおりである。
また、著作権侵害事犯の捜査については、一般的に、次のような手順により行われている。
捜査の過程においては、捜査の端緒が告訴・被害申告であるか否かを問わず、権利の帰属や内容等についての権利者からの事情聴取は当然行うべきものであるとともに、起訴便宜主義(注10)の下で、被害者にとっての被害感情や被害の重み、訴追意思は、公訴提起の要否の判断において当然重視されるべきものであり、一般に、被害者の意思と全く無関係に訴追が行われることはない。
(非親告罪である商標権侵害の場合でも、権利内容の確認や侵害事実の特定、許諾の有無等について確認して事件を立証していく上で権利者の協力は欠かせないものであり、捜査の実務上、権利者にその協力を求めるとともに訴追意思の確認についても考慮がされている。)
| 現行条文 | 罪となる行為 | 罰則 | 親告罪 | 公訴期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1項 | 著作権・出版権・著作隣接権の侵害(私的複製の例外違反、輸入・頒布(輸出)・プログラム・権利管理情報・還流防止対象レコードに係るみなし侵害を除く。) | 10年以下 1,000万円以下 |
7年 | ||
| 2項 | 1号:著作者人格権・実演家人格権の侵害(権利管理情報に係るみなし侵害を除く。) | 5年以下 500万円以下 |
5年 | ||
| 2号:営利目的による自動複製機器の供与 | 5年以下 500万円以下 |
5年 | |||
| 3号:著作権・出版権・著作権隣接権の侵害物品の頒布目的の輸入行為、情を知って頒布又は頒布目的の所持行為、業としての輸出又は業としての輸出目的の所持 | 5年以下 500万円以下 |
5年 | |||
| 4号:プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する行為 | 5年以下 500万円以下 |
5年 | |||
| 死後の著作者・実演家人格権侵害 | 500万円以下 | 3年 | |||
| 1、2号:技術的保護手段回避装置・プログラムの供与 | 3年以下 300万円以下 |
3年 | |||
| 3号:営利目的による権利管理情報の改変等 | |||||
| 4号:営利目的による還流防止対象レコードの頒布目的の輸入等 | |||||
| 著作者名詐称複製物の頒布 | 1年以下 100万円以下 |
3年 | |||
| 外国原盤商業用レコードの違法複製等 | 1年以下 100万円以下 |
3年 | |||
| 出所明示義務違反 | 50万円以下 | 3年 | |||
| 秘密保持命令違反 | 5年以下 500万円以下 |
5年 | |||
(両罰規定) |
第119条第1項若しくは第119条第2項第3号、4号又は第122条の2第1項の罪 | 3億円以下 | (注11) | (注12) | |
| 上記以外(人格権侵害罪も含む) | 各本条の刑 | ||||
特許権の侵害罪(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)については、第196条第2項において「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定され、親告罪となっていたが、平成10年の法改正により、非親告罪化された。その改正の背景としては以下のようなものがある(注13)。
なお、秘密保持命令違反罪については、特許法においても、著作権法と同様、その性質から親告罪とされている。
また、同様の理由で、実用新案権の侵害罪(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)、意匠権の侵害罪(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)についても平成10年の法改正により非親告罪化された(秘密保持命令違反罪については、同様に親告罪)。なお、商標権の侵害罪(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)ついてはかねてより非親告罪となっている。
種苗法の育成者権(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)については、平成10年の種苗法の全部改正以降、親告罪の規定は置かれなくなっている。この背景としては以下のようなものがある(注14)。
一方、半導体集積回路の回路配置に関する法律では、第51条第2項において、回路配置利用権の侵害罪(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)について、引き続き、親告罪が維持されている(注15)。
現在、欧米主要国において親告罪を採用している国はドイツとオーストリアである。ただし、ドイツについては訴追当局による職権関与が例外的に認められている。その他の欧米主要国において、著作権法上に親告罪規定を置いている国は見受けられなかった。また、韓国では、全面改正した著作権法(2006年12月28日公布、2007年6月29日施行)において、営利目的で常習して行われる著作財産権の侵害行為等のいくつかの場合を非親告罪化している。
| 第109条 | 告訴 第106条から第108条まで及び第108b条の場合において、その行為は、告訴があるときにのみ訴追される。ただし、刑事訴追当局が、その刑事訴追に関する特別な公共の利益を理由として、職権による関与を要するものと思料するときは、このかぎりでない。 |
| 第91条 | (侵害) |
| 3 | 訴追は、権利を侵害された者の告訴をまって行われる。 |
| 第140条 | (告訴) この章の罪に対する公訴は、告訴がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りでない。
|
一般に、親告罪とされる罪には、次の2類型が多いとされている。
これらの区分に著作権法の親告罪を当てはめてみると、秘密保持命令違反罪についてはAの類型に近いと考えられるが、それ以外の著作権侵害罪等については、Bの類型に近いものもあれば必ずしもそうでないものもある。これは保護の対象となる著作物等の範囲が広く、その利用態様や規模についても必ずしも営利を目的とせず零細なものから営利目的で組織的なものまで多様であるという著作権制度の特質によるものと考えられる(注19)。
知的財産立国を目指す我が国において著作権の保護は重要であることから、著作権侵害の罪等の法定刑も引き上げられてきたものであり、このような状況の変化を踏まえ、海賊版の組織的な販売等のように一見して悪質な行為については、国民の著作権に関する規範意識の観点から、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるという現状は適切ではないという意見や、法定刑を考慮した場合、著作権等の侵害が前述の「被害が軽微で、被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない場合」に該当するといえるのか検討する必要があるとの意見があった(注20)。
一方で、著作権等侵害は、組織犯罪的な侵害行為から学術論文等の不適切な引用等まで多様な形態で行われうるものであり、また、実態として、引き続き権利者が処罰するまでもないと許容しているような場合もあると考えられる。このような著作権の侵害態様の多様性や表現の自由に関わる面があることを踏まえ、引き続き、被害者の意思を尊重した方がよい場合があるのではないかとの意見があった。
財産権(著作権・著作隣接権)と人格権(著作者人格権・実演家人格権)とでは、保護対象が財産的利益か人格的利益かで異なっており、特に人格権侵害罪については、「訴追して事実を明るみに出すことにより、かえって被害者の不利益になるおそれがある場合」に該当する可能性があることから、財産権侵害罪と分けて考えるべきであるとの意見もあった。
非親告罪とした場合の実務上の問題や効果については、著作権等の侵害実態の調査等に時間を要する場合など、告訴期間(6ヶ月)の経過により告訴できないという事態を避けるべきであるとの意見や、非常に悪質な海賊版等については非親告罪にすることで規制の実効が上がるならば非親告罪の方が適当であるとの意見があった。
これに対して、非親告罪化することによって捜査実務に与える効果や影響に関して、捜査実務の観点からは、
などの意見があった(注21)。
著作権等の侵害行為のうち、侵害の性質等に照らし、海賊版の組織的な販売等の特に悪質な犯罪に関しては、捜査実態等を考慮した一定の条件下で非親告罪化することも考えられるとの意見があったが、この範囲について、
などの意見が出された。
以上のような意見を踏まえると、著作権等の侵害罪についての親告罪の範囲の見直しについては、著作権等侵害行為の多様性や人格的利益との関係を踏まえると、一律に非親告罪化してしまうことは適当でない。なお、例えば現行の犯罪類型のうち一部を新たな犯罪類型としてそれのみを非親告罪とするとの考え方もあるが、そのような要件設定が立法技術上可能かどうかという点や、非親告罪とした場合の社会的な影響を見極めることも必要であり、慎重に検討することが適当である。