| (1) |
問題の所在 |
| |
近年のデジタル技術の発達・普及に伴い、高品質な違法複製や違法送信のおそれが高まっている。一方で、著作物等の複製等を技術的に防止する手段も開発・利用されている。このような環境の中、平成8(1996)年にWIPO新条約 が採択され、「技術的手段(Technological Measures)」に関する規定が合意された。 が採択され、「技術的手段(Technological Measures)」に関する規定が合意された。
我が国においても、WIPO新条約の採択を受けて、平成11(1999)年の著作権法改正において、「技術的保護手段」に関する規定が整備された。同改正法では、違法複製等を効果的に防止するため、技術的保護手段は著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段とし、その技術を、「機器が特定の反応をする信号」を「記録媒体に記録し、又は送信する方式」に限定している。技術的保護手段の回避に係る罰則についても、「専ら」技術的保護手段の回避を機能とする装置・プログラムの譲渡等に限定している。
しかしながら、コピーコントロール機能にアクセスコントロール機能を付加した技術など、著作物の違法な複製や流通を防止するための技術は進歩しており、立法当時の状況とは異なってきているため、現行著作権法の技術的保護手段に関する規定との適用関係を整理し、規定の見直しの必要性の有無について検討する必要がある。
 |
著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT) |
|
|
| (2) |
課題に対する考察 |
| |
 |
「技術的保護手段」を巡る実態の変化 |
| |
平成11(1999)年当時、技術的保護手段の対象であるコピーコントロールとしては、SCMS 、CGMS 、CGMS 、擬似シンクパルス方式 、擬似シンクパルス方式 が、一方、アクセスコントロールとしては、DVDなどに用いられているCSS が、一方、アクセスコントロールとしては、DVDなどに用いられているCSS が開発・利用されていた。これらの種類はごく少数であり、機能も限定されていた。 が開発・利用されていた。これらの種類はごく少数であり、機能も限定されていた。
しかしながら、近年、これらの保護技術を組み合わせた技術が増加している。例えば、DVDにおいてCSSとCGMS等を重畳的に施したものや、DVD-Audioの保護技術であるCPPM 、DVD-Recorderの保護技術であるCPRM 、DVD-Recorderの保護技術であるCPRM 、デジタルインターフェースの保護技術であるDTCP 、デジタルインターフェースの保護技術であるDTCP 等が開発・利用されている。 等が開発・利用されている。
以上のように、コピーコントロール機能にアクセスコントロール機能を付加するといった保護技術の複合化は、無反応機への対応や技術破りによる違法な著作物の流通等への対抗のために必要なものであり、このような保護技術の複合化は、今後さらに進むと考えられる。
 |
|
Serial Copy Management System音楽CDなどに用いられている、デジタル方式の複製を一世代のみ可能とする技術 |
 |
|
Copy Generation Management System映画のDVDなどに用いられる、でじたる方式の複製を「複製禁止」「一世代のみ可能」「複製自由」の3通りに抑制する技術 |
 |
|
いわゆるマクロビジョン方式(映画のビデオテープなどに用いられる、複製をしても鑑賞に堪えられないような乱れた画像とする技術)Content Scramble Systemファイルデータを暗号化(スクランブル)し、暗号鍵を用いてスクランブルを解かなければ、再生を不可能とする技術暗号/復号鍵はライセンスを受けたライセンシーのみが利用できる |
 |
|
Content Protection for Prerecorded Media CSSを強化したもので、暗号システムの改良とハッキング対策が施されているContent Protection for Recordable Media記録・再生用の暗号化の仕組で、CPPMの暗号システムをベースとしている |
 |
|
Digital Transmission Content Protection IEEE-1394等を使って接続した機器間で認証とデータの暗号化を行い、コンテンツの伝送を保護し、不正コピーを防止する技術 |
 |
|
CGMSと同様の複製制御情報機能もあり、複製の世代管理も可能 |
|
|
 |
現行法制度の整理 |
| |
現行制度上、技術的な保護技術については、著作権法と不正競争防止法により立法的措置がなされている。
著作権法では、著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段として技術的保護手段が規定されている(第2条第1項第20号)。また、私的使用を目的とする複製であっても、技術的保護手段の回避により可能となった複製を行うことは権利制限の例外とされる(第30条第1項第2号)。さらに、技術的保護手段の回避のための専用機能を有する装置・プログラムを公衆に譲渡等を行い、又は、公衆の求めに応じて業として技術的保護手段の回避を行った場合には、刑事罰が科せられる(第120条の2)。
したがって、現行著作権法では、コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるが、放送のスクランブルなどコンテンツを暗号化し視聴を制限する手段(アクセスコントロール)は、視聴行為そのものはコンテンツの権利者に無断で行われたとしても「著作権等を侵害する行為」ではないので、技術的保護手段の対象外であると解されている。
一方、不正競争防止法では、「営業上用いられている技術的制限手段」の効果を妨げる機能を有する専用装置・プログラムの譲渡等を「不正競争」と規定し(第2条第1項第10号、第11号)、同行為に対する差止請求や損害賠償請求など民事的救済を定めている(第3条、第4条)。
不正競争防止法では、アクセスコントロール、コピーコントロールのいずれも「技術的制限手段」の対象となる。なお、この「不正競争」については、民事的救済は可能であるが、刑事罰の適用はない。
( ) ) |
「譲渡等」 |
| |
著作権法においては、専用装置・プログラムの公衆への譲渡・貸与、公衆譲渡等目的の製造・輸入・所持、公衆供与、公衆送信、送信可能化、回避サービスの提供(第120条の2)
不正競争防止法においては、専用装置・プログラムの譲渡、引渡し、譲渡等目的の展示、輸出、輸入、送信(第2条第1項第11号) |
| |
著作権法 |
不正競争防止法 |
| 民事的救済 |
刑事罰 |
民事的救済 |
刑事罰 |
| コピーコントロール |
回避を伴う私的複製 |
差止請求権
(民法上の損害賠償請求権) |
なし(第119条第1号括弧書き) |
なし |
なし |
回避専用装置等の「譲渡等」 |
(民法上の損害賠償請求権) |
3年以下の懲役
300万円以下の罰金(併科も可) |
差止請求権
損害賠償請求権 |
なし |
| アクセスコントロール |
回避を伴う私的複製 |
なし |
なし |
なし |
なし |
回避専用機器等の「譲渡等」 |
なし |
なし |
差止請求権
損害賠償請求権 |
なし |
|
|
 |
条約上の要請の検証 |
| |
条約上の要請としては、WCT、WPPTにおいて、「許諾」が必要な著作物等について「技術的手段」の法的な保護及び救済について措置を講じることが求められているが、その内容については、各国が判断することができる。
したがって、少なくとも「著作権等の支分権」に関して「法的保護」することが条約上の要請を充たすものと解される。さらに、条約上の要請を充たした上で、「技術的保護手段」の範囲及びその規制の対象を拡大することは、条約上許容され、各国の判断に任されている。
|
 |
各国の法制度 |
| |
欧州においては、EU著作権ディレクティブにおいて、技術的手段(Technological Measures)は、著作権もしくは著作権に関連する権利、又はsui generis権の権利者により権限を与えられていない行為を防止し又は禁止するよう意図された技術、装置、又は部品を意味しており、「効果のある」(effective)技術的手段の回避に対して、適切な法的保護を与えることとしている。アクセスコントロール、暗号化、スクランブル掛け、その他の信号改変、コピーコントロールのような保護方法等によって、権利者により著作物の利用が制御される場合は「効果がある」とみなす とされており、アクセスコントロール等の技術が著作権等の保護に効果がある場合は、法的保護を与えるべきと考えられるが、その範囲は必ずしも明らかではない。この指令を受け、イギリス とされており、アクセスコントロール等の技術が著作権等の保護に効果がある場合は、法的保護を与えるべきと考えられるが、その範囲は必ずしも明らかではない。この指令を受け、イギリス 、ドイツ 、ドイツ においては、同様の規定をおいている。 においては、同様の規定をおいている。
米国においては、「技術的保護手段を回避する」とは、「著作権者の許諾なく、スクランブルがかかっている著作物のスクランブルを解除し、暗号化された著作物の暗号を解除し、又はその他技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にもしくは損壊すること」とされている 。同法の趣旨として、スカイリンク事件判決 。同法の趣旨として、スカイリンク事件判決 においては、(「アクセス権」といった)新たな権利を創出するものではなく、回避装置が著作権法上禁止されている行為を可能としていることを証明しなければならないという判断が示されている。なお、DeCSS(CSSの解除プログラム)をインターネット上で配付した行為の違法性について争ったDeCSS事件においては、CSSについて、アクセスコントロールであり、かつコピー防止技術でもあるという判断を示している においては、(「アクセス権」といった)新たな権利を創出するものではなく、回避装置が著作権法上禁止されている行為を可能としていることを証明しなければならないという判断が示されている。なお、DeCSS(CSSの解除プログラム)をインターネット上で配付した行為の違法性について争ったDeCSS事件においては、CSSについて、アクセスコントロールであり、かつコピー防止技術でもあるという判断を示している 。 。
 |
|
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society 第6条 |
 |
|
英国 1988年著作権・意匠・特許法(CDPA)第296ZF条 |
 |
|
ドイツ著作権法第95a条 |
 |
|
米国著作権法第1201条(a)(3)(A) |
 |
|
Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.  04-1118 (CAFC. 2004);1201条(a)は、「著作権を侵害する、もしくは侵害を助長するようなアクセスを可能にする場合にのみ、「回避」を禁ずるもので、そもそも、同法は、(独立した「アクセス権」といった)新たな財産権を創設する法律ではなく、財産(著作権)の保有者に対しそれを守る新たな方法を提供するもの、すなわち著作権侵害責任を問う新たな訴因を提供するものに過ぎない。この場合、回避(又は不正売買)を主張する原告は、被告によるアクセスが著作権者の許諾を受けていないことを証明しなければならない。」と判示した。 04-1118 (CAFC. 2004);1201条(a)は、「著作権を侵害する、もしくは侵害を助長するようなアクセスを可能にする場合にのみ、「回避」を禁ずるもので、そもそも、同法は、(独立した「アクセス権」といった)新たな財産権を創設する法律ではなく、財産(著作権)の保有者に対しそれを守る新たな方法を提供するもの、すなわち著作権侵害責任を問う新たな訴因を提供するものに過ぎない。この場合、回避(又は不正売買)を主張する原告は、被告によるアクセスが著作権者の許諾を受けていないことを証明しなければならない。」と判示した。 |
 |
|
Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 111 F. Supp. 2d 294(S.D.N.Y.2000); “CSS, or Content Scramble System, is an access control and copy prevention system for DVDs developed by the motion picture companies, including plaintiffs.” |
|
|
|
| (3) |
現行法の適用関係 |
| |
現行の著作権法における「技術的保護手段」の「回避」に係る規制の範囲については、次の要件により対象が限定されている。
 |
定義(著作権法第2条第1項第20号) |
| |
・「電磁的方法」により、
・著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段であって、
・機器が特定の反応をする信号を、
・音若しくは影像とともに、
・記録媒体に記録し、又は送信する方式
|
 |
私的使用のための複製(著作権法第30条第1項第2号) |
| |
回避(信号の除去又は改変)
|
 |
罰則(著作権法第120条の2) |
| |
・回避を行うことを「専ら」その機能とする
・装置・プログラムの
・譲渡、貸与、製造、輸入、所持、公衆への提供、公衆送信、送信可能化 |
 〜 〜 の要件を充たし、現行著作権法において規制の対象になるものとして、SCMS、CGMS、擬似シンクパルス方式(マクロビジョン方式)といったコピーコントロールに対する回避専用装置・プログラムが挙げられる。 の要件を充たし、現行著作権法において規制の対象になるものとして、SCMS、CGMS、擬似シンクパルス方式(マクロビジョン方式)といったコピーコントロールに対する回避専用装置・プログラムが挙げられる。
また、CPPM、CPRM、DTCP、VCPS等のコピーコントロール機能にアクセスコントロール機能を加えた技術に対する回避専用装置・プログラムについては、解体・分解して、コピーコントロールの回避以外に実用的な意味のある機能を持たない部分がある場合はその部分は回避専用装置等として、現行法においても著作権法第120条の2により、規制の対象となると考えられる。なお、コピーコントロールの回避を行う過程と、アクセスコントロールの回避を行う過程が不可分である場合は、回避装置・プログラムについても、コピーコントロールの回避を専用として行う部分とは認められないことも考えられ、規制が及ばないという考え方もできる。しかしながら、現在のところ、そのような回避専用装置・プログラムが出回る状況とはなっていない。
他方、CSS、CAS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とはならない。しかし、現在では、DVDビデオにおいて、CSSだけではなくCGMSやマクロビジョンを付加することで、コピーコントロール機能の付加を行っている例もある。そのような場合には、コピーコントロールの回避に関しては、著作権法における技術的保護手段の規制が及ぶと解すべきである。
|
| |
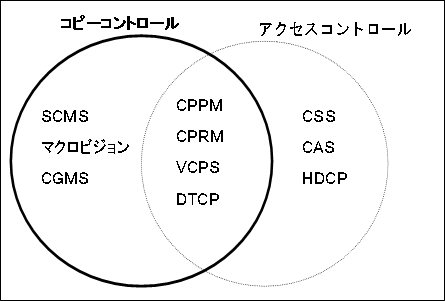
|
| (4) |
基本的な対応の必要性 |
| |
デジタル化・ネットワーク化に伴う権利侵害の危険性の増大に対応し、著作権保護をより強固にするためにコピーコントロールとアクセスコントロールを重畳的に施すような技術の複合化が進められているが、現時点では、複合化によってコピーコントロールに対する現行著作権法の規制の効果が減少するという事態は生じていないようである。
ただし、リッピングソフトを用いて暗号を解除し、DVDの内容をPCに読み出すことによって、コピーコントロールを無効化する場合もあるため、アクセスコントロール技術そのものについても、結果的に複製を抑止する効果があるという観点から、回避装置等について著作権法の規制の対象とすべきという意見もあった。しかし、著作権法の支分権の対象ではない「単なる視聴行為」をコントロールする技術的手段の回避を制度的に防止することは、実質的には視聴等の行為に関する新たな権利の創設にも等しい効果をもたらすという意見もあり、著作権法の趣旨、国際的な議論の動向、技術・法律・契約が相互補完的に機能すべき領域等について十分な検討が必要である。
したがって、現時点では、現行著作権法の技術的保護手段に関する規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかったが、今後も技術動向に注視しつつ引き続き慎重に検討し、平成19(2007)年を目途に結論を得るべきものとした。 |