ビジネスの視点を身につけたDX人材が育っている
導入を検討している先生へ

- 東 義信(あずま よしのぶ)先生 ビジネス情報科
-
本校のようにビッグデータの「RESAS」をデータサイエンスの授業で利用している高校は多いと思います。「RESAS」の活用方法には迷うこともあるでしょうが、オープンデータを簡単な操作でグラフ化できるなど、「RESAS」の利用は決して難しくありません。どんどん授業で利用してみるといいと思います。近年は、授業方法も変化してきています。生徒自身の気づきを促すよう、教員はファシリテーターとしての役割を担うことも大切です。
事例概要
- 実践している学校
-
岡山県立笠岡商業高等学校
- 実践している学科
-
ビジネス情報科1年
- 活用の場面・授業
-
学校設定科目「情報コミュニケーション」・データ分析「笠岡の特徴を捉えよう」
- デジタル教材等を導入したねらい
-
タブレットPCを用いてデータサイエンスを学ぶ学校設定科目「情報コミュニケーション」を実施。DX人材育成の観点から、自ら課題を見つけ、課題解決までのプロセスを経験し、科学的根拠(エビデンス)の重要性を生徒自身に気づかせることがねらい。
- デジタル教材等を活用した指導内容
-
地方自治体のさまざまな取組を情報面から支援するために、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局が提供する「RESAS」(リーサス、地域経済分析システム)を使用し、統計的な探究のプロセスを意識した授業を実施する。生徒は1人1台のタブレットPCを使用する。3、4人のグループに分かれ「笠岡市の観光」など地域性を活かしたテーマのなかから、グループごとに一つのテーマを選択。生徒たちはそれぞれ仮説を立て、「Googleスライド」を使用してお互いの意見を共有する。その後、必要なデータを収集するために「RESAS」や政府統計の総合窓口「e-Stat」や笠岡市のホームページにアクセスし、生徒たちの意見のエビデンスとしてグラフ化したデータを作成し、スライドに貼付する。また、データと自分たちの仮説を比較して総合的に分析してグループごとに発表する。
使用機材:タブレットPC、大型モニタ、HDMIケーブル、Wi-Fi環境
使用教材:Google Classroom、Google スライド、RESAS、e-Stat、市区町村のHP、PowerPoint
- 学習効果等
-
1年生の授業で、仮説を立てて、単なる予想だけでは得られない科学的根拠の必要性を学ぶことにより、2年生、3年生の授業においても、課題解決のためにデジタル教材を利用し、科学的根拠をもとに発表できる人材の育成ができる。
- 先生の感想
-
仮説を立て、データを収集し読み解いていく、という科学的根拠の必要性を学ぶ1年生の授業の成果が、2年生の「総合的な探究の時間」、3年生の「課題研究」をはじめ、あらゆる授業の発表で活かされている。ビジネスの視点、デジタルの視点を活かして課題を解決するDX人材が実際に育っているように感じる。
どんな授業を実践したのか
この授業ではデータの科学的分析をすることを重要視しています。特に、生徒たちに科学的根拠の必要性を気づかせたい、という意識のもとで授業を行っています。生徒はそれぞれタブレットPCを手に3、4名のグループに分かれ、笠岡市の第一次産業、第二次産業、第三次産業の産業別就業者数、日本人観光客数、外国人観光客数というテーマのなかから一つ選択します。テーマ決めのあとは、「笠岡市内で観光客がもっとも多い観光地は笠岡諸島の島々である」など、生徒たちが仮説を立て、あらかじめ用意していたグループごとの「Googleスライド」を使用してお互いの意見を共有します。
その後、必要なデータを収集するために、「RESAS」や政府統計の総合窓口「e-Stat」や、笠岡市のホームページにアクセス。仮説を確認するためのデータを収集していきます。
「RESAS」とは、地方自治体のさまざまな取組を情報面から支援するために、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局が提供する地域経済分析システムです。人口、産業、観光等の9つのマップから構成されており、産業構造や人口動態、人の流れなどのビッグデータをマップやグラフでわかりやすく表示できます。
生徒は集めたデータをスクリーンショットに収め、「Googleスライド」に貼り付けていきます。そのデータと自分たちの仮説を比較し、総合的に分析してグループごとに発表します。
この授業で重要なのは「仮説を立てること」です。仮説を立て、導き出したデータ結果を確認し、生徒たちが仮説の「意外なずれ」を見つけることで、科学的根拠の重要性を学びました。例えば、笠岡市内で観光客がもっとも多い観光地を「笠岡諸島の島々」と仮説していましたが、調べてみると実際には陸地部の道の駅がもっとも多いというデータが出ました。

まずは「RESAS」の利用方法から。生徒たちは自分のタブレットPCを利用して必要なデータを収集していく
どのような工夫をしたのか
「情報コミュニケーション」は新しい学校設定科目ということもあり、年間の指導計画を立てることにもっとも苦戦しました。生徒自身が課題と捉えたことをもとにテーマを設定し、仮説を立証していくうえで情報の収集を行います。そして課題を解決するためにどんなデータが必要なのかを考え、データを収集する方法を計画。実際にデータを集め、整理・分析を行い、「googleスライド」などに考察をまとめ、発表する。この発表までの一連の流れができさえすれば、他の科目でも応用が利くと思います。
本校では2023年度からDXを意識した授業に取り組んでいます。「DX」という言葉の意味を考えると、単にデジタル化を図るだけではなく、学校の授業においては自ら見つけた課題を解決する手段にデジタルを用い、変革を促していくことが一つの切り口であると考えています。
課題の解決には、「商業の見方・考え方」は欠かせません。本校では生徒がさまざまな課題解決に向き合うビジネスプランコンテストに出場し、受賞をしています。これまで、産業教育振興中央会、日本政策金融公庫などが主催のコンテストに出場しました。それらコンテストにおいても、課題解決手段としてデジタルの活用が必要になる場面もあります。ビジネスの諸課題を、デジタルを活用して解決する」という点で考えると、本校における学びとコンテストの取組が有機的につながっているように思います。
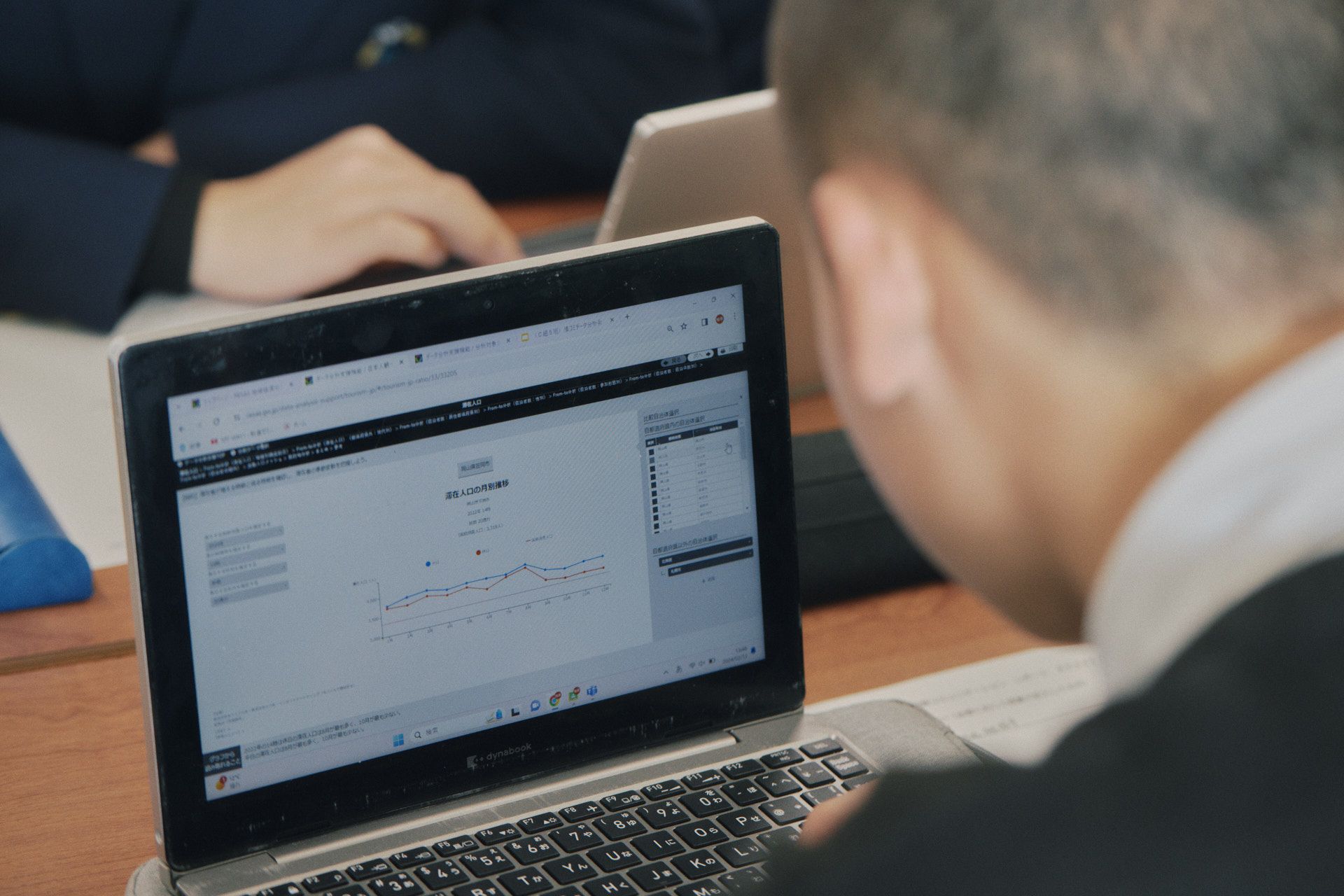
「RESAS」を利用して、仮説から必要なデータを導き出す。生徒たちはデータを比較しながら結果を読み解いていく
どのような苦労を、どのように乗り越えたのか
当初、「RESAS」の使い方について不明な点が多く、とても苦労しました。「RESAS」はビッグデータではありますが、そのデータは最新版ではありません。そのため、最新の人口動態を知りたい場合は、市区町村のデータを利用します。情報の収集は「RESAS」だけでなく、「e-Stat」や市区町村のホームページに掲載されているデータを比較するようにしています。
生徒たちはデータの読み解きを「思い込み」で考えていることが多くありますが、教員からは「間違ってもいい」と声をかけることで、生徒は積極的に仮説を立てていけるようになります。多くの生徒が仮説を立てられない場合は、教員が教室を回りながらヒントを出していきます。仮説を立てたら、生徒は実際のデータ(科学的根拠)を調べます。そして、自分たちが立てた仮説との違いに気づいていきます。
例えば、今回の授業では、笠岡市隣の地域である岡山県里庄町の製造業にまつわるデータを調べた生徒から、「へえ、里庄はこんなに少ないんだ!」という声があがっていました。これは生徒が「笠岡市は里庄町よりも製造業が少ない」と仮説を立てていたためです。この声が聞けた時点で、わたしは授業の目標を達成できたと思いました。このような声を拾うために、席を歩き回りながら聞き逃さないようにしています。

人口などの統計は市区町村のデータのほうが最新版となる。生徒たちはひとつのデータソースだけに頼らず、いくつかのソースを比較しながらデータ収集し、最終的な科学的根拠として発表に利用するとことを自然と身につけていく
生徒にどのような学びの効果があったのか
1年生で学んだ科学的根拠の必要性を、2年生の「総合的な探究の時間」を中心にすべての科目の授業や、ビジネスプランコンテストの取組などで活かしている様子を見ると、本当に嬉しく、やりがいも感じます。1年生のときに情報活用能力を培い、知識や技術を習得した経験が、2年生になったときに誰からも指示されることなく主体的に学習に取り組む姿勢につながっていくと感じます。
筋道を立てて論の展開をするためには、仮説を立てることが重要です。仮説を立てると、それを検証するために自然に調べるようになります。調べたことを説明するには、数値データなど科学的根拠に基づいて発表することになり、相手が納得しやすくなるのです。
科学的根拠の必要性を学ぶことは、高校を卒業したあとも、社会に出てからプレゼンをしたり、取引先と交渉したりするときに活かされると思います。ビジネスの視点(商業の見方・考え方)やデジタルの視点を活かして課題を解決するDX人材が確実に育っているように感じます。

生徒たちが迷っていると、ヒントを出しに行く。また生徒たちがぽろっと発した発言にも「気づき」が多いので、聞き逃さないようにテーブルを回るようにしている
先生にはどのような意識の変化があったか
以前のように黒板に板書して教えるような授業が減少しているように感じます。
今回、取材をしていただいている授業は、はたから見ると生徒が自由に活動しているだけに見えるかもしれません。しかし、生徒たちが何を考えて、何を見ているのか、何を話しているのかをきちんと観察しながら教員がファシリテーションをしています。教員はファシリテーターとして、「グループの中で必ず誰もが一度は発言する」というルールを決めるなどして、発表の経験を積ませていきます。
「主体的・対話的で深い学び」を充実させるための授業をどう展開していくか考え、実行することは本当に難しく、先生にとって課題となる部分です。ですが、社会で通用する技術を培うためにはとても重要な要素だと感じています。そのため、より良い授業を目指して、AIやデジタル機器をどのように活用していくか、教員同士で勉強会を行うこともあります。
授業の目的を考え導きたい方向に生徒を導きながらも、予想外の驚くような答えをする生徒もいますから、教員自身も発見があり、生徒から気づかされることが多いです。生徒の「意外性」を発見できることが、この授業のいい点だと思います。
※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。
※本記事の情報は取材時点(2024年2月)のものです。






