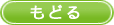はじめに
新法人作業部会は、動燃改革検討委員会報告書(以下「委員会報告書」という。)を受け、平成9年8月に発足した。爾来、動燃改革の具体化に向け、現地調査も実施しつつ検討を進めてきたところであるが、新法人の骨格ともいうべき基本構想の大枠がまとまったので、これまでの作業の結果をここに中間的に取りまとめた。当作業部会としては、今後、さらに検討を重ね、来春を目途に成案を得る予定である。
当作業部会での検討を開始するに当たって、最初に留意した点は、作業の前提と作業の範囲についてである。当作業部会は委員会報告書を受けて発足したものであるから、当然のことながら、そのいずれについても委員会報告書の指示するところに従うことが出発点になる。
作業の前提に関していえば、動燃自らの意識改革や自己改革の問題と、動燃を指導監督する科学技術庁及び動燃の使命を決定する原子力委員会と動燃改革との関連の問題の2点がある。
委員会報告書にあるように、「動燃は解体的に再出発する」とともに、新法人は、「動燃に蓄積された人材・技術・ノウハウ等を最大限に活用しつつ」その事業の大部分を継承することになることを考えれば、動燃自らの意識改革と自己改革が新法人の設立に先立って徹底的に行われなければならず、それが新法人設立の必要条件でもある。組織の改革を通して職員の意識改革を図ることは決して容易なことではないが、逆に、そのような困難な作業に成功した場合にこそ真の改革がもたらされるということも他に例がみられる。本基本構想の立案に当たっては、現在、動燃自らにおいて行われている改革活動が実効を上げるとともに、新法人が動燃の業務、人材、施設や設備等を継承する上で次のような条件が満足されることを前提としている。
-
1)動燃は、新法人への移行までの間に、役員及び職員の意識改革のための施策を具体的に立案しそれを実行するとともに、その事実を国民に向け発信し、自己改革の進展について国民の理解が得られるよう努めること。
2)動燃は、現在実施している業務内容を全面的に点検し問題点や将来の課題等を抽出するとともに、各部門ごとにそれらに対する具体的な対応計画を策定した上で業務引継書を作成し、新法人への引き継ぎの準備を進めること。また、ウラン探鉱、ウラン濃縮及び新型転換炉開発の3つの整理縮小事業については、関係方面と協議の上、整理縮小計画を策定し新法人に引き継ぐよう準備を進めること。
3)特に、安全関係については、動燃は、自らによる安全性総点検と新法人タスクフォースによる現地調査の結果等を踏まえ、施設・設備とその管理・運営等に関し、改善すべき点は改善し、残された課題については明確な改善計画を策定して新法人に引き継ぐよう準備を進めること。
つぎに、当作業部会の作業の範囲に関しては、作業の結果が、逆に、委員会報告書で指摘されている「新組織の裁量権の拡大」にとってマイナスにならないようにしなければならない。新法人の基本構想を示すに当たっては、ある程度は具体的な姿を描かなければならないことから、本来は新法人の裁量権に委ねられるべきことについても言及せざるを得なかったところがあるが、基本的には、委員会報告書によって与えられた指針、すなわち「新組織に想定される体制」をもとにその作業の範囲を特定した。
当作業部会に負託されたことのひとつに、平成9年12月中に予定されている平成10年度の概算要求の政府原案の確定と新法人の設置に関わる法案の作成に当たって必要となる関連事項を検討することがある。特に、本報告書の大きな目的はその点にある。新法人が重点的に取り組むべき事業、事業計画の策定方法等の経営の要件、新法人の組織体制の3点に関し本報告書が言及しているのはそのためである。なお、委員会報告書において整理縮小すべきとされた事業に関する具体的検討は地元との関連等があることから、当作業部会の作業の外とされている。また、日本原子力研究所をはじめとする関係機関との事業の分担や協力の具体的方法についても、当作業部会の作業の範囲を超えているものと判断したが、それらについては、新法人の事業計画に少なからず関係することから、関係機関の間や原子力委員会の場で早急に検討されることを期待したい。
委員会報告書に示されている改革の要諦は、一言でいえば「経営の不在」の解消であり、そのために、経営者の強力なリーダーシップと組織としての使命の国民への発信の重要性が指摘されている。国の法人は国の予算の下で運営されるため種々な指導と監督の下におかれるのは当然である。その下でという制約はつくものの、経営に最大限の裁量権を与えるべきであるという委員会報告書の勧告は、反面においてそれだけ組織に大きな責任が課せられているのであり、それが国民に対する使命の発信義務であることを併せて含意するものと、当作業部会は理解した。
新法人は、安全性に関し特別の配慮を払いつつ競争力をもつ核燃料サイクル技術の研究開発に取り組むことを負託されている。とくに安全確保や危機管理の面で社会的に大きな責任を負っているのであり、この点は、新法人の特殊性ともいってよいであろう。この点での社会的責任に問題があったことが動燃改革の直接的動機であったことを想起すれば、新法人においては、その原因の本質的除去を目指して、社会要請への感受性とアカウンタビリティの高い運営組織とし、社会に開かれた体制への自己改革をいわば自律システム化できる組織とすることが不可欠であり、そのためには、国民との双方向の情報交流にとくに努める必要があることを、本報告書では強調した。
新法人の中核的な研究開発課題は、高速増殖炉及び関連する核燃料サイクル技術とサイクル廃棄物の環境保全技術の2つの分野に集約されるが、いずれの分野も21世紀に向けた長期的課題であり、新法人は、関連する動燃の事業を継承しつつ長期的展望にたってこれらの課題に取り組む必要がある。ここでの長期的展望とは、大競争時代の到来や環境主義の台頭という世界的趨勢に加え、財政事情の逼迫化等の国内情勢の変化を視野に入れてという意味であり、動燃のこれまでの事業の進め方では、このような状況の変化に対応できていないという指摘が委員会報告書にあることを忘れてはならない。新法人においては、このことを十分に自覚し、新しい事業展開を図る必要があることも、本報告書が強調した点である。