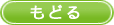第2部 新法人の経営
新法人の経営については、委員会報告書で指摘されている「経営不在」の本質的除去を目指し、事業計画の策定プロセスとその執行における裁量権を明確化するとともに、国民に対し常に組織としての使命等を発信することに努め、また、外部評価メカニズムを導入するなどにより、経営の透明性やアカウンタビリティを確保することを基本的な要件とする。
なお、現在、国において独立行政法人の検討が進められているが、その制度設計には新法人の経営を検討する上で参考となる点が多々あることから、今後、国の検討状況を踏まえつつ、取り入れるべき点については積極的に取り入れていくこととする。
- 経営の要件
新法人が具備すべき経営に関する基本的な要件として以下を提案する。
(1) 事業計画の策定
1)国から与えられる事業目標等
新法人の事業目標は、原子力委員会で定められる「原子力開発利用長期計画」等を踏まえ内閣総理大臣が原子力委員会の議決を経て策定する「基本方針」等において明確化されることが重要であり、その内容としては、例えば、事業実施に係る基本的方向、事業の研究開発目標、その他事業運営に係る配慮事項等が考えられる。
2)中長期事業計画
- 基本方針を踏まえ、理事長は、自らの責任と裁量の下に5か年程度の「中長期事業計画」を策定する。中長期事業計画には、個々の業務の計画、内容等を極力客観的な形で記述する。
- 科学技術庁は中長期事業計画を極力尊重する。
- 理事長は、自らの裁量の下に、時々の状況を踏まえつつ柔軟に中長期事業計画を見直す。また、経営審議会(後述)は、必要と判断される場合、中長期事業計画の見直しを理事長に対し意見具申することができる。理事長はこの意見具申を尊重し、中長期事業計画を見直し、結果を科学技術庁に報告する。
- 理事長は、中長期事業計画に基づき、毎年度「事業年次計画」を策定し、経営審議会及び科学技術庁に報告する。
(2) 理事長の裁量権と業務の評価
1)業務の執行
明確な中長期事業計画の策定を前提に、業務の執行については最大限、理事長の裁量に委ねる。このため、科学技術庁は、業務執行への関与は必要最小限とするとともに、必要な場合であってもその関与の範囲を可能な限り明確化した上で行う。
2)評価・監査
- 理事長は、外部評価の一環として、毎年度の業務の執行結果と中長期的な事業の達成状況について経営審議会に報告し意見を聞く。また、理事長は、その結果を科学技術庁に報告する。
- 科学技術庁は毎年度の業務の執行結果等に関して業務監査を実施する。
- 新法人は内部的にも監事の監査の支援機能を強化する。
(3) 経営の透明性確保
1)経営審議会
- 経営の透明性と社会性の確保とともに経営に対する外部評価メカニズムを導入するため、理事長の諮問機関として「経営審議会(仮称)」を新法人に設置する。
- 経営審議会は、理事長の諮問を受け、経営に関する重要事項について審議し、意見を述べる。
- 経営審議会は、必要に応じて理事長に対し意見具申を行うことができる。
- 経営審議会のメンバーは、広く各界の人材で構成し、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
- 経営審議会の審議結果は公表する。
2)研究開発の外部評価
新法人においては、民間等外部の専門家による外部評価委員会を設置し、研究開発の事前・中間・事後の専門的評価を実施する。その際、民間ニーズやコスト意識の観点からの評価に配慮する。
3)公開シンポジウムの開催
新法人は、組織としての使命を国民に対し常に発信し意見を聞くため、公開シンポジウムを定例化して開催する。シンポジウムにおいては、事業の成果等を公表し国民に広く意見を求め、双方向の情報交流を行う。
(4) 経営理念等の明確化
1)経営理念の周知
経営理念は、新法人の使命に基づく法人存続の基礎とも言うべき概念であり、新法人においては、経営理念を極力わかり易い形で定め役職員をはじめ内外への周知を図る。
2)経営方針の明確化
理事長は経営方針を定め役職員に徹底させる。理事長が交代した場合、また必要に応じて、理事長は経営方針を見直し、状況の変化に柔軟かつ適切に対応する。
3)事業計画の徹底
目標管理制度等を活用し、個々の職員に中長期事業計画、事業年次計画を徹底させるとともに事業年次計画を個々人のレベルまでブレークダウンし業務の範囲と目標を明確にして、職員の責任と意欲のある業務遂行体制を確立する。
(5) 経営による安全強化
新法人においては、安全確保と危機管理を経営の最優先とし、理事長を頂点とする責任体制を明確化する。特に、事故や異常が発生した場合、原因究明のための事故解析を徹底するなど事故に学ぶという姿勢を貫くとともに、報告義務の履行や情報の公開を徹底する体制を整備する。更に、一般防災の面や社会性等も考慮した安全思想の再構築を図る。また、運転管理部門を中心に安全確保と危機管理に必要な資源を事業計画において確保するとともに、その最適配分を行う。併せて、業務品質保証活動等を通じ、安全確保と危機管理に関する業務の継続的な向上を図る。
- 経営の機能強化
経営の機能強化について、その実現に向けた具体的方法は一義的に新法人の理事長に委ねられ理事長の裁量で柔軟に見直されるべきものであるが、新法人発足時の基本的な強化策として以下が考えられる。
(1) 経営体の機能強化
1)新たなリーダーシップ
新法人は、大幅に経営陣を刷新し、責任ある強いリーダーシップの下に再出発する。
2)理事会議の強化
- 専門性に配慮し広い分野からの非常勤理事を積極的に活用するとともに理事会議の運営を強化する。
- 理事長は、経営の最高責任者であり全ての決裁権者であるが、規程で定める重要事項については、理事会議に諮り、了承を得るものとする。
3)理事の機能強化
新法人の経営に係る事業所横断的な業務を担当する経営企画、安全推進等の部門は本部制とし、また、現場責任の重視の観点から各事業所の長の権限を強化し、これらの長には極力理事クラスを充てる。
4)経営に関する企画調整機能の強化
全事業所横断的な経営に係る企画調整機能等の強化のため、「経営企画本部(仮称)」を設置する。
(2) 職員の意識改革
職員の意識改革は、動燃改革の極めて重要な要素であり、職員のみならず役員においても継続的な意識改革の努力がなされるべきであり、特に、管理職の責任感の醸成が極めて重要である。意識改革は、個々人が経営方針を共有し、自ら分担する業務の輪郭が明確な中で自己の責務と裁量を自覚することを前提とし、業務品質保証活動と相まって、社会的使命感、状況変化への感受性、自己革新を可能とする前向きな姿勢を形成することを目標とする。
1)徹底した教育研修の実施
- 新法人においては、役員との意見交換を通じて経営方針の共有を目指す全職員を対象とした「目標意識共有化研修(仮称)」や管理職研修等の各種研修制度の充実とともに、外部との人材交流も含め外部研修に積極的に参加させるなど、自己革新の意欲の醸成や学習機能の強化を図る。
- また、管理職は、職場における日常の業務遂行を通じての教育(OJT)プログラムを作成し、職務遂行上必要な技能・知識のみならず、職務に取り組むにあたっての姿勢・考え方・心構え等を含む教育指導を行い、職員の意識改革を図る。
2)人事評価への反映
意識改革にインセンティブを付与するため、目標管理制度の導入により個々の職員の目標達成度を明確化するとともに、結果を人事評価に反映させる。
3)人事交流の推進
職場環境に開放性を確保し意識改革の触発の機会を与えるため、新法人においては、人事交流計画を策定し、外部及び部門間の積極的な人事交流を実施する。
(3) 人事管理
1)管理職人事制度の刷新
- 動燃においてマネージメント能力の向上が課題となっていることから、新法人においては、能力主義に配慮しつつ管理職の体制を見直し、管理職に昇任・昇格試験制度を導入するとともに厳しい管理職研修等を実施する。
- 管理職の給与については、ラインとスタッフといった業務の特性に配慮し、責任と成果・貢献に応じた処遇が行われるよう給与体系を見直す。
- 職場に活力と適度な緊張感を付与するため、課長級以上の管理職の相当数について恒常的に外部との人事交流を実現するとともに積極的に優秀な若手を登用する。また、管理職には豊富な経験と広い視野が求められることから、外部出向を管理職育成のキャリアパスの一つとして位置づける。
2)人材育成指針の策定等
人事管理は、人を育てることが極めて重要な要素であり、新法人においては、まず「人材育成指針」を策定する。この指針に基づく計画的な人材育成を行うとともに適材適所の人材配置を行い、業務の特性に応じた新たな人事評価制度を導入する。
3)業務特性に配慮した処遇
動燃においては、当直長の権限を明確にしその任に見合う処遇を与えること、また、研究者、事務系職員等の職種の特性を人事評価に反映させること等が求められている。新法人においては、業務特性に配慮し、責務と人事評価に応じた新たな給与制度の導入とともに、当直長の処遇改善、特にスタッフ系技術職員の活用に留意した昇進ルートを設定するなどの複線型のキャリアパスの導入等により、各部門、各職制の職員全員が高いモラルと責任感を持って仕事に向かうインセンティブを付与する。
(4) 業務品質保証活動の強化
新法人においては、業務の高い「質」を組織的に継続して確保するため、業務の改善活動及び改善成果を管理システムとして定着・維持させることを目標に、経営者自らが業務を診断していくなど業務品質保証活動を強化・推進するとともに、各事業所の部門毎にISO9000シリーズ等の認証を目指すなど活動の拡充を図る。