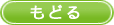第1部 新法人の事業
新法人は、委員会報告書に示されているように、競争力を持つ将来のエネルギー源としての核燃料サイクルを確立することを目指し、世界の諸情勢の変化に対応して、その研究開発の成果が適切に活かされることを目標とする。すなわち、安全確保、環境保全及び国際協調を前提に、将来世代の人類に役立つ技術を提供していくことが事業の目標である。
与えられた経営資源の下にこの目標を達成していくために、新法人においては、整理縮小を含め柔軟な事業計画を策定し、競争力ある技術にとって本質的に重要な枢要技術を特定しつつ研究開発に取り組むなど、計画の最適化を図る。
新法人は、短期的には動燃の事業を継承し安全確保と環境保全に留意しつつ事業の円滑な移行を図る必要があるが、中長期的には競争力ある技術の開発に向けて着実に成果が上げられるよう展望を持って研究開発を進める。
また、新法人は、事業の内容に関し国民に対し説明することに特に努め国民の理解を広く得るとともに、国内外の状況の変化を的確に把握しつつ、社会の要請に適切に対応した研究開発成果の技術移転を図る。
以上を基本とし、新法人の事業の考え方を以下に示す。
- 事業の重点化
動燃の事業が肥大化しているとの反省に立って、委員会報告書に沿って動燃の事業を見直すとともに、高速増殖炉懇談会報告書(以下「懇談会報告書」という。)に示された方向性を踏まえて、新法人の事業を以下のとおり重点化する。
1)高速増殖炉とそれに関連する核燃料サイクル技術の研究開発
新法人が担当する本分野の研究開発は、高速増殖炉、その燃料製造及び使用済燃料再処理から構成され、プルトニウムをいわば中間媒体として、ウラン資源の利用効率の飛躍的向上を図り、資源のリサイクルによる資源保護を実現する原子力の技術体系の確立を目指すものである。
更に、新法人においては、核燃料サイクルの環境への負荷の低減等の社会的ニーズに対応した研究開発を行うことも重要であり、「原子力開発利用長期計画」においてこの観点から有効とされているマイナーアクチニド燃焼等の新たな領域の研究開発に着実に取り組む必要があり、その具体的な進め方については、原子力委員会における検討を踏まえる。
[高速増殖炉に関する研究開発]
高速増殖炉に関する研究開発には、プラント運転管理技術、燃料技術、材料技術、システム設計技術、ナトリウム技術等の課題があり、「常陽」、「もんじゅ」を最大限に活用しつつ研究開発を進める。懇談会報告書において、高速増殖炉の実用化が予定の路線とされていた従来の考え方から脱却して、その将来は新法人による研究開発成果によって決まるとの考え方が明確にされたことを踏まえ、高速増殖炉の研究開発における新法人の責任と役割が、現在の動燃より一層重くなったと受け止めることが重要である。
[高速増殖炉に係る核燃料物質の研究開発]
新法人は、「常陽」、「もんじゅ」の燃料製造を中心に高速増殖炉に係る燃料の研究開発を実施する。なお、新型転換炉の燃料製造に関しては、「ふげん」と連動して整理縮小し、燃料製造施設の廃止措置に関する研究開発に移行する。
[核燃料物質の再処理に関する研究開発]
新法人は、高速増殖炉の使用済燃料の再処理を中心とした核燃料物質の再処理に関する研究開発を実施する。軽水炉の使用済燃料の再処理については、実用化段階に達しつつあることから、新法人においては、民間への技術移転を進めるとともに、民間事業を支援しこれに協力する役割を担うことを重視しつつ必要な研究開発を進める。この観点から、東海再処理工場の軽水炉燃料再処理への活用については、六ヶ所再処理工場が安定的に操業を実施する段階まで役務運転を継続するが、その際、人材の移転を含めた関連する技術移転の積極的な推進や、人材の養成訓練等の重要な役割に十分配慮して運転を行う。なお、その後の東海再処理工場の活用に関しては、施設の老朽化対策等安全性に十分配慮しつつ、施設運営の効率性の観点を含め検討することとする。
2)サイクル廃棄物環境保全技術の研究開発
[放射性廃棄物の処理処分に関する研究開発]
核燃料サイクル技術は、地球環境対策または環境保全の面から、固有の優れた環境調和性を潜在的に有しているが、一方において、放射性廃棄物の発生を伴う。この放射性廃棄物の安全な管理と処理処分の技術を確立することが核燃料サイクルに不可欠である。委員会報告書は「高レベル放射性廃棄物処理処分の研究開発」を中核的事業とするとしているが、新法人では、これを中心に超ウラン元素(TRU)を含む放射性廃棄物も含め、サイクル廃棄物環境保全技術の研究開発を進める。
[施設の廃止措置に関する研究開発]
将来運転を終え廃止を迎える原子力施設が数多く存在することから、安全性と経済性に配慮した解体技術の研究開発等が極めて重要な課題となっている。新法人は、ウラン濃縮、新型転換炉開発からの撤退に伴い、濃縮原型プラント、「ふげん」の廃止措置を行う必要があるが、これらは、有用資材のリサイクルや廃棄物の低減を含めて、安全で効率的な廃止技術の研究開発に貴重な場を提供するものであり、また、新法人が所有するいずれの施設も将来的には必ず廃止措置を必要とすることから、新法人においては、こうした場を最大限に活用し、積極的に原子力施設の廃止措置に係る研究開発に取り組む。
3)対外的支援協力事業
[技術移転等の成果の普及]
新法人においては、事業の成果を円滑に技術移転していくとともに、社会に開かれた事業展開を図ることが重要である。このため、民間のニーズの把握、他の研究開発機関及び民間との緊密な協力関係の構築等に配慮しつつ、人的支援も含め効果的かつ効率的に技術を移転するとともに、要素技術等の一般分野への技術展開を目的とする成果の普及事業を推進する。
[施設の大学等一般への開放]
新法人においては、その施設・設備は極めて固有かつ貴重なものであることを踏まえ、自らが所有する施設・設備を、原子力関連分野は当然のこととして、更にそれ以外の分野も含めて、大学等広く一般の科学技術の研究者・技術者に開放し、貴重な研究開発の場として提供する。
[国際協力]
委員会報告書にもあるように、新法人は事業を進めるに当たって、平和利用技術の国際研究協力等国際貢献に積極的に取り組み、核不拡散にも配慮しつつ、核燃料サイクルの世界的な研究開発の拠点となることを目指す。特に、懇談会報告書では、「もんじゅ」を高速増殖炉研究開発の場として内外の研究者に対して広く開放していくことの重要性を強調している。このため、新法人においては、上記の各研究開発の分野を中心に、安全や危機管理に関する情報交換や核不拡散を含め、国際協力を積極的に行う。
- 整理縮小事業
新法人は、海外ウラン探鉱、ウラン濃縮及び新型転換炉開発の3事業については、それぞれ動燃が策定する整理縮小計画を引き継いでそれに沿って事業を整理していく。その際、これまでの研究開発の成果が最大限に活かされるよう、十分な成果の取りまとめを行うとともに、技術、人材の移転の促進を含めた対応が必要である。
- 海外ウラン探鉱については海外事務所の整理と得られた権益の扱い、ウラン濃縮については機微技術の管理を考慮した濃縮機器の廃棄技術の研究開発、新型転換炉については「ふげん」を活用した廃止措置技術の確立とともに、これらに関連した他の事業所の業務の見直し等が課題となる。
- また、動燃の事業のうち、委員会報告書において新法人には馴染まないとされた基礎研究については、適切に評価した上で、日本原子力研究所等の他機関へ移管するか、または中止することとし、特に業務の移管に当たっては人材の移転も十分に考慮する。この基礎研究には、加速器を用いた消滅処理研究、ビーム利用研究等が含まれる。
- 事業の進め方と事業の合理化
委員会報告書に指摘されているように、「競争力ある技術」の確立を目指し、厳しい財政事情の下に着実にその成果を上げていくためには、新法人においては、「競争力ある技術」にとって本質的に重要な開発課題を枢要技術として特定し、その研究開発に重点的に取り組むとともに、国内外の人的資源や技術、ノウハウを有効に活用する観点から、他の研究機関や研究者等との協力、共同研究等を積極的に進めることが必要である。
(1) 枢要技術への重点化
- 委員会報告書は、5か年程度の期間をカバーする中長期事業目標を定めて開発レベルを着実に向上させていくべき旨を指摘している。限られた予算の下にこれを実行していくため、それぞれの事業目標に即して枢要技術を選定し、その開発に優先的に取り組む。
- 枢要技術の選定に当たっては、原子炉と核燃料サイクルの全体を俯瞰するとともに、開発レベルの進展と取り巻く状況の変化を的確に把握する。更に、他の産業分野における先端的な技術進歩や最新の開発方法を積極的に導入するなどにより、十分なコスト意識をもって研究開発を進める。
(2) 外部研究人材の活用
- 関連する研究開発が他の民間を含めた研究機関で実施されており、それらの機関との協力が有効と考えられるものについては、所有する施設の開放や人的交流をはじめ、委託研究や共同研究を積極的に進める。
- 特に、基礎研究に近いレベルで他機関との連携が重要な課題については、大学における原子力研究の活性化を促す上からも、大学との緊密な協力や共同研究を進める。
- 更に、大学等の研究者の集中的な施設利用や協力が必要となる場合は、任期付任用制度の活用とともにプロジェクト型の研究プログラムを実施する。
(3) 合理化目標の設定
新法人においては、新法人が動燃から継承する業務に必要な人員については、事業の整理縮小または移管、人員を含めた技術移転、安全面からの人員確保、六ヶ所再処理工場の運転状況等を踏まえ、今後10年から15年間程度にわたった長期展望の下に、人員の大幅削減を目指す合理化の目標を定めることとし、また、新法人が実施すべき業務のうち今後新たに展開すべき業務については、厳しく評価した上で適切な人員の規模を確保する。
- 事業計画
新法人においては、後述するように、新法人の発足後、理事長は、その裁量の下に早期に「中長期事業計画」を策定する必要がある。当初の移行期間は動燃の業務を引き継いで実施することも止むを得ないが、職員に新しい目標を与えることが重要であり、自らの事業計画をつくることが新法人の経営陣の最初の仕事となる。その際、以下について十分な配慮を必要とする。
- 委員会報告書では、新法人における意識改革の基本は「役員においても職員においても、自ら分担する作業の輪郭を明確にすること、その輪郭の中では十全の裁量を持ち、従って完全な責任を担うことである。それに加え、それを第三者に明快な説明をすべく常時準備しておくことが必要である。」としており、新法人の中長期事業計画の策定がその出発点となる。
- 中長期事業計画には、整理縮小事業も含め、事業目標の達成に必要な個々の事業計画が資金、人員の点から第三者に客観的な形で明示される必要がある。現在の動燃の資源配分のあり方を抜本的に見直し思い切った重点化を図るとともに、安全確保、廃棄物管理、メンテナンス等に十分配慮した計画とすることが重要である。