課題番号:1810
京都大学防災研究所
次の南海地震に向けた応力蓄積過程の解明
次の南海地震に向けた応力蓄積過程の解明には、GPSやひずみ計を使った地殻ひずみの長期連続観測や、地殻応力の繰り返し測定が不可欠であると考える。そして本課題は、このような観測の一環として、ボアホールをつかった地殻ひずみの観測法を確立し、さらに近畿圏にボアホール・アレーを構築し、長期的かつ連続的なひずみの精密観測を行うことをめざしている。いっぽう、近年の研究により、地殻ひずみをモニターするときには、岩盤の間隙水圧も同時にモニターして、ひずみと間隙水圧の相互作用を間隙弾性論的なフレームワークで解釈しなければ、地殻の(応力)状況を正確にモニターできないことが強く示唆されている。さらに本研究では、これらの測定を補完・サポートするための測定として、重力の長期的な変化を繰り返し測定する。
![]() すでに実施している神岡鉱山の坑内サイトのボアホール井戸での高精度間隙水圧の観測を継続するとともに、そのアレー化をはかり、それぞれのボアホール井戸の大気圧応答、地震波応答、地球潮汐応答を総括的に観測・解析し、岩盤の間隙弾性定数を求める。
すでに実施している神岡鉱山の坑内サイトのボアホール井戸での高精度間隙水圧の観測を継続するとともに、そのアレー化をはかり、それぞれのボアホール井戸の大気圧応答、地震波応答、地球潮汐応答を総括的に観測・解析し、岩盤の間隙弾性定数を求める。![]() 名古屋大学瑞浪地殻変動観測所に設置した新設計のボアホール型たてひずみ計については、サンプリング周波数を20Hz(ヘルツ)に向上させる。
名古屋大学瑞浪地殻変動観測所に設置した新設計のボアホール型たてひずみ計については、サンプリング周波数を20Hz(ヘルツ)に向上させる。![]() ボアホール間隙水圧計やボアホールひずみ計アレーを次の南海道地震のダイレクトなテクトニック圏となる紀伊半島もしくは近畿地方に設置して連続観測を行うことが本計画の第一の目標であるので、なんらかの方策を講じて、懸案を解決したい。
ボアホール間隙水圧計やボアホールひずみ計アレーを次の南海道地震のダイレクトなテクトニック圏となる紀伊半島もしくは近畿地方に設置して連続観測を行うことが本計画の第一の目標であるので、なんらかの方策を講じて、懸案を解決したい。![]() 紀伊半島を中心として重力の長期的な変化を検出するため精密測定をルーチン的に繰り返す。
紀伊半島を中心として重力の長期的な変化を検出するため精密測定をルーチン的に繰り返す。
神岡鉱山坑道内のきわめて近接したのふたつのボアホール井戸(K1、K2)で間隙水圧の連続観測を続行し、その大気圧応答、理論地球潮汐、地震波応答(千島地震)に対する応答をくわしく解析した。その結果、K1井戸については、間隙水圧が理論どおり体積ひずみに比例することを確証した。これらの結果から、G![]() 20 GP、νu
20 GP、νu![]() 0.3を仮定して、loading efficiencyγ
0.3を仮定して、loading efficiencyγ![]() 0.43、Skempton係数B
0.43、Skempton係数B![]() 0.69と決定した。いっぽうK2井戸については、大気圧応答や潮汐応答がみられず、古典的な意味で不圧の井戸であることが明らかになった。ところが地震波応答をみてみると、K1井戸とK2井戸は地震波の帯域でほとんど同一のハイドログラムを書いている。このことはボアホール井戸については、古典的な意味での被圧・不圧の分類がそのまま適用できず、周波数軸での応答特性(ゲインと位相)を把握することが重要であることを示唆している。
0.69と決定した。いっぽうK2井戸については、大気圧応答や潮汐応答がみられず、古典的な意味で不圧の井戸であることが明らかになった。ところが地震波応答をみてみると、K1井戸とK2井戸は地震波の帯域でほとんど同一のハイドログラムを書いている。このことはボアホール井戸については、古典的な意味での被圧・不圧の分類がそのまま適用できず、周波数軸での応答特性(ゲインと位相)を把握することが重要であることを示唆している。
京都大学防災研究所地震予知研究センター 柳谷 俊、梅田康弘、中村佳重郎
有
名古屋大学(山内常生)、東濃地震科学研究所(石井紘)
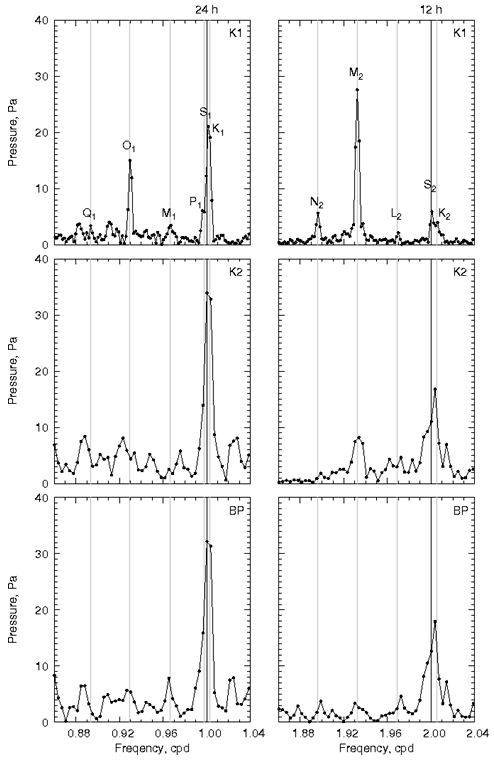 |
| 図1.神岡K1、神岡K2ボアホール井戸(間隙水圧)、BP(大気圧)のおよそ2年間の連続観測記録(1秒サンプリング)よりもとめた日周期および半日周期周辺のフーリエ・スペクトル。K1井戸では主要日週潮、半日週潮のすべてが実際に検出されている。いっぽうK2井戸では、M2近辺にわずかなピークがみられるのを除けば、大気圧の変化にそのまま応答ており、古典的な意味では、K1井戸は被圧、K2井戸は不圧と分類される。 |
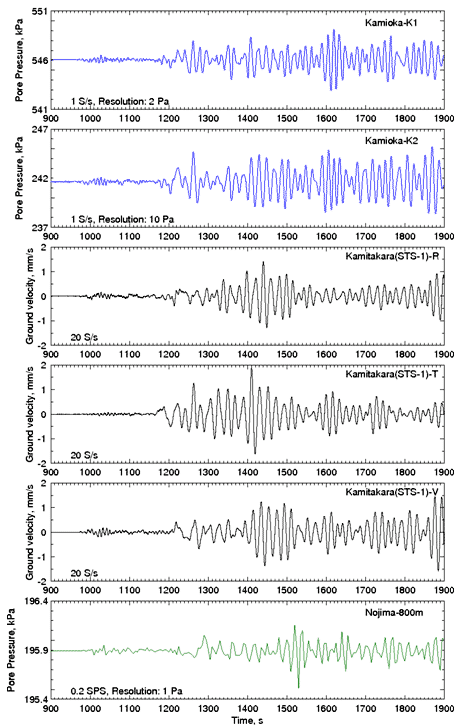 |
| 図2.2006年11月15日の千島地震(Mw(モーメントマグニチュード) |