課題番号:1804
京都大学防災研究所
断層における注水実験および応力状態の時間変化
16年度からの5カ年においては、野島断層における540メートル深度注水実験を中心として、断層近傍岩盤の透水性モデリングの高度化による断層回復過程の検証、注入水の挙動および断層近傍岩盤の破砕構造・クラック分布の推定、注水誘発地震の発生検証および発生過程の解明、断層の不均質構造(特に走向方向)と地震発生特性の関係解明、等の地球物理学的な調査、および、物質科学的な調査(例えば、断層に沿ったシュードタキライトの分布・性状特性等)を行い、包括的な断層(破砕帯)構造の理解を目指す。16年度に第4回目、18年度に第5回目の540メートル深度注水実験を実施する。
18年度は、5回目注水実験を実施してこれまで未解決の課題の解明、および補足データの取得による回復過程の検証、およびモデリングの高度化を行う。さらに、野島断層の破砕帯構造、アスペリティの地震学的および物質科学的な調査等を行い、これらを総合して、上記の到達目標に近づくことを目指す。
18年度は、5回目注水実験を実施して、これまで未解決であった注水誘発地震に関する課題の解明(誘発地震の発生検証、および1,800メートル、800メートルボアホール地震波形の高速サンプリングによる震源過程の解明)をめざす。また、4回目実験時の歪データ(800メートル孔)を補足して、岩盤弾性定数の経年変化を確実に検出する。さらに、4回目実験で水位データ(800メートル孔)のモデリング後半に大きいずれが生じたので、これを再度モデリングするとともに、一時的に透水性が増加したように見えた原因(2004年12月の実験の終了直前に発生したスマトラ北部西方沖の地震、もしくは3ヶ月前に発生した紀伊半島沖・東海道沖の地震の影響、等)の推定を行い、水位データのモデリング高度化につなげる。水位計の高精度化(分解能およびサンプリングの改善、平行観測による従来の水位計感度特性の検定)を行い、過去のデータ再解析、モデリングの改善を実施する。その他、高精度水位計データによる間隙水圧の地震波応答の解析、1995年兵庫県南部地震の直後の回復過程の再検討(地震波散乱係数の時間変化を検出)、他の内陸活断層の地震波散乱係数の推定および野島断層との比較、1,800メートル注水孔での長期間・自然湧水実験による湧水・透水環境の推定、等を実施する。また、1999年台湾集集地震の震源断層である車籠埔断層において注水実験が実施される予定であり、これと共同して、野島断層との比較・検討を行う。
西上欽也・大志万直人・吉村令慧・加納靖之・柳谷 俊(京都大学防災研究所)
東京大学地震研究所(平田 直・山野 誠・他)、東京大学理学研究科(田中秀実・他)、名古屋大学環境学研究科(田所敬一・他)、金沢大学自然科学研究科(平松良浩・他)、高知大学理学部(村上英記・他)、神戸大学理学部(山口 覚・他)、奈良産業大学情報学部(向井厚志・他)、産業技術総合研究所(北川有一・小泉尚嗣・他)、および防災科学技術研究所等、約15機関との共同研究。学内では、京都大学理学研究科(藤森邦夫・他)も参加。参加者総数は約40名。
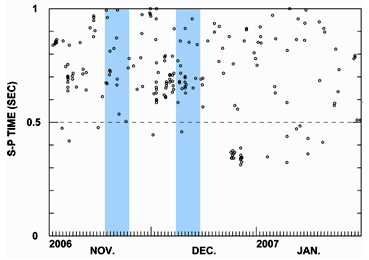 |
| 図1 注水実験(水色期間)の前後における極微小地震の発生時系列。S-Pタイムは800メートル孔底での測定。 |
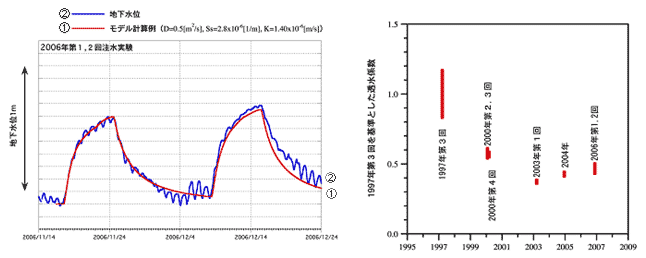 |
| 図2 左:注水に伴う800メートル孔水位変動のモデリング(2006年実験)。青:観測、赤:モデル計算。 右:岩盤透水係数の経年変化(1997年〜2006年の5回の注水実験)。 |
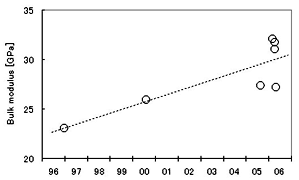 |
| 図3 800メートル孔歪データ(孔口開放・密閉に対するレスポンス)から推定された孔周辺岩盤の体積弾性率の経年変化 |