課題番号:1502
東京大学大学院理学系研究科
日本列島域の地殻活動予測シミュレーションモデルの開発
本研究課題の最終目標は、複雑なテクトニック環境の下にある日本列島域を一つのシステムとしてモデル化し、プレート運動に起因する準静的な応力の蓄積から破壊核の形成を経て動的破壊伝播に至る大地震の発生過程を、膨大な地殻活動データと高度なモデル計算を併合した大規模シミュレーションにより定量的に予測することである。この目標を達成するために、平成16年度からの5ヶ年で以下のことを実施する。先ず初年度は、複数の要素モデルで構成される地殻活動シミュレーションモデルのプロトタイプを「地球シミュレータ」上に完成させる。平成17年度には、地殻変動や地震活動データのインバージョン解析により、プレート境界面の摩擦特性を定める。平成18年度及び19年度には、過去の大地震の活動履歴が再現できるようにシミュレーションモデルを規定するパラメターの調整を行い、平成20年度には広域GPS観測網や地震観測網からのリアルタイムデータを取り込んだ大地震発生の予測シミュレーションを行う。また、計画後期の平成19年度以降には、プレート内の大規模な活断層を地殻活動予測シミュレーションモデルに組み込み、内陸活断層地震の発生サイクルのシミュレーションも試みる。
平成17年度に関東地域を対象に開発した地殻変動データ・インバージョン解析プログラムを日本列島全域の同時解析が出来るように拡張して地殻活動シミュレーションモデルに組み込み、地殻変動データからプレート境界でのすべり/すべり遅れ分布を推定する。この解析結果に基づいてプレート境界及び周辺域の地殻内応力状態の予測シミュレーションを行う。同時に、CMTデータ・インバージョン解析手法を日本列島域の地震活動データに適用して地殻内のテクトニック応力状態を推定し、予測シミュレーション結果と比較する。こうして、日本列島域のプレート境界の現在の固着/すべり状態を把握し、過去の大地震活動が再現できるようにシミュレーションモデルを規定するパラメターの調整を行う。
日本列島域の地殻活動シミュレーションモデル・プロトタイプを高度化し、1968年十勝沖地震及び2003年十勝沖地震を例に取り、プレート境界での準静的応力蓄積−動的破壊伝播−地震波動伝播の連成シミュレーションを行った。また、シミュレーションと地殻活動観測の融合に向け、直接的及び間接的先験情報を併用したベイズモデルに基づく新しい測地データ・インバージョン解析手法を定式化し、日本列島全域を対象とした解析プログラムの開発に着手する一方、地震のCMT解をデータとして地殻内応力状態を推定するインバージョン解析プログラムを開発し、北海道-東北地域の3次元地震発生応力場の推定を行った。
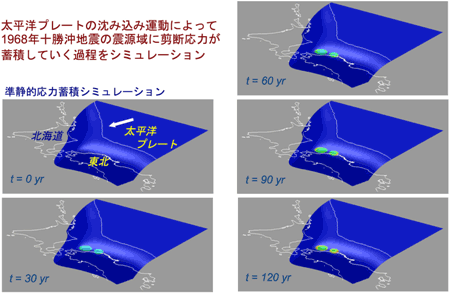 |
図1 プレート境界での準静的応力蓄積−動的破壊−地震波動伝播の連成シミュレーション
|
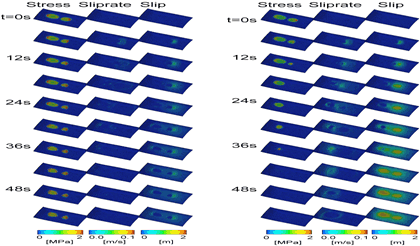 |
図2.プレート境界での準静的応力蓄積−動的破壊−地震波動伝播の連成シミュレーション
|
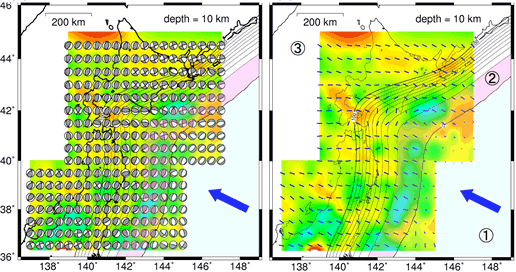 |
| 図2.CMTデータ・インバージョンで推定した北海道-東北地域の3次元地震発生応力場(Terakawa & Matsu'ura, 2006)。左:震源球で表現した地震発生応力場のパターン。右:最大主圧縮軸の方向。 |
松浦充宏、井出哲、深畑幸俊、橋本千尋、橋間昭徳
有
名古屋大学(鷺谷威)、千葉大学(佐藤利典)、防災科学技術研究所(福山英一)