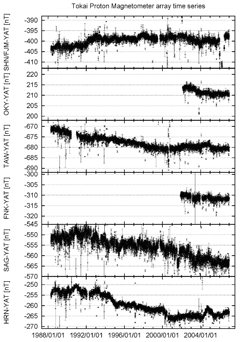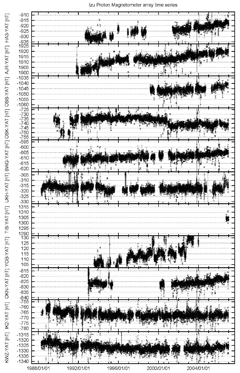(2)研究課題(または観測項目)名
電磁気・重力の同期観測による、地震発生に果たす地殻内流体の役割の解明
(4)その他関連する建議の項目
- 1.(2)イ.内陸地震発生域の不均質構造と歪・応力集中機構
- 2.(2)イ.東海地域
- 2.(2)エ.その他特定の地域
(5)本課題の平成16年度からの5ヵ年の到達目標と、それに対する平成18年度実施計画の位置付け
流体が地震発生に果たす役割について、室内の岩石実験から得られる知見に基づいた理論予測を、野外での観測事実を通じて検証することを目的とする。電磁気観測と重力観測とを、同期して実施することにより、応力変化や地殻内流体の移動やそれに伴う温度変化を高い信頼度で検知する。
従来から行ってきた、電磁気観測、および、重力繰り返し観測を、平成18年度にも伊豆、伊豆諸島、東海地方などで継続し、流体の移動に関連した物理現象を、電磁気の様々な観測項目、重力観測で同時にとらえ、地震発生に流体がどのように関与するかの定量化を目指す。目的を達成するために、最も適当な観測地域、観測項目を考えると共に、松代地震のように明らかに流体が関与する顕著な地殻活動が起こったときに、そこで観測を実施するためのノウハウを蓄積する。
(6)平成18年度実施計画の概要
熱水やマグマなどの高温地殻流体による地震・火山活動が活発な伊豆半島・伊豆諸島、ゆっくりすべりが継続してきて、最近その活動が鈍化した東海地方などで以下の観測を同期して実施する。
- 流体の移動方向を推定するための、電話回線網を用いた面的な地電位変化連続観測(伊豆、伊豆大島)。
- 流体の連結状況を把握するための、人工制御電流源を用いた比抵抗の連続観測(伊豆)。
- 流体の移動量を見積もるための、絶対重力計と携帯型相対重力計とを組み合わせたハイブリッド観測(年間1〜2回の頻度の繰返し測定、伊豆諸島、東海)。
- 高温流体の移動に伴う温度変化および応力変化を検出するための、プロトン磁力計観測網を用いた全磁力連続観測(伊豆、東海)。
特に群発地震活動発生の際には、全期間をとおして重力連続観測を継続することにより、流体の流入・流出の時間的経過を追跡する。重力補正に必要な面的な地殻変動パターンを把握するために、人工衛星干渉SARの解析をおこなう。同時に、全磁力の臨時連続観測点を設ける。
平成17年度までの観測で、重力、電磁気とも、地殻活動に関連するものと思われる興味深い現象をとらえることに成功した。しかし、それぞれに微細な変動であり、地殻活動以外の諸要因が観測量に与える効果を、一つ一つ定量的に検証して消去していく必要がある。平成17年度に引き続き、平成18年度においてもこのための検証的観測を継続して実施する。
(7)平成18年度成果の概要
- 東海地方・伊豆地方における観測
- (1)全磁力観測
東海地方・伊豆地方における、プロトン磁力計を用いた全磁力観測の結果を図1に示す。2004年に特に東海地方西部(HRN)を中心に検出された全磁力差の顕著な増加はその後回復したが、この変化は伊豆地方には見られない。東海地方全体の変化の傾向として、特に俵峰(TAW)で顕著であるように2000年頃に変化が停滞し2004年頃から再び変化が検知されている。この現象が、ピエゾ磁気を介して東海地方西部のゆっくり滑りによる応力変化を反映しているのかどうかを確かめるため、GPSデータの解析により推定された滑りモデル[Ohta et al. 2004, GRL]に基づく応力不均一効果(この場合磁化は空間的に一様)と、磁化の不均一効果(この場合応力変化は空間的に一様)のどちらの効果が、より観測値に反映されるべきかを吟味した。その結果、後者の磁化不均質効果が前者を凌駕し、これは、TAWが南北性の磁気異常西端に位置するという事実と調和的であり、永年変化のトレンド変化の傾向も定性的には説明可能であった。しかし、変化の絶対値を説明するためには、応力磁気係数として通常実験室で決定される値より、10〜100倍大きい感度が必要であることが明らかとなった。従来の研究でも、1年以上の長い時定数を持った変動に対して実験室での応力磁気係数値に比べて大きい感度が必要であることが指摘されていたが、この問題の決着のためには、同係数の時定数依存性を明らかにする必要が有る。
伊豆地方では、群発地震活動域に近い与望島、ならびに手石島での観測を再開した。概して北東部(HA3、AJR、OSS)で全磁力差が増加傾向にあり、中東部では減少傾向の鈍化から増加傾向へと転じている。ただし、昨年度の報告でも指摘していたように地殻内の磁化の不均質による局所的な地磁気の空間分布と、地殻活動とは直接関係しない広域的な地磁気永年変化との合成によって、見かけ上、全磁力差の傾向的な増減が生じえる。1年以上の永年変化の時定数で時間変化を解釈し、観測量から地殻活動起源の成分を抽出するためには、上記応力磁気係数の再検討のほか、磁化構造と地磁気永年変化の考慮が必要である。
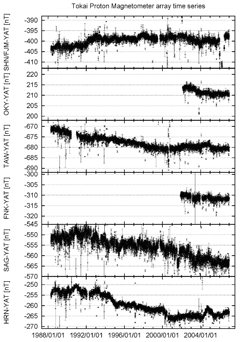 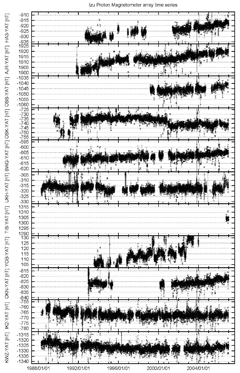 |
図1 1988年から2005年までの、八ヶ岳の全磁力を基準にした東海各地点(左)、伊豆各地点(右)の全磁力差。フルスケールは25nT(ナノテスラ)(東海地方)、30nT(ナノテスラ)(伊豆地方)。観測地点は上から、東海地方は富士宮、奥山、俵峰、舟ヶ久保、相良、春野、伊豆地方は初島、網代、御石ヶ沢南、大崎、沢口、浮橋、手石島、与望島、奥野、池、河津。 |
- (2)比抵抗観測
比抵抗測定精度を上げるため、電流値をモニターするシステムを完成させ、2005年秋より観測にあたったが、わずか数日で落雷のため機器が破損した。昨年度から今年度にかけて電流送信装置を全面的に修理、更新し、雷対策も強化し、ようやく2006年4月20日より観測を再開した。その後、現在まで順調に連続観測データが得られている。機器の修理更新により、電流制御の精度も0.25パーセント程度に向上した。ただ、更新前においても制御の精度は1.5パーセント程度はあり、昨年度までに報告してきた5パーセント程度の電位振幅(見かけ比抵抗)の変動は、電流制御の問題を超えて有意であることが確かめられた。
- 伊豆諸島における観測
- (1)ハイブリッド重力観測
2006年9月、三宅島において、2000年噴火後の重力変化を調べるための重力再測定を実施した。図3に三宅島測候所絶対重力点に準拠して求めた,2004年〜2006年の間の島内の重力変化を示す。過去には2001年11月の火映現象や火口温度の上昇と対応するように重力増加が検出されており、これはマグマヘッドの上昇と解釈されてきた.火映現象のあった2001年11月頃に最高位にあったマグマヘッドは、2002年5月頃までは降下し,それにともなう重力減少がみられた。2002年5月以降は,全島的に重力が増加していた.GPS連続観測や全磁力の連続観測でみても2002年5〜7月ごろが一つのターニングポイントのように見えるのと同じように,重力変動もこの時期を境に様子が変わっている.
今回の測定で顕著な特徴は、2003年6月〜2004年6月〜2006年10月に、島の海岸線から次第に内陸側に重力増加が見られる点である。海面高度付近の地下水層が次第に内陸に向かって発達し始めている可能性が示唆される。このことは、この期間にSO2放出量減少がみられることや、2003年にはなかった小規模噴火が2004年以降におき始めていることと符合するような結果となっている。
 |
図2.2004年から2006年の期間の三宅島における重力変化。単位:μgal(マイクロガル). |
- (2)電磁気観測
2006年3月に三原山中央カルデラ内に3成分磁力計を設置し、従来より継続してきた長基線地電位差観測網を整備した。電磁場データ共に、最高10Hz(ヘルツ)でサンプリングを行い、有線、無線LANを用いてデータ転送を行っている。
(8)平成18年度の成果に関連の深いもので、平成18年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)
(9)実施機関の参加者氏名または部署等名
上嶋誠・小河勉・小山茂・山崎健一・大久保修平・孫文科・松本滋夫・菅野貴之
他機関との共同研究の有無
有
東工大(2名)、京大(2名)、東海大(2名)