課題番号:1402
東京大学地震研究所
日本列島内陸の歪・応力の不均質性の生成原因の解明
本計画においては、他の項目で実施される、地殻内絶対応力とその変化の測定、超精密パルス型制御震源を用いた弾性波による微小応力変化測定、ネットワークMTによる広域比抵抗構造調査、日本列島の歪み速度分布の推定、GPSデータ逆解析による応力変化推定、活断層・歴史地震調査等による過去の大地震の履歴の推定、等の各種研究を総合化して、1.(1)アで解明されるプレート運動に基づく境界条件を与件として、日本列島内部へのひずみ・応力の蓄積過程に関するマスターモデルを構築することを目標としている。
平成17年度に、研究の打ち合わせを実施したほか、他の研究成果を取り込む作業を開始したことから、平成18年度はさらに作業を進め、より広域他項目のデータ収集を行い、データベース化を図る。また、研究集会等を開催して研究の推進を図る。
平成18年度の比較的早い時期に関連研究者による勉強会を開催し、特に日本列島規模のひずみ・応力の蓄積過程モデルの構築に関する研究の推進に関する打ち合わせを行う。
構造データ、変動データ等の収集を進めると共に、共通のグリッド上で、かつデータ様式を揃えたデータベースの構築を進める。
平成18年度においては,地震予知研究の中間評価が実施され,本研究課題には厳しい評価が下された.このことを踏まえ,本研究計画は大幅な計画変更を行った.本研究実施課題は当初,広範な内陸の研究成果を集約し,日本列島内部への歪・応力の蓄積のメカニズムを解明するための基礎的な研究を実施するというものであった.しかしながら,研究体制の不備などから研究が進んでこなかった.このような反省に立って,研究の内容を実現可能な項目に絞ることとした.
平成18年9月20〜22日に京都大学において「測地・地殻変動に関する研究集会」が開催された.ここにおいて,地殻変動連続観測の研究の総括を行うと共に日本列島の地殻変動をより広範な大学の連携のもとに実施していくことが合意された.このことをふまえ,日本列島の歪・応力の蓄積過程を地殻変動連続観測を主体として実施していくことを地震予知研究協議会企画部に提案して認められた.
全国の地殻変動連続観測を実施している大学はワーキンググループを作り,データの公開に向け活動を開始した.このような活動のさなか,平成18年11月15日と平成19年1月13日に千島列島のほぼ同じ場所でマグニチュード8クラスの地震が続発した.そこで,急遽これらの地震に伴う伸縮計データを全国大学で集めることとした.図1は,集められた観測点の分布を示す.また,図2はそのうちの一部観測点のひずみ計記録波形である.
このような記録を集約して解析することにより観測点ごとの計器特性や震源特性を明らかにすることが出来ると期待される.
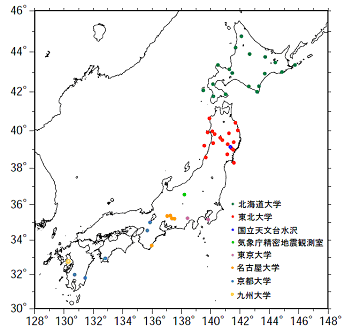 |
図1:千島列島沖地震のひずみ地震計データを採録した観測点(2007年2月地震予知連報告資料). |
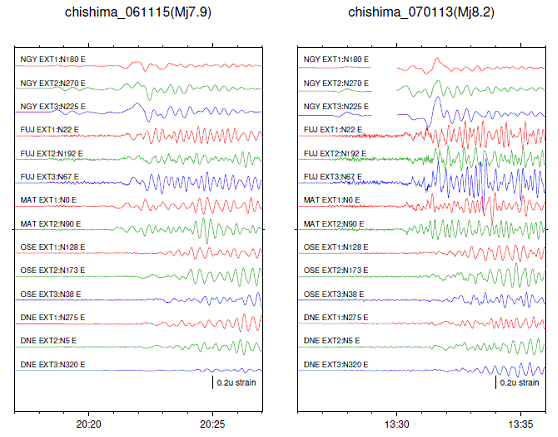 |
| 図2:千島沖地震によるひずみ地震計記録.左:2006年11月15日地震の記録,右:2007年1月13日地震の記録(2007年2月地震予知連資料より). |
有