- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 学術分科会 > 研究環境基盤部会 > 資料4 学術研究の推進体制に関する審議のまとめ(報告)資料(案) > 3‐5 「全国共同利用」について
3‐5 「全国共同利用」について
1.全国共同利用とは
大学共同利用機関、国立大学附置研究所・研究施設において、所有する大型研究設備や資料・データを全国の研究者の共同利用に供し、または共同研究を行い、大学等の枠を越えた当該分野の研究を効果的かつ効率的に推進していくことを目的としたシステム。
2.現状
平成20年4月1日現在
国立大学全国共同利用附置研究所 10大学20研究所
国立大学全国共同利用研究施設 16大学28研究施設
大学共同利用機関法人 4機構16研究所
3.制度的位置付け
国立大学全国共同利用附置研究所
法人化前
○ 国立学校設置法(平成16年4月1日廃止)に基づき同法施行令において位置付け
法人化後
○ 国立大学法人法に基づき文部科学大臣が定める中期目標の別表(教育研究上の基本組織)において位置付け
国立大学全国共同利用研究施設
法人化前
○ 国立学校設置法に基づき同法施行規則において位置付け
法人化後
○ 国立大学法人法に基づき文部科学大臣が認可する中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述
大学共同利用機関
法人化前
○ 国立学校設置法に基づき同法施行令において位置付け
法人化後
○ 国立大学法人法に基づき同法施行規則において位置付け
4.共同利用の機能・形態
A.大型設備利用型
大型の設備や施設を有し、共同利用に供するもの。仕様・企画段階から、各大学の研究者コミュニティが参加。
(例)
高エネルギー加速器研究機構(Bファクトリー)
東京大学宇宙線研究所(スーパーカミオカンデ他)
筑波大学計算科学研究センター(PACS-CS)
B.共同研究型
課題を設定し、それに応じて共同研究あるいは研究討論等を行うもの。
(例)
人間文化研究機構総合地球環境学研究所
京都大学基礎物理学研究所
C.研究資料提供型
学術資料を収集・保存し、共同利用に供するもの。
(例)
人間文化研究機構国立民族学博物館(民族資料、標本)
情報・システム研究機構国立遺伝学研究所(データベース、系統保存)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所(アジア・アフリカ諸地域の言語・文化に関する文献・辞典・辞書等)
D.情報基盤センター
研究・教育等に係る情報化を推進するため、基盤となる設備等の整備及び提供を行うもの。
(例)
東京大学情報基盤センター(スーパーコンピューティング部門)
※ 実際にはこれらの類型が複合して行われている。
5.運営体制
全国共同利用の研究所等には運営協議会等を設置し、管理・運営について、所外の意見を取り入れるシステムが構築されている。
国立大学全国共同利用附置研究所・研究施設
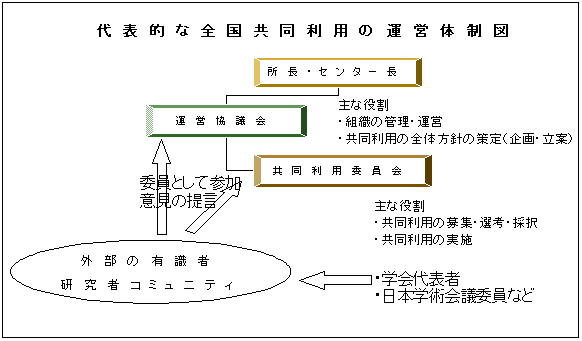
大学共同利用機関
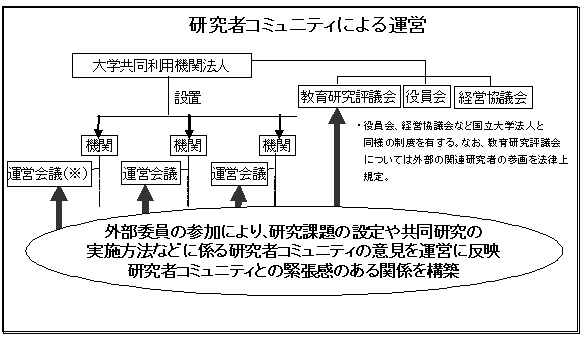
6.共同利用の選定の流れ
大学共同利用機関における一般例
公募
大学等の学術研究機関に対して、公募の通知を送付
↓
事前協議
大学等の研究者は、研究テーマ・研究内容・研究メンバー・経費等について、応募する前に大学共同利用機関の関係研究者と協議
↓
申請
大学等の研究者は、所属長を通じて共同研究計画申請書を大学共同利用機関の長に提出
↓
審査
運営会議の下に置かれた、外部有識者が半数以上を占める共同利用研究(実験)委員会等において申請のあった共同研究計画を審査
↓
決定
大学共同利用機関の長が審査に基づいて採否を決定
↓
実施
大学共同利用機関を共同研究の場として、機関の施設設備・資料等を用いた共同研究の実施
↓
報告
共同研究の終了に伴い、共同研究報告書を大学共同利用機関の長に提出
7.共同利用・共同研究課題数
国立大学全国共同利用附置研究所・研究施設
| 分類名 | 機関数 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|---|
| 理工学系 | 27 | 2,512 | 2,452 | 97.6パーセント |
| 医学・生物学系 | 10 | 487 | 474 | 97.3パーセント |
| 人文学・社会科学系 | 2 | 34 | 29 | 85.3パーセント |
| 大型設備利用型 | 14 | 1,606 | 1,590 | 99.0パーセント |
| 研究資料提供型 | 5 | 236 | 230 | 97.5パーセント |
| 共同研究型 | 20 | 1,191 | 1,135 | 95.3パーセント |
※ 文部科学省調査(研究活動等状況調査)による。
※ 提案及び実施が、国・公・私立大学及び、民間企業等の教員及び研究者を対象として公募により行なわれ、共同利用委員会を通じて採択した共同研究プロジェクトの実施状況。
※ 分野の分類については、国立大学附置研究所及びこれに準ずる研究センターの所長・センター長を会員として組織される「国立大学附置研究所・センター長会議」の分類にしたがっている。
※ 大型設備利用型、研究資料提供型及び共同研究型の形態別分類については、研究活動等状況調査により各機関から示された共同利用・共同研究の実施形態により分類しており、重複がある。
大学共同利用機関
| 分類名 | 機関数 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|---|
| 人間文化研究機構 | 5 | 76 | 55 | 72.4パーセント |
| 自然科学研究機構 | 5 | 1,067 | 1,042 | 97.7パーセント |
| 高エネルギー加速器研究機構 | 2 | 735 | 646 | 87.9パーセント |
| 情報・システム研究機構 | 4 | 418 | 418 | 100.0パーセント |
※ 文部科学省調査(研究活動等状況調査)による。
※ 公募型共同研究の新規採択分の件数。
8.外部研究員の受け入れ状況
○ 国立大学の附置研究所及び研究センターにおける全国共同利用
共同研究実施状況(平成17年度):2,955件
外部研究者の受け入れ状況(平成13~17年度):84,274人(年平均16,855人)
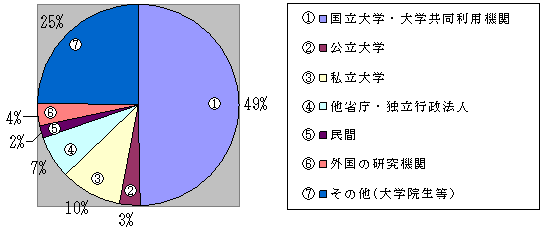
○ 大学共同利用機関
共同研究実施状況(平成16年度):2,686件
外部研究者の受け入れ状況(平成14~16年度):41,656人(年平均13,885人)
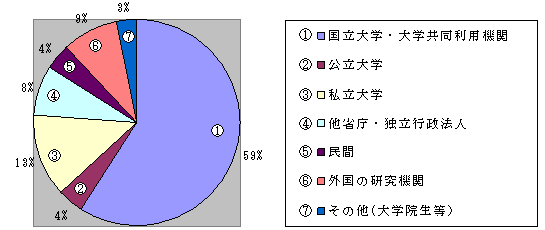
※ データは、文部科学省調査(研究活動等状況調査)による
9.共同利用に係る経費
○ 共同利用に係る経費(運営委員会経費、共同研究経費、共同研究旅費)は、国立大学法人運営費交付金の中で国として措置。
○ 共同利用に参加する研究者は、機関が定める規程等に基づき、研究費などの支給を受け、原則的に、利用者から利用料を徴収することはしていない。
10.附置研究所・研究施設の全国共同利用化
国立大学の附置研究所・研究施設の全国共同利用化については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議している。
法人化後に全国共同利用化した附置研究所・研究施設
平成16年度
なし
平成17年度
京都大学生存圏研究所
平成18年度
東京大学空間情報科学研究センター
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
平成19年度
佐賀大学海洋エネルギー研究センター
平成20年度
京都大学地域研究統合情報センター
全国共同利用化にあたっての観点
- 我が国の学術研究全体における役割・機能、研究活動実績及び大学全体としての支援・協力の状況(人員を含む体制の充実・強化など)
- 共同研究の増加や、研究者コミュニティからの要望の状況
- 全国共同利用化後の共同利用・共同研究の実施に関する計画性・具体性
- 全国共同利用化により、学問分野としての新たな発展にどのように寄与するか(新たな研究領域の創生など)
お問合せ先
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --