- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 資源調査分科会(第19回) 配付資料 > 参考資料4 平成19年度自然資源の統合的管理に関する調査 > 3.各論 第4章 わが国における自然資源管理の現状と統合的管理の必要性
3.各論 第4章 わが国における自然資源管理の現状と統合的管理の必要性
4‐1 現状と課題
4‐1‐1 林業資源管理
(1)現状
1960年代の半ば以降、わが国の森林面積は2,500万ha前後で安定的に推移しているが、この間に人工林の面積割合は全体の31%から41%に高まり、全森林の林木蓄積量は20億m3から40億m3へと倍増している。林野庁が実施している森林資源のモニタリング調査の暫定集計などから推測するに実際の林木蓄積量は50億m3を超えているであろう。
わが国では有史以来20世紀の半ばに至るまで、木材需要のほとんどを国内の森林でまかなってきた。しかし長年にわたって森林が酷使されてきたことも否めない。特に第2次大戦をはさんで過伐が続き、1950年の統計によると森林1ha当たりの林木蓄積量は67m3というきわめて低いレベルまで低下している。その後、外材がスムーズに入ってきてくれたお陰で、国内での森林伐採が急速に減少し、林木ストックの増加につながっていく。かりに外材が思うように輸入できなかったとしたら、わが国の森林は疲弊の度をさらに深めていたであろう。今では森林1ha当たりの林木蓄積が200m3を超え、主要なヨーロッパの諸国と肩を並べるまでになっている。
しかしこれは当初政策当局が描いていたストーリーとはまったく違った展開である。わが国の戦後の林政は「敗戦ショック」に始まった。台湾や満州、樺太などの植民地を失ったうえに、北米やロシアなどからの木材輸入も望めない。7,000万の人口が必要とする木材を国内の森林だけでまかなうにはどうしたらよいか。そこで打ち出された政策が国内の森林の半分以上を成長の早い針葉樹の人工林に切り替えるという野心的な造林政策である。具体的には老齢過熟の奥地の天然林や成長の衰えた里山の広葉樹林を積極的に伐採してスギやヒノキを植えることであった。
たまたまこの当時は木材が不足していて材価が高騰していたために、この「拡大造林」政策は順調に進展する。ただ奥地の国有林などが広い面積にわたって皆伐され、河川の流れが不安定になったとか、土砂災害が多発するといった報告も聞かれるようになった。また山岳地の天然林を伐って植林したものの、うまく成林しなかった例も少なくない。森林構成の急激な変化と針葉樹人工林の拡大で、森林の生態的な安定性が一時的にせよそこなわれていたことは否定できないであろう。
1970年前後から本格化した外材輸入で、木材生産の縮小が始まり、森林伐採に起因する環境問題も次第に影を潜めてゆくが、その一方で木材が売れなくなって肝心の林業経営が回らなくなった。かつて薪炭林として使われていた広葉樹を切り替えて人工林にしたものの、除間伐などの保育作業ができなくなり、不健康な過密林が増えることになった。さらに人工林がしだいに成熟して市場出荷が視野に入ってきているのに、林道・作業道の整備と維持管理がないがしろにされてきたため、効率的な伐出システムが導入できなくなっている。
条件の厳しい場所に植えられた一部の人工林は、放置されて広葉樹が侵入し、自然の状態に戻り始めているが、それ以外の人工林については、利用されないために森林が過密化するという深刻な事態が一般化している。木材の生産を控えることが森林環境の保全につながるという図式はもはや成り立たない。
世界の木材市場を一瞥すると、中国はじめ多くの新興国の台頭で木材の需要が増加の一途をたどっている。製材用針葉樹丸太の世界平均価格は2007年にこれまでの最高を記録し、パルプ材についても同様の指摘がある。この40年間、日本はその強い経済力にものを言わせて、世界の各地から木材をかき集めてきた。それが近年では状況が相当に変わり、思うようには木材が集められなくなっている。
これに加えて、2008年の幕開けとともに京都議定書の第1約束期間が始まった。化石燃料に代わる再生可能なエネルギー源として木質バイオマスへの期待が大きい。おまけに原油先物価格が1バレル90ドルという高止まりになっている。木材のエネルギー価値が製材用丸太とほぼ同様の1万3,000円/m3の時代になった。これが今後の木材利用、ひいては林業・林産業の在り方そのものの根本的な変革をもたらす可能性がある。
(2)課題
わが国の林業が当面する最大の課題は、増加した森林ストックをベースにして、これまでよりもレベルの高い持続可能な森林経営をいかにして確立していくかである。近い将来、木材の価格が上昇すれば、伐採量はおのずと増加するであろう。しかし折角蓄積された林木ストックを無秩序に伐り荒らしてしまっては元も子もない。価格が多少上昇しても50年生程度の人工林では再造林費のねん出が難しいだろう。路網の整備されていないところでは、伐出コストを引き下げるために大きな面積がまとめて皆伐され、跡地の植林をしないまま「伐り逃げ」するということにもなりかねない。九州など一部の地域で広く見られるようになった「再造林放棄地問題」といわれるものがそれだ。
長い間、材価の低迷が続き、一部の森林所有者にとっては人工林を保有することが負担になっている。材価の上昇を契機に急いで換金しようとするのも無理はない。森林を持続的に経営するという意欲をすでに失っている。しかも外材がスムーズに入らなくなって、規格品の大量供給をめざす大型の集成材工場や合板工場が各所で建設されるようになった。これらの工場が国産材の大量集荷を開始するのは間違いない。最悪なのは、この大量集荷と「伐り逃げ」と結びつくことである。できることなら個別経営ないしは地域という単元で持続的に森林が回転していく体制を築くのが望ましい。
世界の各地で実施されている林業経営の方式として一般的なのは、輪伐期が10年以下の超短伐期、30年以下の短伐期、50年前後の中伐期、80年から120年の長伐期などである。わが国の場合、成長の良い九州などでは中伐期をとる例が比較的多いが、それ以外のところでは、これが経済的に成り立たず、中央ヨーロッパの長伐期型に移行しつつある。この場合は、5〜10年程度のインターバルで間伐を繰り返しながら、林木の価値を高めていくことになろう。
間伐ないしは択伐を軸とする方式は環境保全の上からも望ましい方式とされている。ただし、きちんとした路網がないと経済的に成り立たない。中央ヨーロッパの諸国が外材と対抗して伐出コストを引き下げるべく、早くから力を入れてきたのは林道・作業道の整備であった。その結果、森林1ha当たりの路網密度はドイツ西部で118m、オーストリアで87mに達している。それが日本ではわずかに16mしかない。また山岳地形の多いオーストリアでは急傾斜地に向いた架線系の集材機の開発に本格的に取り組み、この国に適した伐出のシステムを確立していった。平坦地の多い北欧諸国にはかなわないにしても、1m3当たりの伐出コストは日本の半分くらいにまで引き下げられている。
それと同時に、中央ヨーロッパでは製材工場や集成材工場の集約化・大規模化が進んだ。これにともなって木材の流通プロセスが合理化され、大型工場に大量の原木を供給するサプライチェーンができあがっていく。ところがわが国の林業・林産業は昔ながらのやり方からなかなか抜け出せない。国産材を挽く製材工場のほとんどは依然として規模が小さく、原木や製品の流通でも改善が見られないのである。
以上の結果として、わが国では森林から木材を出してくる伐出コストが非常に高い。そのうえ、製材コストが高く、流通経費も嵩むとすれば、森林所有者に帰属する山元の立木価格が押し下げられるのは当然であろう。というのも製材品や素材の価格は国際市場で決定され、川上でのコスト増加を製品価格に転嫁することができないからだ。立木価格の低落が森林所有者の経営意欲を失わせ、管理放棄を招来しているように思う。このために山から木材が下りてこず、製材工場の規模拡大もままならなくなっている。
加えて、中央ヨーロッパでは木材産業の変革と歩調を合わせて、木質バイオマスのエネルギー利用が著しく進展した。21世紀に入って特に目立つのは木質ペレットの消費が増加して、年産能力数万トンから10万トン以上のペレット工場が次々と誕生していることだ。ペレットは今や完全な国際商品で、生産国と消費国の色分けができ、競争も熾烈である。木質バイオマスのエネルギー利用においても、市場競争力が問われる時代になった。コストを削減する近道は、通常の木材生産と木材加工の中にバイオマス利用を上手に組み込んでいくことである。
4‐1‐2 農業資源管理
(1)現状
農業はその生産活動を通じて、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全などの多くの効用をもたらす。農業生産活動や集落活動が適切に営まれている限りは、農業の多面的機能も十分に発揮される。しかし、近年の農村人口の減少や高齢化は農地や農業用水路の維持管理に負の影響を及ぼし、耕作放棄という現象はこの負の影響を端的に表現している。各種の対応策が試みられているが、農産物価格の低落や資産としての土地所有にこだわる傾向が事態の改善を妨げている。農地や用水路の維持管理作業は、集落の共同作業で行われるのが一般的であったが、ここ数年集落の関与が大きく後退している。農村地域では資源の有効利用や維持管理にも、人口減少や混住化の影響が出てきている。
一方、農村地域に存在する自然資源は、農業生産活動や社会活動を通じて地域ぐるみでその維持保全が図られてきたが、農家の兼業化や高齢化、農村で過疎化や混住化は集落機能の低下をもたらし、資源維持管理のための仕組みを構築し直す必要に迫られており、加えて自然環境保護の動きが全国的に広まってきている。農業は本来自然界における水・窒素・炭素といった物質の循環を利用した持続可能な生産活動であるが、化学物質の過剰投入や家畜排泄物の不適切な管理による環境への負荷の増大が懸念され、多くの農家が環境保全型農業を志向するようになり、その動きを支援すべく、国と地方公共団体との連携の下に「農地・水・環境保全向上対策」が進められている。森林の整備・保全についても市民の参加意識が高まり、さまざまな主体による活動が活発化している。
(2)課題
農村の過疎化は農家の高齢化・少子化等により農村の集落構造が急速に変化しつつある。人手不足は集落での農業生産、林業生産活動の停滞のみならず、集落機能の低下により農村の社会的維持保全及びその活動を困難にしており、農業資源・林業資源の維持管理のための人的、経済的、法制のシステム全体を構築し直す必要がある。
一方、視点を変えて経済面からみると、農村各地に展開している大資本によるマーケッティング商法が農村の経済自立構造を阻害している。これはスーパーマーケットが流通のやりやすさと人々の嗜好の両面からとった流通を中心とした経済戦略であり、農産物、水産物等の地産地消システムが著しく損なわれるとともに収益も地域外に流出してしまう結果となっている。これらを改革するための課題には、1.大学による人材(リーダー)の養成、2.安心、安全確保を要望する都市住民(消費者)との信頼性確立、3.情報、センサ等関連技術の開発、4.これらを支援する国家組織創設などが考えられる。いずれにせよ1次資源である林業、農業、漁業は協同して地域的特性をいかした流通システムを推進し経済的自立を構築すべきである。
4‐1‐3 漁業資源管理
(1)現状
漁業者は、ごく最近まで、「海洋生物資源は、自然に、無尽蔵に発生する枯渇することの無い資源で、漁獲した人に優先権がある。いわゆる無主物である」と考えていた背景もあり、自然資源、特に漁業資源について管理の必要性が認識されるようになったのは最近で、1つには化石燃料に見られるように資源の有限性が明らかになり、生物資源も含めてあらゆる資源の囲い込みが起こったこと、さらには、1982年に国連で採択された国際海洋法条約で200海里排他的経済水域が世界の潮流になり、水域内での管理が当該国の責務になったことがある。本来、漁業には、漁業資源の帰属を巡る争奪の歴史があり、領海が3海里から200海里と拡大し、規制強化は国際的な傾向である。
日本でも、乱獲による漁獲量の低下は経験的に漁業者に認識されていて、地域漁村では、江戸時代など古くから、「磯の口開け」のように漁期の開始時期の設定など、資源の低下を防ぐために簡単な資源管理が古くから実施されてきた。現在でも、禁漁期の設定、産卵場の保護、漁法の制限、地域重要魚種の種苗法流など、さまざまな漁業資源保護施策が、狭い範囲、主に地域、漁協単位で採られている。
漁業管理の具体例として、地域種、ハタハタの例を取り上げると、ハタハタは日本海からオホーツク海域一帯に分布する1属2科の魚で、通常、水深300m前後の日本海の海底にいるが、冬季、11月頃になると、秋田県男鹿半島沿岸水深数mの藻場に、産卵ために襲来し、藻に卵塊を付着する。ハタハタ漁はこうした性質を利用し、産卵のために寄ったところを一網打尽に漁獲する効率のよいものであったが、逆に、親魚を卵もろともに捕獲することから、以前から乱獲が危惧されていた.実際、1975年頃漁具、漁法の発達もあり20,000t前後の漁獲があったものが、1991年初頭には71tまで激減したことから、秋田県では、1992年9月から1995年8月まで沿岸での漁獲を全面禁漁とし、その間380万尾以上の放流も実施して、資源回復を図った。その結果、近年では2,000tを越える漁獲水準に戻りつつあるが、禁漁期間には漁業従事者の収入は途絶し、禁漁にいたる過程で紆余曲折があり、関係者の経済的打撃は想像以上のものがあった。資源管理、漁業管理の重要性を認識させる大きな出来事でもあった。
日本では、こうした地域種ばかりでなく、魚種によっては地域を越えて回遊する魚も多い。こうした魚種については、地域管理ではなく、国レベルでの管理が必要になる。現在、重要魚種、8種(サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、マサバ及びゴマサバ、スルメイカ、スワイガニ)、については、平成8年の国連海洋法条約の国会批准に伴い、漁獲可能量(TAC:Total
Allowable Catch)に基づく資源管理が導入され、漁獲量が決められている。TACについては、毎年、資源量推計の見直しが行われ、資源量の正確な把握、資源維持に寄与している。世界では資源管理にTAC制度を取る国が多い。
漁業資源管理には、河川域も含まれる。河川は権利関係がもっとも厳しく対立し、調整が困難な水域である。日本における河川管理は淡水資源をめぐって、農業用灌漑、発電、上水と多様な目的をもって利用されているため、複雑な水利権が設定されているが、当初設計には、生物環境保全といった概念が含まれていなかったために、河川に生息する生物にとって優しい環境にあるとはいえない。
ヨーロッパにおける漁業資源管理の歴史も古く、アイルランドとイギリスのタラ戦争は18年間、1958年〜1976年も続いた。こうしたこともあり、北大西洋では資源管理制度が他の海域より整備されている。特に、ノルウェーの制度は先進的で、ITQ方式(Individual
Transferable Quota:譲渡可能個別割当方式)IQ方式のうち、分与された該当量を他の漁業者にも譲渡できるように措置する方式の中でIVQ方式(Individual
Vessel Quota:漁船別漁獲割当方式)を取り、漁獲量を厳しく管理している。
日本は、ロシア、韓国、中国、太平洋島しょ国等、多くの諸外国の排他的経済水域内で、相手国との2国間協議に基づき、漁業を行っているが、その場合も、相手国の資源管理の範囲内での割り当てを受けている。
世界では、近年、マグロは高値で取引され、一方で、漁獲量の著しい減少が起きていることから、その漁業管理に関心が集まっている。マグロに限らず公海における広域回遊魚については、世界的に規制しようとする機運が強い。マグロは、大西洋の「大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)」、東部太平洋の「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)」、インド洋の「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)」、ミナミマグロが回遊する南半球水域の「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)」、地中海の「地中海漁業一般委員会(GFCM)」の5つ国際機関と日本のマグロ類漁業生産の約80%を占める中西部太平洋における資源の保存管理のための委員会を設立する条約(中西部太平洋まぐろ類条約(WCPFC))によって管理されているが、国際管理機関の規則を遵守していない国も多い。日本の属する国際機関としては、東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)や南極海洋生物資源保存委員会(CCAMLA)などもある。
捕鯨に関しては、国際捕鯨委員会(IWC)があり、商業捕鯨再開に向けて、海洋生物資源の適切な利用と言う日本の主張を世界に向けて展開している。
国際農業機関、FAO(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION)、は世界の海を海域に分け、漁業統計から資源状況が多くの海で過剰漁獲に陥っていると報告している(図4‐1‐1参照)。
(2)課題
水産生物は無主物という古い考えがあり、それを払拭し、漁業を科学的論拠に基づき、環境と調和した合理的、効率的産業として運営、近代化していくことが求められる。
生物生産、漁業、には利害関係が絡む。小さな漁村でも、魚の取れる魚場を巡る諍い、乱獲は日常的に見られ出来事で、漁場、漁獲の調整は持続的生産のために欠かせないが、複雑な利害関係を納得させる合理的管理法が必要である。
アワビなどの貝類、ウニなどを除いて、多くの水産生物は、産卵場、育成場、索餌場と回遊する。そのため、マグロに見られるように水産資源管理は広域管理が必要である。そうなると、関係する機関や国は多数に上り、相互の利害関係が複雑になる。
こうしたさまざまな課題に対応し、海洋生物資源の持続的利用、地球・地球環境を保全していくためには、関係者を納得させる客観的、つまり科学的論拠が必要不可欠である。資源・生産から消費に至る海洋に関わる自然、生命現象、生物再生産機構を解明、把握すると供に資源の効率的利用技術を開発することが必要であるが、思考から科学的データに至るまでの知材が不足していることもあり、統合管理の全体構想を描くまでには至っていない。
漁業を取り巻く環境は刻々と変化している。地球規模での温暖化、人口の増加、日本における食糧の安定供給、自給率の向上、食の安全の確保など、新しい事態への対応も喫緊である。
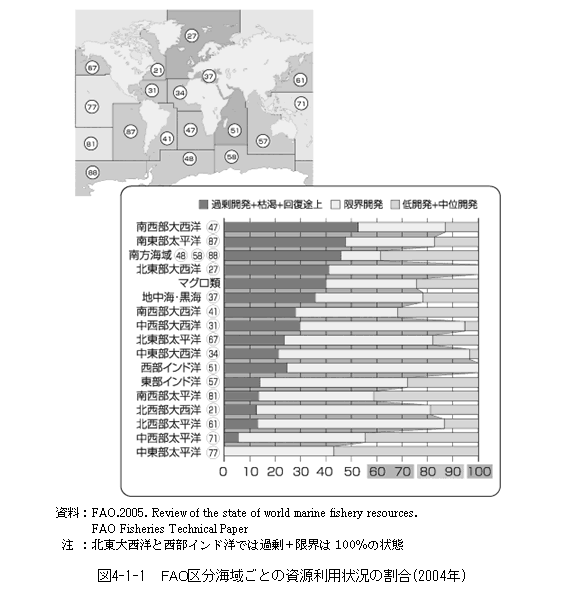
4‐1‐4 海洋資源管理
(1)現状
1.日本列島を囲む海洋の影響
日本の気候と自然資源を作り上げ、現在も維持している最大の要因は海洋である。日本列島の東には世界最大の太平洋が存在するばかりか、列島とアジア大陸との間も日本海によって隔てられている。海水は熱容量が大きい上に大量の水蒸気を大気中に供給してわが国の水資源の源となる。海水は表層も深層も独立に流動して熱と物質を運搬する。海水は二酸化炭素や酸素その他の物質を溶かし込んでそれらの収納庫として大気含有量を自動的に調整する緩衝剤の役目を果している。海水が水産資源の宝庫であることは言うまでもないが、陸から運びこまれるか表層から落下するかして海底に積った有機物からバクテリアと地熱の働きで生成された天然ガス・石油は重要な自然資源である。さらに海底自体が地球内部の活動に基づいて移動し熱水鉱床や重金属団塊を作っている。わが国の陸上に地震や津波、火山噴火などの被害を惹き起こす反面、多くの温泉や火山景観を通じて観光資源をもたらしている。これらは個々独立ではなく相互に密接に関連している現象であるから総合的に把握し統合的に管理されなければならない。以下に夫々について略述し、対応すべき方策を考えたい。
a. 黒潮と親潮
黒潮は冬でも20℃を超える暖流で、深さ800mまでの海水が毎秒2m(1ノット)近い速さで流れている。流域の幅は約100�qで、全流量は毎秒5000万m3に及び、北大西洋のメキシコ湾流Gulf
Streamと並ぶ大規模な表層海流である。塩分濃度は濃く、34‰から35‰(パーミル、千分率)の間で、プランクトンや懸濁物が少ないので透明度が高く黒く見える。黒潮はカリフォルニア海流(南向き)や北赤道海流(西向き)とつながる表層大循環系Gyreの一環であるが地球自転によるコリオリ力を受けて海洋西縁で強められ流域は狭くなる。境界は明瞭で、船から河のように見えることがあって、黒瀬川とも呼ばれる。
北赤道海流が台湾東方で北に向きを変え、狭く強くなって琉球諸島の西沿いを北上し、トカラ水道を経て種子島東方で東向きに転じて四国・紀伊半島南方を通って房総半島沖を太平洋へ抜ける。暖流の右側は特に暖かく、海面が盛り上がっている。琉球南部の石垣島周辺に世界屈指の見事なサンゴ礁が発達しているのはこのためである。
伊良湖岬にココ椰子の実が漂着しているのを若き柳田国男が拾い、それを聞いた島崎藤村が「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一つ、ふるさとの岸を離れてそは波に幾月」という詩を作り、大中寅二が作曲した歌はよく知られている。正にこの黒潮に乗って南洋の島から運ばれたものに違いない。沖縄にはココ椰子は自生していないからである。われわれ日本人の祖先がこの黒潮に乗ってはるばるミクロネシア・ポリネシア地域から到来したという夢を抱かせる事実である。
四国・紀伊半島南方では黒潮が数年に一度大きく南に蛇行することがある。蛇行の北側には冷水塊を生じる。冷水塊表層部には栄養分に富む深層水が湧昇していて、魚類が集まる。蛇行は黒潮が深さ500m以深まで強い時期に起ることが最近の研究で明らかになった。黒潮の底が水深が500mよりも浅い伊豆小笠原海嶺に衝突してその抵抗によって海嶺の手前で蛇行を生じるのだとされている。房総半島東方沖で黒潮(黒潮続流という)は枝分かれして一部は常磐沖を北上する。東向きの流れは太平洋東縁に達するが流速は弱まる。特に流れの南側には小さな乱流ができていて海藻が溜り、魚の産卵場を提供する。
オホーツク海やベーリング海で冷やされた寒冷な水塊が千島列島に沿って北海道南東方に達する表層海流は親潮と呼ばれる。親潮は黒潮に比べて流速は遅く流量は少ないが、氷の下で繁殖したプランクトンと河川から流れ込んだ栄養分が豊富である。親潮は三陸海岸からかなり離れて南下するのが普通で黒潮続流との間に複雑な混合水域を作るが、時として異常に強くしかも海岸に接近することがある。このような状況では東北地方に冷たいやませが吹き、冷害を発生させる恐れがある。黒潮と親潮の現況は人工衛星からモニターされ、観測船と漂流ブイのデータと総合されて海況報告と予想が定期的に公表されている。
長期的な気候変動が黒潮・親潮の流路と流量に与える効果についてはまだよく判っていない。最終氷期に黒潮がどう流れていたかは三陸沖で採取されたピストンコア試料を基に研究が進められている。氷期の黒潮到達緯度は現在よりも南下していたらしく、表層水の温度は現在より4℃ほど低かったが、流量はそれほど衰えていなかったように見える。これは全地球的気候変動が表層大循環にはそれほど影響しないかもしれないことを示唆している。温暖化によって北極海の氷が融けると冷たい表層水はベーリング海を通って太平洋に流れ込み親潮を強める可能性がある。
b.黒潮と親潮と水産資源
黒潮は、太平洋の外縁を流れる表層沿岸流の1つで、地球の自転に伴って時計回りに流れ、台湾沖から三陸間の北上する海流を指す。三陸沖で親潮とぶつかり、混合し、米国側に向かう離岸流となる。黒潮は、上流で赤道域を通るために、水温は冬季でも20℃近く、夏季は30℃と高くなる、本来は起源が外洋水であるために貧栄養で、中国大陸沖合いを流れる間に、陸域から栄養塩の補給を受け、生産性が多少上がる(季節に拠るが、クロロフィルa量で12.8mgChlm3に達する)。
一方、親潮は、北部太平洋に形成される反時計回りの沿岸流で、アリューシャン列島から三陸沿岸までの海流を呼ぶ。親潮の起源は海洋大循環の深層湧昇流であるために、水温が低いものの、栄養塩豊富な、生産性の高い海水である。南下するに従い水温が上昇し、高い生産性(季節によるが、クロロフィルa量で150mgChlm3に達する)を発揮する。特に、水温が高い黒潮との合流域は世界の3大漁場として名高い。
2006年に親潮域(黒潮との混合域も含め)で大漁漁獲された代表的な魚種(低温性魚)としては、サバ62万t(以下漁獲量には日本海他の海域の漁獲も含む)、イワシ47.4万t(1989年には448.8万t)、サケ・マス類24.6万t、サンマ24.4万t、タラ類24.3万t、スルメイカ22.2万t、ヒラメ・カレイ類6.0万t、他ホタテなどがあり、日本の総漁獲高(445.7万t)の過半を占めている。また、こうした水域には、イワシ、サンマのように動物・植物プランクトンを餌とする魚種が多いのもその特徴である。豊富な栄養塩は海藻類の生育にも適していて、コンブは親潮域で育つ。
一方、黒潮域は、水温が温暖なために、水産生物の産卵、発生に適しているが、栄養塩が少ないために定着性の魚より、餌を求めて大きく動き回る回遊魚が多い。2006年の主要漁獲魚種(暖水性魚)は、カツオが39.9万、成魚になると600�sにも達するマグロが25.8万t、タイ類は2.5万t、アジ類で21.4万tが挙げられ、魚種は多いものの多獲性魚は少ない。ワカメは、主として冷水域に繁茂するが、徳島県など日本列島のかなり南でも養殖される。モズクは暖海性で、沖縄県で養殖が盛んである。
漁獲量から見ても、黒潮より親潮の生産性の方がかなり高く、生息する生物量も多い。
c.日本海の海況
黒潮の一部が東シナ海の水塊と混じった温暖水が対馬海峡を通って日本海に流れ込んでいる。この対馬暖流は日本海を温暖にして冬でも凍結しない環境を形成している。日本海流入直後の塩分濃度は低く、33‰以下の表層水が日本海の入り口をふさいでいる。低塩分水が嫌いなカツオが日本海にいないのはこのためである。対馬海流の大部分は本州寄りを北上して津軽海峡を抜けて太平洋に達するが、一部はさらに北上して宗谷海峡からオホーツク海に出る。日本海内で反時計回りに動く循環流の存在も知られている。水分の蒸発が激しいのでしだいの塩分濃度を増している。
冬季にシベリアから吹き出す冷たい北西風は暖水表面から多量の水蒸気を吸収して日本列島の脊梁山脈に衝突上昇して氷晶を生じ、本州と北海道の日本海沿いに豪雪を降らす。地球温暖化に伴ってもし対馬暖流が今よりも強くなるとそれだけ冬の蒸発量が増えて日本海側の積雪はかえって増加する可能性がある。現在の積雪は高山山頂のごく一部を除いて春から夏にかけて完全に融けて万年雪や氷河を残さない。融けた雪は森林の樹木の根に支えられてゆっくりとせせらぎとなり川に集まって田畑を潤す。日本海側に雪を降らせた乾燥した気団は「乾っ風」として太平洋岸の平野に吹き降ろす。この気候が関東平野に二毛作を可能にして豊穣な農地を広げている。
北部日本海の表層水は冬季に冷やされて密度が大きくなって海底まで沈降して日本海独自の底層水塊を形成する。底層水には冬の大時化で激しく波立った海面から取り込まれた酸素や二酸化炭素が豊富で、カニなどの底棲生物の繁殖を助けている。底層水は島弧斜面や大和堆などの海底台地に沿って湧昇し海底の栄養分を表層にもたらすのでスルメイカやブリ、サバなどの魚類も豊富である。日本海の鉛直混合は15年ほどでひと回りする。外洋の鉛直循環が2000年かかっているのと好対照である。
約1万年前までの氷期には海面が少なくとも120m低下していた。日本海を囲む海峡の水深は対馬海峡と津軽海峡で140m以浅、宗谷海峡は55m以下、間宮海峡は12mにすぎないなので、氷期の日本海は太平洋に対してほとんど閉じていた。対馬海峡は辛うじて通じていたが、当時の黄河河口は今よりも対馬に近かったために塩分の薄い河川水が日本海に流れ込んで日本海の表面を覆った。塩分が少ない表層水は冬に冷却されても密度が上がらず沈降がとまった。海底への酸素の補給が停止し、日本海の底は還元状態になった。堆積物は現在の黒海の海底のように真っ黒になり、底棲生物は絶滅した。約6000年前に氷期があけて海面が現在の高さに戻ると太平洋の水は日本海に流れ込んだ。いったん途絶えた底棲生物種も太平洋から運び入れられて再び繁殖を始めた。日本海の生物種が外洋と異なり、遥かに多様性を欠くのはこのためである。
最終氷期の最盛期(約2万年前)には海面低下によって北部の海峡は陸化あるいは凍結して動物は(人類も)容易にアジア大陸から渡来できたと思われる。対馬海峡には海域が残っていたが間隔はごく狭く、簡単な手段で越えることができたであろう。
d.沖縄南部のサンゴ礁
図4‐1‐2に示した琉球列島南部の先島(さきしま)諸島(宮古島、八重山諸島石垣島など)にはオーストラリア北東部のグレートバリアリーフやミクロネシアの群集に匹敵する350種類以上の熱帯性造礁サンゴが生育している。サンゴ礁の本体を造るサンゴ虫は動物だから酸素を消費して二酸化炭素を放出するが、共生する石灰藻やズーザンテラという単細胞藻類(植物)が炭酸同化作用を行って二酸化炭素を吸収し、結果として重要な二酸化炭素吸収体となっていることが最近の詳しい研究によって確かめられている。礁の上に生えるマングローブや芭蕉などの植物や礁湖内に発育する植物プランクトンも二酸化炭素を吸収する。礁湖内には多種類の魚類が集まっている。
サンゴ礁の発達は黒潮による温暖で清涼な海水の供給に加えて沖縄トラフの存在が大陸からの細粒堆積物を堰き止めていることも重要な要因である。サンゴ礁の役割は環境や景観だけではない。1771年の八重山諸島沖地震は波高85mに及ぶ大津波を惹き起こし石垣島に1万人もの死者を出したが、バリアリーフの背後の村落は被害を免れた。サンゴ礁は防波堤の役目を果たしたのである。
沖縄のサンゴ礁の保全は気候温暖化防止と並んで津波・高潮災害予防や観光資源振興の観点からも重要である。海岸工事からの土砂流入は特に厳しく取り締まられなければならない。観光客増加に伴う汚染水の流入も注意深く規制される必要があろう。陸上の樹木伐採により発生する洪水も3.5〜3.6%の塩分濃度を必要とする造礁サンゴの生育を阻害する。
e.大東島と沖ノ鳥島
沖縄本島の約350km東に南・北大東島の2島がごく接近して存在する(図4‐1‐3参照)。南大東島は面積30.57km2、最高高度75.2m、北大東島は面積11.94km2、最高高度74mで両島とも中央が低く平坦で、周囲を地元で「はぐ」と呼ぶ高さ数mの崖で囲まれている。この崖が台風襲来の際の防風壁の役割をして内部は比較的静かである。両島では戦前からサトウキビの栽培が盛んで、収穫期には大勢の季節労働者が訪れる。北大東島の中央には大きな製糖工場があって高い煙突が南島からよく見える。南大東島と沖縄本島那覇空港との間には毎日1往復の定期航空便が飛んでいる。
南・北大東島は隆起環礁で琉球諸島のサンゴ礁とは全く異なる。中央の平坦な凹地は礁湖Lagoonであったが現在は海面上10mにある。大東島の構造と成因を明らかにするために戦前1930年代に2度の掘削が日本独自の計画として実施された(杉山、1934、1936)。米国がビキニ環礁やエニウェトク環礁で掘削を行ったのは戦後かなり経った水爆実験直前だったことを考えると世界に先駆けた独創的な業績であった。
大東島のサンゴ礁石灰岩の厚さは500mを超え、戦前の掘削では基盤岩までは届かなかった。大東島が乗る大東海嶺は5千万年前頃赤道以南で生成されその後北上しながら沈降したことが1978年1月の国際深海掘削計画航海によって証明された(Klein,
Kobayashi et al, 1978)。南北大東島を乗せた環礁はいったん海面下深く没した後琉球海溝の外側隆起帯まで移動して隆起したとされている。南大東島の160�q南には沖大東島という孤島がある。高さ31.3mの平坦な頂を持つ隆起卓礁である。嘗ては海鳥の糞からできたリン鉱石の採取が行われたが戦後長らく米軍の射撃場だったために調査が遅れた。
これらの島々は沖縄本島の真東に位置するので琉球の古い伝説ではアガレヒラシマ、ニライカナイなどとして日の出と共に神々の宿る島として崇められていたことが民俗学的考証によって明らかにされた(柳田国男「海神宮考海上の道、1978所収」。これらの島々(もしかするとさらに東南方の沖ノ鳥島も)の存在が古くから民間に知られていたことが判る。恐らく漁師が発見し漁獲基地として利用したのであろう。
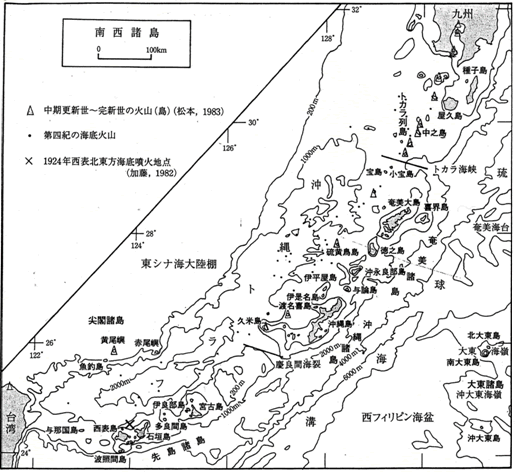
図4‐1‐2 南西諸島の位置図及び地学的特徴
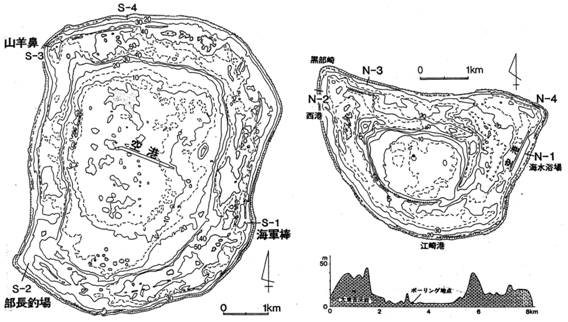
図4‐1‐3 南・北大東島の平面図と北大東島の断面図
沖ノ鳥島は九州パラオ海嶺と大東海嶺の交点にあって激しい沈降を免れたために小さいながらも島であり続けている。20o25'N,146o05'E
にあって台湾やハワイより南にあるわが国唯一の熱帯の領土であり、わが国の経済専管水域EEZの基点として重要視されている。全体は東西4.5�q、南北1.7�qの礁嶺に囲まれたサンゴ礁だが満潮時には2つの小島を残して水没する。現在はその島に気象観測塔などが設置され、波蝕防止工事が施されている。筆者(小林)は最近フィリピン海全体に敷設されつつある海底観測ステーションを結ぶ海底ケーブルの総括基地として太陽発電を含む発電設備と放送衛星を通じたデータ発信局としての役割を持たせるべきだと考えている。
沖の鳥島に新たにサンゴを育成して州島を大きくする計画が提案されている(大森、谷口、2005)。計画の概要は1.サンゴ礁上の潮汐流など海水の流動を詳細に観測して、礁内をできるだけ静穏にして海水の滞留を促すための仕切堤を設置する。2.海水循環の中心付近にサンゴの卵、幼生の滞留と成長を助けるコンクリート製の育成礁を設置する。3.礁湖内にできるサンゴなどの石灰質生物遺骸(サンゴ砂)を沖合に流出させずに礁上に堆積させて州島を造る。4.州島が成長すると海鳥がとまって糞をして肥沃な土壌ができ、ココ椰子などの植物が芽吹いて島を緑で覆う。成果がでるまでには百年かかるかもしれないが、実験は既に宮古島などで行われ成功の見通しが立っている。私案ながらもし沖縄のサンゴ礁からサンゴ砂を運んで埋めたて、ナウル島辺りからリン酸肥料を持ってきて撒けば、植物の成長はさらに早いだろう。最初に繁るのはマングローブかもしれないので、一部伐採してココ椰子を植林することになろう。技術が確立すれば沖ノ鳥島だけでなく、温暖化による海面上昇で水没する危険に晒されている島嶼諸国を救うことができると期待されている(茅根、2004)。
2.東京湾とその沿岸域
海洋と内陸の接点である沿岸域の全長は、入り組んだ入り江や岬、半島が多い日本列島では一部の多島海地域と同様に長い上に人口が集中している点では世界に類を見ない。その場所は魚や海藻などの生物自然資源が豊富である一方、埋め立てによる住宅・工場用地造成と浚渫による大型船航路及び港湾の整備が進められてきた。本報告書には6‐3に愛媛県の事例を記してあるので、ここでは首都圏に関係が深い東京湾について広い視野から略述する。
東京湾は三浦半島の観音崎と房総半島の富津岬に挟まれた浦賀水道以北の面積1,100km2の内湾で、水深は横浜本牧岬東方の中の瀬(水深20m)以北では40mより浅く、海底地形は単調である。沿岸には多摩川、隅田川(荒川)、江戸川、養老川、小櫃川などが運んだ土砂が厚く溜り、滑らかな海岸線から沖1‐2kmは潮間帯か水深2〜3m以内の浅瀬が幅広く連なっていて、海苔の養殖かアサリ、ハマグリの潮干狩りが行われていた。
江戸初期以来営々と埋め立てられてきたのはこの浅瀬である。港湾は浚渫によって整備され、先ず横浜港が、次いで東京港が開かれた。羽田沖の干潟には飛行場が造られ、次第に拡張されて羽田空港になった。房総半島側は冬季関東平野を吹き渡る北西風が当るために頻繁に出入を要する商港はない。三浦半島南部は地層(第三紀層)が硬く、侵食を受け難いので、深い入り江が残って横須賀港を提供した。
戦後高度経済成長期には湾北部の埋め立てが急速に進んだ。サンドポンプで海底の土砂を吸い上げては陸側に積み上げる工法が取られて海側に水深20mの溝ができて生態系を壊すなどの被害も頻発した。現在では簡便小型のマルチナロービーム音響測深機(商標名SeaBatなど)によって浚渫側と埋め立て側の海底をモニターしながら作業をすすめる方式が採用されて改善された。野鳥の集まる干潟の一部(大井干潟など)は保存され、江戸川河口域にはリクリエーション目的の人工海浜が造成された。
東京湾北部とそれに面する関東平野南部は年1mmの割合で沈降を続けている(貝塚、1988)。江東地区は地下水汲み上げによってさらに急速に沈下しておりいわゆるゼロメートル地帯を発生させた。地盤沈下量は江東区、墨田区一帯で1m40cmに達し、時と共に荒川上流に波及した。沈下は大正5年頃から大きくなり、戦前の最盛期には年平均10〜15cmの沈下量を示した。戦時中から戦争直後にかけては沈下量が減少したが、これは疎開と被爆による揚水量の縮小と相関がある。地盤沈下は地下水面(それ以上には水がない面)の低下と関連することがわかった。地下水位は1955年以後59m低下している。揚水の使途は工業用と水道(井戸水)用が40%、建築物(冷却)用10%、農業用5%である。このように大量の揚水によって地層中の水が搾り出され、地下水圧が低下して粘土質の地層が収縮したのが地盤沈下の原因である。「工業用水法」、「ビル用水法」などの規制によって沈下はかなり改善されたとはいえ未だ問題を残している。
地盤沈下は江東、市川、船橋、千葉における1970年ころの天然ガス採取からも起った。目標のメタンは水溶性なので、結局は揚水に頼ることになる。しかも、ガス田は深さ700mないし2000mにあり、深さ200m以内の工業用水よりも影響が大きい。工業権を公的に買い上げることでこの地域のガス採取は停止された。現在は地盤の硬い外房地区の茂原、大多喜でガス採取が続けられている。
自然沈降域の南側には丹沢・葉山・嶺岡(房総半島富浦・鴨川山地)が隆起している。房総半島南部は普段はやや沈降しているが関東地震、元禄地震などの大地震に際して1.5〜6m隆起した。半島南端に見られる段丘群はこのような地殻変動の繰り返しで生じた。
東京湾の海水表層には潮汐作用によって湾に出入りする潮流のほかに大森・羽田—木更津線の南北それぞれに環流が存在する。冬はいずれも時計周りだが、夏は北が反時計回りになる。夏には陸水の流入が増えて塩分濃度が下がる上に日射で表層水温度が上昇するため、低密度の表層水は高密度の深層水と成層構造を作り、大気中の酸素は海底に届かなくなる。表層にリンやアンモニアに富む生活排水が流れ込むと浮遊性の微小藻類が異常増殖して「赤潮」が発生する。プランクトンの遺骸は特に環流の中心部で海底に落下して酸化分解し、ますます海底を還元的な「へどろ」にしてしまう。1970年前後の汚染最大時にはこの有機物過剰域は10m以浅の沿岸域を除いて東京湾北部全域に広がったが、人為的汚染が収まってきた1978年には周辺域はむしろ底棲生物生産量が高い富栄養域に転じた。
冬季には陸からの淡水の流入が夏の半分以下になる上に表層水は冷やされて鉛直混合が促進される。海底にも酸素が補給され、海底にシズク貝やヨッパネスピオンなどの底棲生物が繁殖する。北西季節風によって沿岸から吹き払われた表層水の後に栄養分に富む深層水が湧き上がるので、沿岸部には海苔や海藻が増え、ハゼなどの魚が獲れる。
浦賀水道以南の湾口部には水深100mを超える東京海底谷が入り込んでいる。表層水は黒潮系の外洋水と混じり合っている。塩分濃度も34‰で黒潮に近く、湾奥の31‰以下よりはるかに大きい。水温は高く。表層10m以深では冬でも18℃を超える。館山沿岸には僅かながら冠水性サンゴが生育している。館山沖ではサバやサヨリなどが釣れる。
3. 日本周辺の大陸棚と自然資源
a.地理学的大陸棚と大陸斜面上部
沿岸から沖に向かうとかなりの距離まで水深120mほどの平坦面が続く。これが地形から見た大陸棚である。その幅は地域によってさまざまだが、常磐沖では25ないし30kmで沖に向かって僅かに(平均傾斜0度7分)深くなる。水深140mに達した外縁(Shelf
Break)から突然深く、急傾斜になって水深6000mを超える海溝に続いている。大陸棚は氷期に海水面が低下した時期にできた波蝕面上に堆積物が溜まった所だと考えられている。最終氷期(かってはヴルム氷期と呼ばれた)の最盛期は約2万年前なので、それ以降の地殻変動の影響は一部を除いてそれほど大きくない。
大陸棚の深さは高等学校地学の教科書には深さ200mで統一され、今もって続いている。故佐藤任弘元水路部(海上保安庁海洋情報部)長の述懐によると、これは1950年代の沿岸水深図の精度が悪く、一般向けには100m間隔の水深図を示すのがせいぜいだった時に、100mの等深線よりかなり遠くまで大陸棚が延びていることを示すために次の等深線である200mを採ったのだろうと言われる。日本沿岸の地形測量は1970年以来詳細に実施され、10m間隔(沿岸沿いの一部1m間隔)の等深線を示した「海の基本図」が完成し、1983年のマルチナロービーム測深器の導入以来数十cm以内の精度の地形図が公表されている現状を見れば初等教育の記述も速やかに改善されなければならない。
大陸棚には深海から栄養塩に富む深層水が地形に沿って湧昇している場合が多く好い漁場となっている。プランクトンの遺骸は次々に海底に積る。河川から供給されたやや粗粒の堆積物が厚く積っている。後氷期(洪積世ともいう、氷期があけて海面が上昇を保持馬手以来現在まで)の堆積層だけで2kmを超える厚さの地域が多いが、基盤年代は日本周辺では新第三紀(約2千万年前)で、メキシコ湾や北海の1億年に比べて遥かに若い。
大陸棚外縁の外側は6〜7°の傾斜で深さを増すが、日本海のようにそのまま水深3000m以上の深海盆につながる地域と、本州太平洋側のように水深6000m以上の海溝に達する所がある。東海沖、四国南方のように水深4000m程度の南海トラフと接する地域もある。日本海と南海トラフの大陸斜面では陸から河川で運ばれた堆積物が厚く(>3000m)積っている。富山海底谷や天竜海底谷のように河口から遥か沖合いまで河から流出した土石流が侵食した谷が見られる。谷沿いの崖では比類地層の露頭断面が潜水調査船から観察できる。
大陸斜面に厚く積った堆積物には大量の有機物が含まれているので、メタン資源の宝庫である。
b.国連海洋法上の大陸棚
わが国は国連海洋法条約United Nations Convention on the Law of the Sea,
UNCLOSに1996年7月20日に正式加盟した。その結果「大陸棚限界画定」に必要な地形・地質学的証拠を国連に設置された「大陸棚の限界に関する委員会」に2009年までに提出して審査を受けなければならない。その審査を通って勧告を受ければ沿岸から200海里を越えて海底資源開発に関する主権的権利を行使できる「大陸棚」を「最大350海里または、2500m等深線から100海里のいずれか遠い方を超えない範囲において、大陸斜面脚部からの距離が60海里の地点まで、または、堆積岩の厚さが大陸斜面脚部からの距離の1%となる地点まで延伸できる」。
日本のような海溝域(活動的縁辺域)では大陸斜面脚部を定義する傾斜の最大変化点の一意に定まらないことが多いことに配慮して「科学的・技術的ガイドライン」において「大陸性地殻と海洋性地殻の遷移域における傾斜最大変化点」と定められているため、わが国においては大陸・海洋地殻遷移域を明らかにするために屈折法探査により地殻の厚さと地震波速度を決定すると共に、ドレッジと小規模ボーリングによる基盤岩の試料採取が必要になった。これらの要請を満たすために、2006年に内閣官房の総合調整の下で「大陸棚調査・海洋資源等に関する省庁連絡会議」において関係省庁が緊密に連携して大陸棚調査と取得データの検討を実施することが決定された。
当面は海底地形精密調査と地殻構造探査(一部)を海上保安庁海洋情報部が、文部科学省がJAMSTECを中心として地殻構造探査を担当し、経済産業省(産業総合研究機構とJOGMEC)が基盤岩岩石採取を担当し、地殻構造探査の一部を日本大陸棚調査株式会社に委託して実施している。
日本周辺は元来条約で想定された大西洋型縁辺域とは大幅に構造が異なるため、全く新しい西太平洋型大陸棚縁辺域モデルを、学術論文による国際的認知を含めて構築して行かなければならない。これほど高精度かつ高密度な探査は世界でも類を見ないもので、観測技術、解析ソフトの高度化と審査後のデータの学術的利用に対してその波及効果はきわめて大きい。
c.大陸棚と大陸斜面上部のメタン資源
海底に堆積した有機物はバクテリアの働きで分解されてメタンを生じる。やや深い地層中で地熱作用で発生するメタンもある。地層深部のメタンは海洋地殻の沈み込みに伴ってできたデコルマ面(水を多く含んだプレートのすべり面)やその上に生じる分岐断層を通り道にして地層浅部に浮上し、条件が整った箇所に集結する。海底は水温が低く(3℃前後)水圧は高い(100mで10気圧)ので、メタンは水分子に取込まれて固体の水加物Hydrate(Clathrateとも言う)を形成する。水加物は遊離の気体に比べて著しく体積が小さいので、狭い容積中に多量の気体物質を取込めるという特徴がある。
地層深部では地熱の作用で温度が高いためにある深度以下では水加物は再び分解して遊離のメタンになる。この固相液相境界面では音波速度が急変するので、連続音波探査によって海底相似面Bottom
Simulating Reflector、BSRとして検出できる。BSRは東海沖や日本海新潟沖で明瞭で大量のメタンの存在を示している。日本海溝北端の十勝・日高沖にはBSRが顕著だが、三陸沖ではBSRは明瞭でない。
遊離メタン層に達した高角断層が海底まで続いているとメタンは断層を通って海底に泡立つ。条件が合えば海底上で再び葡萄の房状の水加物になり、遠くから魚群探知機で発見されることがある。直江津沖(水深800m)のメタン(松本ほか、2006)は注目を集めた。浮上したメタンは海面に達する前に海水にすべて溶解しているらしいので大気汚染の心配はないが、万一大気中に放出されるとメタンの温室効果は二酸化炭素の12倍なのでその影響は無視できない。
海底へのメタンの湧き出しは南海トラフでも発見された(Kuramoto, 1998; Ashi
& Tokuyama, 1997)。ここでもメタンは大気到達前に海水に溶けている。さらにゆっくり湧出するメタンは海底直下で泥中にしみ込んだ海水と反応して炭酸石灰殻をつくると同時に硫化水素となって海底に湧出しシロウリ貝の群集を育てていることが潜水船調査の結果判明した(Kobayashi,
2002)。
東海沖のこの湧き出し点のすぐ近くの付加体 (水深945m)で掘削長3500mを超える海底掘削が行われ、海底下1100m以深にメタン水加物の存在が確認された(Tsuji
et al, 2004)。メタンはうまく安価に回収できれば二酸化炭素をほとんど出さない燃料として有用だと考えられる。賦存量の見積りと存在状況のさらに詳しい調査が緊急に必要である。メタンは万一海底付近に漏れても直ちに水加物になって海底局所に積るから一部で取沙汰されているような採取時の事故による海底汚染の心配はない。
d.大陸棚の石油・天然ガス資源
新潟沖、秋田沖では陸上油田の延長として大陸棚で採掘が続けられている。常磐沖の天然ガス(ブタン、プロパンなど)も有望視されている。北海道周辺のオホーツク海大陸棚、日本海側の留萌から利尻島に至る天北沖、奥尻沖や十勝沖も堆積物は厚いが油田の存在は踏めである。
東シナ海は堆積物の厚さが5�qに達する所もあって油田・天然ガス田の存在が注目されているが、わが国と中国、韓国間の権益関係が未解決のため1960年代にUN
ECAFEをバックに実施された堆積層探査(Emery et al, 1969)以来公表された資料が乏しい。
4.沖縄トラフの熱水鉱床
琉球諸島の西に沿って水深2000m弱の窪みが長く延びていて沖縄トラフと呼ばれる。「しんかい2000」が1994年に300℃を超える激しい熱水噴出を発見したのはその南部の伊平屋凹地、伊是名海穴であった。その後南部の第四与那国海丘や鳩間海丘、北部の南奄西海丘でも熱水噴出が見つかっている。熱水噴出孔から立ち上る黒煙にはニッケル、銅、亜鉛などの重金属硫化物が多量に含まれているので黒煙そのものかその堆積物をうまく採取できれば有用金属資源として利用できる。噴出が現在進行中なので、いったん採掘しても次々と生産されてくる持続的資源である。
熱水噴出は小笠原西方の七曜海山列でも知られているが、堆積した硫化物は底層水中の酸素によって急速に酸化され、海水に溶解してしまう。沖縄トラフでは周囲から運ばれる堆積物によって被覆され酸化と溶解を免れる。堆積層直下にかなりの量の重金属鉱床が埋積している可能性が高い。金属鉱床として有用であろう。
沖縄トラフの特異な現象は熱水に伴う二酸化炭素の湧出ととその水加物化である。堆積物中のメタンが熱水の熱で分解し、酸化されて二酸化炭素となって噴出するが、海底の低温と水圧によって直ちに水加物になって葡萄の房状をしている。この現象そのものは自然資源としての意義は薄いかもしれないが、海底における天然二酸化炭素水加物の振る舞いは工業産出物としての二酸化炭素の海底処理に対して好い指針を与える。メタン水加物採取船に固化二酸化炭素を積んで行ってメタン採取作業終了後に同じ孔か周囲の海底に二酸化炭素を投棄すればそのまま水加物として安定に保管される。
5.小笠原東方の海山・海台群と重金属資源
本州の約1000km南に南北に並ぶ小笠原群島は南端に近い父島と母島が特に大きく人口も多い。父島の約50km北には小さな5島からなる婿島列島がある。父島の二見港には晴海埠頭から定期船が通っている。どの島も自然公園として美しく、海亀など多様な海洋生物の生息地である。いずれも環境保護の教材を与える貴重な存在であるが、サンゴ礁生育の北限にあり、黒潮の流域から離れているためにサンゴ礁は未発達である。
小笠原群島は伊豆七島・硫黄島などの活火山列よりも150km東にあり、伊豆小笠原海溝から80kmしか離れていない。4千3百万年前に太平洋プレートの移動方向が北向きから現在の西北西むきに変った直後に沈み込んだばかりのプレート先端が融けて生じた火山岩からできている。父島にはボニナイトBoniniteと呼ばれる富マグネシウム安山岩を産し、母島海岸には4千3百万年前の化石である貨幣石Numulites
boninensisが散在する。
地形学的な大陸棚は広く、東西の幅約20km、南北には小笠原群島すべてをつないで200km近く延びている。行政的には沖ノ鳥島や硫黄島なども東京都小笠原村に属する。これらを含めた場合は小笠原諸島と呼ぶことになっている。
母島東方110kmには母島海山と名付けられた海山(山頂水深1050m)があってその付近で伊豆小笠原海溝の深みは途切れている。堆積物は厚く水深3200mを切る浅部が東に続いている。さらに東には全体として小笠原海台と呼ばれる高まりが少なくとも300km太平洋に向かって延びている。海台の裾野の堆積物はかなり厚い。海底地形と海底地殻構造は現在精密調査中であるが、地殻はかなり厚いようで大陸地殻と呼べるほどである。この自然条件はわが国の専管経済水域(EEZ)を母島から東へ延伸できる用件を備えている(図4‐1‐4参照)。
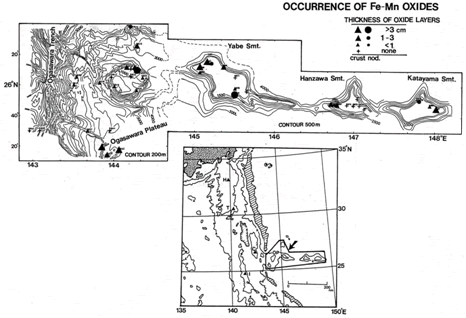
図4‐1‐4 小笠原海台とそこに産する富コバルトクラストの分布
小笠原海台に乗る海山には山頂水深が1000m以浅のものもある。東部の海山はやや深く山頂が1500m誓い深さのものもあるが、頂上は平坦である。いずれの海山にも肩の部分に厚さ数cmの重金属水酸化物のクラストで覆われている。金属の大部分は鉄かマンガンだが、コバルトを1ないし2wt%含むものがあるのでその資源として貴重である。同様な富コバルトクラストは小笠原海台の南やわが国最東端の領土である南鳥島を囲む200海里の南半円内に多数分布する海山上にも存在する可能性が高い。採取法はすでに考案され成功を収めている。無人潜水機ROV(Remotely Operated Vehicle)、AUV(Autonomous Underwater Vehicle)や曳航型テレビで賦存状況と化学成分を精密調査して置く必要がある。
6. 沖ノ鳥島の利用
国連海洋法条約の第121条「島の制度」の第1項で「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と規定されていて、この定義では「沖ノ鳥島」は一応「島」ということにはなる。しかし、第3項に、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」という規定があり、「沖ノ鳥島」は国連海洋法条例では島としての条件を満たしていない。従って、現状のままで沖ノ鳥島の排他的経済水域や大陸棚の権利を主張することにはやや無理がある。そこで、日本の主導の下で、以下のような活動を起こし、上記第3項の解決を目指すことを提案する。
第1は、沖ノ鳥島に研究所を設置して、地の利を生かした研究や技術開発を国際共同の枠組みで実施する。研究者・技術者は日本人を始め世界各国から来ることになるが、研究所の運営は日本主導で行うので事務・技術・滞在などの支援はできるだけ日本人が行う。研究課題としては、上述の1.サンゴ礁の創生を始めとして、2.太平洋の熱帯域で、通常は観測船でないとできないような、陸地の影響の無い環境でのさまざまな実験・研究(観測船の限られた空間や動揺による影響の無い状態で可能。しかも長期的、連続的にも。)、3.その他、広く実験・研究課題を世界中から公募して、適当な課題を選択して実施していく。
第2は、沖ノ鳥島をエコツーリズムの基地の1つとすることである。太平洋にも、2002年までミッドウエー島でエコツーリズム事業が行われており、その他の島でもエコツーリズムが盛んである。ただ、これらの島と大きく異なるのは、沖ノ鳥島では海面上に現れている陸上部分の面積が極めて小さく、従って定住者が全くいなかったことである。しかし、沖ノ鳥島には人が定住する島や無人島などとは異なった魅力があり、それらを抽出して、エコツーリズム事業とする。
第3は、上述の海底観測ステーションを結ぶ海底ケーブル基地としたり、放送衛星を通じたデータ発信局を設置して利用する。
沖ノ鳥島の利用では、大量の物資は船舶輸送を利用することとし、人などの輸送には水上飛行艇(日本では自衛隊が使用)などを活用して、迅速化する必要がある。
(2)課題
1.海洋基本法とわが国の自然資源
2007年7月に成立、施行された海洋基本法はその第二十二条に「国は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の状況の把握、海洋環境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施並びに海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備に努めるものとする。 2.国は、地方公共団体の海洋に関する施策の策定及び実施並びに事業者その他の者の活動に資するため、海洋調査により得られた情報の提供に努めるものとする。」として海洋調査の推進と情報公開をうたっている。また海洋科学技術の研究開発に関して第二十三条で「国は、海洋に関する科学技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及を図るため、海洋科学技術に関し、研究体制の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化その他の必要な措置をとるものとする。」と明記している。国民教育と人材育成については第二十八条で「国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育および社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。 2.国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、大学などにおいて学際的な教育及び研究が推進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と書かれている。私はこの第二十八条がとりわけ対応不足のように感じていて、4章2‐2節に対応策を記した。
2.自然資源の統合的管理上の課題
自然資源を取り巻く環境(気候、人口、産業発展など)が常に変動していることは既に第2章にも詳しく論じられている。その将来を予測し対策を立てることは現代の急務である。その際に過去の変動を復元してその因果関係を明らかにすることは問題解決にきわめて有効である(「温古知新」)。過去のタイムスケールは対象によって異なるが、先ず数百年、次に有史以来の情報が必要であろう。できるならば最終氷期終了以来2万年間の自然資源変動を把握することが未来を把握するためにぜひとも望ましい。さらに今から40万年前の間氷期には現在よりも温暖だったことが知られていて、もしかすると地球温暖化後の未来の鏡なのかもしれない。
これらの情報は陸では沼や湖に溜っている花粉の分析から復元できる。屋久杉の年輪も役に立った。海では海底堆積物のピストンコア試料が有効である。ただし西太平洋では水深が深すぎて炭酸石灰の殻を持つ微化石が海水に溶けてしまっていてデータが不足である。2000mよりも浅い平頂海山山頂に積った堆積物が役立つと思われるので、堆積物の分布状態の精密調査が望まれる。現生サンゴ礁の石灰岩のコア試料も有効で、この収集と分析は1980年代に日本のグループの手で実施されたが、現生サンゴ礁が沖縄を除いては熱帯にしか存在しないために中緯度のデータが手に入らないのが欠点である。
氷床の鉛直コアは含まれている酸素の同位体分析を通じて好い古環境指標になる。日本の南極観測隊が採取した南極氷床中央部(ドームふじ)のコアは最良の記録を提供できると期待されている。グリーンランド氷床との比較から南北両極の温暖化・寒冷化がほとんど同時に(数十年以内の差で)起っていることがわかった。氷期・間氷期のサイクルが地球軌道要素による天文学的原因によるならば北と南の変化は逆位相になってもおかしくない。南北をいちはやく結ぶ仕組みが存在するに違いないので、これが将来の変動にも大きな働きをする可能性がある。
参考文献 4‐1‐4節
(1) Ashi J. & Tokuyama, H., 1997、Cold seepage and gas hydrate BSR in
the Nankai Trough, Proc. Intern. Workshop on Gas hydrate studies, 256‐273.
(2) Emery, O. K. et al., 1969, Geological structure and some water
characteristics of the East China Sea and the Yellow Sea, United Nations
ESCAFE, CCOP, Tech. Bull., 2, 3‐43.
(3) Klein, J., Kobayashi, K. et. al., 1978, Off‐ridge volcanism and
seafloor spreading in the Shikoku Basin, Nature, 273, 746‐748.
(4) Kobayashi, K., 2002, Tectonic significance of the cold seepage zones
in the eastern Nankai accretionary wedge‐an outcome
of the 15 years' KAIKO projects, Mar. Geol., 187, 3‐30.
(5) Kuramoto, S., 1998, Sea floor explosion by gas hydrate disociation
at off‐Omaezaki eastern Nankai accretionary wedge, Abstr. Symp. KAIKO0Tokai,
p.13.
(6) Tsuji, Y., Ishida, H., Nakamizu, M., Matsumoto, R. & Shimizu,
S., 2004, Overview of the MITI Nankai Trough wells: A milestone in the evaluation
of methane hydrate resources, Resource Geol., 54, 1, 3‐10.
(7) 大森信,谷口洋基,2005,沖ノ鳥島の陸地化水深計画,みどりいし,16,1‐4.
(8) 貝塚爽平,1988,東京の自然史(増補第2版),紀伊国屋書店,239pp
(9) 茅根創,2004,水没する環礁州島とその再生—太平洋島嶼国とわが国国境の島々の国土維持,Ship
& Ocean Newsletter, 99, 2‐3.
(10)杉山敏郎,1934,北大東島試錘について,東北帝国大学地質学古生物学教室研究邦文報告,11,1‐44.
(11)杉山敏郎,1936,第2回北大東島試錘について,東北帝国大学地質学古生物学教室研究邦文報告,25,1‐34.
4‐1‐5 土地資源管理
(1)現状
農村には、農地、農業用水、多様な生態系、美しい景観などのさまざまな地域資源が存在する。農業はその生産活動を通じて、食料を供給するだけではなく、これらの資源を有効に利用することによって、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成など、人間の社会的営みに多くの効用をもたらしている。このような農業の有する多面的機能について、2001年11月、日本学術会議は幅広い学術的な見地から表4‐1‐3のような答申を行っているが、農業生産や食料生産の確保その他農業のもつ多面的機能の発揮には、農地や農業用水などは最も基礎的な資源であり不可欠な社会資本である。
表4‐1‐3 日本学術会議の答申で示された農業の多面的機能
| 1 持続的食料供給が国民に与える将来に対する安心 |
| 2 農業的土地利用が物質循環系を補完することによる環境への貢献 1〉 農業による物質循環系の形成 (1) 水資源の制御による地域社会への貢献(洪水防御、土壌浸食防止、地下水涵養、等) (2) 環境への負荷の除去・緩和(水質浄化、大気調節、等) 2) 2次的(人工的)自然の形成・維持 (1) 新たな生態系としての生物多様性の保全等(生物生態系保全、遺伝資源保全、等) (2) 土地空間の保全(優良農地の動態保全、みどり空間の提供、等) |
| 3 生産・生活空間の一体性と地域社会の形成・維持 1) 地域社会文化の形成・維持 (1) 地域社会の振興 (2) 伝統文化の保全 2) 都市的緊張の緩和 (1) 人間性の回復 (2) 体験学習と教育 |
資料: 日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価について〈答申〉」(平成11年11月)
農業生産活動や農村集落組織が適切に営まれている限りは、農村に存在する諸々の資源が有効に活かされ、農業の多面的機能も十全に発揮されることになろう。すなわち、自然環境や生物多様性などを含めて農村には多様な資源があり、また相互に関わりあってその機能が発揮されているのである。例えば、山林は雨水の保留によって国土保全の役割を果たし、健全な水循環は生態系の保全や景観の保持に寄与する。しかし、農村の有する資源が適切に管理されず、一度その特質や機能が損なわれると、人々の社会的な活動にも支障を来しかねないし、その復元には多大な時間と経費とを投入しなければならない。従って、その賦存の形態や賦存量に見合った適切な保全管理への取組みが常に必要とされているのである。
わが国の耕地面積は、過去40年間に、主として人為的な壊廃(非農業用途への転用が半ばを占める)によって22%も減少し、作付け延べ面積も40%強の減退を記録している。この間、都市化の進展に伴って農村人口特に農家人口も激減した。総人口に占める農家人口の割合は、1965年の31%から2005年には7%にまで落ち込んでいる。その上、農業就業者の高齢化も進み、総務省「労働力調査」によれば、農業就業人口に占める65歳以上人口の割合は、1970年の12%から2005年には47%(販売農家についての農林水産省の調査では58%)にまで上昇している。このような農家人口の減少や高齢化が農地や農業用水路の維持管理に負の影響を及ぼし、耕地の壊廃や作付面積の減少をもたらしていることは想像に難くないし、その中でも、耕作放棄という現象は資源管理に対する負の影響がもたらした結果を端的に表現していると言えるであろう。
最近は耕地の非農業用途への転用の勢いは収まる傾向にあるが、耕作放棄がそれを上回って増加しており、耕作放棄が耕地面積減少の大きな要因になっている。耕作放棄面積はこの10年間に1.6倍に増加し、2005年現在では38.6万ha、耕地面積の8%にまで達している。最近の耕作放棄地の増加は土地持ち農家や自給的農家によるものが多く、販売農家による耕作放棄地面積は減少する傾向にある。現在38.6万haを数える耕作放棄地面積の42%は土地持ち非農家、21%は自給的農家にものである。また、耕作放棄地面積は中間農業地域に最も多く見られるが、耕地面積に対する割合は山間農業地域で最も高く、労働力不足と生産性の低さが耕作放棄の主な発生要因とされているが、虫食い的な開発や都市的地域での相続による農地の分散化なども耕作放棄に繋がっている。平成17年〈2005年〉に改正された農業経営基盤強化促進法によって、耕作放棄地所有者への指導や担い手への農地集積への働きかけ、その他農地利用増進のための権利移動や賃借権の設定などのための施策が実施に移されている。しかし、農産物価格の低落傾向による営農意欲の低下や農家が資産として土地の保有にこだわる傾向が、事態を改善させることを妨げている。
(2)課題(土地及び水資源管理の仕組み)
農地や農業用水路の維持管理にかかわる作業は、地域によってその具体的な内容には違いがあるが、農村集落の共同作業として行われる場合が一般的である。しかし、農村集落の変質(人口の減少、混住化、高齢化、等)によってその様相が変わってきている。例えば、農業用水路の維持管理を集落の共同作業で行っている集落を対象として行った調査の結果を2000年と2005年とについて比較してみると、共同作業への参加人員が減少した集落の数は全体の19%になっている1)。また農林水産省が行った調査に結果によると、表4‐1‐4に示すように、農道や農業用水路の管理についての集落の関与の仕方がここ数年の間に大きく後退したと判断せざるを得ない。すなわち、集落農家全戸での共同作業は1990年代に既に減少傾向にあったとはいえ、集落管理という形態はここ5年間に急激にその比重を落とし、集落として管理が行われていない割合が最近の5年間に、農道では35%から48%へ、用水路では22%から40%へと、それぞれ急増しているのである。なお、なお、農林水産省農林水産政策研究所の資料2)は、集落管理から非集落管理に移行した集落では、集落管理が行われている集落に比べて農地面積の減少が進んでいることを明らかにしており、共同作業の困難化が農地の壊廃にも影響を及ぼしていることを窺わせる。
表4‐1‐4 農道及び用水路の集落管理
| 調査年月 | 農道の管理 | 用水路の管理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集落数
1000 戸 |
集落管理
% |
全戸共同
% |
集落不管理
% |
集落数
1000 戸 |
集落管理
% |
全戸共同
% |
集落不管理
% |
|
| 1990 年2月 | 133 | 65.0 | 57.6 | 35.0 | 128 | 75.6 | 42.4 | 24.4 |
| 2000 年2月 | 122 | 64.6 | 51.5 | 35.4 | 123 | 78.2 | 39.9 | 21.8 |
| 2005 年12月 | 106 | 51.4 | - | 46.1 | 106 | 60.4 | - | 39.6 |
註:
(1)%は各項目に関する集落数の善集落数に対する割合
(2〉全戸共同は集落管理の内数
(3)集落不管理には水利組合等集落外組織管理を含む
資料:農林水産省統計部「ポケット農林水産統計」 平成14,16年度版
農道や農業用水路等の維持管理に関する地域の共同作業については、農家の7割が負担に感じているとしており、作業内容に応じて農家や非農家その他地域住民等の多様な主体の参加を期待する農民が多いという。また一般市民の6割は、農家が中心となった農地や用水路の維持管理活動が集落構造の変化等により脆弱化していることを認識している、という調査結果もある3)。多様な資源に恵まれている農村地域では、人口の減少や混住化などによって資源の有効な利用のみならずその維持管理にも悪影響がでてきているが、我々はその現実を見きわめ、資源利用の活性化に真剣に取り組まなければならない段階に来ていることを認識しなければならないであろう。
参考文献 4‐1‐5節
(1) 農林水産省「農林業センサス付帯調査 農村集落調査」 平成17年
(2) 農林水産省農林水産政策研究所「農業集落の変容が農村地域社会に及ぼす影響調査」,平成18年7月
(3) 農林水産省「農村の地域資源(農地、農業用水、等)の維持管理に関する農家の意向」,平成17年2月農林水産省「国民意識調査」,平成18年1月
4‐2 統合的管理の必要性と提言
4‐2‐1 生態系資源
(1)林業資源
かつての日本は山から出てきた木質材料を無駄なく利用することで世界に知られていた。除伐・間伐で出てくる細い丸太もそれなりの使い道があったし、スギやヒノキの枝葉まで燃料として使われていたのである。ところが1980年代あたりから、人工林を伐採しても市場に出ていくのは比較的値段の高い部分だけで、低質の二、三番玉や除間伐材の多くは出しても引き合わないということで林内に捨てられるようになった。木材利用の集約化が進む世界の大勢とはまったく逆である。製紙用チップの大部分は海外から輸入され、木屑類も化石燃料に圧倒されてほとんどエネルギー生産には使われない。
世界全体の流れは、良質のムク材に替わって、並材、低質材を使った集成材や合板のような「再構成木材」が主流になりつつある。再構成木材はオートメーションによる大量生産が可能なだけに、安いコストで生産できる。これがムク材の価格を押し下げているのだ。となれば、優良材だけに頼る方式を改め、量的に多い並材・低質材を最大限に無駄なく利用するということになるのだが、並材・低質材の場合は、林業・林産業の統合や規模拡大がないと有効利用が難しい。
わが国の林業・林産業が当面する最大の課題は、優良材生産に偏重した一番玉林業から脱却し、国内の森林から出てくる多種多様な木質系のマテリアルを無駄なく順次使い切っていく「カスケード利用」を実現することである。そのために必要なのは、木材の生産・加工・流通システム全体の変革であり、ポイントとなるのは次の3点だ。
イ)建築用材、パルプ材、燃料用バイオマスなどの木質マテリアルを山から一体として収穫・搬出するシステムを確立すること。一例をあげると、山で伐倒した林木を枝の付いたまま全木で林道端まで引出し、枝払い、幹の切断、切断された丸太の仕分けまでを機械(プロセッサやハーベスタ)で一貫して行うシステムがそれである。
ロ)零細な森林所有の境界を超えて、間伐等の山での作業ロットをできるだけ大きくし、機械類の効率的な導入を図ること。加えて自分の森林を管理できない所有者が急増しており、この面からも、さまざまな所有者の森林をある程度地域的にまとめて間伐などを組織的に実行することが不可欠になっている。
ハ)木質マテリアルのカスケード利用が徹底できるように林産業の統合と集約化を推し進めること。例えば、最良の材は建築用の無垢の材として出荷し、欠陥のあるものは集成材などに加工して付加価値を高め、その後に残る残廃材で電気と熱を生産して木材の加工や乾燥用のエネルギーに振向ける。こうした一貫システムは林産業の統合と集約化によって実現される。まさに「ウッドコンビナート」だ。
森林バイオマスのエネルギー利用も林業・林産業の発展と密接に結びついている。北米や北欧などの一部の地域においては、木材工業の統合と規模拡大が進展する一方で、木材の伐出においても高度に機械化された生産システムが普及し、森林から出てくる木質マテリアルが余すところなく使い尽くされる体制が確立した。
わが国ではこの点が十分に理解されていない。「木材が駄目ならエネルギーで」といった安易な風潮が見られるのは残念なことだ。通常の木材生産・加工・流通システムのなかにしっかりと組み込まれない限り、森林バイオマスのエネルギー利用は経済的に成り立たない。また木質エネルギー部門をうまく組み込まなければ、林業・林産業の近代化は果たされないのだ。
森林資源を「統合的に」管理するという場合、いくつかの視点があると思うが、本節のこれまでの論議は木材の生産、加工、流通にかかわる全プロセスの統合を念頭においたものであった。これと並んでもう1つ重要なのは、森林が果たすべきその他の環境保全的、社会的な諸機能との調整の問題である。
森林資源は林産物を供給する生産的資源であるとともに、自然環境の不可欠の部分を構成する環境資源である。高度に発達した工業化社会において、環境としての森林の役割はきわめて大きく、今後さらに高まることは間違いない。その一方で木材の需要も世界的に増加している。しかも経済活動としての林業・林産業の分野では、市場経済にゆだねる傾向が一段と強まってきた。早く言えば、「官」の役割が後退して、「民」がどんどん表に出てきている。各国の木材産業が孤立的な地場産業として展開しているうちは、官主導でも何とかやっていけたのだが、木材市場の国際化とともに、状況の変化がきわめてダイナミックになり、「官」特有の硬直的なやり方ではとても対応できなくなったからである。
もちろん公共部門の役割がなくなったわけではない。林業の最も基本的なインフラである林道・作業道の路網整備はそのひとつだし、国ないし地域全体の森林管理を持続可能な方向に誘導するのも大事な仕事である。さらに重要なのは森林環境を保全することだ。今後広い地域から大量の木材が集荷されるようになり、大型の伐出機械類が入ってくるようになると、その環境インパクトが無視できない。
わが国の場合、水源保護や国土保全、さらには保健休養など公益面で重要な森林については保安林制度で保護されることになっている。森林以外の用途への転用が禁止されていたり、森林の取扱いについても制限を受けることもある。しかし全森林の半分近くにも及ぶ保安林のうち禁伐などの強い施業規制を受けているのはごく一部で、大部分は通常の施業なら何の差支えもないほどに規制が緩い。大面積に皆伐して造林しないで放置しても処罰されないのだ。
イギリスでは国営造林に代わって民間の企業的な林業経営が盛んになっているが、この国では樹木の伐採に対する規制が厳しく、国有林であれ、私有林であれ、政府の許可なしには伐採が許されない。日本の林野庁に相当する林業委員会の基本的な任務は、「善良な森林施業」を推進することであり、伐採許可制度はこのための手段となっている。つまり善良な施業の条件を満たしていないと伐採は許可されない。許可するか否かを判断する際の指針となっているのが、イギリス政府が定めた林業基準である。
この基準は、1992年の「環境と開発に関する国連会議・地球サミット」に端を発する「持続可能な森林経営の規準と指標」づくりと連動している。具体的な基準と指標の作成は地域ごとに進められているが、ヨーロッパ諸国は98年に「汎ヨーロッパの規準と指標」を定め、持続可能な森林管理の原則として次の項目を指示している。
- 森林資源及びグローバルな炭素循環に果たす森林の役割を維持し、適切に向上させること
- 森林生態系の健康と活力を維持すること
- 木材・非木材にかかわる森林の生産的機能を維持・増進すること
- 森林生態系における生物多様性を維持・保全し、適切に向上させること
- 特に土壌と水にかかわる森林生態系の保護機能を維持し、適切に高めること
- その他の社会経済的機能と条件を維持すること
イギリスの林業基準にはこの要件が組み込まれている。森林資源の統合的管理というのはこうした要件のすべてが満たされるように管理していくことであり、木材生産の大前提でもある。
前述のように、わが国森林の林木蓄積量は今や50億m3を超えている。これをベースにして高いレベルで木材を持続的に生産しうる体制を確立することが、当面の最大の課題である。そのための第1の要件は、山から下りてくる木質材料を余すところなく使い尽くすカスケード利用のシステムを確立することだ。そしてこの種の「ウッドコンビナート」が有効に機能するためには森林からの安定した木材の供給が不可欠であり、林道・作業道の整備、施業の集団化、能率的な伐出システムの導入が求められるのもそのためである。これらはいずれも「持続可能な森林経営の規準と指標」を満たしていなければならない。わが国においても、イギリスの伐採許可制度のような強制力の強い措置を導入すべきであろう。
(2)農業資源
農地や農業用水、多様な生態系、等の農村地域に存在する自然資源は、地域住民は勿論、国民が広く享受している農業の多面的機能の発揮にも深く関わっており、農家を主体とする農業生産活動や集落での社会的活動を通じて、地域ぐるみでその維持保全が図られてきた。しかし、農家の兼業化や高齢化、農村での過疎化や混住化、等によって農村集落には構造的な変化が生じ、農業生産活動の停滞のみならず、集落での社会的な活動にも沈滞が見られるようになってきた。このような農村での諸活動の沈滞化や集落機能の低下は、農村資源の維持保全及びその活用を困難にしてきており、あらためて資源維持管理のための仕組みを構築し直す必要に迫られていることが痛感される。他方、自然環境保護の動きが全国的に広がってきており、全国の半数を超える集落で景観や地域環境の保全活動が、また7%の集落で自然動植物の保護活動が行われ、近年その割合が上昇傾向しているともいわれ1)、自然環境保護の動きが更に活発化することも期待される。
自然環境保全に関しては、農業のみならず森林整備の面でも新たな動きが見られる。森林を整備し保全してゆく上で重視すべき機能に応じて「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」に区分し、それらの区分毎に望ましい森林の姿やそれに誘導するための森林施業の考え方を明らかにし、適正な整備・保全による望ましい森林の状態が確保されされるための施業実施の条件整備に取り組むこととしている、そのため、針広混交林、広葉樹林、大径木からなる森林等へ誘導する多様な施業の適切な実施に向けて、森林所有者への情報提供、間伐などの適切な施業技術の普及、低コスト・高能率な作業システムの整備など、森林整備の低コスト化への努力が進められている。
一方、環境問題に対する国民の関心が高まるなかで、農業生産のあり方にも環境保全をより重視する方向に転換することが求められよう。農業は本来自然界における水・窒素・炭素といった物質の循環を利用した持続可能な生産活動である。しかし、肥料や農薬などの過剰投入や家畜排泄物の不適切な管理による環境への負荷の増大、具体的には、地下水の硝酸性窒素濃度の上昇や湖沼・海域での富栄養化などが懸念されるようになってきた。これを受けて、全国の販売農家の約半数が化学肥料・農薬等の投入の低減や堆肥による土作りなどに取り組んでいるし、稲作農家の40%、露地野菜作農家の65%、など多くの農家が何らかの形での環境保全型農業を志向しているのが現状である。
環境保全を重視した農業への取組みが広がるなかで、農業が本来有する自然循環機能を維持増進するという観点から、地域的な広がりを持った取組みが求められている。そのため、農業者の環境保全をめざした着実な実践活動のみならず、地域全体としての纏まりをもった共同の取組みを推進すべく、2005年3月には「環境と調和のとれた農業生産活動(農業環境規範)」が策定され、この規範の実践と各種支援策とを関連付ける取組みが進められている。また、農村の有する資源の質を高めながら、更に将来に亘っての保全を考えて、2007年度からは、化学的薬剤使用の大幅な削減などの環境保全のための相当程度の纏まりをもった先進的共同活動への支援を内容とする「農地・水・環境保全向上対策」が、国と地方公共団体との緊密な連携の下に進められることとなった。なお、この対策の実施に向けてのモデル的取組みとして、農業者や農業関係諸団体だけではなく、自治体・町内会・学校・PTAといった多様な主体の参画が促されており、具体的な活動内容としては、水路沿いの花の植え付け、草刈りや泥浚いなどといった地域環境の整備・保全のための活動の輪が広がってきている。
森林の整備・保全についても市民参加の意識が高まってきており、NPOをはじめとするさまざまな主体によるボランテイア活動を中心とした動きが活発化している。その内容は、上下流域の住民等が連携して行う水源地域での森林作りや、漁業関係者等の行う河川上流での森林作りなど、きわめて多岐に亘っている。また、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として森林の整備・保全活動を通じた社会貢献を意図する企業が見られるようになっており、内閣府が実施した「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」では、「植林・間伐などの森林を守る活動」に対する協力を社会貢献と考える企業が多かった2)。
参考文献 4‐2‐1(2)節
(1) 農林水産省「農林業センサス付帯調査 農村集落調査」 平成17年
内閣府「自然の保護と利用に関する世論調査」 平成18年9月
(2) 内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」 平成17年11月
(3)漁業資源
海の利用は、古から交流のための海上交通手段、17世紀にはいると領土拡大を目指した新大陸進出へのルートとして開発利用されてきた。現代の海洋の利用はいわば戦略的な意味合いが強く、今でも海洋科学先進国の米国やフランスはそうした側面を色濃く残し、研究でもそうした分野に資金を投入している。日本はそうした国々とは異なり、国内陸域にタンパク質資源が少ないと言った事情から、食料資源としての水産物の利用、海の平和利用、と言うことで海に接してきた。特に、明治以降、日本の水産物利用科学は世界に例を見ない形で発展し、現在でもすり身化技術、鮮度保持技術、マグロの冷凍技術、グルタミン酸に代表される呈味性の研究など水産物の利用科学は世界の最先端を行く。さらに、ハード技術では、魚の探査技術、テグス開発に見られる漁具漁法技術、漁船の造船技術、ソフトでは当時最も効率的とされた水産物の流通機構など水産を取り巻く総合的な技術が整っている。利用している魚種は世界で最も多く、質量からいえば現在でも築地市場は世界で最も取扱量が多い市場だろう。世界中の海で漁獲可能な魚種、オキアミや深海の魚種も含めて潜在資源量を研究開発したのは日本の調査船である。こうした世界をリードする科学技術を活用し、世界に貢献することが可能であり、海洋水産物の恩恵を得てきた国として果たすべき役割となるだろう。日本は、こうした技術知識を生かして、世界の海の管理、海洋の利用と保全、に関して、国際舞台でもっと強く主張すべきだと考える
現段階では、自然の水産資源の再生産は人為的管理下にはなく、自然環境に依拠せざろうえないと言う点で、陸域の農林物生産とは決定的に異なる。たとえ特定種の資源増大を狙い種苗の大量放流を図ったとしても自然の産卵数とは比較にならないし、少ない親魚から遺伝子の似た大量の稚仔魚を作成し、放流することは自然の多様性を攪乱する要因になりかねない。水産資源管理に人為的要因が入り込むことは、できる限り排除すべきかもしれない。例えば人間にとって有用だからと言って、特定の単一種だけ利用する、放流すると言うことは生物連鎖を乱すことになる可能性があり、こうした手法は絶滅が危惧される場合とかに限定すべきかもしれない。
海を生産場としでどう利用、保全していくかは今後問われる。沿岸域は接続する漁村や漁協が一義的に管理の主体になる。近年、養殖産業が盛んになり、安定した食糧供給を担うことが期待されるが、一方で、養殖産業は沿岸環境、とりわけ、沿岸生物連鎖に影響することが推定される。ここの海域で沿岸の天然生物資源、環境にどのような影響を及ぼすかを評価して、沿岸域の適切な管理を図っていくことが求められるだろう。沖合い域は水産生物の育成の場として重要で、より広域管理が求められ、県レベルで施策を立て管理することが必要だ。日本近海の排他的経済水域は世界でも有数な好漁場を形成している。こうした海域の保全と管理は日本の水産食糧の安定供給の中枢にある。単に少数の有用種の利用を図るのではなく、食物連鎖を頭に入れて、複数種の効率的総合利用を図るべきだろう、また、そうした海域の基礎生産の向上、底上げを図ることも有効かもしれない。研究が必要である。さらに、排他的経済水域では外国漁船も操業を行っている。そうした船にも、漁業環境、漁業管理を遵守してもらうことが重要になる。公海での資源争奪はますます厳しくなり、漁業規制が強化されるに違いない。公海における漁業資源の研究、開発は日本が戦後取り組んできた技術であり、恐らく、優れた総合的ノウハウを持つ唯一の国だろう。こうした知見を生かし、公海での日本の権利、海洋の平和利用、を主張、確保していくためにも、国際会議の場に積極的に打って出ることが求められる。
多くの水産生物資源は回遊する。マグロやカツオはその代表的な魚種である。そのために、再生産にいたるまで、地球の運動、海流など地球規模でのさまざまな自然環境の複雑で、微妙な影響を受けることになる。地球環境が変化すれば、自然の水産生物資源は柔軟で、したたかであり、そうした変化に適応して再生産のために新たなバランスを模索する。そうした反面、一方で、些細なことに敏感で脆弱でもある。地球上では、近年の地球環境の変化に伴い、毎年多数の生物種が絶滅していると言われていて、ヒトがそうした起因になっているとの指摘もあるが、そうした絶滅を人為的に加速する事態は避けるべきであろう。
水圏の有効利用は、漁業管理、生産管理だけでは達成できない。生産から消費までの科学技術、つまり、地球規模での物質循環を視野にいれ、自然と調和した技術を開発することが必要である。そうした点で、漁獲物の有効利用、廃棄物、炭酸ガスを排出しない加工法などの研究も課題となり、他分野、異業種との連携が今後必要になる。
自然の水産資源にどのような要因が影響を及ぼすかについては、まだまだ未解明ことが多い。特に、漁業管理を地域で実行していくためには、その場その場で条件が違い、それら充分に把握することが不可欠であるが、現段階での科学的研究は不十分であるといわざろう得ない。自然の水産資源管理の基礎は緻密な科学的研究を展開し、その論拠に基づいた方策の立案にあるが、さらに考慮すべきことは、資源に及ぼす影響には、自然現象のみならず、経済的、社会的ニーズなどソフトにかかわる問題、それ以外に時代と供に新たに起こる地球の温暖化などの要因も含まれる。こうした側面も含めて漁業管理を図っていくことが欠かせない。また、こうした資源管理を考える場合、ヒトが自然を超える存在としてではなく、地球と言う環境の中でヒトと自然との長期で、安定した相互関係を維持できるような思考も重要である。
(4)森林土壌資源と森林資源
1.森林土壌資源
a.土壌の生成的特徴
一般に、岩石から、暗色の表層、黄褐色〜赤褐色を呈する中間層、淡色の下層からなる土壌断面をもつ土壌が生成される過程は、物理的土壌生成過程と生物的土壌生成過程に大別される。
イ)物理的土壌生成過程
土壌の物理的土壌生成過程は、火成岩、水成岩、変成岩、火山灰或いはそれらを構成する1次鉱物(注1)が、地表の温度や水分条件下においてルーズな含水物質へ形態的・組成的に変化する過程であり、風化作用(weathering)とも呼ばれる。大きく、機械的作用により岩石が砕片化する過程と、化学的な作用により、岩石を構成する1次鉱物が粘土鉱物や遊離酸化物などの2次鉱物(注2)に変質する過程にわけられる。
土壌生成の先ず最初の過程であり、土層を形成する母材(parent material)が生成されるが、一般に新鮮な岩石の風化の進行は極めて緩慢であるため、ある程度の厚さの土層が形成されるためには地質学的長時間を必要とする。
例えば、風雨に晒されている数千年前の古代遺跡に使用されている岩石でも、その風化は彫り込んである絵や文字が読み取り難くなっている程度であることなどからも、その長期性をうかがい知ることができる。
ロ)生物的土壌生成過程
前述の物理的土壌生成過程で生成された岩石の砕屑物や各種2次鉱物などからなる鉱質物質に、主として植物や土壌生物の遺体に由来する有機物が加わるなどにより、暗色を呈する表層(A層)、遊離酸化鉄により黄褐色〜赤褐色を呈する中間層(B層)、岩石の砕屑物や2次鉱物などからなる淡色の下層(C層)、などからなる土壌断面が形成され、それらの形成と共に土壌が肥沃になる過程である。
一般に森林土壌には無数の土壌動物や微生物が棲息しており、(表4‐1‐5、4‐1‐6)それらの働きにより鉱質土層に加わる落葉・落枝などの有機物(高分子有機化合物)は順次分解され、最終的に無機物いわゆる可給態養分となる。
表4‐1‐5 動物量の豊かな土壌の例(表層土1m2当たり)
| 線虫 | 1,000,000 ~ 6,000,000 |
| ダニ | 70,000 ~ 100,000 |
| トビムシ | 50,000 ~ 70,000 |
| ミミズ | 150 ~ 500 |
注)青木, 1987
表4‐1‐6 微生物の豊かな土壌の例(土壌1g当たり)
| 細菌 | 16,900,000 |
| 放線菌 | 1,340,000 |
| 糸状菌 | 205,000 |
| 藻類 | 500 |
注)Burges, 1971
その有機物(セルロース、ヘミセルロース、リグニン、タンパク質などの高分子有機化合物)が分解される一連の過程の中で生成されるポリウロナイド、ポリフェノール、キノン、ポリペプチドなどの分解産物が、再び重合・縮合反応を起して腐植(humus)と呼ばれる暗色不定形高分子有機化合物群が生成される。
この腐植は、その生成過程(ポリウロナイド、ポリフェノール、キノン、ポリペプチドなどの重合・縮合)を反映して、カルボキシル基(‐COOH)や水酸基(‐OH)などの反応基に富む。そのため化学的活性度が高く、カルシウム、マグネシウム、カリ、アンモニウムなどの陽イオンを電気的に結合保持する能力に富み、また、粘土鉱物などからなる土壌粒子を結合させて土壌の集合体、即ち団粒構造(Soil
structure)の形成を促進するなどにより、土壌の理学的及び化学的性質を向上させる働きが大きい。また、腐植自身も高分子有機化合物群であるから、いずれ土壌動物や微生物の働きで分解され無機化して植物の養分となる。
一般に土壌表層(A層)の暗色系統の色は腐植の集積に由来するので、表層の黒色味が強く、従って腐植の集積量が多い土壌ほど肥沃度が高いとされている。
ハ)森林土壌の再生問題
一般に、森林が伐採されるなどにより落葉落枝(litter)などの有機物の土壌への供給が絶たれると、それらを栄養源とする土壌動物や微生物の活性度の低下や棲息数の減少が引き起こされるため、腐植の生成が減少し、団粒構造などが劣化するので、土壌の理学的及び化学的性質の劣化が進行する。
さらに、土壌を被覆していた落葉・落枝などに由来する有機物堆積層(Ao層)が有機物分解の進行などにより消失すると、露出した表層土壌の浸蝕流亡が開始される。
伐採跡地に植生が自然侵入したり人工造林が行われて落葉・落枝の供給が再開されると、土壌動物や微生物の活動が再び活発となり、それらの棲息数の増加や活性度の上昇及び腐植の生成が進むなど、前述の生物的土壌生成過程により肥沃な暗色表層が再生される。
しかし、この生物的土壌生成過程が進行するためには、ある程度の厚さの土層が残されていなければならず、浸蝕流亡によりほとんどの土層が失われてしまった場合は、先ず前述のような物理的土壌生成過程により岩石から土層が形成されなければならなくなる。
わが国の森林土壌における暗色を呈するA層の発達速度は一般に年間1�o程度と推定されているところから、生物的土壌生成過程による肥沃な暗色表層の再生は数十年から数百年のオーダーで進行すると考えられる。
しかし、土壌侵食により流亡した土層の再生の場合は、ある程度の厚さの土層が形成されるには地質学的長時間を要することから、その再生は実質的には不可能と考えられている。
b.団粒状構造の形成と働き
森林土壌では、物理的土壌生成過程で生成される極めて微細で粘着性のある粘土鉱物と、生物的土壌生成過程で生成される反応性に富む腐植などを結合物質とし、土壌の乾湿の繰り返しや根系・土壌動物などに由来する応力による脱水収縮作用により、土壌粒子の集合体、いわゆる団粒構造が形成されている。そのため土壌内には団粒構造内の微細な孔隙から、団粒構造間の粗大な孔隙まで、いろいろなサイズの孔隙が無数存在する。
一般の森林土壌の孔隙率はおよそ50〜70%であり、火山灰土壌のような特殊な土壌では孔隙率が80%に達するものも報告されている。
そのため、降雨などに際しては、粗大孔隙が通路となり大量の雨水を土壌内に浸透させ、下流の一時的な増水を抑制することにより洪水を防止すると共に、地層深くまで浸透させた雨水を徐々に渓流に流出させることにより、無降雨期の下流地域の渇水を防止するなど、水源緩和機能が発揮される。
また、森林植物が成長するためには、養分・水分と共に呼吸のための空気が地下にある根に供給されなければならないが、微細な孔隙が養分と水分の貯蔵庫となり、粗大な孔隙が空気の通路ともなることによって、植物の健全な成長が保持される。
そして、成長する植物の蒸散作用などにより地域の微気象が緩和され、光合成作用により二酸化炭素の固定が行われるなど、環境保全機能が発揮される。
更に、団粒構造の発達した土壌内には無数の土壌動物や微生物が棲息し、絶えず有機物分解が行われることによって、植物や動物の遺体などの有機性廃棄物の大量の地表への蓄積、いわゆるエントロピーの増大により地球環境が熱死の状態になることが防がれている。
団粒構造の発達した良好な森林土壌の存在なくして、地球環境の保全は考えられない所以である。
c.有機物堆積層と物質循環
森林土壌は一般に表層ほど肥沃度が高いが、表層ほど浸蝕により失われやすいという致命的な欠陥を有している。
従って、森林土壌が資源としてその機能を十分に、かつ持続的に発揮していくために基本的に大切なことは、浸蝕により流亡しないことと、表層の団粒構造を維持し続けることである。
土壌を侵食から守る方法は、人工的手段による場合はいろいろな土木的方法が考えられるが、わが国の森林土壌のようにほとんど全て斜面に位置する土壌を水蝕なり風蝕などの侵蝕から防ぐ最良の自然の方法は、土壌の表面が常に有機物堆積層で被覆された状態に保つことである。
また、団粒構造は腐植や粘土鉱物などの結合物質によりその安定性が保たれているが、特に腐植の働きが大きいことから、団粒構造の安定性と腐植の含有量との間には密接な関係が存在する。
この腐植は、前述のように、土壌動物や微生物による有機物分解の過程で生成されるが、腐植自身も有機物であることから、分解作用により常に消耗する。
そのため、団粒構造を安定的に保つためには常に腐植が供給される必要があり、そのために必要な十分条件は土壌表面に有機物堆積層が常に保全されていることである。
以上のように、森林土壌を物理的に侵蝕から守り、腐植の供給源となり土壌の団粒構造を安定的に維持するためには、有機物堆積層の存在が唯一無二の条件であるが、その有機物堆積層の存在のためには、森林状態が常に維持され絶えず落葉・落枝が土壌に還元されなければならない。
森林、土壌、土壌動物、微生物、及びそれらを取り巻く大気は互いに密接な関係を及ぼしあっていることから、それらはまとめて森林生態系(forest
ecosystem)と呼ばれるが、森林生態系では植物と土壌との間で常時物質循環が行われており、循環量が多いほどその森林生態系の健全度が高いことから、そのような物質循環作用はまた森林の自己施肥作用とも呼ばれている。
従って、森林土壌をできるだけ良好な状態に保つためには、その森林生態系をできるだけ健全な状態に維持することである。
d.森林土壌資源の統合的管理
旧ソ連の土壌学者であるドクチャイエフ(Dokuchaev)が19世紀後半に土壌は大気や水と同様に自然物(natural
body)であると定義し、「土壌学」を体系化してから、早や 1世紀半が経過した。
土壌はバイオマス生産や環境保全のためになくてはならない大切な資源であると同時に、その生成的特異性のゆえにその利用に際しては保全が絶対条件であるが、土壌学は地質学、鉱物学、地形学、地理学、気象学、物理学、化学、生物学、生態学、環境科学など多岐にまたがる典型的な学際的学問であるため、すぐ足元にあるなど極めて身近にある割には、一般の人にその機能や重要性がなかなか十分に理解されていない。
特に、わが国の面積の3分の2を占める森林の下に生成されているいわゆる森林土壌は、いずれも山地(傾斜30度以上の急斜面に分布する森林土壌の割合、国有林36%、民有林26%)に分布していることから、一般に土層が厚くなく、しかも多雨気候のもとでその表層は常に浸蝕の危険に晒されている。
そのため、森林伐採などに伴い地表を被覆している有機物堆積層が撹乱されたり減耗すると、土壌表層の浸蝕・流亡の危険性が高くなる。
土壌侵食により表層などが失われると、森林の成長を支える土壌の理学的及び化学的性質が劣化するなど、森林の再生力が低下すると共に、水源涵養機能などの公益的機能も低下する。
しかも、土壌は一旦侵食により流亡したら、前述のように再び生成されるためには地質学的長時間が必要となるため、流亡した土壌の再生は実質的に不可能である。
そのため、連続的或いは度重なる土壌侵食により土層が失われると、遂には荒廃する。
従って、森林に何らかの働きかけをする場合、山地の多いわが国では土壌侵食の防止を先ず何よりも優先しなければならない。
一般に森林の伐採方法や時期を決める際には、生産性や採算性を重視した所有者の意向が優先されるが、その前に、土壌侵食危険度に基づいた大まかな施業制限の網を全森林にかぶせるなど、統合的な森林土壌保全管理を進める必要がある。
土壌侵食危険度に基づいた大まかな地域区分としては、次のようなものが考えられる。
- 生態保全区:山頂、稜線、斜面上部、山腹凸型斜面など、地形的に土壌侵食を最も受け易く、しかも土層の発達が不良なところ。全面伐採禁止にして、現存植生をできるだけ健全な状態に保つ管理により、有機物堆積層をできるだけ良好な状態で維持して土壌を保全し、環境保全機能、水源涵養機能、生物多様性保持機能などの公益的機能の発揮を期する。
- 施業制限区:斜面中部〜斜面下部などの土壌侵食の危険性はあるが、土層がある程度発達しており、土壌保全を重視する施業の採用により森林経営が可能なところ。近年、環境保全に対する意識の浸透や、材価低迷による伐採意欲の喪失、労働力不足などのため、長伐期施業や複層林施業などが選択されるケースが増えているが、択伐を基本とした天然林施業も含めた、非皆伐施業がこの区に最適である。
- バイオマス生産区:斜面下部緩斜面などの地形的に土壌侵食の危険性が少なく、しかも土層が厚く発達しているところ。周囲の景観や環境保全などに十分配慮しつつ、スギ、ヒノキなどの人工林施業や多収穫早生樹種による短伐期施業などにより、土壌生産力の万度の発揮を期するなど、国土の有効利用を図る。
土壌侵食により荒廃の危険性の高いところでは、浸蝕の可能性を完全に封じ込める森林管理により森林の各種公益的機能の発揮を期し、土壌侵食による荒廃の危険性の少ないところでは、森林の各種公益的機能の発揮と共に、持続的にバイオマス生産に使用するなどできるだけ森林土壌資源を有効に活用すべきである。
森林を構成する樹体はセルロース、ヘミセルロースなどからなるが、それらはいずれも高分子の炭水化物であり、分解すれば糖類、アルコール、エチレンなどとなる。
土壌における有機物分解のように、微生物の働きでセルロース、ヘミセルロースなどを分解して糖類、アルコール、エチレンを生成すれば、現在行われている蒸煮・爆砕分解法などのように大量のエネルギーを使用する必要もなく、しかも環境汚染物質などを排出することもない。
21世紀は世界的に食料不足、石油の枯渇、環境問題などの解決に迫られているが、適切に管理される森林生態系による環境保全機能とバイオマス生産機能により、それらの問題の解決に大きく寄与することが可能である。
また、バイオマスエネルギー利用も着々と進められており、「21世紀は森林の世紀である」とも言われる所以である。
国土の3分の2が山地地形のため森林にしか利用できないわが国において、そこに生成分布する森林土壌は、他の資源の少ないわが国にとって極めて貴重な資源であり、しかも、適切に管理される限り、何回でも繰り返し利用が可能である。
われわれの世代において、僅かでもその貴重な森林土壌資源を浸蝕などにより失い、森林生態系の健全度を低下させ、その生態環境保全機能、水源涵養機能、生物生産能力などを低下させることは、子々孫々にいたるまで大きな禍根を残すこととなるであろう。
土壌侵食危険度に基づいた統合的管理により、森林土壌資源をできるだけ有効に利用しつつ健全な姿で次世代へ引き継ぐことはわれわれの責務である。
参考文献 4‐2‐1(4)節
(1) 土壌調査法編集委員会(1978):土壌調査法.博友社
(2) 土壌養分測定法委員会(1970):土壌養分分析法.養賢堂
(3) 日本ペドロジー学会(1997):土壌調査ハンドブック.博友社
(4) 日本の森林土壌編集委員会(1983):日本の森林土壌.日本林業技術協会
(5) 森林土壌研究会(1993):林野土壌の調べ方とその性質.林野弘済会
(6) 八木久義(1994):熱帯の土壌.国際緑化推進センター
補注 4‐2‐1(4)節
[注1]:マグマや熱水から最初にできる鉱物を1次鉱物(初生鉱物,primary mineral)という。長石類,橄欖石類,輝石類,角閃石類,雲母類、火山ガラスなどがある.
[注2]:既存の1次鉱物が水や空気と反応するなど,化学反応により変質したものを2次鉱物(secondary
mineral)という.カオリン鉱物やモンモリロナイトなどの粘土鉱物(層状アルミノ珪酸塩鉱物,lay
mineral)や,Fe,Al,Siなどの酸化物である遊離酸化物(free oxide)などがある.
2.大径材、高品質材等の生産のための森林資源
わが国は南北に細長く連なる花綵列島であるため変化に富んだ気候条件下にあり、「山地」と「丘陵」の占める割合が約73%であるなど山国であるため、亜熱帯林から亜寒帯林まで多様な森林が分布しており、その森林面積は約2,500万haと国土の3分の2を占めている。
そのうち天然林は1,338万ha、人工林は1,040万ha、その他は137万haである。
立木の総蓄積は35億立方メートル、森林資源の蓄積増加量は人工林を中心に7,000万m3/yと推定されている。
また、近年の年間木材需要量は1億立方メートル前後で推移しているが、安い外材の輸入と、乾燥材、集成材、繊維板などの需要が増加するなど木材の利用構造の変化、及び、国産材の供給量の減少などにより、木材自給率は20.5%と低迷している。
1,040万haにも及び全森林の約40%を占める人工林については、これから成熟期を迎えるものもあるが、多くはいまだ25〜35年生であり、育林のための手入れを必要としているものが多い。
しかし、折からの材価の低迷、山村地域の過疎化・高齢化、林業労働者賃金の高騰などのため林業活動が停滞し、そのため間伐、枝打ちなどの手入れ不足に陥っているところが多く、それら人工林資源の劣化、生態環境の悪化、各種公益的機能の低下などが憂慮されている。
また、古代からの森林資源の過剰利用などにより天然林の劣化が進み、わが国の文化的遺産である各種木造重要文化財建造物の補修用の大径材、高品質材、及び特殊材等の調達に支障をきたしているなど、森林資源の管理に関して問題が多い。
a.大径材、高品質材等の生産のための統合的森林資源管理
わが国では文化財保護法により国宝或いは重要文化財に指定されている建造物(寺院、神社、城郭、民家等)は約3,600棟あるが、その約90%が木造建造物である。
それらの木造重要文化財建造物保存のためには適切な管理、修理が必要であるが、そのためにはヒノキ、スギ、マツ、ケヤキ、クリ、ヒバ、モミ等の大径材(径40cm以上、樹齢300年以上)、高品質材(赤身8割以上、無節、上小節、年輪幅3mm以下)、及び特殊材(幅2尺以上、厚さ70〜80mm)等が必要不可欠とされている。
しかし、古代からの森林資源の過剰利用及び近年の社会情勢や経済状況の激しい変化に伴い、それらの木造重要文化財建造物の修理に必要な大径材や高品質材、及びケヤキ、クリ等の広葉樹の特殊材の生産が極端に減少し、木造重要文化財建造物の修理用資材の安定的供給に支障を来たしている。
従来、木造重要文化財修理用の木材は一般市場から調達されてきたが、大径材、高品質材等は大学演習林、篤林家の持ち山、或いは非常な奥地の国有林などに僅かしか残されていないため、近年、一般の市場に出てくることは滅多にないのが現状である。
しかもそのような大径材、高品質材等については、わが国では極く一部を除き、計画的な育成がなされていないため、生産面で将来的な供給の見通しが全く立たない状況であり、わが国の宝でもある重要文化財建造物保存修理事業の遂行上から極めて深刻な状況に陥っている。
かつてわが国は、木材資源に大変恵まれていたと言われている。
例えば、東大寺大仏殿は創建後2度戦火で焼失し、再建の度に規模が縮小されたが、それでも未だに世界最大の木造建築物とされている。
この大仏殿が創建されたのは天平勝宝4年(西暦752)であるが、その際には直径1m、長さ30mのヒノキの大径材が84本使用され、それらは田上山(かつてヒノキの大木が茂っていたが、藤原京、大仏殿などの造営のために伐採され尽くしハゲ山と化したところで、湖南アルプスとも呼ばれ、環境破壊の模式地とされている)、甲賀山、及び伊賀山などから調達されたといわれている。しかし、治承4年(西暦1180)、平家の軍勢により焼き討ちされ建久6年(西暦1195)に再建が開始されたが、その時使用された元口2m、長さ21〜27mのヒノキ大径材は、但馬(兵庫県)や美作(岡山県)では既に枯渇していたため、周防国(山口県)などから調達されたという。永禄10年(西暦1567)の応仁の乱で再び焼失すると、その再建は142年後の宝永6年(西暦1709)となるが、既に国内ではヒノキ大径材が枯渇していたため、建物の規模を3分の2に縮小し、しかも柱は何本もの材を寄せ集めて鉄の輪で締め付けたものを使用し、通しの材が必要な2本の梁だけは、日向国霧島山(九州)から調達した元口1.3m、長さ23mのアカマツ2本が使用された。
このようにわが国の森林資源の劣化が急速に進行し大径材等の供給能が低下したため、20世紀最後の伽藍建築といわれた奈良薬師寺の金堂と西塔の再建、及び京都平安神宮の再建、明治神宮の鳥居などに使用されたヒノキの大径材は、もはや国内では調達が困難であったため、台湾中央部の山岳地から伐り出された台湾ヒノキが使用された。
また、大量のヒノキ大径材を必要とする伊勢神宮の20年毎に行われる式年遷宮では、かつては、内宮・外宮背後の神路山、大照山、神塩山等の神宮林から必要材の伐り出しが行われていたが、1回の遷宮で使用されるヒノキが大量(直径1m前後の大径材40本を含む11,000本以上の良質材が必要)であるため神宮林だけではまかない切れなくなり、興国4年(西暦1343)の第35回内宮式年遷宮からは、三河国、美濃国、伊勢国大杉谷などからの調達が行われた。
しかし、それらの地域でもヒノキ大径材が枯渇してきたため、1709年からは、木曾谷、裏木曾などからも伐り出されるようになり、現在では、樹齢200〜300年のヒノキ大径材が安定的に供給できるよう計画的に植林された、それらの旧神宮備林(1906年設定、現木曾国有林)から調達が行われている。
そのため、伊勢神宮では、遷宮用のヒノキ大径材を以前のように神路山等の神宮林から自前で調達するべく、伐期予定を200年以上とする森林経営計画を大正15年(西暦1926)に編成し、ヒノキ林の育成を続けている。しかし、式年遷宮用のヒノキ大径材が供給されるまでには400〜500年を必要とするため、神宮林だけで御造営用材を質・量ともに完全に自給できるようになるまでには、まだ200年以上かかるとされている。
そのような木造重要文化財建造物の修理用大径材、高品質材等の安定的供給に支障を来たしている現状に鑑みて、全国演習林協議会では、平成9年度から科学研究費補助金による「大径材及び高品位材の供給に関する研究」で、全国26大学の附属演習林13万2000haを対象に、文化財修理用資材として利用可能な大径材(径40cm以上、樹齢300年以上)、高品位材(赤身8割以上、無節、上小節、年輪幅3mm以下)、及び特殊材(幅2尺以上、厚さ70〜80mm)の賦存状況調査を実施した。
調査対象樹種は、文化財修理用資材として需要の見込まれる26種であるが、その結果スギ87本、カツラ37本、ヒノキ28本、アカマツ28本、ケヤキ26本、エゾマツ25本、モミ22本、トドマツ16本、ツガ15本、サクラ類14本、クスノキ13本、ブナ12本、カヤ10本、シオジ9本、クリ7本、カシ類7本等の計370本の存在が確認され、それらの分布台帳を作成した。
それらを試験研究上の重要度及び法令上の制約の観点からみると、54%にあたる201本が学術上の特別な意義を持ち、61%にあたる227本に自然公園、保安林、鳥獣保護区などの法的な制限が加えられており、そのような制約の全くないものは全体の僅か9%に当る32本で、しかもカツラやスギなどの特定の樹種と地域に限定されていた。
調査と同時に行われたアンケートによれば、大径材・高品質材育成林分、またはその育成の計画を持つ大学は13大学であったが、総括すればそのような計画に完全に否定的な意見は少なく、なんらかの条件が整えば大径材・高品質材の育成計画を持つ大学が多いことが判明した。
また、環境庁は1988年から「巨樹・巨木林調査」を行い、地上から1.3mの幹周囲が300cm以上の樹木が、単木で28,800本、樹林で25,103本(7,365件)、並木で1,895本(579件)あり、その多くは寺社などの境内林であったと報告している。
更に林野庁は、1999年に国有林に自生している樹齢100年以上の樹木のうち山のシンボル的な巨木を調査し、うち282本を「森の巨人たち百選」として推薦した。
このように、奥地の国有林、寺社などの境内林、一部の篤林家の持ち山、その他などにもまだ少なからず単木状の大径木或いはその候補木、及びそれらが生立する老齢の天然林や人工林が残されているが、それらはいずれも見本林、学術参考林、保護林、自然公園などの比較的強い伐採を規制する枠がかかっていることが多く、それらが一般市場に出てくることは滅多にない。
文化財補修用樹種を含む天然林などの調査を国有林や民有林においてもできるだけ早く行い、大径材、高品質材等が採取或いは将来採取できる森林などの実態を把握し、要件にかなうできるだけ多くの森林などを、大径材等を育成・採取するための超長期の保存林、即ち、文化財用備林として地域社会などの同意を得ながら設定すると共に、大径材、高品質材等の新たな供給体制を整える必要がある。
文化財用備林として最低限必要な条件は、1.生物・生態学的に大径木の育成が可能である、2.備林としての登録に所有者が同意する、3.伐採搬出に伴う規制がないか或いはその規制解除が可能である、の3点である。
従って、設定する林分や単木の育成や林地の保全に関する、国としての経済的な支援体制も重要である。
以上のような、現状での最善と考えられる対処療法と共に、材価の低迷、林業労働者の賃金の高騰、高齢化・過疎化に伴う山村地域での若年林業労働者不足などに起因する林業の極度の不振が続いている現状ではあるが、そのような経済的事情に左右される林業とは別に、真の長期的視点に立った、文化財補修用の大径材、高品質材等の計画的な生産のための国有林、民有林、大学演習林などにまたがる統合的な森林資源管理計画の策定を、国家として急ぐ必要がある。
その森林資源管理計画は、大径材、高品質材等を育成・採取することを目標とするのであるから、俗にいう「100年の大計」では不十分で、200〜300年或いはそれ以上の遠大な計画でなくてはならない。
わが国の多数の国宝などを含む木造重要文化財修理の問題は、単なる森林資源調達だけの問題ではなく、大切な民族の遺産を守る国民的な課題である。
b.人工林などの統合的森林管理
戦後半世紀余りで、1000万haに達したスギ、ヒノキ、カラマツなどによるわが国の人工林は、西南日本を中心に徐々に成熟期に達しつつあるが、依然としてその70%近くは35年生以下であり、いまだ育成途上にある。
わが国では、比較的気候条件に恵まれているため植栽木の成長もさることながら、草本類、ササ、ツル等の植物が繁茂しやすいことから、植栽から20年生程度までの下刈り・除伐を含む集中的な手入れと、その後の適切な数度の間伐が不可欠である。従って、それら若齢人工林を健全で活力ある森林に育てていくためには、保育、間伐等の森林施業を適切に行わなければならない。
そのような手入れを怠ると、ササ・クズ等の繁茂、竹林化、或いは過密林分化し、成長量の低い質的に劣化した森林に変化したり、気象災害や病虫害に弱い森林となり、森林としての価値が低下する。
また、人工林面積の70%はスギ或いはヒノキの単純林であるが、特に、間伐遅れで過密になったヒノキの若齢林分では、林内の光が不足するため潅木や下草などが姿を消し、遂には有機物堆積層も消失することがある。そのようなところでは、ヒノキの落葉は砕片化しやすく簡単に雨水で流されてしまうので、露出した土壌表層の地表流による侵食・流亡が始まり、遂には土壌が荒廃する。
しかし、それらの林業活動を支える山村地域においては、過疎化・高齢化の進行、伐出費用の高騰による経営コストの上昇や木材価格の低迷による林業経営の収益性の悪化により、林業労働力の減少及び高齢化が急速に進行し、保育、間伐等の森林施業を適切に行うことが極めて困難な状況に陥っており、手入れ不足林分が急増している。
因みに、林業就業者数は、昭和35年の約44万人から平成7年の約9万人へと激減し、50歳以上の高齢者の比率は、昭和35年の約24%から平成7年の約69%へと急上昇した。
また、わが国の森林面積の60%以上が私有林であるが、私有林の所有構造は小規模分散的であるため零細林家が多く、不在村地主の所有する森林の管理の手抜きも含めて、私有林では管理放棄林分の増加が著しい。
また、近年、狩猟禁止などに伴うニホンジカなどの急増により、林内植生や植栽木の食害が深刻化している。特に、奥日光、丹沢、大台ケ原などでは被害が甚大で、林内植生がほとんど全滅状態のところもある。
このような状態を放置すると、折角植林した人工林の資源的劣化、更には土壌侵食による森林生態系の荒廃による国土保全、環境保全、水源涵養機能などの喪失が進み、山村地域の荒廃のみならず、国民全体の生活にも重大な影響が及ぶことが危惧される。
しかも、森林或いは森林生態系の成立基盤である土壌が浸蝕により流亡すると、その再生は不可能であるから、各種の多面的機能の喪失などの問題は子々孫々に至るまで及ぶことが想定される。
これまでの林業では、数十年に一度の伐採収穫による木材収益により植栽・育林・間伐・伐採などの全ての森林の整備に関わる費用が賄われ、数十年間にわたる多面的機能の発揮は副次的なものとされ、無償で提供されてきた。
しかし、近年の木造建築数の減少による木材需要状況の悪化や海外からの安い外材の輸入等による木材価格の下落、林業労働者の賃金の高騰、更には山村の過疎化・高齢化による若年労働者不足など林業を取り巻く情勢が極めて厳しいものとなり、林業活動が経済的に立ち行かない現状では、そのような従来の方式で森林を健全で活力ある状態に維持していくことが大変困難となっている。
森林は、木材等林産物の供給、国土の保全、水資源の涵養、気象緩和や防音・大気浄化などの生活環境保全、保健・文化・教育的利用の場の提供等の、多様な機能を有しており、国民生活と深く関わっている。
そのため近年では、環境保全や水源涵養機能への要望と共に、森林との触れ合いや生物多様性の保全に対する国民の要望が高まっており、公益的機能と共に、文化、教育的な面での森林の果たす役割に対する期待が増大している。
また、総理府の「森林・林業に関する世論調査」によれば、森林が発揮する各種機能に対する要望の大きさは、(1)山崩れや洪水などの災害を防止する働き、(2)水資源を蓄える働き、(3)貴重な野生動植物の生息の場としての働き、(4)大気を浄化したり、騒音を和らげたりする働き、の順になっており、木材等林産物の生産機能に対してよりも、公益的機能の発揮に対する国民の期待が高くなっている。
更に、地球環境問題に対する関心が世界的に高まる中で、二酸化炭素を吸収し炭素を貯蔵する森林の温暖化防止の働きに対しても、国民の関心がとみに高まっている。
そのような森林が発揮する各種公益的機能のうち、土砂流出の防止、土砂崩壊の防止、水資源の涵養、保健休養、野生生物の保護、酸素の供給、大気の浄化などの機能について、それと同等の機能をもつとみられる施設の建設等に要する費用で評価する代替法により金額として計量化したところ、その評価額は林野庁(2000)では年間約75兆円、日本学術会議答申(2001)では年間約70兆円と試算されており、いずれにしても森林の公益的機能の大きさ・重要さをうかがい知ることができる。
従って、木材生産による収益により森林を整備していくような従来の方式はこの際棚上げして、国民全体の利益のために、森林を健全な状態に維持して公益的機能の発揮を期することに重点をおき、例え公費を投入してでも適切な森林整備により安全で豊な国土の形成を進め、生産される木材は副次的に考えるような発想の転換が必要ではないかと思われる。
特に、零細林家や不在村地主などのように森林の管理・経営を行うことが困難であるか或いは経営意欲がなくて最低限の管理水準を確保できない森林については、所有が細分化されている森林の経営の委託や森林の譲渡などにより森林を集約して、森林組合などによって公的に一括管理する方式により、新たな雇用創出と山村地域活性化などを図るべきである。
また森林整備に際しては、前述の土壌侵食危険度区分に基づき、地域の森林が生態保全区に相当するところでは、人工林、特に不成績造林地の多い拡大造林地も含めて自然林指向施業を採用し、施業制限区では複層林施業や針広混交林択伐林への誘導、バイオマス生産区では、周囲の景観や環境にも十分配慮しつつ、スギ、ヒノキ、その他多収穫早生樹種などにより土壌生産力を万度に発揮させる集約的林業により木材生産活動を展開することにより、多面的機能の発揮を期するなど国土の有効利用を図るべきである。
そのような、土壌侵食危険度も考慮に入れた持続的な地域森林整備計画を作成し、それに基づき公的資金の投入により長期的視野に立った統合的な森林資源管理を行うことにより、生態環境の保護と整備を進めると共にバイオマス生産も進め、経済・社会の持続可能な発展に貢献することが大切である。
また、ニホンジカなどの野生動物被害についても、その食害が激しい地域では、公的機関による個体群の維持管理のための個体群動態の研究を進め、適正な個体数コントロール法などを早急に確立する必要がある。
森林は文化のバロメーターと言われるが、その国の文化的レベルが森林の整備状態に反映されていることが多い。
森林の整備・管理を立地環境条件などに即して統合的かつ適確に行い、次世代に健全な姿の森林資源を引き継ぐため、受益者である国民全体が応分の負担をするなど、森林の整備・管理を社会全体で支えていく体制づくりが急がれている。
参考文献 4‐2‐1(5)節
(1) フリー百科事典「ウィキぺディア」:神宮備林
(2) 北村昌美(1981):森林と文化.東洋経済新報社
(3) 只木良也(1981):森の分化史.講談社現代新書
(4) 八木久義(2000):大径材及び高品位材の供給に関する研究.科学研究費補助金基盤研究 (A)(1)研究成果報告書
4‐2‐2 海洋資源
(1)統合的管理の基本問題とその克服
わが国における自然資源管理上の最大の問題は管理が対象別に独立に行われている点である。陸、海、大気はまったく別々に扱われ、陸でも農地と森林、河川、海岸は別なチームが手掛けている。所轄官庁もいわゆる縦割りで、研究者の学会も細かく分かれていて交流は少ない。最近ようやく地球惑星科学合同学会ができてかなり改善された。多くの大学でかつての地学科、地質学科、鉱山学科などが地球惑星科学科や環境システム学科などに衣替えしているのは一応の進歩である。海洋では2007年から東京大学に海洋研、生産研、地震研、理学部、工学部、農学部の枠を超える「海洋アライアンス」(施設長浦環教授)が設立されたのは注目されてよい。学問や手法の垣根を越えて統合的に管理を進めるのは容易なことではないだろうが、自然資源の正しい理解と将来の展望を得るにはどうしても必要である。
(2)具体的提言
提案のひとつは日本周辺の統合無人観測ステーション網の建設である。海底には地震と地殻変動、津波を観測するケーブル付ステーションの構想が進んで、一部は実現を見ている。エルニーニョ海域には日米で多数のブイを設置して観測を続けている。しかし、日本周辺におけるさらに多くの対象と分野を網羅する統合的観測の必要性である。従来見落とされていたとして指摘したい対象は、1.海流鉛直分布(海底から表層まで)の時間変動の連続観測と 2.魚群や鯨の行動の広域・連続監視 3.底層流と底棲生物(シロウリ貝など)の群集とその生態の関係を探る連続観測である。これらを分野別独立でなく、統合的管理の趣旨に沿って合同観測を進めるのである。駿河湾熱海・伊藤沖の初島から海底湧水域のシロウリ貝群集までJAMSTECによって引かれたケーブル先端のテレビと観測機器は、伊豆半島沖地震に伴う海底土石流を見事に捕らえ、シロウリ貝の放精(卵?)行動を記録するという画期的な成果をあげた。今後のよい見本である。その基地である初馬の実験室はもう少し整備して博物館としてPRすれば自然教育にさらに大きな貢献が期待できる。
海底からブイまで立ち上げたワイアーの途中各深度にCTDO=塩分濃度(電気伝導度測定)、温度、水深(水圧)、酸素濃度測定装置を置いて連続観測する。海底と表層には濁度計を付ける。海底上十数mから数百mごとに数個と表層500m毎に2〜3個の海流計を設置して流向・流速を連続測定する。海底にはテレビを置いて底棲生物の行動や土石流を監視する。表層には魚群探知機とテレビを着け、一定時間ごとに周囲をスイープして魚群の行動をモニターする。往来船との衝突を避けるために最上部のブイは海面から10m以深に沈めておく。
最も重要な地点は海底ケーブルで結んで電源を補給し、記録をリアルタイムで回収する。それ以外の地点では、ケーブルなしでそれぞれ個々に記録を収録し、定期的に回収すると共に電源を補給する。いずれは研究船がわざわざ機器を回収しなくても音響通信でデータを回収し、電力はトランス方式で充電することが可能になろう。自律航走型の海中ロボットAUVにこれらすべてをまかせるのが将来に夢である。
ごく近い将来、わが国EEZ内のどこかに、かつての明神礁が西ノ島のような海底火山爆発が起こる可能性はごく高い。伊豆半津東方の海底噴火も記憶に新しい。海底火山噴火でも七曜海山列のように1000m以深の活動ならば水圧のお蔭で爆発の危険は少ないが、海面すれすれの噴火では55年前の「第五海洋」の遭難と同じ問題を惹き起こす。その際に活躍するのは危機管理訓練を受けた自律自航型ロボットAUVである。海上を航行する無人自動船「まんぼう」は既に実績があるが、海底の活動域に近付いて観察と測定を行うのはAUVしかない。遭難を避けるには温度と濁度を連続モニターして異常があったらすぐ以上が少ないほうに避けて母船に帰り着く性能を持つロボットを用意する必要がある。
海山を幾つか選んで総合的調査を行う計画も早期に実現してほしい。海山の上の海面は湧昇の影響で魚が豊富で海鳥が集まることは漁業関係者の間でよく知られていた(「やまみ」)。海山に沿う底層流の分布や化学成分と山頂部の生物分布を詳しく調査し、生態を明らかにすることは自然資源管理の第一歩である。かつてギヨーと呼ばれた平頂海山で平坦な山頂に堆積している石灰質軟泥のコアを回収して北太平洋の古環境を復元する目論見は既に述べた。
もうひとつの提言は南北大東島の自然遺産指定である。それは隆起サンゴ礁という稀有な自然であるのに加えてビキニ掘削の30年前に学術掘削が行われたという科学遺産であるからである。南大東島には気象通報でおなじみの大東島測候所があり数人の気象官が常駐して環境保護に当ってきたが気象観測の無人化に伴い人手がなくなったので、せめて小笠原並みの環境レンジャーを大東村役場において監視指導を担当させたらいかがであろうか。現地の製糖工場とも好い関係を保ち続けることも望ましい。これは海洋基本法第二十六条「離島の保全等」の具現化のひとつでもある。
沖縄南部の現生サンゴ礁は地元の熱心な観察やNPOの力でかなり好く保全されている。国民の貴重な財産として今後も末永く守り続け、できれば拡大させたいものである。
(3)自然資源に関する教育の振興
自然資源の統合的管理は国民全体の理解と協力がなければ成功しない。残念ながら日本国民の自然に関する基礎知識は諸外国に比べてきわめて低いと言わざるを得ない。これは特に小学校における「自然」教育が不十分、不完全なためであると私は痛感している。体験学習としてごく身近な自然に目を向けさせるのはよいが、わが国の回りにはさらに多様な自然が存在することを忘れている。例えば、小学校で使用される日本周辺の地形図は戦前の方が美しくかつ精密であった。特に現在使われている地図の海底地形はあきれるほど粗末である。
対策の第一歩は小学校、中学校の学習指導要領を改善して、わが国の自然資源にもっと時間を取って詳しく教えられるようにすることである。高等学校の入学試験にも多くの出題があるように仕向けることが望ましい。小学校、中学校教員の再教育も必要かもしれない。高等学校の一般理科でも自然資源教育が進むように学習指導要領を改訂してほしい。高等学校の選択科目に人文地理はあるのに自然地理がないのにかねて疑問を持っていた。「地学」では最も基本的な自然資源は既習・既知と看做されてほとんど触れられない。その上地学を選択する生徒数は減少の一途で、教員を置かないが学校も増えているようである。
社会教育には7月なかばの「海の日」を海洋基本法施行、国連海洋法条約加盟記念日として、海洋レジャーだけでない自然資源活用の必要性をもっと大規模にPRすべきである。
4‐2‐3 土地資源
(1)環境保全への取組み
農地や農業用水、多様な生態系、等の農村地域に存在する自然資源は、地域住民は勿論、国民が広く享受している農業の多面的機能の発揮にも深く関わっており、農家を主体とする農業生産活動や集落での社会的活動を通じて、地域ぐるみでその維持保全が図られてきた。しかし、農家の兼業化や高齢化、農村での過疎化や混住化、等によって農村集落には構造的な変化が生じ、農業生産活動の停滞のみならず、集落での社会的な活動にも沈滞が見られるようになってきた。このような農村での諸活動の沈滞化や集落機能の低下は、農村資源の維持保全及びその活用を困難にしてきており、あらためて資源維持管理のための仕組みを構築し直す必要に迫られていることが痛感される。他方、自然環境保護の動きが全国的に広がってきており、全国の半数を超える集落で景観や地域環境の保全活動が、また7%の集落で自然動植物の保護活動が行われ、近年その割合が上昇傾向しているともいわれ4)、自然環境保護の動きが更に活発化することも期待される。
自然環境保全に関しては、農業のみならず森林整備の面でも新たな動きが見られる。森林を整備し保全してゆく上で重視すべき機能に応じて「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」に区分し、それらの区分毎に望ましい森林の姿やそれに誘導するための森林施業の考え方を明らかにし、適正な整備・保全による望ましい森林の状態が確保されされるための施業実施の条件整備に取り組むこととしている、そのため、針広混交林、広葉樹林、大径木からなる森林等へ誘導する多様な施業の適切な実施に向けて、森林所有者への情報提供、間伐などの適切な施業技術の普及、低コスト・高能率な作業システムの整備など、森林整備の低コスト化への努力が進められている。
(2)農地・水・環境保全
環境問題に対する国民の関心が高まるなかで、農業生産のあり方にも環境保全をより重視する方向に転換することが求められよう。農業は本来自然界における水・窒素・炭素といった物質の循環を利用した持続可能な生産活動である。しかし、肥料や農薬などの過剰投入や家畜排泄物の不適切な管理による環境への負荷の増大、具体的には、地下水の硝酸性窒素濃度の上昇や湖沼・海域での富栄養化などが懸念されるようになってきた。これを受けて、全国の販売農家の約半数が化学肥料・農薬等の投入の低減や堆肥による土作りなどに取り組んでいるし、稲作農家の40%、露地野菜作農家の65%、など多くの農家が何らかの形での環境保全型農業を志向しているのが現状である。
環境保全を重視した農業への取組みが広がるなかで、農業が本来有する自然循環機能を維持増進するという観点から、地域的な広がりを持った取組みが求められている。そのため、農業者の環境保全をめざした着実な実践活動のみならず、地域全体としての纏まりをもった共同の取組みを推進すべく、2005年3月には「環境と調和のとれた農業生産活動(農業環境規範)」が策定され、この規範の実践と各種支援策とを関連付ける取組みが進められている。また、農村の有する資源の質を高めながら、更に将来に亘っての保全を考えて、2007年度からは、化学的薬剤使用の大幅な削減などの環境保全のための相当程度の纏まりをもった先進的共同活動への支援を内容とする「農地・水・環境保全向上対策」が、国と地方公共団体との緊密な連携の下に進められることとなった。なお、この対策の実施に向けてのモデル的取組みとして、農業者や農業関係諸団体だけではなく、自治体・町内会・学校・PTAといった多様な主体の参画が促されており、具体的な活動内容としては、水路沿いの花の植え付け、草刈りや泥浚いなどといった地域環境の整備・保全のための活動の輪が広がってきている。
森林の整備・保全についても市民参加の意識が高まってきており、NPOをはじめとするさまざまな主体によるボランテイア活動を中心とした動きが活発化している。その内容は、上下流域の住民等が連携して行う水源地域での森林作りや、漁業関係者等の行う河川上流での森林作りなど、きわめて多岐に亘っている。また、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として森林の整備・保全活動を通じた社会貢献を意図する企業が見られるようになっており、内閣府が実施した「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」では、「植林・間伐などの森林を守る活動」に対する協力を社会貢献と考える企業が多かった5)。
参考文献 4‐2‐3節
(1) 農林水産省「農林業センサス付帯調査 農村集落調査」 平成17年
内閣府「自然の保護と利用に関する世論調査」 平成18年9月
(2) 内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」 平成17年11月
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課資源室
-- 登録:平成21年以前 --