- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 資源調査分科会(第19回) 配付資料 > 参考資料4 平成19年度自然資源の統合的管理に関する調査 > 3.各論 第3章 人口問題が生態系資源及び土地資源等に与える影響
3.各論 第3章 人口問題が生態系資源及び土地資源等に与える影響
3‐1 人口動向
3‐1‐1 世界の人口動向
(1)第2次大戦後の人口爆発とその終息見通し
20世紀、とりわけ第2次大戦後の後半世紀は人類史上類をみない人口爆発の時代であった。先進地域の人口も1960年代まで続いた一大ベビーブームで大きく増加したが、(1950年当時世界人口の67.9%を占めた)発展途上地域(以下、途上地域と呼ぶ)は、先進諸国で開発された抗生物質、DDT等により感染症による死亡が激減し、多産多死(高出生率・高死亡率)のバランスが崩れたため爆発的な人口増加を経験した。世界人口の増加率は1950~55年の1.78%から上昇を続け、1965~70年に2.02%でピークに達した。途上地域のそれは同時期に2.04%から2.49%に増加した。世界ならびに途上地域の人口は1950~1970年の20年間に各々25.4億人から37.0億人へ、17.2億人から26.9億人へと増加した(表3‐1‐1参照)。
表3‐1‐1 世界の主要地域別人口の推移:1950‐2050
(百万人)
| 世界の主要地域 | 1950 | 1970 | 2005 | 2025 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 先進地域 途上地域 アフリカ アジア 東部アジア 南部・中央アジア 南東部アジア 西部アジア ヨーロッパ ラテンアメリカ 北米 オセアニア |
2,536 814 1,722 224 1,411 670 511 178 51 548 168 172 13 |
3,699 1,008 2,690 364 2,139 987 777 287 88 657 288 232 21 |
6,515 1,216 5,299 922 3,938 1,522 1,646 558 212 731 558 332 33 |
8,011 1,259 6,752 1,394 4,779 1,655 2,146 686 293 715 638 393 41 |
9,191 1,245 7,946 1,998 5,266 1,591 2,536 767 372 664 769 445 49 |
資料:(United Nations,2006)
この時代の世界ならびに途上地域の人口爆発は地球規模の脅威ととらえられ、60年代後半から国連を中心とする国際社会において、途上地域における人口増加抑制のために強力な取り組みがとられはじめた。具体的には、途上国政府自身の家族計画プログラムによる出生抑制政策であり、それに対する国連人口活動基金(UNFPA)を中心とする国際機関ならびに米国を中心とする先進諸国の支援である。1974年には、そのUNFPAの主催により、世界の人口増加問題に関する第1回政府間会議(世界人口会議)が開催され、「世界人口行動計画」が採択された。その後、家族計画プログラムに対する国際協力に加え、途上諸国自身の家族計画プログラムならびに経済社会開発の進展により、アジアNIESを筆頭に途上諸国の出生率は70年代、80年代に次々と低下を始め、今日までに、サハラ以南のアフリカを除けば、すべての地域で出生力転換が進行してきた。世界ならびに途上地域の人口増加率は70年以降低下を始め、2000年~05年には各々1.24%と1.44%に達した。世界ならびに途上地域の人口はそれでも大きく増加して、2005年には各々65.1億人と53.0億人となった。
90年代に入って以降、2年ごとに改訂される国連による世界人口の将来推計の将来値が下方修正を続けるようになった。すなわち、2050年の世界人口は1990年推計では100.2億人であったが、その後の推計では縮小を続け、最新の2006年推計では91.9億人となった(ただし、2002年推計以降はやや上方修正が続いている)。下方修正の理由は、1.90年代に入って途上地域全体で出生力転換が予想以上に順調に進んできていることが明らかになったことと、2.主としてサハラ以南のアフリカにおけるHIV/エイズの広がりが予想以上に深刻で、その影響により死亡率が上昇し、人口増加の勢いを抑制するほどであることが分ってきたことである。これに70年代から始まった先進地域の少子化(人口置換水準以下への出生率低下)が恒常化し、しかも出生力転換を終えた途上諸国もまた次々と少子化状況に陥ったことも、世界人口の見通しを変えさせる要因となった。
(2)世界の高齢化
世界的にみて出生力転換が順調に進展し、やがて人口増加の終焉も予想されるようになるとともに世界的な高齢化(グローバル・エイジング)への関心が高まってきた。一般に、出生率が伝統的な高出生率から近代的な低出生率に変化するにつれて人口の高齢化が始まる。先進諸国の多くは19世紀半ば以降20世紀前半までに出生力転換を終えたが、その過程で20世紀初頭から高齢化を開始した。高齢化の程度を65歳以上人口割合(高齢化率)で計るとすると、先進諸国の高齢化率は1900年当時4~8%であったが、1950年には先進地域全体で7.9%となり、2005年には15.3%にまで上昇している(表3‐1‐2参照)。途上地域は20世紀第3四半期の人口激増期には人口の若年化を経験した(1950~70年に15歳未満人口割合が37.4%から41.7%に上昇した)が、その後出生力転換が十分に進行した国から順に高齢化が始まっている。途上地域全体の高齢化率は2005年現在なお5.5%にとどまるが、既に出生力転換を終えた東アジアの高齢化率は8.8%に達している。世界の主要地域のなかではサハラ以南のアフリカのみが、今なお高出生率が続いているため、きわめて若い人口構造となっている(サハラ以南の15歳未満人口の割合は2005年で43.4%の高さである)。
21世紀は世界的な高齢化の時代となる。先進地域は1970年代から続く少子化のために(副次的には長寿化も加わって)今後も一段と高齢化が進み、2050年の高齢化率は、先進地域全体で26.1%、国別にも20%~40%となる。2005年現在で世界人口の約8割を占める途上地域の高齢化率も2050には14.7%となる。主要地域別には、全体として少子化が進行中の東アジアは2050年の高齢化率が24.8%になるが、出生力転換がまだ始まっていないサハラ以南のアフリカのそれは5.8%にとどまるであろう。世界全体としては、高齢化率は2005~2050年に7.3%から16.2%へ上昇するものと予想されている。
表3‐1‐2 世界の主要地域別 年齢3区分別人口構成の推移:1950‐2050
(%)
| 1950 | 2005 | 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢区分 | 年齢区分 | 年齢区分 | |||||||
| 世界の主要地域 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
| 世界 先進 途上 アフリカ サハラ以南 アジア 東部アジア 南部アジア 南東部アジア 西部アジア ヨーロッパ ラテンアメリカ 北部アメリカ オセアニア |
34.2 27.4 37.4 41.8 36.2 34.2 37.8 38.5 38.7 26.2 40.2 27.2 29.9 |
60.7 64.8 58.7 55.0 59.7 61.3 58.5 57.7 56.9 65.6 56.3 64.6 62.8 |
5.2 7.9 3.9 3.3 4.1 4.5 3.7 3.8 4.4 8.2 3.5 8.2 7.3 |
28.3 17.0 30.9 41.4 28.0 20.9 33.6 29.3 33.1 15.9 29.6 20.5 24.9 |
64.4 67.7 63.6 55.2 65.6 70.4 61.8 65.2 62.3 68.2 63.9 67.2 65.8 |
7.3 15.3 5.5 3.4 6.4 8.8 4.7 5.4 4.6 15.9 6.3 12.3 10.3 |
19.8 15.2 20.6 28.0 18.0 14.9 19.5 17.9 20.9 14.6 18.0 17.1 18.4 |
63.9 58.6 64.7 65.2 64.5 60.3 67.0 64.5 65.7 57.9 63.5 61.4 62.2 |
16.2 26.1 14.7 6.9 17.5 24.8 13.5 17.6 13.4 27.6 18.5 21.5 19.4 |
資料:(United Nations,2006)
このように21世紀の世界は全体として高齢化が進むことになるが、同じ高齢化と言っても先進国の場合と途上国の場合では、当面、社会経済的意味合いを大いに異にする。途上国の場合、出生力転換を終えてからの少なくとも30~40年間は、高齢化といっても子ども人口の減少と生産年齢人口の増加によるところが大きく、それによって生産年齢人口(働き手)にとっては被扶養人口(子どもと高齢者)の扶養負担が小さくなるため、経済の成長にとって有利な人口構造となる(生産年齢人口割合が65~70%に達する)。このような時期を近年、(出生力転換によってえられる経済的な恩恵という意味で)「人口ボーナス」期と呼ぶことがある。先進国中、日本は1950年代末から70年代にかけて、この「人口ボーナス」を利用して高度経済成長を達成したが、80年代~90年代にかけてアジアNIESが、ついで90年代以降のタイ、中国などが人口ボーナスの恩恵を享受しつつある。この人口ボーナス期は出生力転換後の一時期(30~40年)に限られる。この時期にうまく経済発展を進めることができない途上国は、その後の高齢化過程で経済発展のための資本蓄積と高齢者扶養という二重の負担を負うことになる。先進地域の場合には、今後の高齢化の進展は文字通り高齢者扶養負担の極端な増加につながるため、前述の人口減少とあわせて経済成長の足かせとなる可能性が大きい。
(3)世界の都市化
第2次大戦後の人口爆発の過程で、世界の都市人口はそれ以上に爆発的に増加を続けた。すなわち1950年時点で世界の都市人口は7億4千万人で、農村人口(18億人)を大きく下回り、世界人口に占める比率も29.0%にすぎなかった。都市人口はその後農村人口を大きく上回る伸び率(1950~2005年で年率2.6%)で増加を続けたため、2005年には31億6千万人に膨れあがり(農村人口は33億5千万人)、世界人口に占める比率も48.6%に達した。2007年には、ついに世界の都市人口が農村人口を上回ったとみられている(表3‐1‐3参照)。
表3‐1‐3 世界の主要地域別都市人口割合:1950~2050
(%)
| 世界の主要地域 | 1950 | 1970 | 2005 | 2030 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 先進地域 発展途上地域 アフリカ アジア 東部アジア 南部・中央アジア 南東アジア 西部アジア ヨーロッパ ラテンアメリカ 北部アメリカ オセアニア |
29.1 52.5 18.0 14.5 16.8 16.5 16.4 15.4 28.6 51.2 41.4 63.9 62.0 |
36.0 64.6 25.3 23.6 22.7 27.8 20.4 21.4 44.6 62.8 57.0 73.8 70.8 |
48.6 74.0 42.7 37.9 39.7 44.5 30.6 44.1 65.0 71.7 77.5 80.7 70.5 |
59.7 80.6 56.0 50.0 54.1 62.4 43.0 61.8 72.5 77.8 84.6 86.7 72.6 |
69.6 86.0 67.0 61.8 66.2 74.1 57.2 73.0 79.3 83.8 88.7 90.2 76.4 |
資料:(United Nations,2004)
先進地域、途上地域別にみると、先進地域では1950~2005年で農村人口は3.9億人から3.2億人に減少を続け、都市人口のみが4.3億人から9.0億人へ増加を続けたため、都市化率は52.5%から74.0%へ大きく上昇した。先進地域では18,19世紀に始まる産業化の過程で、第2次、第3次産業の集積する都市の人口が膨れあがり、都市化率を高めてきた。第2次大戦後もその流れは変わらず、農村部から都市部への人口(とりわけ若年人口)の移動、および都市人口自体の若年化による自然増加率の高さによって都市人口の増加が続き、農村人口は逆に若年人口の流出、及び農村人口の高齢化による自然増加率の低下(しばしばマイナスとなる)によって減少してきたため、先進諸国における都市化率の上昇が続いてきた。同じ1950~2005年の期間に途上地域では、農村人口も14.1億人から30.3億人へ2倍強増加したものの、都市人口は3.1億人から22.6億人へ7.3倍増となったため、都市化率も18.0%から42.7%へと大きく高まった。途上地域の都市化の進展も、基本的には先進地域の場合と同様、経済発展にともなう産業化の進展によるものであるため、大まかにみれば経済発展水準と都市化水準はほぼ対応している。しかしながら途上地域の場合、20世紀後半は人口転換のさなかにあり、人口増加が急激であったため、農村自体の人口も増加を続けてきた。また農村における人口増加によって[農地/人口]比が低下し、人口の「押し出し(プッシュ)」圧力が強まったため、都市における十分な労働力需要(プル要因)がないままに農村から都市への人口移動が進み、特に大都市に巨大なスラムが形成される大きな要因となった。主要地域別にみると、アジア、アフリカは全体として都市化率が低く、1950~2005年で各々16.8%から39.7%へ、14.5%から37.9%への変化にとどまるのに対して、ラテンアメリカの都市化率は41.4%から77.5%へと大きく上昇し、今日、ヨーロッパの水準(71.7%)を上回っている。
国連の予測によれば、世界の都市化の趨勢は今後も変わらないとみられている。2005~2050年の45年間についてみると、農村人口は今後年率0.4%で減少するのに対し、都市人口は1.56%で伸びを続けるため、2050年の都市人口は64.0億人、都市化率は69.6%に達する。今後45年間の世界人口の伸びはすべて都市人口の増加によることになる。先進、途上地域別にみると、先進地域では今後も農村人口の減少が続き、都市人口は年率0.39%で増加を続けるため、2050年の都市化率は86.0%に達する。途上地域の場合も農村人口は2020年ごろから減少を始めるのに対し、都市人口はなお年率1.09%の高率で増加を続けるため、2050年の都市人口は52.3億人、都市化率は67.0%となる。主要地域別にみると2050年の都市化率は、ラテンアメリカは88.7%とヨーロッパ(83.8%)を上回り、アジア、アフリカも各々66.2%、61.8%まで高まるものとみられている。世界の都市化の趨勢を都市規模別にみると、世界全体で人口100万人以上の大都市、人口1000万人以上の巨大都市が増加しており、それらに居住する人口も人口割合も急増しているが、これは主として途上地域の都市の増殖によるものであり、この傾向は今後も2025年まで変わらないものとみられている。
(4)世界の人口動向が資源・環境に及ぼす影響
90年代初めごろまでは、21世紀半ばに100億に達し、その後も増え続ける世界人口と地球の食糧、資源、環境はうまく折り合えるのかという地球規模的問題が危機的に論じられた。その際、『人口爆弾』を著したアールリッチなどは、人口爆発を地球規模的問題の最大の元凶と見ていた。もちろん、BRICs(ブラジル、インド、中国)に代表される途上諸国の経済開発の急激な進展もあり、食糧、資源、環境についての地球規模的課題が決して重要性を失った訳ではなく、地球温暖化問題などはむしろ今日一段と現実味を帯びつつある。しかしながらこと人口要因に関してみるならば、今日の世界人口の増加には明らかにブレーキがかかってきており、今世紀の第4四半期には世界人口の減少が始まるという見方が有力となりつつある。例えば、国連の超長期推計(2002年推計ベース)では、世界人口は2075年の92.2億をピークにして減少をはじめるとみている。ただし、このことを逆にみるならば、世界は、今後70年間なお30億人の人口増加と、それによる資源、食糧、環境への圧力の増大を受け入れざるを得ないことを示しているともいえる。
一方、今世紀前半における世界人口の高齢化の進展は、なお主として先進諸国を中心とした動きであるが、資源・環境との関係では、先進諸国の経済の縮小、社会保障の肥大化が政府の財政全般を圧迫し環境保全のためのリソース配分を低下させることになると、国内環境にとってマイナス(例えば、山林の放置)となるばかりか、政府開発援助(ODA)の減少という形で、地球環境保全のための途上国支援の縮小につながる可能性もある。ただし、高齢者1人当たりの資源・食糧消費は青壮年層よりも小さいため、特に人口減少時代に入る21世紀の第4四半期以降は、世界全体としての高齢化は資源・食料への需要を低下させ、環境への負荷を小さくする面がある。
他方、経済発展に伴う都市化の進展は市域の拡大による農地の宅地化を促す。また一般的にみると都市の生活は農村の生活に比べて1人当たりのエネルギー消費量が高く、多様かつ高タンパクの食品への需要も強い。そのため都市人口の増加、都市化の進展は農地の減少につながるとともに、資源や食糧の需要を増やし、環境への負荷を高める側面がある。
3‐1‐2 アジアの人口動向
(1)アジアの地域別人口の動向
アジア(国連の定義による)は世界3大文明の発祥の地を含むため、歴史的に人口が多く、他地域に比べて人口密度も高かった。1800年当時、世界人口は8.9億人と推定されているが、アジアの人口はその66%(5.9億人)を占めていた。途上地域で人口爆発が始まったころの1950年には、アジアの人口は14.1億人で世界人口の56%であった。1800~1950年の150年間の年平均人口増加率はわずかに0.3%に過ぎなかった。しかるに1950~70年の20年間は増加率が年率2.1%と高まり、1970年のアジアの人口は21.4億人(世界人口の57.8%)に達した。その後人口増加は減速傾向(1970~2005年の35年間の年平均人口増加率は1.7%)となったが、2005年のアジア人口は39.4億人(世界人口の60.4%)にまで膨れ上がった(表3‐1‐1参照)。
アジアは、国連の定義によれば4つの地域に分けられる。日本、中国を含む東部アジア、インドを含む南・中央アジア、インドネシア、タイなどの南東部アジア、主としてイスラム圏の西部アジアである。前2者は歴史的に人口密集地域であり、後の2者は歴史的には人口密度の低い地域であった。1950年の人口は各々6.7億人、5.1億人、1.8億人、0.5億人であったが、その後年率2%前後の高い人口増加率が続いたため、各地域とも大きな人口増加を経験した。ただし、他の地域に比べると東部アジアは主として中国の変化によって1970年頃から人口増加の減速傾向が顕著となり、西部アジアはもっとも緩やかな減速傾向に留まるなど、地域間の差が大きくなった。そのため1950年からの55年間に、東部アジアの人口は2.27倍の増加にとどまり15.2億人に、南・中央アジアは3.2倍で17.7億人、南東部アジアは3.1倍で5.9億人となったが、西部アジアは4.1倍で2.3億人となった。
国連の最新の人口推計によれば、東部アジアの人口はさらに減速傾向を強め、2025年頃には減少に転ずるとみられており、2050年の人口は15.9億人である。他の地域は減速傾向を示しつつも、なお大きく膨れ上がり、2050年の人口は、南・中央アジア25.4億人、南東部アジアは7.7億人、西部アジアは3.7億人となる。アジア全域では2050年に52.7億人となり、世界人口の57.3%を占めることになる。
(2)アジアの少子化と高齢化
アジアの全域並びに地域別の人口の増加が近年減速傾向になったのは、死亡率の低下に見合った出生率の低下(多産から少産への出生力転換)が進んできたからである。1950年代前半における4つの地域の合計特殊出生率(TFR)は5.7~6.5と極めて高水準であったが、60年代後半でもなお5.4~6.0と高水準を維持した。しかしながら、その後東部アジアのTFRは急激に低下し、1990年頃には人口置き換え水準を下回り、2000~05年には1.7と少子化状況を呈するに至っている。他の3地域の出生率低下はより緩やかであるが、2000~05年には、南東部アジアのTFRはすでに2.5と出生力転換の最終段階にあるものの、南・中央アジアと西部アジアのTFRは3.2と人口置換水準(ほぼ2.1)にはまだ距離がある。前述の、近年における4地域の人口増加率の違いは各々の地域が出生力転換のどの段階にあるかによってほぼ決められている。アジアにおける出生力転換の背景としては、経済発展による産業化、都市化、初等教育の普及・教育水準の上昇,保健水準の上昇・乳幼児死亡率の低下、などがうみだす少産志向の広がりと、安定した政権の下で実施される政府による家族計画プログラムの両方が重要である。
なお今日の途上国では、出生力転換を達成するとTFRはそのまま人口置き換え水準を割り込んで低下していくことが一般的である。2000~05年時点で、少子化状況にある国はアジアでは14カ国であり、TFRが1.4以下の超少子化の国・地域は日本とアジアNIES(韓国、台湾、シンガポール、香港特別区)など8カ国・地域に限られる。
出生力転換が起こると人口は高齢化を開始する。それは、出生率の低下により子供人口の割合が低下することにより、人口ピラミッドの「底辺からの高齢化」が進むからである。1950年時点では4地域の年少人口割合は34~39%と大きな違いはなかったが、2005年では東部アジアは21%、南東部アジアは29%、南・中央アジア(34%)と西部アジア(33%)と大きな開きが出ている(表3‐1‐2参照)。これはもっぱら出生力転換の速度の違いによる。出生力転換を既に終えている東部アジアでは、老年人口割合は2005年で9%であるが、他の3地域では55年前とそれほど変わらず5%前後である。東アジア人口の生産年齢人口割合は1985年頃に65%を超え、2005年には70%となっており、今まさに人口ボーナスを享受している段階といえる。南東部アジアは2005年に65%を超えて、人口ボーナス期に入ったが、他の2地域は、今後の出生率が順調に低下を続けて初めて、そのような時期を迎えられるといえる。アジア人口は全体として今後も高齢化が進むが、2050年までに高齢者扶養負担の問題が大きな政策的課題になるのは東部アジア地域(2050年の高齢化率は25%)のみであろう。
(3)中国とインドの人口動向
中国とインドは世界の“巨大人口国”である。両国の人口は2005年現在で各々13.22億人と10.97億人で世界人口の20.2%と16.8%、途上地域の人口の25.0%と20.7%を占める。そのため、これら2カ国の人口動向が世界(ならびに途上地域全体)の人口動向を大きく左右することになる。1965~70年をピークにして世界(ならびに途上地域全体)の人口増加率が大きく低下に転じたのは、中国の増加率が大きく低下したからであった。
中国とインドは第2次大戦後、政治的には、前者は共産党の一党独裁体制、後者は(世界最大の)民主主義体制をとり続けた点で対照的であるが、経済的には長い間計画経済体制をとり続け、経済発展が進まなかった点で共通している。しかしながら両国とも、近年、経済政策が市場経済化の方向に大きく転換し、持続的な経済成長が始まった点でも共通している。両国の経済発展は、巨大人口国であるがゆえに、世界のエネルギー資源、その他の再生不能資源、食糧、環境に長期的に甚大な影響を及ぼすことは明らかであるが、ここでは両国の人口動向にのみ焦点を当てて比較してみたい。
1950年、中国の人口は5.5億人、インドの人口は3.6億人で、両国の人口比は1対0.64であった(図3‐1‐1参照)。両国の人口は20世紀後半に大きく増加し、中国の人口は1981年に10億人に達し、インドの人口は1999年に10億人に達した。2005年の人口は中国が13.2億人、インドが11.0億人で、両者の比は1対0.83に縮まった。これは1970年代以降、中国の人口増加率がインドに比べて急激に低下したためである。国連の人口推計によれば、中国の人口は2030年の14.5億人でピークとなり、以後減少して2050年には14.0億人になると予想されている。それにたいして、インドの人口は21世紀前半は一貫して増加を続け、2035年には中国の人口を追い越し世界一となり、2050年には15.3億人になるものとみられる。
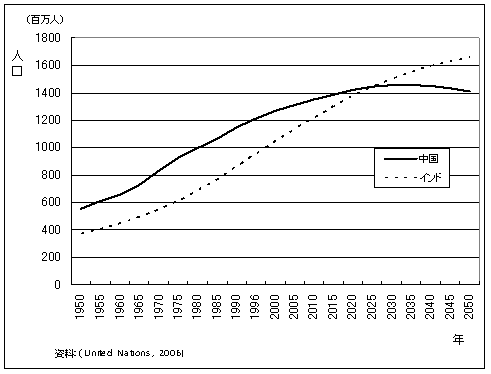
図3‐1‐1 中国及びインドの人口推移
近・現代において一国の人口が急激に増加を続けるのは、多産多死(高出生率・高死亡率)の伝統的人口動態バランスが崩れ、多産少死(高出生率・低死亡率)の状況が生まれるからで、人口増加は少産少死(低出生率・低死亡率)の近代的人口動態バランスに転換するまで続く。
このような人口転換の過程を左右するのは平均寿命と合計特殊出生率の動向である。まず、年齢別死亡率を集約した指標である平均寿命(男女込み)は、1950~55年時点では中国40.8歳、インド37.4歳と大きな違いはなかったが、2000~05年現在では中国(72.0歳)とインド(62.9歳)の差は9歳開いて入る。次に出生率であるが、合計特殊出生率(TFR)は、1950~55年の時点では中国6.2、インド6.0と両国とも高水準でほとんど差がなく、この状況は1970年頃まで変わらなかった(図3‐1‐2参照)。しかるに、1965~70年から中国のTFRは急低下し1990~95年までの25年で人口置換水準以下の1.9となった(2000~05年は1.8とされる)。それに対して、インドの出生率低下は緩やかで、2000~05年現在でもなお3.0とされ、人口置換水準に達するのは2025~30年、1965~70年から60年間かかるものと予想されている。
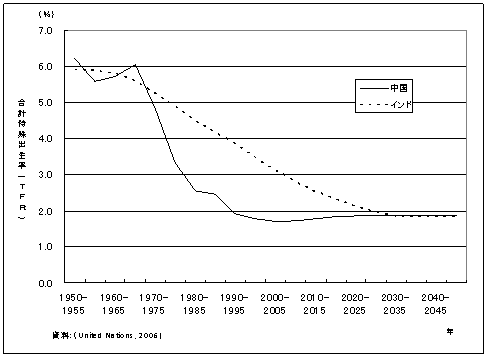
図3‐1‐2 中国及びインドの合計特殊出生率
インドは世界で始めて(1951年に)政府による家族計画プログラムを開始した国であり、それから既に50年強を経過したにもかかわらずなお出生力転換を終えることができない。それに対して1979年になって「一人っ子政策」を始めた中国の出生力転換は、先進国中最も急激な転換を経験した日本と同等あるいはそれ以上の速さである。
中国は1970年代、80年代の急激な出生力転換によって、年少人口割合が急減し生産年齢人口割合が急上昇した(表3‐1‐4参照)。1985年以降今日まで生産年齢人口割合は65%~70%に達し、まさに「人口ボーナス期」を迎え、これを利用して急速な経済発展を続けている。国連の推計では生産年齢人口割合が65%を割るのは2035年以降であり、今後先進国と同様の(超)少子化が進まない限り、人口ボーナス期はまだ優に30年続く事になる。これに対してインドの出生力転換は中国に比べてきわめて緩やかであり、2025年ごろにようやく終焉するものとみられている。そのため、インドの年齢構造変化そのものも日本、アジアNIES、中国などと違って、緩やかであり、生産年齢人口が65%を超えるのも2015年以降と予想されている。ただし、生産年齢人口割合の上昇は既に始まっており2000年には60%を超えているため、インドの場合も、これから「人口ボーナス」を利用し一挙に経済発展を進める好機が訪れると言える。
表3‐1‐4 中国とインドの年齢3区分別人口構成の推移:1950‐2050
(%)
| 中国 | インド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0‐14歳 | 15‐64歳 | 65歳以上 | 0‐14歳 | 15‐64歳 | 65歳以上 | |
| 1950 | 33.5 | 62 | 4.5 | 37.5 | 59.4 | 3.1 |
| 1955 | 37.1 | 58.3 | 4.6 | 38.8 | 58 | 3.1 |
| 1960 | 38.9 | 56.3 | 4.8 | 40.4 | 56.6 | 3 |
| 1965 | 40.2 | 55.4 | 4.4 | 41.5 | 55.3 | 3.2 |
| 1970 | 39.7 | 56 | 4.3 | 40.9 | 55.9 | 3.3 |
| 1975 | 39.5 | 56.1 | 4.4 | 40.1 | 56.5 | 3.4 |
| 1980 | 35.5 | 59.7 | 4.7 | 39.4 | 57 | 3.6 |
| 1985 | 30.5 | 64.5 | 5.1 | 38.7 | 57.6 | 3.7 |
| 1990 | 27.7 | 66.8 | 5.4 | 37.8 | 58.3 | 3.9 |
| 1995 | 26.6 | 67.4 | 6 | 36.6 | 59.2 | 4.2 |
| 2000 | 24.9 | 68.2 | 6.8 | 35 | 60.4 | 4.6 |
| 2005 | 21.6 | 70.7 | 7.7 | 33 | 62 | 5 |
| 2010 | 19.6 | 72 | 8.4 | 30.7 | 64 | 5.3 |
| 2015 | 18.5 | 71.8 | 9.6 | 28.7 | 65.6 | 5.8 |
| 2020 | 18.3 | 69.8 | 11.9 | 26.7 | 66.5 | 6.7 |
| 2025 | 18 | 68.4 | 13.7 | 24.8 | 67.5 | 7.7 |
| 2030 | 17.3 | 66.5 | 16.2 | 22.9 | 68.3 | 8.8 |
| 2035 | 16.4 | 64 | 19.6 | 21.1 | 68.9 | 10 |
| 2040 | 15.6 | 62.2 | 22.2 | 19.7 | 68.9 | 11.3 |
| 2045 | 15.2 | 61.8 | 22.9 | 18.8 | 68.4 | 12.8 |
| 2050 | 15.3 | 61 | 23.7 | 18.2 | 67.3 | 14.5 |
資料:(United Nations,2006)
3‐1‐3 日本の人口動向
(1)超少子化と人口減少社会の到来
日本の総人口は明治初年の1870年から2005年までの135年間に、3400万人からほぼ一貫して増加を続け1億2千800万人に達した(図3‐1‐3参照)。これは、ちょうどこの時代が人口転換の時代であったからで、死亡率の低下に出生率の低下が追いつくまで総人口が増加を続けたということになる。2005年の国勢調査の結果は、総人口が2004年からわずかに減少したことを明らかにした。おそらく2005年は日本の人口史上の大きな分岐点になると考えられる。すなわち、日本の人口は、いったん減少を始めると、少なくとも50年、おそらくは1世紀にわたって減少を続けると予想されているからである。国立社会保障・人口問題研究所の2006年推計によれば、日本の総人口は2005年の1億2800万人から2050年の9500万人まで減少し、さらに(その参考推計によれば)2100年には4500万人と今日の人口の3分の1強になるものと推計している。
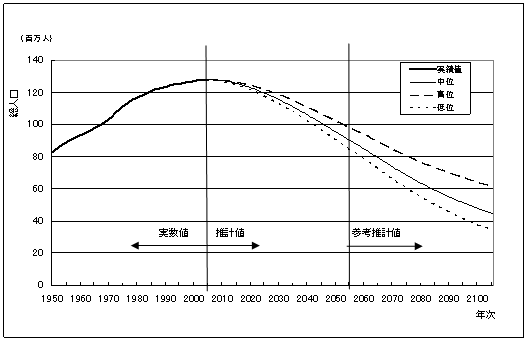
図3‐1‐3 日本の総人口の推移
このように日本が今後「人口減少の世紀」を迎えるのは、ひとえに1970年代半ばから続く少子化のゆえである。日本の合計特殊出生率(TFR)は1974年に人口置換水準(2.07)を下回って以来30年間おおむね低下を続け2005年には1.26となった(図3‐1‐4参照)。この少子化現象は他の先進諸国とほぼ共通するものであり、その共通の人口学的要因は「出産の高年齢への先送り」である。先進国のなかには、80年代半ば以降に30代の女性の出生率上昇(キャッチアップ現象)により出生率をある程度戻した国(北欧諸国、フランスとベネルックス諸国、米国など)もあるが、日本、南欧諸国、ドイツ語圏の諸国は、キャッチアップ現象が弱く、現在までのところ出生率が低下、低迷の一途をたどり、近年では「超少子化国(lowest‐low fertility countries)」などと呼ばれる。日本の人口が今世紀の半ば以降人口減少を相当程度減速させられるかどうかは、主としてこの超少子化状況を脱することができるか否かにかかっている。少子化、さらには超少子化の背景は複雑であるが、その中心的要因が「女性の社会進出による仕事と家庭の両立の難しさが増大したこと」にあるのだとすれば、1.男女共同参画社会への価値観の転換が十分に進むこと、2.仕事と子育ての両立支援に向けた政策が強化されること、3.企業社会が「両立」を可能にする方向に仕事と雇用のあり方を見直すこと(ワーク・ライフ・バランスの確立)が超少子化克服の鍵となろう。
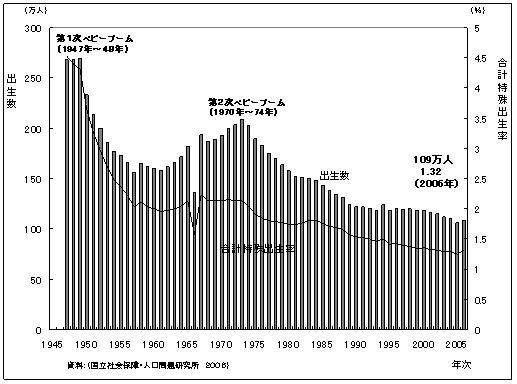
図3‐1‐4 日本の合計特殊出生率:1947~2006
(2)超高齢社会の到来
日本の人口は1950年代の出生力転換の成功とともに直ちに高齢化を開始した(1955年の高齢化率は5.3%であった)(図3‐1‐5参照)。しかしながら、その高齢化は「人口ピラミッドの底辺からの高齢化」であり、特に70年代半ばまでは子ども人口が急激に減少し生産年齢人口が急激に増加した「人口ボーナス期」であった(1955~1975年の20年間に生産年齢人口は39%増加し、総人口に占める割合は70%弱となった)。日本は、これを利用して高度経済成長を成し遂げ「豊かな社会」を築き上げた。高齢化は、60年代以降の中高年を中心とした死亡率低下による長寿化と70年代半ば以降の少子化によって一段と進行し、高齢化率は1975年に7.9%、2005年に20%に達した。日本は高齢化の原因である出生力転換も長寿化も他国に類をみない速さであり、それに1970年代半ばからの少子化、さらには超少子化状況が加わったために、日本の高齢化のテンポは世界一速い上に、将来の高齢化率も未曾有のレベル(2050年に40%)になるものと予想されている。
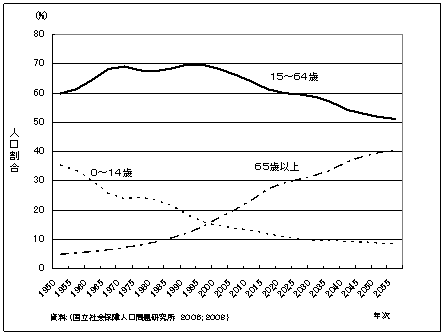
図3‐1‐5 日本の年齢3区分別人口の推移:1950‐2055
(3)都市化と東京圏一極集中
日本は、明治の近代化開始以降今日まで、人口転換による総人口の増加を経験すると同時に、その地域分布構造を大きく変化させてきた。明治の初年、日本は「農村社会」であり「地域割拠の社会」であった。その後の近代化過程において、都市化と三大都市圏への人口集中は戦前も緩やかに進んだが、大きく進行したのは戦後の高度経済成長期である。1955~1970年には非三大都市圏全体の人口はほぼ横ばいであったが、三大都市圏の人口は3244万人から4734万人へ46%増加し、全国人口に占めるシェアも36.8%から48.2%に増大した(図3‐1‐6参照)。この時期は、非三大都市圏から三大都市圏への人口移動が最も活発な時期で、三大都市圏の人口増加のほぼ半分はこの人口移動によるものであった。
高度経済成長期以降は人口移動の沈静化がみられるが、それでも非三大都市圏の人口流出基調は変わっておらず、しかも非三大都市圏の高齢化が進んでいるため自然増加(=出生‐死亡)も小さくなっている。そのため非三大都市圏においては、大規模中核都市をもつ県、三大都市圏に隣接する県を除くと、ほとんどの県が1985年以降人口減少県に転じた。一方、三大都市圏の人口構造は比較的若く、自然増加率が非三大都市圏を上回る。人口移動については、三大都市圏のうち、阪神圏はおおむね人口流出地域に転化し、中京圏は人口流入地域ではあるが、流入人口の規模は小さくなり、東京圏のみが相当程度の人口流入が続く地域となってきている。その結果、2005年の三大都市圏人口は6276万人、そのうち東京圏の人口は3448万人、全国人口に占めるシェアは各々49.1%、27.0%となっている。今日、国民の2人に1人は三大都市圏に住み、4人に1人強は東京圏に住むことになった。都市化率は戦後の1950年~2005年に33.8%から66.0%に上昇し、今日では国民の3人に2人は都市に居住することになった。日本は明治の近代化開始からの130年間で、農村社会から都市社会へ、「地域割拠の社会」から「三大都市圏中心の社会」とりわけ「東京圏中心の社会」に変わってきたと概括できよう。
これからの人口減少社会において、これまで続いてきた都市化の趨勢、東京圏への一極集中構造に変化が見られるであろうか。国立社会保障・人口問題研究所の都道府県別推計人口によると、2005~2035年において非三大都市圏の諸県は人口減少と高齢化が一段と進むとみられている。他方、三大都市圏のうち阪神圏は人口減少が続き、中京圏はほぼ人口増加を止め2010年からはっきりと減少を開始し、東京圏のみはしばらく増加を続けるものの、これも2015年頃から減少を始めるものとみられている。その結果、2035年の三大都市圏人口の割合は52.2%に上昇、なかでも東京圏の割合は29.8%に高まるものと予想される。この推計は2000~2005年の人口移動の流れ(東京圏への人口流入)が続くことを前提としており、現在の産業の立地構造が変わらず労働力需要の分布構造が変わらないかぎり、三大都市圏、とりわけ東京圏への人口集中はますます進むことを示唆している。もちろん人口減少社会の中で地方分権が促進され、地方が生き残りをかけ地域産業の活性化に努力し、地域経済が活発化することになれば、人の流れも変わってくるであろうが、現時点ではそのような対抗的動きははっきりしない。
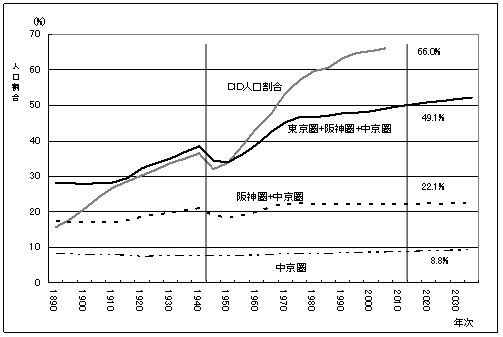
図3‐1‐6 日本の都市化と3大都市圏の人口割合の推移
(4)日本の人口変動が資源・環境に及ぼす影響
かりに21世紀の日本人口が3分の1強にまでも減少するとすれば、国民総生産は大幅に縮小し、資源・食糧需要も環境への負荷も大きく減少することになるが、さらに人口減少によって1人当たりの豊かさ自体も損なわれるとすれば、資源・食糧需要・環境への負荷はさらに小さなものになる。1人当たりの食糧、資源の消費量は高齢者(とりわけ後期後期高齢者層)で小さいため、超高齢社会の到来は、食糧、資源の需要の低下要因となって表れる。また人口高齢化が貯蓄率低下、投資の減少を通じて経済成長に対してマイナスの影響を与えるとすれば、食糧・資源消費はさらに減少することになろう。ただし都市化の進展は、どちらかというと資源、食糧の需要・環境負荷の増大要因として作用するものと考えられる。
参考文献 3‐1節
(1) 阿藤誠,2000.『現代人口学』日本評論社
(2) 国立社会保障・人口問題研究所、2006. 『日本の将来推計人口:平成18年12月推計』
(3) 国立社会保障・人口問題研究所,2007. 『都道府県別将来推計人口:平成19年5月推計』
(4) 国立社会保障・人口問題研究所,2008. 『人口統計資料集2008』
(5) 日本人口学会編,2002. 『人口大事典』培風館
(6) Council of Europe, 2006. Recent Demographic Developments in Europe,
2005.
(7) Lutz, Wolfgang et al. (eds.), 2004. The End of World Population
Growth in the 21st Century, Earthscan.
(8) United Nations, 2006. World Population Prospects, 2006 Revision.
(9) United Nations, 2003.Long‐Range Population Projections.
(10)United Nations, 2007.World Urbanization Prospects, 2005 Revision.
3‐2 生態系資源への影響
約1万年前、自然的な地球温暖化を背景に、人類は農耕を発明し現在に連なる新しい文明世界への歩みを始めた。そして、地質時代の植物群の遺産(化石エネルギー資源)を利用することで、現在のような優れた科学技術文明に到達し、いまや地球のみならず近くの惑星までもその影響下に包み込み、人間圏という独自の世界を築き上げている。
しかし、人類は生物という大枠から脱する事はできない。それは、人類の生存を支えるエネルギー摂取の様式が、約40億年前に原始生命が地球に誕生して以来長期にわたり守り続けているシステムとほとんど同様だからである。それゆえ、緑色植物群の産みだす林業・農業等(バイオマス)資源は、人類をふくむ全生物群の生存エネルギー資源ともいうことができる。
3‐2‐1 人口増加による食料生産とバイオ燃料生産に投入するエネルギー
(1)食料生産と化石エネルギー
人類の生存エネルギー獲得は自らの労働(筋力)のみに頼る段階から出発して、家畜の力そして多くの機械・肥料・農薬などを利用する高収性農業段階へと進化してきた。このような進歩・発展により、先進国農業が
- 労働生産性の飛躍的な上昇
- 土地生産性の急上昇
2つの大きな成果を挙げ、多くの人々に潤沢に食料を供給し、豊かで便利な市民生活をもたらしたことは、広く知られている通りである。
しかし、食料生産の飛躍的な拡大をもたらした高収性農業技術のすべては化石エネルギーの大量投入によって生まれ維持されている。例えば、窒素肥料1㎏は約2万kcal、農薬1㎏は2.4万kcalの化石エネルギーを投入して生産されている。それ故、近代の食料生産様式は、太陽エネルギーを生存エネルギーへ変換するという農業本来の性格を、太陽エネルギーと化石エネルギーとを生存エネルギーへ変換するという性格へ様変わりさせた趣がある。それにつれ肥料・農薬による周辺環境の汚染が進み、安全な食料生産が損なわれ、周辺環境が劣化してきた。また、有限の資源‐化石燃料の枯渇が食料生産の停滞と崩壊、そして食品の高騰を招きかねないという心配も朧げながら視野に浮かんでいる。
食料生産の化石エネルギーへの依存性の分析は、1970年代のオイルショック時に世界的に実施された(例えば、Lockerez,
1977;Duckhamら, 1978;Pimentel and Hall, 1984;宇田川,1977)。これらの研究によると、食料生産への化石エネルギー投入の多寡は次のエネルギーの生産/投入比(ε)によって評価される。この比(ε)は、各種エネルギー産業の生産効率の評価に用いられるEPR(Energy
Profit Ratio)と同一である。この比は、1より大きいほどエネルギーの単位投入当たりの生産エネルギーが多いこと、すなわちより経済的にエネルギーを生産し利用できることを表している。
ε=(収穫物量×発熱量)/生産技術のエネルギー換算積算
これらの結果を総合して、食料生産システムの生存エネルギー生産/投入エネルギー比を比較すると図3‐2‐1のようになる。図にみられるように、自らの筋力とわずかな家畜の力を借りる自給自足農業では、エネルギー比は3~10の間にあり、自らが生産へ投下した筋力エネルギーをはるかに上回る生存エネルギーを獲得している。しかし、生産した生存エネルギー量はわずかで、多くの人を扶養する事は出来なかった。多くの化石エネルギーを投入する高収性農業では、エネルギー比は一般作物栽培で0.4~3.0と急減し、より多くの化石エネルギーが生産へ投入され、人の力を主として投入化石エネルギーの操作に使用されるようになってきた。これにより、土地生産性と労働生産性とが飛躍的に上昇した。例えば、現在米国の農民は1人で数十人を扶養出来る程の食料を生産している。果樹・野菜の露地栽培で0.13~1.6、畜産で0.1~0.6と低下している。特に不良気象下で営まれるハウス野菜栽培では、0.01~0.03と著しく低くなっている。
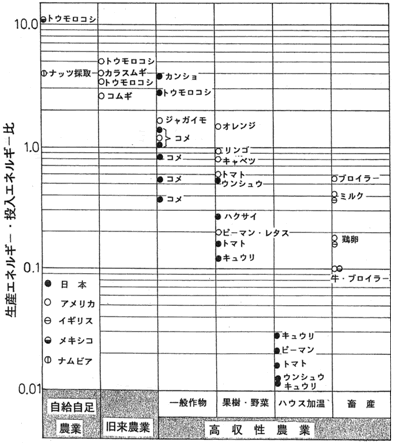
注) 宇田川, 1977;Pimental and Hall, 1988;Duckham et al., 1981;資源協会,1994より作成
図3‐2‐1 各食料生産システムの生産エネルギー/投入エネルギー比の比較
これからわかるように、化石エネルギー依存度の高い生産技術の開発・利用により現代の高収性農業は少ない従事者でより多くの生存エネルギー(食料)を生産し供給できるようになっている。これにより、第2・3次産業部門への大規模な人口移動が可能になり、科学技術文明は新しい地球的な情報通信化時代へと移行してきた。しかし、高収性農業の成功は4つの資源(環境・生物・技術・エネルギー)をセットで不足無く利用できるか否かに掛かっている。これゆえ、現在から近未来にかけての地球環境と地球生態系の人為的な劣化や化石エネルギー資源と淡水資源の不足そして世界人口の更なる増加を考えると、ここ約半世紀の趨勢をそのまま今後へ延長することはむずかしい。
(2)バイオ燃料生産とエネルギー
化石燃料の高騰を受けて、再生可能な代替エネルギーとしてバイオ燃料(バイオエタノールやバイオデーゼル油など)が注目を集めている。既に2006年に37GLのバイオエタノールが製造され、主として自動車燃料として使用されている。この他、ダイズ・ヒマワリ・ナタネなどからバイオデーゼル油も作られ使用されている。このため、小麦・ダイズ栽培からトウモロコシ・サトウキビへの大規模な転作が行われ、小麦やトウモロコシの価格が高騰し、多くの人々が食料の値上がりに直面している。
このような問題の他に、多くの食料資源の燃料への転換がエネルギー生産の観点からプラス(positive
energy return)かマイナス(negative energy return)かという問題が残っている(Pimentel
and Pimentel, 2008)。Hall(1984)は液体燃料生産へのバイオマスの利用には次のような欠点があると指摘して
イ)バイオマス資源は広い範囲に分布し、その集荷には多くのエネルギーが必要
ロ)多くの場合、50~85%の水分を含み、乾燥に多くのエネルギーが必要
ハ) 低エネルギー密度で、化石燃料の1/2~1/3
ニ)炭素含量が低く、化石燃料の約1/2
ホ)耕地・林地からのバイオマス(作物・森林残滓)の搬出は土壌浸食を促進し、地力低下を招く
バイオマス燃料の大量生産の推進は重大な問題を含んでいると結論している。
3‐2‐2 バイオマス資源の人類による利用
現在、人類はその生存をバイオマス資源(食料)へ委ねているばかりでなく、医薬・衣料・建築・燃料・紙などの原料として植物バイオマスを広範に利用している。これらのバイオマス資源は、下のような土地(気象条件を含めて)で生産され収穫されている。
農耕地:1.5 Gha(一般作物 91.3%、永年作物 8.7%)
牧野:3.41Gha(草地・放牧地)
森林:3.87Gha
収穫される生産物(Y)をバイオマス量(B)へ換算するには下の関係式が利用できる。
B=Y(1‐w)/h
ここでwは収穫物の水分率(0 ‐1.0),h(=Y/B)は収穫指数(または収穫係数)。西暦2000年度の収穫資料及び水分率・収穫指数に関する資料を用いて求めた人類による植物バイオマス資源の利用量は下のようになる。
農耕地ルート:5.56Gt乾物/年
牧野ルート:4.77Gt乾物/年
森林ルート:3.69Gt乾物/年
それゆえ、前世紀末における人類による植物バイオマス資源の直接利用率は近似的に次のように評価される。
14.03Gt/120Gt=11.7%
ここでは、陸上の潜在植生の年間生産力に近い純1次生産量(120Gt乾物/年)を仮定して利用率を求めた。実際には、陸上植生の生産力は地球気候の変化によって著しく変化するので(Beerling
and Woodward. 2003)、近未来には当然違ってくるだろう。
Vitousekら(1986)は土地利用パターンの変化・砂漠化・土壌劣化・気候変化などの影響を考慮して、人類による陸上植生のバイオマスの直接・間接利用率を次のように評価している。陸上植生のバイオマス生産量がやや多めに評価されているが、高位利用率では約40%という高い数値を得ている。
低位利用率: 5.2Gt乾物/132.1Gt乾物= 3.9%
中位利用率:40.6Gt乾物/132.1Gt乾物=30.7%
高位利用率:58.1Gt乾物/132.1Gt乾物=38.8%
Seino and Uchijima(1992)は、岩城(1981)が提示した地目別の植生生産力の発現率(林地1.0;農耕地0.81;樹園地0.80;草地0.63;民生用地0.0)と土地利用パターン資料を利用して、人類による陸上植物バイオマスの利用率を39.7%と評価している。この値は、Vitousekらの高位利用率とよく一致している。
これらの結果及び西暦2050年における世界人口(約90億人)と経済規模(約50兆$/年)とから、人類による陸上植生バイオマスの利用率の変化を図3‐2‐2のようにモデル化することができる。いま、陸上植生群のバイオマス生産量を120~130Gt乾物/年とすると、前世紀末(世界人口約60億人、世界GDP約30兆$/年)に、人類は自らのために全バイオマス生産量の25~35%を直接・間接に獲得利用していた。そして残り65~75%がその他の野生生物群に利用されていたことになる。
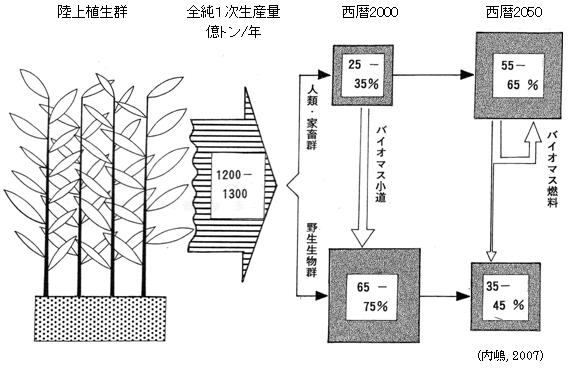
図3‐2‐2 陸上植生バイオマスの人類による利用率の時代的な変化モデル
ここで注目すべき事は、人類・家畜利用ブロックと野生生物群利用ブロックとがバイオマスバイパスで結ばれている事である。このバイパスは小動物・微生物群からなる食物連鎖網そのもので、人類・家畜ブロックの残滓・廃棄バイオマスが、それらの生物群を生かしながら野生生物群へと流れている。これにより表層土壌の肥沃度が維持・増進され、陸上植物群の活発な生育とバイオマス生産が保持されていることを忘れてはならない。
一方、今世紀半ばには増大する世界人口とバイオマス資源への肥大する需要を満たすために、人類によるバイオマス資源の利用はさらに拡大し、人類・家畜利用は55~65%に増加し、そして野生生物群利用は35~45%に減少する可能性が高い。すなわち、人類は陸上植物群の年間バイオマス生産量の半分以上を利用しつくす可能性がある。しかも、重要なことは、両ブロックを結び土壌肥沃度の維持に大きな役割を果してきたバイオマスバイパスが極端に痩せ細る心配があることである。それは、化石エネルギー資源の減少に連れてバイオマス燃料への要求が肥大し、多量の植物バイオマスそして植物残滓がバイオマス燃料の製造に振り向けられるためである。
このような植物バイオマス資源の人類による過剰利用は、単に土壌肥沃度の低下を招くだけでなく、約40億年の進化の歴史をもち地球生態系と人類社会とを物言うこと無く支えてきた植物界を始めとする生物圏を次の2つの面から危機に陥れる可能性がある。
イ)生物界を扶養する生存エネルギーの不足
ロ)野生生物群の安全な生息場所の縮小・消失
地質時代の生物種の大絶滅(Extinction)の幾つかは、地球環境の著しい劣化によって上記2つの事象が発生した時代によく対応している。それゆえ、人類によるバイオマス資源の過剰な利用は、過去の地質時代のそれに匹敵するような生物種の人為的な大絶滅をもたらすと心配されている。そして、その予兆が既に多く報じられている(Constanza et al., 2005;Lincoln, 2006)。
3‐2‐3 生態系各資源への影響
(1)農業資源
地域的な差はあるものの、過去40年間に世界の人口は倍増しているし、1人1日当たりの食物熱量供給量も、1961/63年の2288kcal/人/日から2000/02年の2803kcal/人/日へと、23%の増加を記録している。言うまでもなくこれを可能にしたのは食料(作物、畜産物、加工食品)生産の拡大であり流通技術の発達である。地球上の一部には貧困や政治的な不安定による飢餓や栄養不良といった問題が未だに存在するが、世界全体としてはその人口を養うに十分な食料が生産されているのである。20世紀以降人類は農業生産技術の発達によって多くの便益を享受してきた。病害虫による農作物の被害は長い間、農業に携わるものを悩ませてきたが、20世紀に目覚ましい発展を遂げた化学技術によって作り出された合成農薬がその問題を解決した。また、窒素、燐酸、カリなどの工業的に製造される化学肥料は、手間暇のかかる堆厩肥に代わって作物に栄養分を供給するようになった。
農業の近代化と生産力の増大は、化学的に合成された農薬や肥料の投入増加によって促進されたが、使用された化学物質の一部は水や大気を介して広く環境に拡散し、あるいは食品を介して流通し、農業者のみならず一般市民や動植物にまで被害を及ぼすに至った。レイチェル・カーソンの「沈黙の春」1)は、綿密なデータを駆使して農薬の恐ろしさを世に訴えたが、大量に施用される化学肥料も土壌中に残り、やがて水に溶けて耕地の外に流れ出す。栄養過多となりプランクトンが増殖して水質が汚濁した地下水や河川は、水中の魚や水生植物・微生物などの生命を危うくするばかりか、これを水道水として利用する市民の健康を損なう恐れさえも出てきた。合成農薬や化学肥料に代表される化学物質の大量使用はしばしば農業の化学化といわれるが、最近までわれわれは、化学物質の環境への流出には無頓着であったし、あるいは自然が浄化してくれるものと何らの対策も採ってこなかったのである。
環境へ流出する化学物質が少量であった時代には、その被害は目立つほどではなかったが、大量生産・大量消費の時代を迎えて事態は急速に深刻の度を深めるようになった。しかも、たとえ少量であっても人や動植物に重大な生殖障害をもたらすダイオキシン等の内分泌撹乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の流出が次第に明らかになってきた。われわれ人間の生活や社会的な活動によって不用意に排出されるこれらの物質によって、われわれを取り巻く環境が急速にまた広く汚染されるようになってきたのである。
(2)漁業資源
日本は、明治以降、外貨獲得、国民の栄養源確保のために遠洋漁業を振興してきた。こうした外洋への進出により外国との摩擦が起こり、漁業権を巡る係争を繰り返してきた。こうした事情もあって、乱獲や水産資源変動や乱獲には敏感であるが、近年問題となっている地球環境、人口爆発に対しては、水産関係者の関心は希薄であった。
世界の人口は、2008年現在66億、2050年には91億に達すると予測されている。1987年には50億程度だったことを考えれば、世界の人口の増加は急速である。こうした急拡大は、近年、水産、漁業に2つの大きな問題を人類に投げかけている。1つは、食用資源としての水産生物資源の重要性、もう1つは、海洋開発も含めて水域汚染、水環境汚染への影響である。
a.食用資源としての水産生物資源
地球上の陸域面積は有限である。農耕牧畜は、人類の誕生以来、拡大を続け、必然的に土地利用は限界に近づいている。今や、地球の肺といわれるアマゾンの原生林すら大豆、トウモロコシ生産のために開墾され、地球の温暖化を加速する乱開発との指摘もある。農耕牧畜を行うための土地の限界は、陸上食糧生産の限界を意味する。事実、FAOの統計では、食糧生産の伸びは頭打ちを示している。現在、世界の飢餓人口は8億人に達しているとの報告もある。こうした飢餓に世界の食料資源の配分の不均衡が関与しているにしても、今後、推定されるような人口増加があり、さらに、食糧生産の停滞と言う将来の動向を勘案すれば、今後飢餓人口の拡大は確実である。必然的に、未利用資源、海洋生物資源、の開発、利用に目が向かうことになる。1980年頃までは、世界の他の国が魚を食料として漁獲していなかったと言う事情もあり、水産資源の利用については、日本の独壇場で、世界の海で漁場開発、輸入を自由に行ってきたが、1977年に日本も国際海洋法条約に基づき200海里設定以降、上述の食糧生産環境の変化もあり、海洋生物資源に対する世界の潮流は、食料資源としての水産物利用に関して、日本の独占を許さない状況に向かいつつあり、資源争奪の場になりつつある。一方で、FAOの漁獲統計によれば、1990年に1億t前後であったものが、2003年には、世界の漁獲量は1.3億tまで暫増し、その内1/3は中国が漁獲(中国は、近年生産量を急速に伸ばしているが、その漁獲統計は過大だとの見方がある)し、漁獲圧が高まっている。日本の生産は475万tを占めるに過ぎない。日本の急減には、乱獲に伴う漁場環境・資源環境の悪化が関係していると考えられている。世界の海洋生物資源利用についても、ほとんどの魚種で、利用できる漁獲量の満限に近く、マグロなど一部魚種では乱獲状態にあり、世界の総漁獲量も限界に近いとの見方が広がっている。
人口問題は、漁業生産を増大させる方向で働き、自然資源、環境に対し過大な負荷をかけることになり、資源状態の悪化が危惧されている。公海上の、マグロなど高度回遊魚には、自然資源の保全と言った観点ばかりでなく、種の保存の観点からも国際規制が強まる傾向にある他、海洋資源は沿岸国のものだけでなく、人類共通の財産との主張の高まりを受け漁業を取り巻く環境は複雑である。
b.海洋環境に及ぼす影響
人類の活動は、自然環境に影響を及ぼす。その活動が小さく、狭い場合、影響は限定的であるが、産業活動のように規模が拡大すると、影響は社会的で、水俣病やタンカ‐事故による原油流出のような重大な公害、健康被害、海域汚染、を引き起こすこともある。近年、人の活動は地球規模に広がり、もたらす影響も大きい。化石燃料の消費による温暖化がその典型だが、海洋でも、国際海洋汚染防止法が施行されているものの、日本海のゴミ問題、海洋汚染、船舶のバラスト水による生物種撹乱など問題は多様で、深刻である。サケ類、アユなど遡河性魚類は、海と母河を往復するが、回帰過程でヒトの生活圏を通過するために、環境ホルモンなどにより繁殖に直接・間接影響すると危惧されている。
人口増加は、その活動に伴ってさまざまな人工物質、化学物質、廃棄物を生み出し、海洋に排出、蓄積される。それに伴って、海洋環境の悪化、水産生物生息環境の劣化、漁業生産の低下と連鎖し、深刻な結果をもたらすと考えられるが、影響は緩慢であり、現時点で、資源の将来を予測できる段階にはないし、その因果関係を明確に証明することも難しい。
(3)土地資源
a.生産要素としての土地資源
経済辞典は、資源(resource)を「生産に必要な労働、土地、自然資源などの本源的生産要素や生産手段としての資本財の集合の全体」とし、経済学の主要課題を「有限な資源の効率的利用の条件を明らかにすること」と説明している。土地は人間が居住し生活を営むための不可欠な地球上の資源であり、農林業という経済活動は土地という本源的な生産要素に働きかけ、その効率的な利用を図るという人間の営みである。農林業にとっての土地資源は単にある広がりを持った地表というだけではなく、人間がその社会生活を維持し向上させてゆくために働きかける対象のひとつである。
国際連合食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations
: FAO)の統計2)によれば、2002年現在、世界の総土地面積(内陸水域を除く総面積)は130億6694万ha、農用地面積(耕地、永年作物作付地、永年牧草地の面積)は50億688万ha(永年牧草地を除けば15億3447万ha)、そのうち耕地面積(単年作物及び単年牧草作付地、並びに一時的休耕地)を14億405万ha、森林面積を38億6880万haとしている。このうち、世界の人口の2.0%が居住するわが国の総土地面積は3645万ha、農用地面積は519万ha(永年牧草地を除けば476万ha)、うち耕地面積は442万ha、森林面積は2408万haとなっており、それぞれ世界全体の0.28%、0.10%(永年牧草地を除けば0.31%)、0.31%、0.62%を占めるに過ぎない。
世界の人口は過去40年間に約2倍に増大しているが、この間に世界の森林面積は4%の減少を記録し、農用地(永年牧草地を除く)及び耕地面積はそれぞれ11%及び8%の増加となっており、大雑把にいえば人口の増加が農用地を増やし森林面積を減らしてきた。この間に、世界の工業用材の生産量は僅か0.6%しか増加していないのに、世界の1人当たり食料生産指数は61%(年率1.2%)上昇し、人々の栄養水準は農用地面積拡大率を超える速さで改善されてきたのである。このような世界の動向とは異なり、わが国での土地資源の利用状況には次のような変化が見られる。
森林面積は過去40年間に5%弱の減少(年率ほぼ0.1%程度でなだらかに減少)を記録しているが、工業用材の生産量は68%の減少、用材の自給率は1960年代前半の80%水準から今では20%を割ってしまっている。食料供給の面でも、1人1日当たりの食物熱量供給量は40年前の2300kcal台から30年前には2500kcal台に、そして20年前に2600kcalを超えて1996年には2670kcalのピークを記録し、以降緩やかな減少傾向にあるとはいえ、飽食といわれる状態を維持しているが、食物熱量供給量で計った食料自給率は年々低下を続け、1960年代前半の75%前後から今や40%を割り込むような状況となっているのである。
農用地や食料生産の減少傾向の続くなかで飽食といわれる状況にあるわが国とは異なり、人口増加が問題とされる一部の開発途上諸国では栄養不足人口の削減への努力が求められている。1996年の世界食料サミット及び2000年のミレニアムサミットでは、ベースライン期間(1990年)と2015年の間に飢餓人口を約8億人から4億人に半減するという意欲的な目標が設定された。人口の増加率の高い開発途上国特にサブ・サハラ・アフリカでは、この目標の達成には格段の努力が必要と見られ、栄養不足人口比率が35%‐開発途上国平均では18%(2000~02年現在)を超えているような国々ではむしろ事態は悪化の方向にあるともいわれている。しかしサブ・サハラ・アフリカ全体としては、遅々たる歩みではあるが、明らかに栄養水準は向上していると見られる(表3‐2‐1参照)。勿論、アフリカの栄養水準の向上には食料援助の寄与を忘れるわけには行かないが、人間の働きかけによる土地生産力の向上の効果も無視できないであろう。
既述のように、現在わが国の農用地及び耕地面積は、それぞれ世界の0.28%及び0.31%を占めるに過ぎないが、40年前及び20年前のこの値はそれぞれ0.43%及び0.42%、ならびに0.42%及び0.32%であった。また、40年前及び20年前の農業就業者数割合は、それぞれ世界全体の1.5%と0.6%であったが、現在は0.2%にまで低下している。先進諸国での農業生産における労働土地比率(man‐land‐ratio)の低下、そして開発途上諸国での労働土地比率の上昇は現代では一般的な傾向ではあるが、わが国におけるその低下速度の大きさは際立っており、土地生産性の高さも群を抜いていると称してよいであろう(表3‐2‐2参照)。
表3‐2‐1 食物熱量供給量と栄養不足人口比率
|
|
食物熱量供給量 (kcal/ 人 / 日 ) | 栄養不足人口比率 ( % ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-71 | 1990-92 | 2000-02 | 1969-71 | 1990-92 | 2000-02 | |
| 世界 | 2430 | 2708 | 2803 | |||
| 先進国 | 3200 | 3273 | 3314 | |||
| 日本 | 2521 | 2634 | 2624 | |||
| 開発途上国 | 2120 | 2537 | 2667 | 36 | 20 | 17 |
| アフリカ | 2140 | 2175 | 2254 | 35 | 36 | 33 |
| 南アジア | 2040 | 2317 | 2389 | 34 | 26 | 22 |
資料:
FAO, World Agriculture : Towards 2010 An FAO Study, 1995, Rome
FAO,
The State of Food and Agriculture 2005, 2006, Rome
農林水産省総合食料局 「食料需給表
平成16年度」 平成18年3月
表3‐2‐2 農業の労働土地比率と土地生産性:国際比較
| 労働土地比率 (人/ha) | 土地生産性 (ton/ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1980 | 2002 | 1969-71 | 1979-81 | 1999-2001 | |
| 世界 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 1.77 | 2.20 | 3.10 |
| 先進国 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 2.89 | 3.40 | 4.54 |
| 日本 | 2.38 | 1.48 | 0.55 | 5.05 | 5.26 | 6.12 |
| 開発途上国 | 0.76 | 0.89 | 1.20 | 1.25 | 1.56 | 2.28 |
| アフリカ | 0.59 | 0.94 | 1.24 | 0.80 | 0.94 | 1.03 |
| 極東 | 1.12 | 1.26 | 1.98 | 1.33 | 1.67 | 2.71 |
註:
(1)労働土地比率は耕地に対する比率。 土地生産性は単位面積当たり穀物収量。
(2)先進国は旧ソ連を除き、開発途上国には中国を含まず。
資料:FAO, Production Yearbook 1978, 1991, 2003.
日本農業の土地生産性そして労働生産性の高さは高度に発達した生産技術がもたらしたものである。土地が労働力その他の生産要素に対して相対的に稀少な日本農業では、まず耕地単位面積当たりの生産性を高めるための技術(品種改良、土地改良、育苗法改良、肥料や農薬使用法の改良、等)が発達し、1960年代以降は労働節約的機械化技術体系の導入とその発達が技術進歩をもたらし、整備された普及制度の下でこれらの技術が広く行き渡った。そして、優れた資質を備えた勤勉な農民の存在が、農業の生産性の高さを実現させてきたのである。過去40年間に、わが国の農用地及び耕地の面積は世界のそれの0.4%から0.3%にそのシェアを落としてきたが、上述のような生産性の高さを考慮すれば、わが国の農用地及び耕地の世界農業に対する寄与率はそれ以上に評価されることになろう。すなわち、農業生産資源としてのわが国の土地は、その面積では極めてマイナーな存在と言わざるを得ないが、農業生産への実質的な貢献という点では、名目的な面積以上の役割をはたしているといえよう(表3‐2‐3参照)。
表3‐2‐3 世界における日本の耕地面積のシェア
(%)
| 世界 | 先進国 | 日本 | 途上国 | アフリカ | 極 東 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実面積(1万ha) | ||||||
| 1980 | 132595 | 31.9 | 0.41 | 43.7 | 9.6 | 19.4 |
| 2002 | 140405 | 29.2 | 0.31 | 46.3 | 10.6 | 17.8 |
| 生産力で評価した面積 | ||||||
| 1980 | 100.0 | 49.1 | 0.98 | 30.9 | 4.1 | 14.7 |
| 2002 | 100.0 | 42.8 | 0.61 | 34.1 | 3.5 | 15.6 |
註:
(1)生産力で評価した面積=実面積x各地域の穀物収量/世界平均収量
(2)先進国は旧ソ連を除き、途上国には中国を含まず
資料:FAO, Production Yearbook 1991, 2003
わが国の農業生産指数は1986年をピークとして下降に転じ、現在の水準はピーク時の71%にまで低下している。この間耕地面積は15%の減少を記録し、土地生産性は16%も低下したことになるが、表3‐2‐3が示唆するように、最近では耕地面積のみならず高い技術水準の維持も困難になってきたといえよう。農家人口の急減や高齢化の進行が農業生産性の伸びに暗い影を落とすようになってきたことは否定しがたく、経済構造の変化や都市化の進展が農業生産資源特に土地資源の維持管理に困難をもたらしつつあることを示すものであろう。
b.土地資源の減少と海外依存
土地資源は、広義には地表全体に関わるものであろうが、農業生産にとっては農用地、なかでも耕地がもっとも基本的な資源であり、古来その整備に人力や資本が投入され、制度が作られ、運営の仕組みが整えられてきた。人類の歴史の大部分を占める農業社会は言うまでもなく、近々200年の工業化社会になっても、土地制度はその仕組みを変えながらも社会経済の基本的なシステムであり続けたが、現代におけるその仕組みを変える大きな要因は人口及び資本の流れであろう。1960年代以降のわが国経済発展の跡を辿って見ると、人口及び資本の都市集中と都市の地価高騰、その土地を担保とする企業の規模拡張が見られるし、交通手段の整備とともにその傾向は地方へも波及していった。農村の変貌はその人口及び農地面積の急速な減少によって代表させることができる。すなわち、1965年に総人口の31%を占めていた農家人口は、1975年には21%に、1985年には16%に、1995年には12%に、そして2005年には7%へと急激に減少した。また耕地面積も拡張するよりも壊廃する方が多く、しかも自然災害に起因するよりも人為的壊廃(非農業的用途への転用や耕作放棄など)によるものが多く、2005年現在の耕地総面積は1965年当時の600万haの78%の水準まで落ち込み、作付け延べ面積も40%強の減少を記録している。耕地の壊廃面積のうち自然災害によるものは、人為壊廃に比べれば量的にも少ないし年変動が大きいが、多くの場合は耕地として復元される可能性をもっている。一方、人為壊廃面積の40~50%を占める非農業的用途に転用された耕地は、農業生産資源からは排除されたものとせざるを得まい(表3‐2‐4参照)。
表3‐2‐4 耕地の拡張壊廃面積(全国、田畑計)
(1000 ha)
| 年次 | 拡張 | 壊廃 | うち人為改廃 |
|---|---|---|---|
| 1966 ~ 1970 | 250.5 | 41209 | 395.9 |
| 1971 ~ 1975 | 231.7 | 499.7 | 485.8 |
| 1976 ~ 1980 | 182.2 | 293.5 | 288.2 |
| 1981 ~ 1985 | 110.4 | 192.7 | 188.1 |
| 1986 ~ 1990 | 80.1 | 216.1 | 214.2 |
| 1991 ~ 1995 | 35.6 | 240.7 | 236.3 |
| 1996 ~ 2000 | 17.1 | 224.9 | 221.1 |
| 2001 ~ 2005 | 21.8 | 160.5 | 148.2 |
註 :5年間の累計を示す。 壊廃=自然災害+人為壊廃
資料:農林水産省「耕地および作付面積調査」
長い歴史を通じて造成され維持されてきた農業生産のための土地資源は、過去40年間に上記のような量的な減少を記録しているが、耕地などの機能の維持・改善に直接関わる農業就業者数の減少や高齢化が土地資源の質的な劣化に繋がっていることは否定し得ないであろう。また、長期にわたる稲作の減反政策は土地生産性の低下をもたらし、農業生産指数はここ20年間低下傾向を辿ってきており、国内農業の更なる縮小が懸念される。1990年代初め以来安定的に推移してきている食生活の内容と人口の動向を考えれば、総体としてのわが国の食料需要が今後拡大するとは考えにくいが、国内生産の縮小が続けば、食料の輸入依存度はむしろ高まると見てよいであろう。
世界最大の食料輸入国であるわが国は、人口では世界人口の僅か2%を擁するに過ぎないが、食料輸入額では世界全体の11%を占めている。他方、世界人口の8割が居住する開発途上諸国の食料輸入額は、世界の食料貿易額の29%に止まっているのが現状である。高度の工業製品を中心にした輸出によって外貨を稼ぎ出しているわが国が、その外貨の9%を食料輸入に充当しているのに対して、食料不足低所得開発途上諸国では、稼いだ外貨の13%を食料主として穀物の輸入に向けている。世界の食料貿易額は年々拡大する傾向にあるが、その伸びは商品貿易額全体の伸びには及ばない。しかし、低所得開発途上諸国では食料輸入額が商品輸入総額の伸びを上回る勢いで増加しているのである。つまり、世界の食料貿易市場における低所得開発途上諸国の比重の高まりは必須のことと考えられるし、これらの諸国とわが国とが世界の食料貿易市場において激しく競い合い、主要食料輸出国の食料生産資源に対する奪い合いが現実化しないとも限らないのである。
カロリーで測った食料自給率が最近40%を割り込んでしまったわが国の食料需給の現状は、飽食といわれる食生活に対する国内食料生産資源の乏しさ、あるいは資源利用の不適切さを表現しているというべきであろう。食料自給率40%というのは、わが国総人口の6割の7600万人分の食料が、外国の農地で外国の農業就業者の手によって生産されていることを意味する。わが国と外国(世界平均)との土地及び労働生産性の差を勘案して、日本人7600万人分の食料生産に必要とされる外国の耕地や農業就業者の数を推計してみると、耕地面積では1200万ha(現在の日本の耕地面積の2.6倍)、農業就業者数では1600万人(現在の日本の販売農家の就業者数の2.9倍)という結果が得られる。すなわち、現代の日本人の食生活を維持するには、国内生産資源だけではなく、その3倍の海外の食料生産資源に依存せざるを得ないのである。因に、2005年3月に公表された「食料・農業・農村基本計画」の試算では、輸入が途絶し、2015年に予想される利用可能な国内資源のみを利用して熱効率優先の食料生産が行われた場合には、国民1人当たり食物熱量供給量は、飢餓状態に近かった1940年代後半の1800~2020kcal(現状の72~77%)程度のなるという推計が行われている。
(4)水資源
水は土地と同じく、生計維持のための生産システムを支える自然資源の基礎を構成する。水資源の確保によって人々は生産性の向上を実現し、暮らしの安定と多様化を可能にする。水の供給を含む生態系の持続可能性は貧困の減少や緩和に関わっており、灌漑システムのある地域の貧困レベルは、そうでない地域のレベルよりも20~30%低いといわれている3)。灌漑は生産量の増加や実収入の向上、雇用の拡大から食料価格の下落まで、貧困を削減するさまざまな恩恵をもたらしているのである。
水の惑星といわれる地球上の水の97.5%は海水で、淡水は2.5%に過ぎず、しかも、人間の利用が可能な淡水はその17%に過ぎないという。水は無限に再生産可能な資源で、雲から降った雨は河川を通って海へと流れ、蒸発して再び雲へと戻って行くが、その供給量は有限であり、地球上の人すべてについて1人当たり6900立方メートルに相当するとされ、1人当たり最低必要量とされている1700立方メートルからすると、ずっと多くの水が世界には存在することになる。しかし、利用可能な水の量の地域間分布の格差は大きく、世界の淡水資源の31%を有するラテン・アメリカの1人当たりの水の量は南アジアのそれの12倍に相当するという。
過去100年間に世界の人口は4倍になり、工業用水と生活用水の利用を中心に水使用量は7倍になったと言われるが、シクロマノフ(I.A.Shiklomanov)の推計によれば、1950年当時1480リットルであった世界の1人1日当たりの水使用量は、最近では1700リットル前後で推移しており、農業用水の割合も1950年当時の79%から69%に低下しているが4)、食料を生産するのには家事に使う水の量の70倍もの水が必要とされるのである。わが国の年間降雨量1700㎜は世界の平均を大きく上回っており、灌漑比率(灌漑面積/耕地・永年作物面積)も55%と世界の平均18%を遥かに超えており、いわゆる水ストレスが問題になることはないが、わが国が輸入する食料の生産に琵琶湖の水量の2.5倍もの水が利用されているといわれていること(いわゆるvirtual
waterの輸入)には、われわれとしてはもっと関心を持ってよいであろう。
(5)土地及び水資源の利用システム
土地や水といった自然資源のみならず、多様な動植物やあらゆる投入財が農林業という経済活動に直接的にまた間接的に必要とされており、その機能を十分に発揮させるためには、それらの開発・投入・保全のための法制度を含む社会経済的なシステムが整えられなければならない。そしてそのシステムは、農林業だけではなく社会全体の人間活動を方向づける役割を有し、時代とともに変化し、また現代社会のように国内的要因だけではなく国際的な動きにも対応せざるを得ないであろう。現代社会の経済では、資本と人間とがその効率的な利用を求めて流動的に地域間を移動するし、グローバルな経済との交流も当然視野に入れておかねばならない。しかし農林業に関する限りは、自然を要因とした地域社会との繋がりをもった個性的な発展が、社会の活性化や環境問題への対応として重視されるであろうし、農林地や水といった農林業生産資源の存在形態、あるいはその開発・利用・維持保全のための地域的特色をもった資源の管理システムが重要な役割を果たすことになる。
農林地及び農業用水等は農林業の生産活動にとって最も基礎的な資源であり、食料や生活資材の安定供給確保ならびに2次的自然の形成や維持に不可欠の社会共通資本とされ、これらの維持整備のために多くの努力が傾注されてきている。例えば、現在(2005年)わが国の総耕地面積465万haのうち、水田面積の6割が30アール以上に区画整理されており、畑地面積の7割以上で農道が、2割に灌漑施設が設けられているなど、優良な農業生産基盤が整備されている。また、全国に約40万kmに及ぶ農業生産のための用排水路、約7千個所のダム、約21万個所の溜め池等が、全国の年間水使用量の3分の2に相当する566億立方メートルの農業用水の利活用を可能にし、その運営管理のために集落組織や土地改良区などの組織が機能している。総面積240億ha強の林野のうち、林野庁によって管理運営されている国有林、地方公共団体が管理する公有林の面積は、全林野面積のそれぞれ30%及び14%を占めているが、134億haの民有林の66%は森林組合加入者の所有となっている。
このように、資源の維持管理に必要な社会システムが作られ運用されてきているが、時の経過とともに資源の保持管理に問題が生じてくることは避け難い現実であろう。気象変動や自然災害による資源の劣化は勿論、人口の変化や人間の社会的な活動そのものがもたらすものも無視し難く、少なくともその例証としてわが国における農用地の減少を挙げることはできよう。
参考文献 3‐2‐3節
(1) Carson, Rachel L., Silent Spring, Houghton Mifflin Co., 1962,
Boston
(2) FAO, Production Yearbook Vol.57‐2003, Rome
FAO, The State of Food and Agriculture 2005, Rome
(3) Husain, Intizar., "Pro‐poor Intervention Strategies in
Irrigated Agriculture in Asia. Final Synthesis Report,"
International Water Management Institute, 2005, Colombo
(4) Shiklomanov, I. A., World Water Resource and their Use, 1999
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課資源室
-- 登録:平成21年以前 --