| ≪ |
天体分野≫
| ● |
銀河形成シミュレーション【10ペタフロップス級】
宇宙を構成する大規模構造物質の基本単位である銀河がどのように形成されたかを明らかにするために、100億個の粒子を用いた、銀河の現実的な(超新星※による加熱、重力崩壊など)成長過程に基づいた形成シミュレーションを行う。
これにより、銀河の形成過程、銀河の形態分類(ハッブルの音叉系列※)の意味を明らかにする。
 |
 |
 |
 |
 |
| ※ |
| 超新星 |
: |
比較的重い星が進化して死を迎える時、大爆発を起こしたもの。小柴博士のノーベル受賞は、超新星爆発時のニュートリノ観測が主な理由である。 |
| ハッブルの音叉系列 |
: |
米国の天文学者ハッブルが規定した銀河形態の分類方法 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
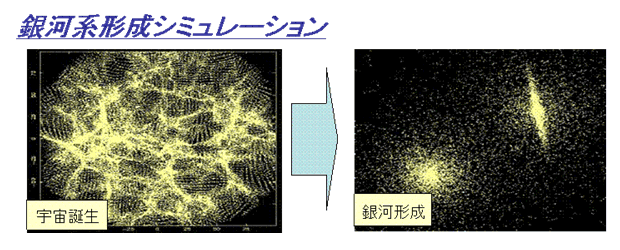 |
| ● |
惑星形成シミュレーション【10ペタフロップス級】
地球を含めた太陽系惑星・衛星の起源を明らかにし、その宇宙における発生頻度を評価するために、1000万個の粒子を用いて、原始太陽系円盤の中の微惑星が相互に散乱と衝突・合体を繰り返しながら成長し、現在の姿になるまでをシミュレーションする。
これにより、人間の居住可能な地球型惑星が太陽系近傍に存在する数を知ることができる。
さらに、土星の環の起源とそのダイナミクスを明らかにし、カッシーニミッション(NASA(ナサ)が1997年10月に打ち上げた土星探査機カッシーニの土星調査)の観測と比較する。 |
| |
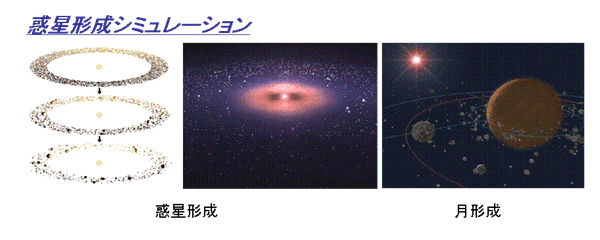 |
|