- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 人材委員会 > 資料2‐1 科学技術分野の理解増進活動 関連資料 > 8.科学技術理解増進活動を担う人材に関する調査
8.科学技術理解増進活動を担う人材に関する調査
・科学科学館・科学系博物館職員が考えている現在の問題点(PDF:118KB)(※下記参照)
英国の主な科学コミュニケーター養成コース
出典:「科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について」
| 大学コース名 | コースの種別・期間 | 種類と定員 | 講義内容 | 主な就職先 |
|---|---|---|---|---|
| ロンドン大学インペリアルカレッジ 科学コミュニケーション グループ | 修士課程、全日制は1年、夜間コースは2年 | 科学コミュニケーションコース(40人)、科学メディア制作コース(10人)、技術翻訳コース(5人) | セミナーがコアカリキュラム | 主にマスメディア、翻訳会社、企業、国際機関 |
| ロンドン大学ユニヴァーシティカレッジ科学社会論学科 | 学部、修士課程(1年)、博士課程 | 科学社会論学科内に併設 | セミナー、科学社会論・科学史関連の講義 | マスメディアその他 |
| バース大学科学・文化・コミュニケーション・プログラム | 修士課程(全日制は1年、夜間は2~4年) | 科学コミュニケーション・メディア研究コース(12~15人) | 科学一般と科学技術理解増進、コミュニケーション技術の習得 | メディア、博物館、教育機関、企業 |
| オープン・ユニヴァーシティ (放送大学) |
1998年創設の修士課程(3~7年) | 科学(科学コミュニケーション、科学と社会) | 科学コミュニケーション、科学社会論ほか、7つのモジュールプログラムから選択 |
米国の主な科学コミュニケーター養成コース
出典:「科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について」
| 大学コース名 | コースの種別・期間 | 種類と定員 | 講義内容 | 主な就職先 |
|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア大学サンタクルス校科学コミュニケーションコース | 修士課程(1年) | サイエンスライティング・コース、サイエンスイラストレーション・コース、各10名 | ライティング・コースは、執筆、編集、ワークショップが軸。イラストレーション・コースは実技主体 | マスメディア、プログラム・マネージャー、学芸員、博物館等の美術担当他 |
| ボストン大学科学・医学ジャーナリズムコース | 修士課程(1年半) | 科学・医学ジャーナリズム・コース、15~20名 | 演習と講義 | メディア、 大学広報部他 |
| ジョンズホプキンス大学ライティング・セミナーズ | 修士課程(1年) | サイエンスライティング・プログラム、5名 | セミナー中心 | メディア、 博物館、広報部 |
| ニューヨーク大学ジャーナリズム・マスコミュニケーション学部 | 修士(1年) | 科学・環境報道コース、12~15名 | セミナーと講義 | メディア |
| マサチューセッツ工科大学サイエンスライティング・プログラム | 修士(1年) | サイエンスライティング・プログラム、5名 | セミナー、他学部の講義 | 2002年秋創設 |
・研究職以外の方面へ進出を考えたときに興味のある職種(年齢別)、(職位別)(PDF:57KB)(※下記参照)
青少年のための科学の祭典の出典参加者の内訳
| 出展者総数対象数 | 6413 | |
|---|---|---|
| 小学校教員 | 972 | 15.2% |
| 中学校教員 | 845 | 13.2% |
| 高等学校教員 | 1477 | 23.0% |
| 高専教員 | 36 | 0.6% |
| 大学教員・学生 | 557 | 8.7% |
| その他学校 | 68 | 1.1% |
| 教育センター | 108 | 1.7% |
| 教育委員会 | 46 | 0.7% |
| 科学館博物館職員 | 111 | 1.7% |
| 行政関係 | 66 | 1.0% |
| 企業 | 161 | 2.5% |
| その他団体 | 87 | 1.4% |
| 所属判明者数 | 4534 | 70.7% |
| 所属不明者数 | 1879 | 29.3% |
- 対象は1995年度以降・任意提出の勤務先から分類・不明者には、無職、勤務先等調査以前の情報を含む・所属が大学の場合は教員か学生か不明・その他学校には、幼稚園、保育園、盲・聾・養護学校を含む・行政関係には、国立研究所、県立研究所・試験場を含む
青少年のための科学の祭典入場者データ
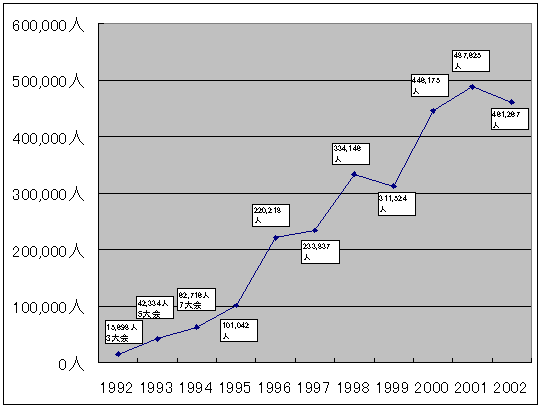
サイエンス・レンジャーからの意見・要望
自分たちを取り巻く現状について
○ 授業や部活顧問など忙しい中でSR活動をするのはかなり大変。また、熱心に外での活動を行うと、自校の生徒への教育をないがしろにしているという同僚の目がある。
○ SRは、地域で何らかの活動をしている。私も仲間たちとグループをつくり実験教室を開催している。費用は、通常、主催者が負担するが、自分たちの意志でやろうとするときは、自己負担で行っている。
○ 僻地の子供たちにも楽しい実験を経験させたい。という願いでキャラバンを計画しているが、苦しい財政の為、自治体負担の実験教室は先細りが実態。
○ なかなか外に出ようとしない教員が多い現実がある。グループで実験教室をする時の研修会では、「メンバー一人が、仲間を一人連れてきましょう」と言うことで口コミのような形で地道に増やしている状態。企画する者は少数でも、実施する場合は、運営する者の人数をできるだけ多くする。実験の講師もできるだけ多くする。などの工夫が必要
○ あくまでも子どもために、理科大好きの(いや理科に興味を持って欲しい教員になること)集団を、個人を作り出すことが大切。指導方法などではなく、実験そのものに興味を持って欲しい。その魅力を伝えられたら最高。
○ 理科研究会の予算も削られ、活動が先細りになっている。会員も半減した。
○ 教員自身が必ずしも理科について課題意識を持っているとは限らない。小学校ではあらゆる教科を指導する大変さを持っている。そのために理科はあっさりしようと言う考えは起こりうる。そのような先生に魅力を感じさせるためにちょっとした観点で実験がしすくなる、楽しい、面白いを体験させたい。
サイエンス・レンジャー活動を行うには
○ 人事異動などで先生が変わると活動が変わることがある。先生が変わっても同じ活動を続けられる体制作りが必要。
○ 原則的には一般教員の現場に知れ渡ることが重要だと思う。当然、指導主事などのレベルにも理解が必要である。つまり現場に対して、理科推進のための協力という意味の強調が重要。
○ 大事なのは二一ズの把握である。講師として企画立案しても、我々が二一ズを捜しだすのは難しい。
ボランティア活動にはどのような条件が必要か
○ 親子科学教室は結構参加者が多い。一緒に楽しむことが今重要だと思う。特に母親の影響は大きいだろう。親子教室で7割から8割は母親である。
○ 平日の勤務のときは、出動しにくい。夏休み等の長期休校のときが望ましい。
○ 地元の人とのネットワークができると交流ができる。そうなると年に数回しか使わない機材を使いまわしできるなど資金や資材の効率的な運用が可能。
○ 資金があれば僻地での実験教室も可能。現実は資金不足のため見送っている。
SRが地域コーディネーターとして他学校に出動することについて
○ 県教委から通達があると行きやすい。
○ 文科省のバックアップが明確だと出やすい。
○ 個人的には行きたいが、自分の業務を他の人に任せることになり、管理職よりも同僚の目が気になる。
○ 活動には資金が必要。謝礼をもらっても交通費分だけ抜き、残りは活動資金にまわしている。
○ SRとして公的に認知されていないので、私たちが、実験教室に出るときや、研修会に出るときに、上司の許可を得るのにずいぶんとエネルギーを使う。何かあるときは出動させよという通達が県教委から市教委へおろしておくと出やすいし、上司が判断しやすい。
お問合せ先
科学技術・学術政策局基盤政策課
-- 登録:平成21年以前 --