 |
子どもへの保護者の関与の度合いの低さ |
| |
| [調査結果] |
| ○ |
家庭での親子の関わりについてみると、日本の保護者は子どもに生活規律・社会のルールを身に付けるようにしつけることや、ほめる・叱るなどの子どもとコミュニケーションをとることの度合いが、他国と比較して低い(図5)。
一方で、育児不安を感じたり、子どものことでどうしたらよいか分からないと感じる親が、以前と比較して増加している(図6)。また、子どものことに関して家族が協力してくれないことについて、保護者の約2割が相談できる相手がいないと回答している(図7)。
家庭教育についての考え方については、保護者に子どもの自主性を尊重する傾向が強まっており、親子間の考え方等に衝突の少ない、いわゆる「仲良し家族」が増えている(図8)。一方で、3〜6割の保護者が、基本的な食事マナーや社会のルール等の指導を学校で行ってほしい、あるいは行うべきだと考えている(図9,10)。
|
| [これまでに得られた知見] |
| ○ |
子どもの情動(感情のうち,喜怒哀楽のように表情・動作に表れやすいもの)の発達の基盤として、乳幼児期において親子間の愛着形成が重要な役割を果たすことや、良好な家庭環境を築き保護者が子どもに肯定的に接することが、子どもの意欲を高めることが明らかとなっている。
具体的には、保護者が「悪いことをしたときに叱ってくれる」「いいことをしたときにほめてくれる」「困ったときに相談にのってくれる」と感じている小学生は、よく遊ぶ友達や悩み事を相談できる友達が多く、学習面においても「分からないことを調べる」「じっくり考える」ことなどが得意だという研究結果がある。また、父親と子どもの間の良好な親子関係がある場合に、子どもの自立性がより一層育まれると推察している調査結果もある。 |
|
| |
| 日本の青少年は、生活規律や社会のルールについて保護者から直接しつけられることが少ない。 |
| 図5 |
|
お父さんやお母さんから言われること(国際比較) |
|
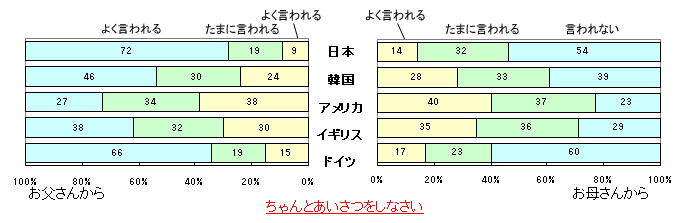
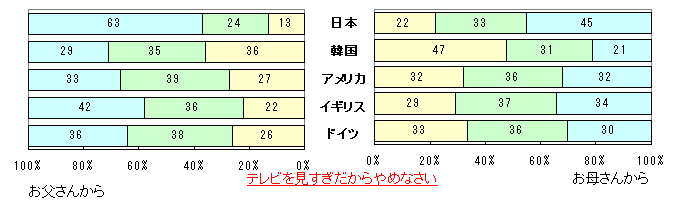
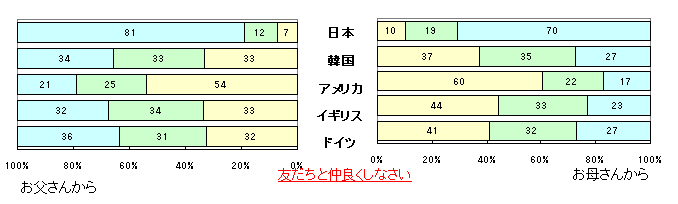
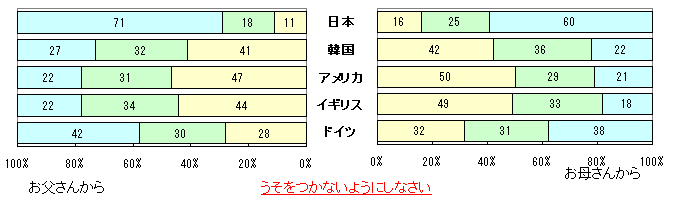 |
|
子どもの体験活動研究会
『子どもの体験活動等に関する国際比較調査』 |
|
| |
| 約6割の母親が育児不安を感じ、家族が協力しないと感じる保護者の約2割には相談相手がいない。 |
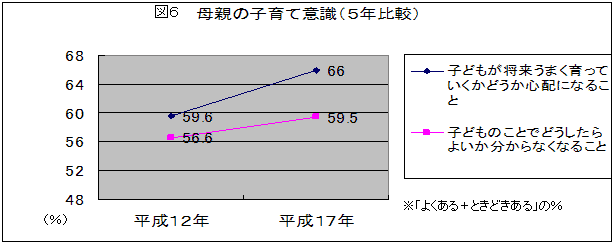 |
ベネッセ教育研究開発センター
『幼児の生活アンケート』(平成17年)
|
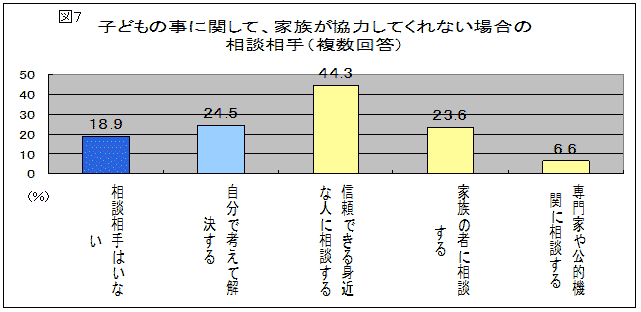 |
厚生労働省
『平成16年度全国家庭児童調査結果の概要』 |
|
| |
| できるだけ子どもの自由を尊重する親でありたいと考える保護者が増えている。 |
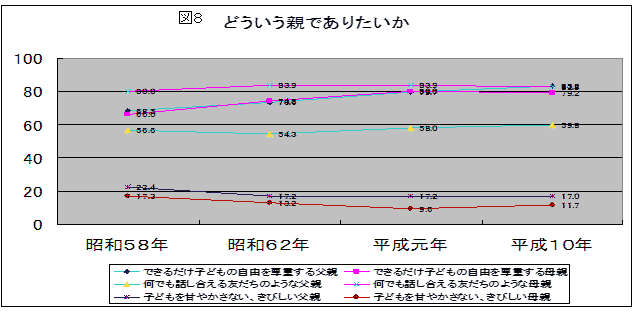 |
NHK放送文化研究所
『中学生・高校生の生活と意識調査』(平成15年) |
|
| |
| 3割の保護者が基本的な食事やマナーの指導を、6割の保護者が社会のルールやマナーの指導を学校に期待している。 |
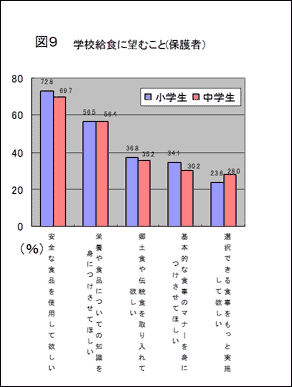 |
|
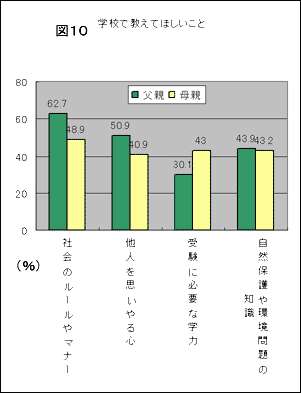 |
日本体育・学校健康センター
『平成12年度児童生徒の食生活等実態調査』 |
NHK放送文化研究所
『中学生・高校生の生活と意識調査』(平成15年) |
|
 |
地域の大人の青少年への関わりの少なさ |
| |
| [調査結果] |
| ○ |
調査結果によると、地域の教育力が低下したと感じている大人が多く(図11)、また、地域の大人から叱られたり助けられたりしたという実感を持つ青少年が少なくなっている(図12)。
|
| [これまでに得られた知見] |
| ○ |
近所の人にほめられたり叱られたりした経験がある小・中学生は、生活体験・お手伝い・自然体験等の多様な経験のある者が多く、また、生活習慣や道徳観・正義感が身に付いている者の割合が高いという調査結果がある(図13)。また、地域の大人の働きかけ等が、地域の青少年の非行を抑止すると推察している研究結果もある。このように、地域の大人が青少年へ関わることには、重要な教育的意義を持つことが明らかとなっている。 |
|
| |
| 5割以上の大人が自らの子ども時代に比較して地域の教育力が低下したと感じている。 |
| 図11 |
|
保護者自身の子ども時代と比較した「地域の教育力」 |
|
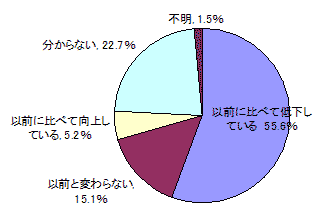 |
日本総合研究所
『地域の教育力に関する実態調査』(平成18年) |
|
| |
| 近所の大人からしかられたり助けられたりした経験のある青少年が少ない。 |
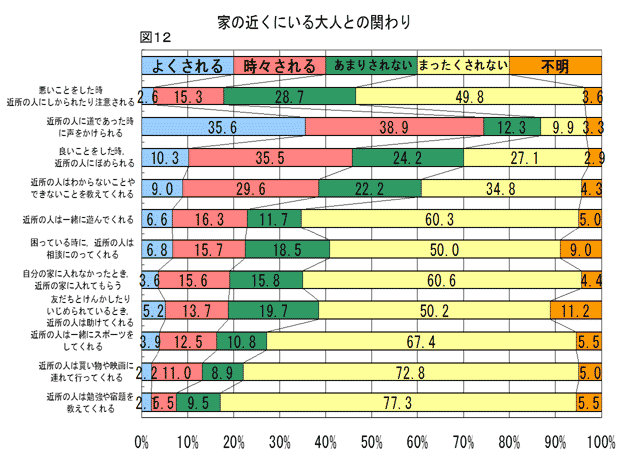 |
|
日本総合研究所
『地域の教育力に関する実態調査』(平成18年) |
|
| |
| 大人からほめられたり叱られたりした経験の多い小中学生には、生活習慣や道徳観・正義感が身についている者が多い。 |
| 図13 |
|
ほめられたりしかられたりした経験と体験活動の関係 |
|
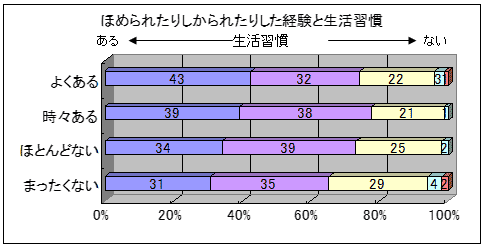
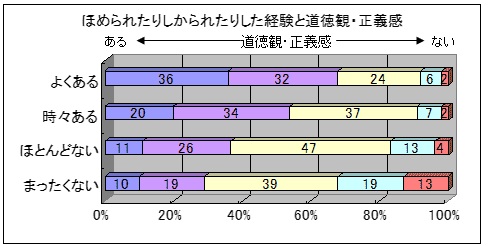 |
|
国立オリンピック記念青少年総合センター
『青少年の自然体験活動に関する実態調査』(平成17年) |
|
 |
仲間と交流する体験の少なさ |
| |
| [調査結果] |
| ○ |
12〜17歳の青少年の自由時間の過ごし方をみると、「テレビ」「漫画」「CD等で音楽鑑賞」「テレビゲーム」など、一人遊びが大半を占めている(図14)。また、小・中学生のテレビ視聴時間は他国と比較して長くなっている(図15)。さらに、学校から帰宅後に友達とほとんど遊ばない小・中学生が約3割という調査結果がある(図16)ほか、小学生の青少年団体への加入が以前と比較して減少しており(図17)、青少年同士が関わる活動をする小・中学生の割合が減少していることを示す調査もある(図18)。
このように、青少年が学校外で仲間と過ごす体験が少なく、その時間も短い中で、祖父母と一緒に住む家庭数の減少や兄弟姉妹数の減少といった家庭環境の変化もみられる(図19,20)。
|
| [これまでに得られた知見] |
| ○ |
青少年が仲間とともに課題を達成していく体験を通じて、積極性や主体性を発揮できるようになることが明らかとなっている。また、仲間とのコミュニケーション体験、特に異年齢集団において年上の者が年下の者に頼られたり、年下の者が年上の者に助けられたり守られたりする体験を通じて、青少年が自己を相対化し客観的に見つめる力を培うとともに、自分の存在意義を実感し、集団活動への意欲をさらに高めることも明らかとなっている。 |
|
| |
| 青少年の自由時間の過ごし方は一人遊びが多く、特にテレビ等の視聴時間は諸外国よりも長い。 |
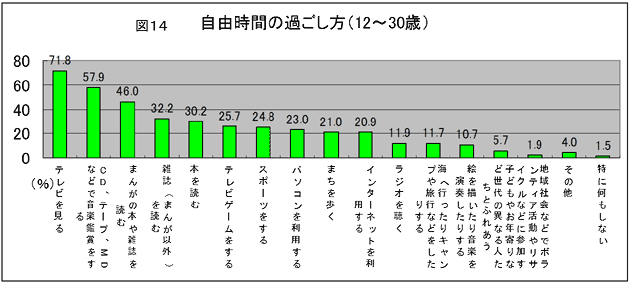 |
内閣府
『情報化社会と青少年』(平成14年)
|
|
|
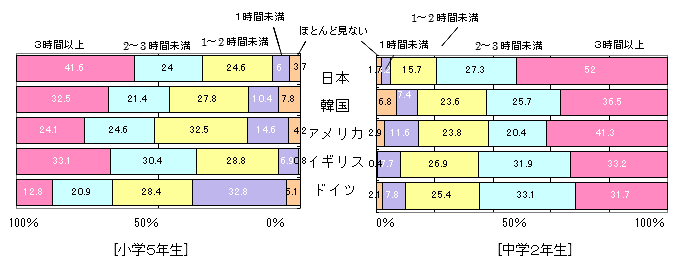 |
子どもの体験活動研究会
『子どもの体験活動等に関する国際比較調査』 |
|
| |
| 小5〜中2の平均3割が学校から帰宅後、ほとんど遊んでいない。 |
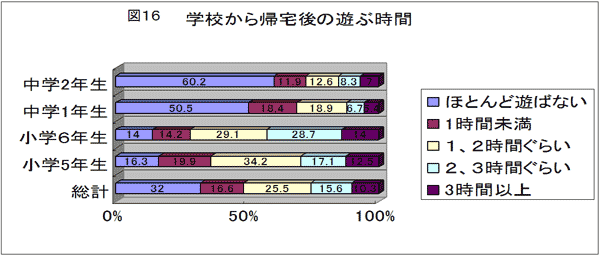 |
川村学園女子大学
『平成16年度子どもたちの体験活動等に関する調査研究のまとめ』 |
|
| |
| 青少年同士が関わる活動をする小・中学生の割合が減少している。 |
| 図17 |
|
図18−1 |
 |
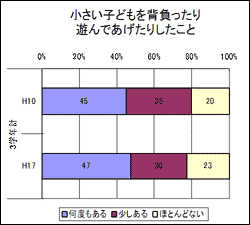 |
| 図18−2 |
図18−3 |
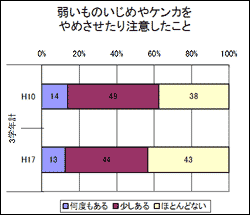 |
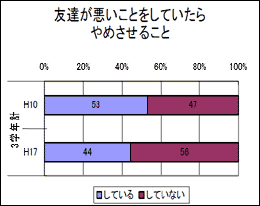 |
| ※ |
3学年計 小4、小6、中2生の合計 小4、小6、中2生の合計 |
|
|
| |
| 祖父母と同居する青少年や兄弟姉妹の多い青少年が減少している。 |
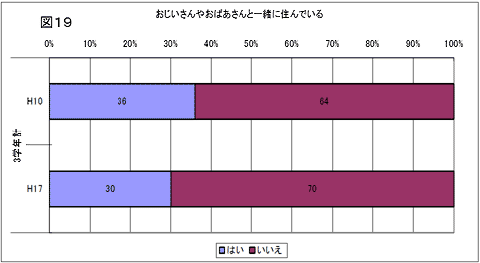
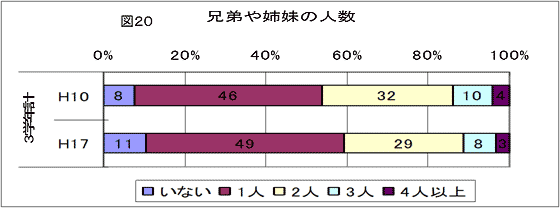 |
| ※ |
3学年計 小4、小6、中2生の合計 小4、小6、中2生の合計 |
|
図17〜20まで いずれも国立オリンピック記念青少年総合センター
『平成17年度青少年の自然体験活動等に関する実態調査』 |
|