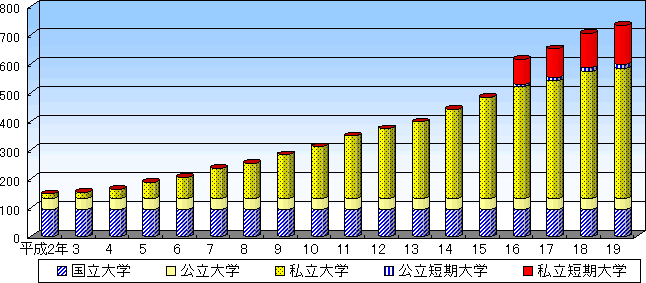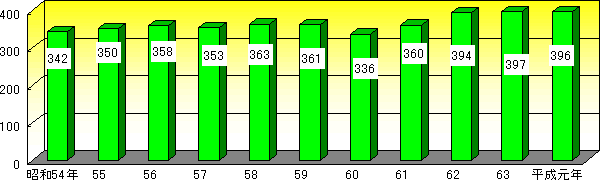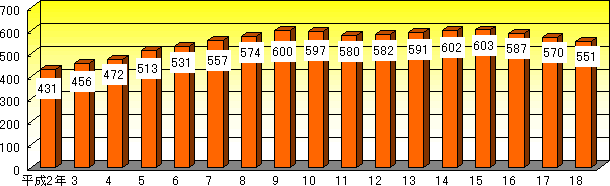| (1) |
目的及び趣旨
|
| |
○ |
大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として実施。
|
| ○ |
各大学が、大学入試センターと協力して、同一の期日に同一の試験問題により共同して実施するもの。
|
| ○ |
各国公私立大学は、大学教育を受けるにふさわしい能力・適性等を多面的に判定するため、大学入試センター試験と独自の試験を組み合わせることにより選抜を実施。
|
| (2) |
共通第1次学力試験との比較
|
| |
共通第1次学力試験
(昭和54年〜平成元年) |
大学入試センター試験
(平成2年〜) |
- 国公立大学のみ利用
- 5教科17科目
- 受験を要する教科・科目は5教科7科目
(昭和62年から、原則5教科5科目)
|
- 国公私立大学で利用
(平成16年度から短期大学も利用可)
- 6教科28科目(平成18年度〜)
- 利用する教科・科目数の利用の仕方は各大学の自由
(アラカルト方式)
|
|
| (3) |
大学におけるセンター試験の利用方法の例
|
| |
【1.センター試験と個別学力検査を課す例】 |
| |
| ○ |
センター試験において、6教科23科目の中から6教科7科目を選択解答させる。 |
| ○ |
個別試験において、3教科の学力検査を課す。 |
| ○ |
センター試験、個別の学力検査、調査書を総合して判定。 |
|
| 【2.センター試験と個別試験(小論文、面接)を課す例】 |
| |
| ○ |
センター試験において、4教科15科目の中から4教科6科目を選択解答させる。 |
| ○ |
個別試験において、小論文と面接を課す。 |
| ○ |
センター試験、小論文、面接、調査書を総合して判定。 |
|
| 【3.センター試験を資格試験的に用いる例】 |
| |
| ○ |
センター試験において、6教科20科目の中から6教科7科目を選択解答させる。 |
| ○ |
6教科7科目の900点中540点以上の者のうちから、募集人員の10倍までの者を総得点の順位に従って、第一段階選抜合格者とし、小論文課す。 |
| ○ |
小論文と調査書を総合して判定。 |
|
| 【4.センター試験の成績を複数年度利用する例】 |
| |
| ○ |
大学が指定する全教科・科目について、直近の年度又は前年度のいずれを利用するかを個別学力検査の出願時に届出。(ただし、科目毎に年度を替えることは不可。) |
|
| (4) |
センター試験の意義
|
| |
 |
個別試験との適切な組み合わせによる入試の個性化、多様化が進展
|
 |
国公立大学だけでなく私立大学を含めた入試の改革 |
| |
国公立大学の利用に加え、利用私立大学は年々増加
平成16年度からは短期大学も利用が可能
|
 |
難問・奇問の減少 |
| |
センター試験の出題内容等が、各大学の個別試験の出題にも好影響し、難問・奇問が減少
|
 |
身体に障害を有する受験者への配慮で先導的な役割 |
| |
点字や拡大文字等による出題や、介助者の配置、代筆解答の導入等を率先して実施
|
 |
新教育課程の実施に伴う高校教育の多様化を支援 |
| |
平成9年度からの出題教科・科目を5教科18科目から6教科31科目に増加させ、高等学校教育の多様化を大学入試の面から支援。また、平成14年度から外国語の選択科目に韓国語を導入(6教科32科目)。
さらに平成18年度から、新教育課程に対応し、6教科28科目に変更。
|
| (5) |
センター試験利用大学(平成19年度)
|
| |
| 国立大学 |
|
83大学(全大学) |
| 公立大学 |
74大学(全大学) |
| 私立大学 |
451大学(私立大学の約83パーセントが利用) |
| 計 |
594大学
|
| 公立短期大学 |
15短期大学(公立短大の約52パーセントが利用) |
| 私立短期大学 |
135短期大学(私立短大の約35パーセントが利用) |
| 計 |
150短期大学
|
| 受験者数(平成18年度試験) |
| |
506,459人 |
|
| (6) |
国公立大学の入学試験科目数(平成19年度)
|
| |
|
| 大学入試センター試験 |
| |
大学 |
学部 |
| 6教科を課す |
75
 47.8) 47.8) |
180
 32.8) 32.8) |
| 5教科を課す |
126
 80.3) 80.3) |
387
 70.5) 70.5) |
| 4教科を課す |
69
 43.9) 43.9) |
92
 16.8) 16.8) |
| 3教科を課す |
90
 57.3) 57.3) |
153
 27.9) 27.9) |
| 2教科を課す |
19
 12.1) 12.1) |
24
 4.4) 4.4) |
| 1教科を課す |
7
 4.5) 4.5) |
7
 1.3) 1.3) |
| 課さない |
2
 1.3) 1.3) |
2
 0.4) 0.4) |
|
| (注): |
 書きは、全利用大学・学部数に対する割合(パーセント)を示す。 書きは、全利用大学・学部数に対する割合(パーセント)を示す。 |
|
| (7) |
志願者数・利用大学数の推移
|
| |
1 |
共通第1次学力試験及び大学入試センター試験の志願者実績(千人)
|
| |
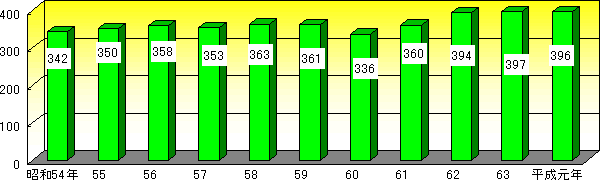 |
共通第1次学力試験
|
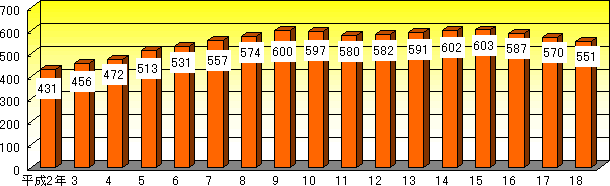 |
| 大学入試センター試験 |
|
| 2 |
大学入試センター試験利用大学・短期大学数
|
| |
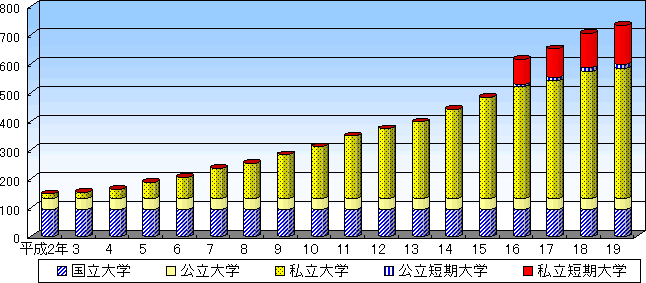
|
| 3 |
平成19年度センター試験日程 |
| |
| 期日 |
試験教科・科目 |
試験時間 |
【本試験】
第1日
平成19年1月20日(土曜日) |
公民 |
「現代社会」,「倫理」,「政治・経済」 |
9時30分〜10時30分 |
| 地理歴史 |
「世界史A」,「世界史B」,「日本史A」,「日本史B」,「地理A」,「地理B」 |
11時15分〜12時15分 |
| 国語 |
 国語 国語 |
13時30分〜14時50分 |
| 外国語 |
 英語 英語 , , ドイツ語 ドイツ語 , , フランス語 フランス語 , , 中国語 中国語 , , 韓国語 韓国語 |
【筆記】15時35分〜16時55分
【リスニング( 英語 英語 のみ)】17時35分〜18時35分 のみ)】17時35分〜18時35分 |
第2日
1月21日(日曜日) |
理科 |
「理科総合B」,「生物 」 」 |
9時30分〜10時30分 |
数学 |
「数学 」, 」, 数学 数学 ・数学A ・数学A |
11時15分〜12時15分 |
数学 |
「数学 」, 」, 数学 数学 ・数学B ・数学B ,「工業数理基礎」, ,「工業数理基礎」, 簿記・会計 簿記・会計 , , 情報関係基礎 情報関係基礎 |
13時30分〜14時30分 |
理科 |
「理科総合A」,「化学 」 」 |
15時15分〜16時15分 |
理科 |
「物理 」,「地学 」,「地学 」 」 |
17時〜18時 |
| ※1. |
  は,2つの科目を総合したもの又は2つ以上の科目に共通する内容を盛り込んだ出題 は,2つの科目を総合したもの又は2つ以上の科目に共通する内容を盛り込んだ出題 |
| ※2. |
リスニングテストの解答時間は30分であるが,解答開始30分前からICプレーヤーの作動確認・音量調節等を受験者本人が行うため,試験時間は60分となる。 |
|
| (8) |
近年における大学入試センター試験の改善
|
| |
大学入試センター試験に関しては,大学審議会答申等を踏まえ,以下の改善に取り組んでいるところ。 |
| 大学審議会答申「大学入試の改善について」(平成12年11月22日) |
| |
【提言事項】 |
| |
○ |
大学入試センター試験の成績の資格試験的な利用 |
| ○ |
教科・科目横断型の総合的な問題や総合的な試験の推進 |
| ○ |
リスニングテストの導入 |
| ○ |
年度内の複数回実施 |
| ○ |
成績の複数年度利用 |
| ○ |
成績の本人開示 |
| ○ |
新学習指導要領への対応 |
|
|
|
| |
| ○ |
韓国語の導入 |
| |
平成12年3月の中曽根文相の訪韓の際,韓国の教育部長官から,大学入試センター試験における韓国語の導入の要望があり,これを受け,同年9月23日に日韓首脳会談において,森総理大臣より導入する旨を表明し,平成14年度試験(2002年1月)から実施
|
| ○ |
成績の複数年度利用 |
| |
各大学の判断により,前年度の大学入試センター試験の成績を当該年度の入学者選抜に利用することが可能
|
| ○ |
成績の本人開示 |
| |
入学者選抜終了後(おおむね4〜5月頃)に希望者に対して大学入試センター試験の成績を開示 |
|
|
| |
| ○ |
短期大学の参加 |
| |
新たなに短期大学も,大学入試センター試験を利用することが可能
|
| ○ |
教科「理科」のコマ数を2コマから3コマに変更 |
| |
従来は,「物理」と「生物」が同一のコマとなっていたため,受験生が両科目を同時に選択することができないという問題を解消するための措置 |
|
|
| |
| ○ |
新学習指導要領への対応【リスニングテストの導入を含む】 |
| |
| ・ |
平成15年度から高等学校で実施されている学習指導要領に対応して,平成18年度からの大学入試センター試験の出題教科・科目を変更(6教科32科目から6教科28科目) |
| ・ |
「外国語」教科の「英語」科目にリスニングテストを導入 |
|
|