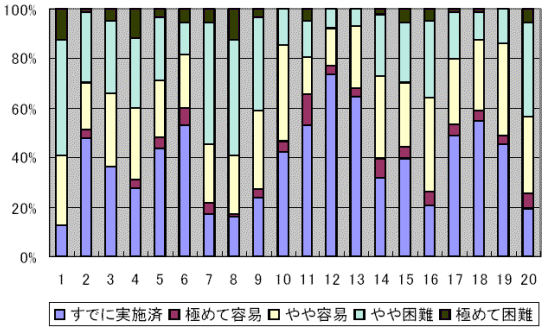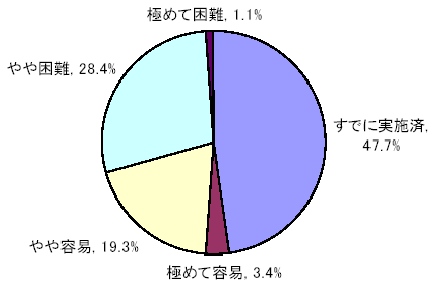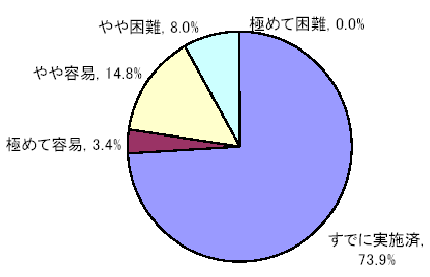| 1) |
理念・目標を実現するための全教員の意識改革 |
| |
意識改革は実現されたとする回答比率(12.5パーセント)が前回調査の比率(16.4パーセント)より低く、今回の20項目の中で最低を示したのは意外な事実ではあるまいか。意識改革への動きは徐々に前向きになっているものの、このような依然として停滞する数字を読む限り、その背景には意識改革を阻む条件が厳然と横たわっている事実があると言わなければならず、一方ではそのような条件を排除することが重要な課題になるとともに、他方では教養教育を推進するためには全体には依然として意識改革が重要な課題であるとみなされる。
|
| 2) |
教養教育の全学的な実施・運営体制の整備 |
| |
この項目への肯定的な回答が、前回と比較して10ポイントも減少している事実は、衝撃的であると言えるかもしれない。そこには、意識改革が停滞しているのに加え、実施・運営の体制そのものの整備の困難性が意識されている現状のあることを見逃せないであろう。改革の意識と体制とは相即の関係にあると推察すれば、意識の推進と体制の推進という双方の前向きな推進なくしては、現状の打開はおぼつかないと容易に考えられる。
|
| 3) |
教養教育と専門教育の有機的連携の確保 |
| |
両者の有機的連携の確保は、前回より若干増加傾向にあることが判明した。しかし伸び悩みに注意すべきであろう。このことは、上記したように、教養教育と専門教育との連携がある程度展開した事実を示唆するが、同時に教養教育の独自性が徐々に失われている実態を裏書きすることを示唆するとも読めるであろう。
「知の再構築」やカリキュラムの再編成が実現されて、学際的かつ学融的な視点からの教養教育と専門教育の有機的な連携が実現するには、カリキュラム編成や教員の意識等の質的な側面との関係が重要な鍵を握っているのであるから、量的な側面の進展のみでは解決できない。その点、すでに考察したことを踏まえ、教養教育が前進よりもむしろ後退している現状を総合的に勘案すると、両者の質的な統合や融合は未だに程遠く、全体的には進捗状態が芳しくない実態に留まっている。
|
| 4) |
ボランティア活動等関連の授業科目開設 |
| |
具体的に様々な科目の開設状態を検討してみると、多くの科目を開設し、相当の効果を上げていると回答した大学は少なくないことが分かる。ボランティア活動関連の授業科目開設は、まだ少ないにもかかわらず、前回と比較すると前進している。
|
| 5) |
インターンシップ等関連の授業科目開設 |
| |
実施率(43.7パーセント)はボランティア科目開設に比べ高く、比較的順調である。
|
| 6) |
キャリア教育等関連の授業科目開設 |
| |
半数以上(52.9パーセント)が実施しているように、1999年の中教審答申で提案された以降に急速に導入が進展したとみなされる。
一般的に、フリーターやニートが増加現象を辿る現実がある以上、それを阻止する方策は、人生全体を視界にいれたキャリア教育の充実に求める必要があるであろう。その意味では、日本におけるキャリア教育の従来の発展状態は必ずしも十分であったとは言えず、現在も今後の展開が期待される段階に留まっているとうほかない。その経緯や現状を考慮すると、曲がりなりにも、大学での取組みが進展しつつある事実は注目されてしかるべきであろう。
|
| 7) |
国際舞台で活躍できる能力の育成 |
| |
この項目への回答を見ると、実施済み(17.0パーセント)がかなり低調であり、実施困難の割合も高い。前回と比較しても改善が見られないことから、今後、どのような対応をするかが問われる状態にある。グローバル化の進展は、大学教育への挑戦であり、従来のカリキュラムや指導体制では、国際舞台で活躍できる能力を育成するには無理があるに違いない。上述した教養教育のカリキュラムの開発や充実と密接に関係している事実を考慮すると、骨太の改革を必要としており、小手先の改革では通用しないであろう。その意味から、この項目は今後の取組みが期待される段階に留まっていると言わなければならないだろう。
|
| 8) |
単位制度の実質化(授業外学習時間の確保) |
| |
20項目中、意識改革に次いで低く、実施困難とする割合(59.1パーセント)も、同様に低い。前回と比較すると、実施率は多少上がっているが、単位制度の実質化が容易だとする割合は下がっている。単位制度の実質化は思ったよりも困難であることが次第に認識されてきていると読める傾向であろう。想えば、単位制度の形骸化は戦後、アメリカのシステムを導入したとき以来進行して現在に至った事実である。
この事実こそ、単位制度が日本的風土や土壌の中で骨抜きにされ、定着しなかった何よりの証拠であるとみなしてさしつかえあるまい。これを本来の単位制度に復元し、予習時間、授業時間、復習時間があいまって所定の単位が授与される仕組みを回復しない限り、教育の量的側面は達成されても、肝心の質的側面はなんら達成されたことにはなるまい。単位制の充実は、教育の質的保証の重要な柱である以上、きわめて立遅れた現状の迅速な改革が課題である。
|
| 9) |
厳格な成績評価の実施 |
| |
前回より改善されているとはいえ、問題がないのではない。なぜなら、内容の吟味が不可欠な状態にあると言えるからである。厳格な成績評価は、厳格な単位制度の運用、それと関連したGPA制度や履修科目登録の上限設定 CAP制度の運用、等と密接に連関した教育過程の一環を形成している以上、他の運用が適切でこの運用のみが不適切という現象が生じることはあまり現実的であるとは言えないだろう。その点、他の運用と同様、多少の改善が見られるとしても、その内容は十分検討されるべき段階に留まっている。そこには、前回より改善されたとはいえ、依然として厳密な成績評価が十分行なわれているとは言えない現実が横たわっているのであり、それは日本の大学教育の質的保証が未だ不十分な状態に低迷していることを物語る証拠の一端を示しているというほかあるまい。 CAP制度の運用、等と密接に連関した教育過程の一環を形成している以上、他の運用が適切でこの運用のみが不適切という現象が生じることはあまり現実的であるとは言えないだろう。その点、他の運用と同様、多少の改善が見られるとしても、その内容は十分検討されるべき段階に留まっている。そこには、前回より改善されたとはいえ、依然として厳密な成績評価が十分行なわれているとは言えない現実が横たわっているのであり、それは日本の大学教育の質的保証が未だ不十分な状態に低迷していることを物語る証拠の一端を示しているというほかあるまい。
厳格な成績評価は、教育過程の仕上げの部分であることにかんがみ、教育目的・目標の設定、カリキュラムの編成、GPA制度、CAP制度、履修指導、教育指導のあり方、といった一連の過程を通して実現する、教育効果の総決算である。他の側面が自信を持って遂行できる段階に到達することと、厳密な成績評価が遂行されることとは、連関性が高いはずであり、その意味でこうした連関性が達成されていない現状では、教育改革は未だ半ばに過ぎないのではあるまいか。
|
| 10) |
履修指導の充実 |
| |
この項目への回答を見ると、前回より前進しているが、成果の検証が不可欠な段階にある。
|
| 11) |
履修科目登録の上限設定 |
| |
既に半数以上が実施しており、前回より前進している。上記の単位制度の実質化が不十分な状態にあることと連動して考える必要があり、履修科目登録の上限設定 CAP制の改善が量的に増加を見たからといって過大評価するのではなく、単位制度の改善によって学生の学力向上に奏功したか否か、教育効果の内容面の検討が課題である。 CAP制の改善が量的に増加を見たからといって過大評価するのではなく、単位制度の改善によって学生の学力向上に奏功したか否か、教育効果の内容面の検討が課題である。
|
| 12) |
FD(ファカルティ・ディベロップメント)の実施 |
| |
前回の実施率が低く困難度が高かったのと比較すると、今回は隔世の感がするほど大きな進展を示した。その点では、FDが大学制度や組織に定着する制度化の動きは長足の進歩を遂げたと観察できるに違いない。その背景には、1998年の大学審答申によってFDが努力義務とされ、最近では機関別認証評価において義務化されている動きがあるなど、強制力が作用していることとの連関性があるのではなかろうか。
しかし、現状は十分な段階へ到達しているとは読めない。他のFDに関する研究でも実証されているように、実際に内容を吟味すると、FDの制度化は量的に進展を示した第1段階から、質的内容が吟味される第2段階へ移行する過渡期にあると把握できるのではあるまいか。少なくとも、教員の研究志向が教育志向よりも依然として強固であること、カリキュラム編成、履修指導、教育指導、厳格な成績評価、といった一連の改革が不十分との印象を与えること、等を勘案すると、FDが第2段階への入り口にあっても、いまだに初歩的段階を卒業するまでに到達してないと観察することは難しくないだろう。
他の研究では、FDの制度化は直線的に進展するのではなく、一見成功した後に挫折や失敗に直面する傾向が見られ、螺旋的に進展することが明らかになっている。そこには量的発展では一見成功を収めていると見えても、それは見せかけの現象であって、質的には問題を孕む事実が存在するのである。その意味で量的進展が見られる事実は評価できるとしても、それのみをもって無闇に評価できないだろう。
|
| 13) |
シラバス活用 |
| |
この項目は、FDの実施率に次いで比率が高いものの、前回と比較すると、実施率は変わらないのに、困難度はやや増えている点が注目に値する。問題は、シラバス活用の本来の意味が実現しているか否かにある。学習者の学習を支援し、学習効果が実際に上昇しなければ無意味である。量的普及ではなく、果たして学生の学習効果に貢献しているか否かを問う、成果の検証が問われる段階に入っている現在、教員は行く手に立ちはだかる困難性を改めて意識しているのではあるまいか。
|
| 14) |
マルチメディアの効果的な活用 |
| |
実施率はあまり高くないという事実は前回調査と変わっていない。なぜ進展を見ないかを検討して、改善を図ることが今日の課題となっている。IT革命によって、教授技術の改革が日程にのぼって久しいが、伝統的な教授方法と新たな技術革新の間には相当の距離が存在しているから、理工系の教員の場合はともかく、文系教員の場合には前者に代わって後者のマルチマディアを自由自在に活用するまでに至るには、意識変化が欠かせないし、相当な訓練や研修が欠かせないだろう。したがって、数字上である程度の進展があっても、内容の上でマルチメディアを専門的に活用し十分な教育効果をあげるまでには、時間を要するのは当然の成り行きであるに相違ない。今回の調査結果には、意識的にも行動的にも教員が躊躇する実態が透けて見えるのではあるまいか。
|
| 15) |
教育活動の評価の実施 |
| |
前回に比較して、教育活動の評価実施は確かに前進している。それにもかかわらず、一見して前進して定着しているように見えながらも、その結果、実際に教育成果が上がっているのか否か、教養教育の質的保証が実現しているのか否か、具体的な評価内容までは立ち入った検討をしていないので、内容的な詮索はできない。上記の考察からも窺えるように、量的に改革が進展しているとの回答は種々の項目において見られるものの、実質的な成果に関しては必ずしも十分であるとは言えない実情にあることが分かった。その点、内容に関わる検討を深めるとともに、それに即した改革が不可欠である。
|
| 16) |
優れた教育活動を行っている教員の顕彰 |
| |
教員の研究業績に対する顕彰は、国内外の学界において頻繁に行なわれる傾向がある半面、教育業績に対する顕彰は等閑に付されてきたことを勘案すると、今回の調査結果において量的な増加が見られることは、教育改革の進展を示す一つの確たる証拠と解されるはずである。とはいえ、顕彰の数が教育効果の業績と直結しているか否かはなお検証する必要があり、量的な増加が生じていることのみでは、不十分である。教育の成果や質的保証との関係の検討が課題であろう。
|
| 17) |
単位互換制度等の拡大 |
| |
この項目への肯定的な回答は、前回より大幅に増加している事実がある。その中で、地方の中規模校は困難度が高いのは、置かれる地理的条件やある程度の独立志向があることが作用していると解される。
ここで、単位制度の不備に関しては上で検討した通りであるから、そのことを想起すると、互換制度は単位制度を前提として成り立つ制度であることに言及せざるを得ない。互換制度は、等質な単位制度の充実を踏まえて展開される度合いが少なくないから、そもそも単位の質保証に格差がある場合は、十分な進展を期待できないであろう。各大学の単位制度が厳格さを増し、大学間の単位制度遂行への等質化が実現することによって各大学間の単位に対する信用が増加するのであり、そのような段階に至るには、まず厳格な成績評価など単位制度の根幹をなす整備が欠かせない。
|
| 18) |
学長のリーダーシップを確立する組織運営体制の整備 |
| |
この項目への肯定的回答が、前回より大きく進展したことは、大学改革が学長のリーダーシップを期待する方向へ進行している事実と関係が深いはずである。国立大学法人が出現した現在、従来の地位は高いが権限が付与されていない学長職から、地位も権限も付与され、権威が大幅に増した学長職とでは大きな落差があるに違いない。教授会が権限をもつボトムアップ型の管理運営方式から学長が権限をもつトップダウン型の管理運営方式が出現した現在、学長のリーダーシップは当然強化される方向へと踏み出したとみなされる。本調査結果においても、それを支持し、推進するための組織体制は大幅に整備されたことが分かる。
大幅な整備がなされた中で、果たして具体的成果があがっているのか否かは質問してないので不明であるが、今後は、大学毎にその成果の有無がきびしく問われる段階に突入し、中期目標・計画の成否、運営費交付金の成否、社会的評判の成否、等の要因と連動しながら、リーダーシップの成果の有無によって大学の盛衰の差異が具現する方向に向かうに違いないと予想される。
|
| 19) |
自己点検・評価の充実 |
| |
前回よりも進展している。2004年度から導入された機関別認証評価制度の前提に自己点検評価が当然だとされる時代に移行している現在では、前回より肯定的回答に進展が見られるのは当然の結果であると観察される。機関別認証評価等が義務化された国立大学法人では、その成果をいかに教育研究の質的充実や保証に連携させるかが問われる段階に入っている。あらゆる外部評価や第三者評価の実施には、自己点検・評価の実施が不可欠の前提になっている以上、一層の充実が課題とならざるを得ない。
|
| 20) |
認証評価機関以外の第三者評価システムの導入 |
| |
前回では、第三者評価システムを導入した国立大学は未だかなり低率(9.1パーセント)であったし、困難とする割合(47.3パーセント)もなお高かった。今回は、さらに機関別認証評価以外の第三者評価の導入を尋ねたが、実施率(19.5パーセント)、困難度(43.7パーセント)ともに、進展がはかばかしくない実態がみられる。その原因は何であろうか。法的に義務化が位置づけられた機関別認証評価への対応だけでも相当の負担となっている中で、その他の第三者評価システムの導入が伸び悩むのはある意味で想定できる結果であろう。最近、大学内部での「評価疲れ」が進行し始めている事実が観察されているが、この伸び悩みの数字はまさしくそうした「評価疲れ」の実情を直截に反映しているのではあるまいか。
今回の調査結果がこのような推論を喚起する側面がある限り、外部評価や第三者評価が義務化し、その前提に膨大な作業や労力を必要とする自己点検・評価が不可欠になっている現在は、大学教員・職員の「評価疲れ」を誘発することなく、しかもなおかつ教育・研究の効果を一層高めることの可能な、第三者評価の形態の開発が問われる時代を迎えつつあると考察できるのではあるまいか。 |