参考資料2 教育実習の実施例
| |
教育養成系大学・学部 |
一般大学・学部 |
| 上越教育大学 |
信州大学(一般学部) |
| 概略 |
→ 1年次に僻地小規模校、特殊教育諸学校での観察、参加。2年次に幼稚園での観察・参加を位置づけ、発達段階、学校規模、障害の有無による教育の差異について理解させ、教職を目指す上での課題と自覚を高める。 |
|
|
→ 直接的な指導実習を通して、児童理解を深め、児童の実態や心情を理解し授業に関する実践的能力を高め、学級経営、特別活動に参加する中で、教師の職務と責任を理解させ、教職を目指そうとする意欲と堅実な態度を育てる。 |
|
→ 中学校・高等学校教員免許状の取得希望者に対して、初等教育実習の経験の上に、中・高等学校における生徒の発達特性の理解の上に、学習内容の系統性、発達段階を考慮した学習指導法について理解を深め、学級経営及び特別活動の実践力を高め、中学校・高等学校教員としての資質・能力の育成を図る。
|
→ 教科、教職専門科目の学びを通して取得した 理論・知識・技能を教育現場での実地体験で確認するとともに、実際に生徒に接し教育指導に あたることによって、教師としての適性を把握 し、現場での教育の在り方、方法等を学ぶ。 |
| 教育実習の受講要件 |
- 「教育実地研究3(初等教育実習)」の履修に当たっては、以下の事項を満たしていること。
- 卒業要件単位のうち、60単位(「教育実地研究1(観察・参加)」を含む。)以上について、前年度までに修得していること。
- 「教育実地研究2(授業基礎研究)」について、前年度から引き続き履修又は単位を修得していること。
- 「教育実地研究3(初等教育実習)」を履修しようとする年度において、「初等の各教科 指導法」について、履修又は単位を修得していること。
|
- 学部により異なるが、教職に関する科目の殆どを修得済であるか、一部を履修中であること。
|
| 大学の教員と指導教員による連携 |
- 教育実習指導教官が定期的に実習校を訪問し、指導教員との連絡調整を行う。また、卒業論文指導教官も受け持ちの学生の研究授業等に合わせ、実習先を訪問する。
|
- 近隣の実習校については、教育実習担当の教官が訪問する。
|
| 事前・事後指導 |
→ 2年次は基礎的授業技術、3年次は学習指導案の作成の仕方を中心に、教育実習に必要な理論、技術、方法の習得、態度の育成について学ぶ。
- 実習の成果のまとめ、反省及び授業の問題点等について実施。講義4時間。
|
→ 教育実習の意義と課題、教育実習の準備と心得、学習指導の実際、教師の意味と役割などの内容を行う。
- 教育実習の報告及び反省について1日程度(2コマ)実施(翌年度実習を予定している3年次生も出席)。
|
| 教育実習の受入校 |
|
|
| 単位認定評価基準 |
- 実習校からの評価表を基に、成績一覧表を作成し、全実習校による実習評価の会議に諮る。その上で、学内の教育実習委員会で審議を行い、評価を決定。
|
- 実習校からの評価表を基に、各学部の実習担当委員(教務委員会、学務委員会等)が総合的に判定。
|
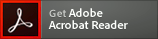
PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。