- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 初等中等教育分科会 > 教員養成部会 専門職大学院ワーキンググループ > 教員養成部会 専門職大学院ワーキンググループ(第2回) 配付資料 > 参考資料 フィンランドの教員養成・教員資格について
参考資料 フィンランドの教員養成・教員資格について
(出典:OECD教員政策事業フィンランド国別報告書(2003)による-仮訳)
1.概況
教員数
(義務教育・後期中等教育):約66000人<2002年現在>
懸案問題
- 2000~2010年までに、20000人以上の教員が退職予定。
(⇒教員養成・研修の規模を拡大することが、今後数年間の政策課題) - 90年代以降学校現場に権限移譲がなされているが、学校内の組織化があまりなされておらず、運営責任を教員で共有する習慣が根付いていない。マネージメント文化の醸成と、リーダーシップの分譲と責任分担の明確化、教員全員が学校運営に参画する意識化が今後の課題。
教員の社会的地位
- 伝統的に高い。そのため数学・特定の自然科学分野を除いては、教員不足の問題はない。
- しかしながら、教員を巡る近年の問題、例えば、生徒指導の問題、薬物濫用・アルコール問題、不登校問題等の増加により、教職は厳しい職業との認識が高まっていることを受けて、最近では、若者の間で職業としての人気が下がっており、教員養成に優秀な志願者を十分に惹きつけるための方策を必要と言われている。また、最近10年間で、教員養成課程への男性志願者の占める比率が減少傾向にある。
- 2002年に教職員組合が「フィンランドは教員を求めている」と題し、教職の重要性、社会に果たす役割に関する認識を喚起すべくプロジェクトを展開している。
教員養成大学数
- 初等・中等教育教員養成:11大学
- 専門教育教員養成:5専門教育教員養成カレッジ(ポリテクニークと連携実施)
(⇒ 教員の大量退職や教員養成の重要性に鑑み、2001~2003年期に11大学に増加。クラス担当教員養成、特殊教育教員養成、語学、数学及び自然科学教科担任教員養成について特に養成規模を拡大。2004~2006年期には、上記に加え、教科指導法に関する履修機会の拡大とともに、教育相談担当カウンセラー、体育教員の養成規模についても増加予定。)
教員養成大学入学資格
- 後期中等教育卒業者であれば誰でも入学受験可。
- 専門教育教員養成課程入学については、後期中等教育卒業者で職業資格及び職業経験を有している者。
教員養成を取り巻く現状
- 80年代以降、特に90年代に学校に教育に関する決定権を移譲する教育改革を推進している。その趣旨は、学校を取り巻く地域社会のニーズに学校が速やかに対応できるように、決定権を出来るだけ学校現場に移譲するというもの。
⇒ これにより、全国カリキュラムガイドライン(教育目標、各教科の総授業時間(前期6年間、後期3年間でまるまるという定め方))は教育省が策定し、具体的な週当たりの各授業時間等は自治体又は学校が、勤務校の教育課程の編成及び教科書の選定の決定権は教員が持つことなった。
現職研修
- 教員として就職後は、教員は年間最低3日間は学校外にて研修を受ける義務がある(研修受講費用は無料。研修費用は主に地方教育委員会が負担。研修内容及び実施方法は、雇用者たる地方教育委員会が定める)。
教員採用
- 各地方教育委員会毎に行われ、新聞等によって、当該地域のみならず、全国規模で公募される。
2.教員養成課程について
今後の課題
- 2000~2010年までに、20000人以上の教員が退職予定。
(⇒ 教員養成・研修の規模を拡大することが、今後数年間の政策課題)
教育養成課程
- 教育及び教員養成を目的とする学部の他に、一般学部においても行われている。
- 教員養成を行っている大学は11大学。
1.教職関連課目
- 大学が運営する教員訓練学校又は附属学校(teacher training school)において履修。主に教科指導法等に力点が置かれている。学位課程履修時又は、学位課程履修後に履修も可能。おおよそ1~1.5年の課程。
2.修士課程履修内容
クラス担任(全教科担任)教員:5年課程(160単位:1単位40時間計算)
- 言語及びコミュニケーション関係科目
- 主要教科関連科目
- 1~2の他教科関連科目
- 教育学関連科目
- 義務教育で教える教科に関する指導法等科目
- その他自由選択
<教職課程履修者が留意すべき点とされている事項>
- 人間の成長全般に関する理解の増進
- 教師と学生との双方向のやり取りに勤めること
- 教育に関する科学的理論の修得と実際の教育活動への適用
教科担当教員:5~6年の課程(160単位又は180単位の課程)
- 教科担当教員養成のための主な授業科目内容は、主専攻とする教科の教科知識に関するもの。
- 主専攻の教科については35単位以上履修すること(後期中等教育担当教員については、主専攻の教科については55単位、副専攻の教科については35単位を履修)。
- その他、教職関連科目を35単位以上履修すること。
外部評価
- 教員養成課程の質については、教員養成大学に、機関及び分野別の外部評価か、教員養成に特化した評価を受けることが義務付けられている。高等教育評価協議会(Higher Education Evaluation Council)に委ねられており、直近では、全ての教員養成大学及び専門教育教員養成課程は、各々、1999年、2000年に評価を受けている。
- 評価結果は、主に、教員養成課程の改善勧告を行う際の基礎として活用され、改善実施状況は追跡調査される。
(例:2001年教育省は、評価結果に基づき改善勧告を行っており、その後の改善状況は、各大学の年次評価を通じて行っており、次回の国レベルの評価は2005年を予定している。)
3.教員資格
教員資格については法令で規定されている(最新改正2002年)。
1.校長の資格要件
- 修士号以上を有すること。
- 法令に規定している該当教育に関する教員資格を有すること。
- 十分な教職経験を有すること。
- 全国教育委員会(National Board of Education)による教育管理職のための認定資格を有すこと、あるいは、大学において教育管理・運営に関する授業を15単位以上履修すること、もしくは教育管理・運営に関する十分な知識を有すること。
- 完璧に言語(主にフィン語)を読み書きできること。大学、その他高等教育機関における証明書にて保証するか、別途試験結果にて保証すること。
2.教員の資格要件
クラス担当教員(義務教育1~6年(初等教育レベル)、就学前指導)
- 教育又は教員教育に関する修士号を有すること。
(総合学校(初等教育レベル)で教える必要がある各教科及び総合科目に関して履修) - 修士号取得以外に、教職関連科目を35単位以上履修すること。
- 言語(主にフィン語)を適切に読み書きできること。必要とあれば、全国教育委員会(National Board of Education)が、指導言語として適切な運用に当たっての基準を示すこと。
教科担当教員(義務教育7~9年(前期中等教育レベル)及び後期中等教育レベル)
- 修士号以上を有すること。
- 主専攻の教科については35単位以上履修すること(後期中等教育担当教員については、主専攻の教科については55単位、副専攻の教科については35単位を履修)
- 教職関連科目を35単位以上履修すること。
- 言語(主にフィン語)を適切に読み書きできること。必要とあれば、全国教育委員会(National Board of Education)が、指導言語として適切な運用に当たっての基準を示すこと。
教育相談担当カウンセラー
- 関係法令に規定している該当教育に関する教員資格を有すること。
- 学生カウンセリングに関する修士号以上を有すること。
- 言語(主にフィン語)を適切に読み書きできること。必要とあれば、全国教育委員会(National Board of Education)が、指導言語として適切な運用に当たっての基準を示すこと。
幼稚園教育担当教員
- 関係法令に規定している教育内容に相当する学士号を有すること。
- 言語(主にフィン語)を適切に読み書きできること。必要とあれば、全国教育委員会(National Board of Education)が、指導言語として適切な運用に当たっての基準を示すこと。
特殊教育担当教員
- 教育又は教員教育に関する修士号を有し、当該学位課程において特殊教育に関する内容を履修していること。
- 関係法令に規定されている所要資格を有すること、
又は
- 特殊教育に関する修士号以上を有すること。
- 言語(主にフィン語)を適切に読み書きできること。必要とあれば、全国教育委員会(National Board of Education)が、指導言語として適切な運用に当たっての基準を示すこと。
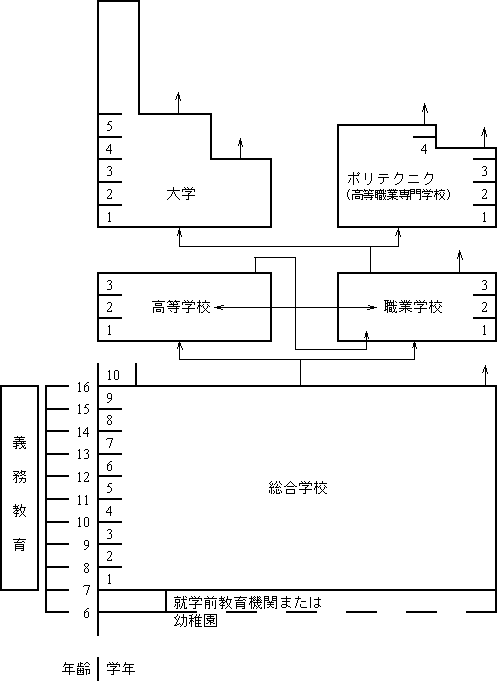
フィンランドの教育システム(フィンランド教育文化省資料より作成)
お問合せ先
高等教育局専門教育課