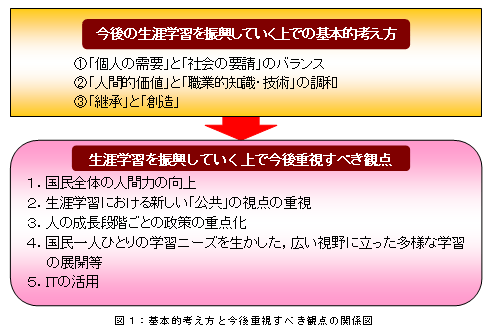
| |
特定の世代の人だけではなく,若者を含むあらゆる層の学習者の多様なニーズ(需要)に対応し,人間的価値の追求と職業的な知識・技術の習得の実現に資するようにすることが必要である。特に,働き盛りの世代,中でも,職業生活,地域生活等の様々な活動と家庭生活との両立等の課題を持つ人々に対応することが重要である。このため,誰でも,いつでも,どこでも学べるように,大学や公民館,図書館等の改善を図ることが必要である。また,国民一人ひとりの学習ニーズを生かした,個々人が利用しやすく,学習意欲が高まるような学習機会の提供等を図っていくことが必要である。 |
| 市町村等において,あらゆる資源の把握と有効活用を図ることが必要である。学習の資源としては,学校,公民館,図書館,博物館,生涯学習推進センター,青少年教育施設,文化施設,スポーツ施設等の教育施設のみならず,児童館等の福祉施設,さらには,商店街や神社・寺院,公園などの地域にある身近なものや,山林,河川などの自然なども活用することができる。 また,地域の様々な学習情報や,高齢者や大学生,保護司,PTA,青少年関係団体,スポーツ指導者などの地域の人材を把握し,積極的に発掘することにより,学習者に提供することが重要である。 |
|
| 学校教育におけるやり直し,学び直しができる体制づくりを図ることが必要である。また,廻り道や試行錯誤が許容される社会づくりを図ることが必要である。日本の社会は,年齢主義による入学・就職システムがいまだ主流となっており,学校教育における学び直しや職業生活の再チャレンジができにくいという面がある。したがって,生涯学習の振興を進めていく上で,高等学校段階を終了した後での入学留保制度の導入,海外留学,ボランティア休学,労働体験,社会体験などの「自分探し」や,進路の試行錯誤をすることが許容される社会づくりと,学歴社会から学習歴社会への移行が必要である。 | |
| 生涯学習の振興を考える場合,新たに教える,学ぶという視点だけではなく,人生の各段階の活動・体験の中に人格形成に当たって有益に働く面と不適切に働く面の両方があることに配慮するという視点を持つことが必要である。例えば,テレビが提供する情報には有益なものも多い反面,幼児期にテレビを見る時間が長過ぎると,それ以降,対人関係をつかさどる感情が阻害されるといった知見が発表されていることもその例と言える。情報化社会には光と影の両面があり,情報を活用する力とともに批判的に読み解く力を身に付けさせることが重要である。 | |
| 人格形成にあたって,「子どもの姿は,大人の姿を写した姿である」と言われるように,大人の社会規範の低下についても十分留意することが必要である。 |