| 注1) | 子どもゆめ基金 民間団体が行う子どもの体験活動などに助成を行うための制度で,独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに設置されている。 (助成対象活動)
|
||||||||||||||||||||||||
| 注2) | サービスラーニング アメリカ等において,大学の正課教育の中にボランティア活動等の社会貢献活動を導入したもの。 サービス・ラーニングとは,「社会の要請に対応した社会貢献活動に学生が実際に参加することを通じて,体験的に学習するとともに,社会に対する責任感等を養う教育方法」であり,大学教育と社会貢献活動との融合を目指したものとされている。 |
| 注3) | セメスター制度 1学年複数学期制の授業形態。一つの授業を学期(セメスター)ごとに完結させる制度。諸外国では一般的。セメスター制は,1学期の中で少数の科目を集中的に履修し,学習効果を高めることに意義がある。さらに,セメスター制には,単位互換,社会人受入の拡大や大学間の円滑な転入学を可能とし,国際交流や大学間の連携協力の促進に寄与する。 |
| 注4) | ギャップイヤー イギリスにおいて習慣として行われている延期入学の仕組み。ある年度に入学を決めて(合格して),実際の入学は翌年度とするもので,その間に学生は,ボランティ ア活動をしたり,労働体験を積んだり,特定の技能などについて集中的に学習を行ったり,又は,目的を持って長期の海外旅行により見聞を広める等をする。 |
| アメリカ (1998年) |
イギリス (1997年) |
日本 (1996年) |
オランダ (1998年) |
フランス (1996年) |
ドイツ (1996年) |
韓国 (1999年) |
|
| 活動参加率 | 55.5 | 48.0 | 25.3 | 24.0 | 23.4 | 18〜16 | 13.0 |
| 注) | 1.アメリカはIndependent Sector "Giving and Volunteering in the United States"(1999年),イギリスはThe National Centre for Volunteering "National Survey of Volunteering in the UK"(1997年),日本は総務庁「社会生活基本調査報告」(1996年),オランダはThe Netherlands Organizations for Voluntary Workers "NOV Barometer 1998",フランスはThe Fondation de France "Giving and Volunteering in France 1997",ドイツはEURO-Volunteer Information Pool(EU委員会から助成されたプログラム),韓国は統計庁「社会統計調査報告書」(1999年)により作成。 |
| 2. | 各国の調査におけるボランティア活動の定義 |
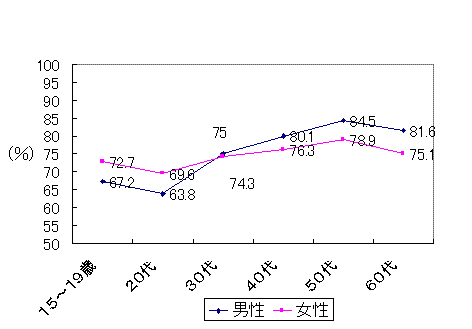
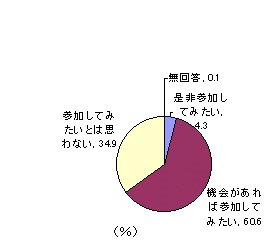 |
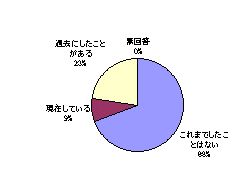 |
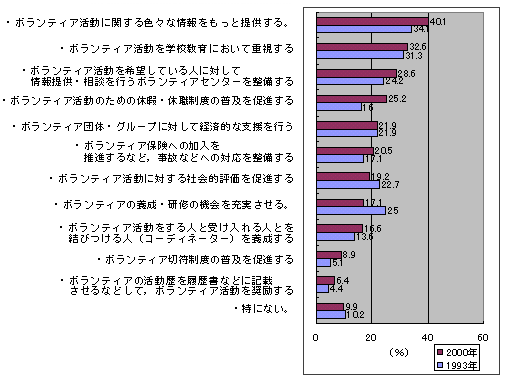
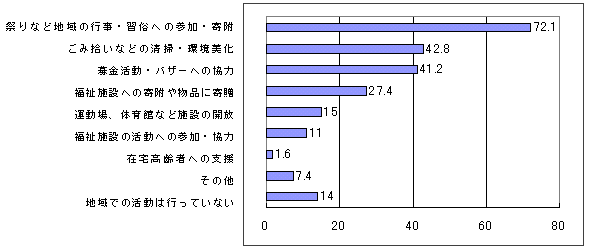
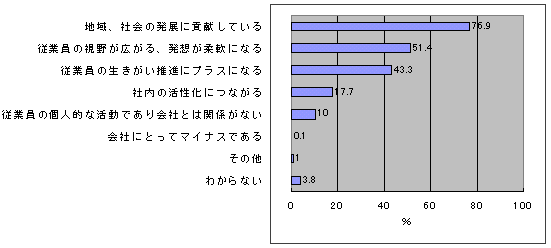
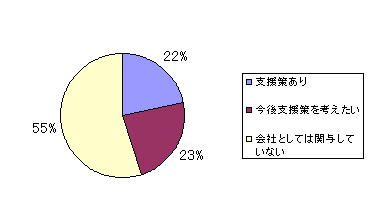
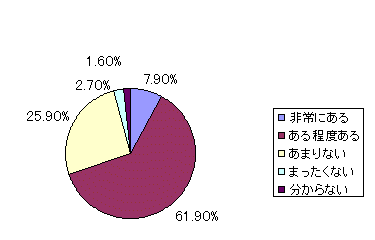
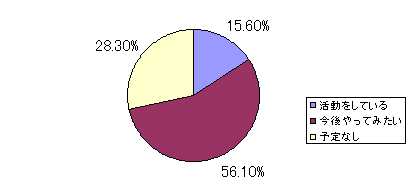
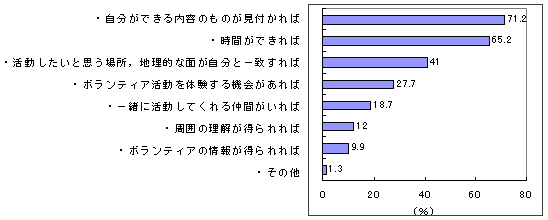
| 自分の得意なことを地域の人たちと一緒にすること | |
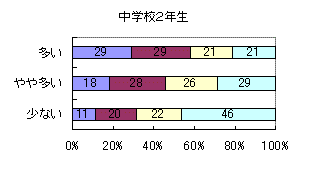 |
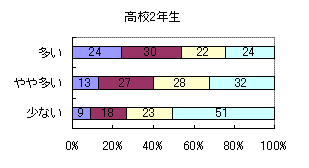 |
地域のボランティア活動に参加すること |
|
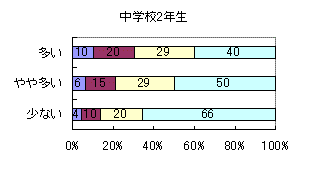 |
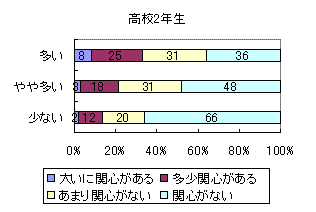 |
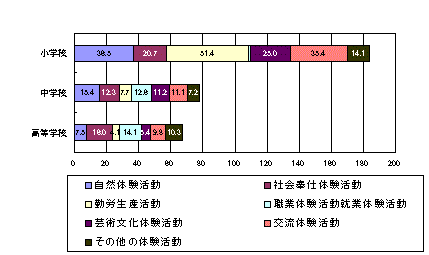 |
注)数字は,小学校は6年間,中,高等学校はそれぞれ3年間で実施されている体験活動の総単位時間 (小学校は1単位時間45分,中,高等学校は1単位時間50分) |
| 全体 | 男性 | 女性 | |
時間的に余裕のある人がやる 思いやりのある 魅力的な 信頼できる みせかけの 人気のある 遊びより面白い 責任感のある おせっかいな やりがいのある 冒険的な 勉強になる かっこいい 恥ずかしい 明るい まじめな なくてはならない 金では得られない 困った人を助ける 無報酬の 強制的な 社会のために役立つ 自ら進んでする 社会を変革する |
57.0 92.4 47.8 76.3 15.7 12.1 9.9 89.3 15.4 73.4 37.9 84.6 20.9 27.8 46.3 86.5 88.4 88.2 94.3 78.5 10.3 93.0 83.7 56.5 |
60.5 90.7 40.7 70.9 18.3 10.7 7.3 86.9 17.7 63.1 36.2 78.9 19.4 31.7 43.2 87.1 86.3 87.6 93.7 78.1 10.3 92.3 79.7 51.1 |
54.0 94.2 54.0 81.4 13.6 13.5 12.2 91.6 13.5 82.4 39.6 89.7 22.2 24.7 49.3 86.2 90.6 89.1 95.3 79.7 10.4 94.0 87.4 61.7 |
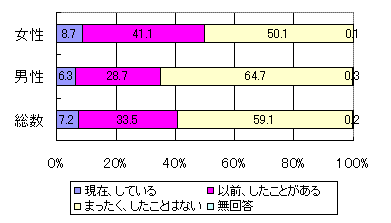
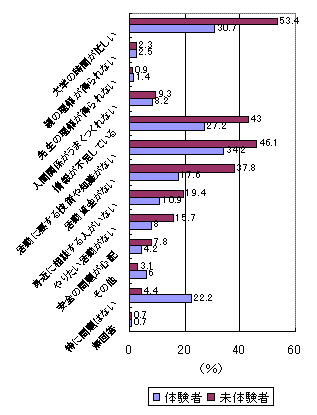
|
・・・ |
| ☆ | シチズンシップ教育の定義:社会的・道義的責任(social and moral responsibility) 生徒の精神的,社会的,文化的成長を促進し,学校のクラスにおいてもクラスを越えた場でも,より自尊心と責任感のある人間に育成する。 |
| ☆ | 2002年9月から11〜16歳の中等教育においてシチズンシップ教育が必修化されることが,ナショナル・カリキュラムの中で規定された。5〜11歳の初等教育では独立教科として必修とはしないものの,各教科にその内容を組み入れ,充実を図ることが決まった。
今後は各学校ごとにシチズンシップ教育が推進され,その中でコミュニティ・サービスの体験学習が用いられていくことが見込まれている。しかし,イギリスでは教育課程における学校や教師の自由裁量度が大きく,ナショナル・カリキュラムに強制力は余りないため,どの程度の時間をかけてどのようにシチズンシップ教育を実施するかは現場の裁量に負うところが大きい。 |
| ☆ | これまで学校で行われてきたシチズンシップ教育の事例:Haverstook school ロンドンの下町に当たるカムデン地区にある鉄道の操車場の跡地にできた学校で,約45種類の言語を話す子どもがいるなど,多民族・多文化の生徒で構成されている。特別教育の必要な子どもや,給食費の払えない貧困家庭の子ども,避難民の子どもなど,教育上困難な問題を抱えている生徒の割合が多い。 ドラマの授業で生徒が有料の演劇会を開き,自分たちの励みとするとともに,その収益金を老人ホームに寄附している。 視察者など外部からの訪問者があった場合には,生徒会の役員が校内を案内するとともに,学校の現状について説明している。 以前は,暴力事件が多発していたが,これらの活動によって生徒が落ち着き,学校運営も着実に良い方向に進み始めている。 |
|
・・・ |
|
・・・ |
| ☆ | T大学における取組 社会における奉仕活動やNPO活動への参画を通じて,経営学の手法による問題解決の方法を実地に体験するとともに,実社会システムの構造や機能及び問題点について理解を深めることを目的とした講義を開講している。その講義の一環として,2週間程度学外へ出てインターンシップを実施しており,体験内容のレポートを提出させ,評価を行っている。 |
||||
| ☆ | I大学における取組
|
||||
| ☆ | O専門学校における取組 英米語学科に就業年限2年の国際ボランティアコースを設け,ボランティア活動のリーダーとなるべき人材育成を行っている。具体的には,様々なNGO団体の活動に参加して国内で実習を行ったり,海外においても研修を実施しており,在学中に少なくとも1回は,長期休暇を利用してボランティア研修へ参加することが卒業の要件となっている。 |
||||
| ☆ | S短期大学における大学ボランティアセンターの例 S短期大学では,ボランティア情報・相談窓口の不足に悩む学生のために,大学にボランティアセンターを開設している。センターは,センター室長,ボランティアコーディネーター,運営委員(教職員,学外有識者),学生運営委員によって運営され, |
|
・・・ |
| ・ | メール,情報誌等による情報提供 |
| ・ | ボランティア休暇制度(半年以上の長期,2週間程度の短期等) |
| ・ | コミュニティ活動制度(就業時間中の一定時間,地域のボランティア活動に参加する制度) |
| ・ | 従業員の募金活動に対するマッチングギフト制度(一定の金額を上乗せして募金する制度) |
| ・ | 表彰制度 |
| ・ | 職員が自発的に無報酬で被災者支援,障害者,高齢者支援等の社会に貢献する活動を行う場合に有給で,年間5日間の特別休暇を認める。 |
| ・ | 職員研修における介護等実地体験研修の実施。 |
| ・ | 職員及び退職者を対象とし,専門知識を地域社会活動に活かすための人材派遣事業の発足 |
| ・ | 個人的にボランティア活動に結び付く通信教育を受講する者に対する受講経費の補助 |
| 等 |
| 参考事例5 |
| 国 名 |
実施主体 | プログラム名 | 期 間 | 対象 年齢 |
概 要 |
| ア メ リ カ |
CNS (Corpora-tion for National Service) (政府) |
AmeriCorps VISTA (Volunteers in Service to America) |
1 年間 |
18 〜 |
・ホームレス、識字教育、所得向上、地域活性化などの貧困対策を行うための、1年間の全日制のボランティア・プログラム ・参加者支援: ・年間約6,500人参加 |
| AmeriCorps NCCC (National Ci-vilian Commu-nity Corps) |
10ヶ 月間 |
18 〜 24 |
・若者が10〜12人のチームを組み全米の5つの施設で共同生活を行い、環境、生活、教育、災害救助、安全などの実際のサービス提供を行う。 ・参加者支援: ・年間約820人参加 |
||
| その他 |
・その他、CNSはアメリコアプログラムとして、個別に助成を行っており、その中には、長期フルタイムボランティアの企画もある。 | ||||
イ ギ リ ス |
GAP (Gap Act-ivity Pr-oject) (ギャップイヤー活動支援団体) |
ギャップイヤー(慣習であり、政府等が推進しているものではない) | 16ヶ 月間 |
18 〜 25 |
・ボランティア活動の他、活動自体は、旅行・アルバイト等多彩。 ・GAPでは、活動者に向いた活動をインタビューを通じて決定する他、期間中に海外で行うボランティア活動に対する支援を行っている。 |
| CSV (Communi-ty Servi-ce Volun-teers) (ボランティア団体) |
CSVのフルタイムボランティアプログラム | 4ヶ 月〜 1年 間 |
16 〜 35 |
・CSV職員によるインタビュー後、希望者の最も意向にあった活動が選ばれる。 ・活動時間:40〜50時間/1週間 ・活動後1ヶ月後及び活動終了後にレポート提出 ・参加者支援: ・年間に2,500人参加(海外からの参加者含む) |
|
| ド イ ツ |
連邦家族・高齢者・婦人・青少年省 | 兵役代替奉仕(Zivildienst) | 国内 11ヶ 月間 海外 13ヶ 月間 |
18 〜 27 男子 |
・介護・援助サービス、技術、事務、園芸、調理手伝い等。 ・参加者支援: ・18万人以上参加(1961〜1999) |
| 社会活動年(FSJ(Freiwilli-ges Soziales Jahr)) | 6ヶ 月〜 1年 間 |
17 〜 25 |
・看護・教育・家事の援助等といった医療、福祉分野でのヘルパー活動。 ・参加者支援: ・年間1万人以上参加 |
||
| 環境活動年(FOJ(Freiwil-liges okologisches jahr)) | 6ヶ 月〜 1年 間 |
16 〜 27 |
・保護活動、動植物や庭園の世話、環境保護の広報、環境教育のアシスタント等 ・参加者支援: ・1,500人参加(1993〜1998の間、約8割が女性) |
||
| 日 本 |
日本青年奉仕協会 (民間) | ボランティア365 | 1 年間 |
18 〜 30 |
・活動先:文化、地域振興、高齢者福祉、教育などの各分野で活動する団体・機関・自治体約230ヶ所 ・参加者支援: ・研修:事前・中間・総括の3回 ・約60人/年間参加(男:女=4:6、募集は7月と10月の2回) |
|
・・・ |
| ☆ | 青年海外協力隊事業の概要 開発途上地域の住民と一体となって当該地域の経済及び社会の発展に協力することを目的として,原則として2年間,青年を海外に派遣する。昭和40年度に事業が発足して以来,約2万2000人を派遣しており,農林水産,加工,保守総操作,土木建築,保健衛生,教育文化,スポーツの分野で活動している。 |
||||||
| ☆ | シニア海外ボランティア事業の概要 開発途上国からの技術援助の要請にこたえるため,幅広い技術・豊かな経験を有する中高年を1年ないし2年間派遣する。平成2年度に事業が発足して以来(平成2〜7年度の間は「シニア協力専門家」事業),約750名を派遣しており,計画・行政,公共・公益事業,農林水産,鉱工業,エネルギー,商業・観光,人的資源,保健・医療,社会福祉の分野で活動している。 |
||||||
| ☆ | 青年海外協力隊の活動を支援する事業 〜青年海外バックアップ・プログラム〜 青年海外協力隊の活動を一時的・短期に支援する要員を派遣し,協力隊事業のより一層の効果的な実施を図るための取組。 |
||||||
| ☆ | E大学における海外インターンシップ E大学においては,2年生以上の学生を対象に,海外インターンシップを実施し,単位として認定している。 学生は事前準備の座学を受講した後,
その他,ガーナ,ケニア,エクアドル(ガラパゴス),オーストラリア,ハワイ,ブータン,ベトナム,ドイツ等において国立公園の運営の実態調査などを中心とした活動も行っており,この経験を卒業論文に生かす学生もいる。 また,これがきっかけで青年海外協力隊に参加する在学生,卒業生も出てきている。 |
|
・・・ |
|
・・・ |
| ☆ | 地方(センター) エリア内の活動団体に関する情報、活動プログラムに関する情報、イベント情報等や推進体制の紹介、指導者募集等の広報などを行うためのホームページの開設 等 |
| ☆ | 国 各地方自治体のセンターのホームページ、関係府省、関係機関・団体等のボランティア情報等を含め、これらを利用しやすい体系に整理してリンクを張るなど、関連する情報を総覧できるシステムの構築 等 |
|
・・・ |
| ・ | ネットワーキング(行政・活動団体間,学校・家庭・地域間) |
| ・ | きっかけづくり(広報・PR) |
| ・ | ボランティア人材の確保・養成 |
| ・ | 地域住民や団体等が行う活動の企画や実施に関する相談対応 |
| ・ | 地域の課題・ボランティア活動のニーズ把握 |
| ・ | 地域資源の発掘(人的資源や活動団体の発掘,活動の場の開拓) |
| ・ | 地域住民等への活動に関する情報の発信 |
| 等 |
|
・・・ |
| ☆ | 文化ボランティアの呼び掛け〜文化ボランティア通信〜 文化庁においては,平成14年2月から,「文化ボランティア通信」を発刊し,各地の活動を紹介して参加者を募るのと同時に,関係者の情報を発信し,文化ボランティアネットワークの形成を行いたいとしている。 |
| ☆ | アメリカ大統領の奉仕活動拡充の呼び掛け 2002年2月,アメリカのブッシュ大統領は,一般教書演説で「全国民が一生のうち2年間,あるいは通算4,000時間を奉仕活動に費やそう」と提唱し,地方遊説で市民に参加を求めている。そのため,既存の海外援助団体,地域の教育活動などを行う団体の大幅な拡充,医師,看護婦,警察官のOBなどを中心としたボランティア組織網の創設などを提唱している。 |
(生涯学習政策局政策課)
ページの先頭へ