| 資料 |
| 4.国民の奉仕活動・体験活動を支援する社会的仕組みの整備 |
|
| 奉仕活動等に関する現状及び課題を踏まえ、個人、学校、関係団体等の活動をサポートできるような以下のような仕組みをつくることが有効である。 |
| (1) | 奉仕活動・体験活動を支援する仕組みづくり |
| 1) | 協議会・センターの設置(図 |
| 特に学校内外での青少年の奉仕活動・体験活動の円滑な実施のためには、国、都道府県、市町村のそれぞれのレベルで、関係行政機関、ボランティア推進団体、学校など関係者による連携協力関係を構築するための協議の場(協議会)を設けるとともに、コーディネーターを配置し、活動に関する情報提供、相談・仲介などを通じて、奉仕活動・体験活動を支援する拠点(センター)を設けることが必要である。このようなセンターは、一般の社会人や学生等の活動のセンターとしても機能しうると考えられる。 | |
| また、協議会やセンターの設置・運営、更には各種施策等の展開にあたっては、国レベルにおける関係府省や全国規模の関係団体等による連携はもとより、地方においても、教育委員会と首長部局、更には行政と学校、社会教育施設、社会福祉協議会等の関係団体、地域の経済団体、地域の代表者など関係機関・団体等の密接な連携が必要である。 | |
| なお、協議会については、関係する行政部局が多く、広く関係団体等の協力を得ることが必要であるため、行政が中心となって運営することが妥当である。 | |
| 一方、センターについては、既に蓄積されたノウハウ等を活用するとともに、機動的かつ柔軟な運営を確保するため、教育委員会など行政がその機能を担うほか、状況に応じてボランティア推進団体等に委ねることも有効である。特に市町村のセンターについては、幅広い関係団体等との協力関係が構築できる場合には、教育委員会のほか、社会福祉協議会ボランティアセンターなど既にコーディネイト等を活発に行っている団体等に委ねるなど地域の実情を勘案した柔軟な対応が適当であると考えられる。 | |
| 2) | 国及び地方を通じた情報システムの構築 |
| 情報の発信は、誰もがいつでも容易に必要な情報を得ることができるシステムが求められる。 |
| (図 |
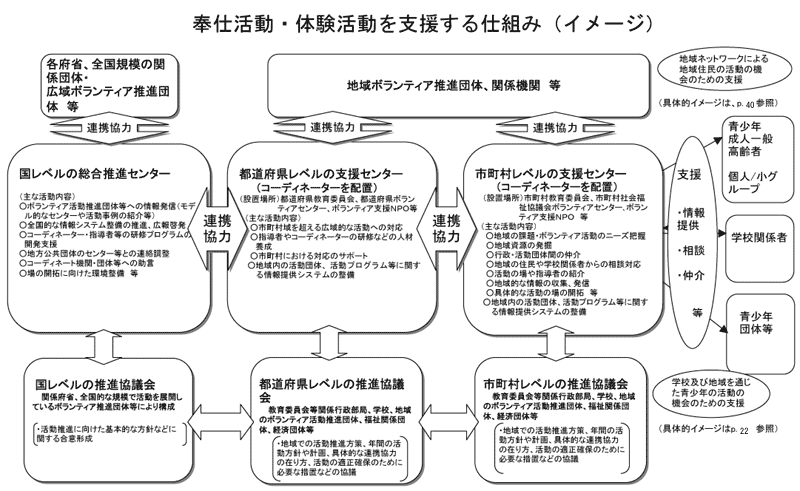
| 特に市町村、都道府県レベルでは、前述のセンターを中心に、既存のボランティア関係の情報データベース等を活用しつつ、地域内の活動団体や活動プログラム等に関する情報を整理し、活動を始めようとする個人、学校関係者、ボランティア活動関係者等様々な個人や団体の求めに応じて必要な情報を提供するシステムを構築する必要がある。(表 |
| 国レベルにおいても、関係府省、ボランティア関係機関・団体等が連携協力し、全国的なボランティア情報等を利用しやすい体系に整理し、上記の地方のセンターの情報とともにリンクするなど関連する全ての情報が総覧できる情報システムの構築が必要である。 | |
| なお、情報システムの整備に当たっては、可能な限り広く収集し掲載することが適当であるが、例えば、特定の団体の誹謗中傷、政治や宗教への利用など不適切な活動の可能性があると判断される場合には管理者で削除するなどのルールを決めておくことが適当である。また、ボランティア指導者等の人材等についての情報の登録に当たって、センターのコーディネーターなどが適切な判断を行うことが適当である。 | |
| 更に、将来的には、国及び地方を通じて、各種情報をデータベース化し、活動分野、年齢、親子など参加形態、地域等により参加し得る活動が検索できるシステムや、生涯学習の視点を踏まえた活動手法や活動事例などの情報提供、希望団体自体による情報提供のために開放できるスペースの提供などの工夫が求められる。 |
| (2) | 地域ネットワークの形成(図 |
| 奉仕活動・体験活動を日常的な活動として、着実に実施していくためには、市町村のセンターのほか、地域の実情に応じて、社会福祉協議会、自治会、民生委員、青年会議所、商店会等地域の団体が連携協力して、小学校区単位で公民館や余裕教室等を活用し、地域住民が日常的に活動に取り組むために集うことができる身近な地域拠点(地域プラットフォーム)を整備することも有効であると考えられる。ここでは、市町村のセンターを補完して、身近なエリアでの活動の場の開拓や地域住民の活動への参加を促すことが想定される。 | |
| 一方、地域住民の生活圏域に応じた広域的なボランティア活動等のニーズに応えるため、例えば、高等学校通学区域単位などで、県内のボランティア推進団体、大学、NPO等が連携協力して、広域的な拠点(広域プラットフォーム)を整備していくことも検討に値する。 |
| (3) | コーディネーターの養成・確保 | |
| コーディネーターに期待される役割 | ||
| コーディネーターは、奉仕活動・体験活動の推進において重要な存在であり、センターないし仲介機関にあっては、活動参加を希望する者と活動の場を円滑に結びつけるため、活動の準備、実施、事後のフォローアップなど活動の各過程を通じて、参加者に対する活動の動機付け、情報収集・提供、活動の場の開拓、受入先の活動メニューの提供、活動の円滑な実施のための関係機関等との各種の連絡調整などの役割を担う。 | ||
| また、学校などの参加者を送り出す施設や福祉施設などの参加者を受け入れる施設にあっても、コーディネーターの役割を担う担当者が必要であり、送出側では事前指導や関係機関等との連絡調整、受入側では参加者へのガイダンス、活動内容の企画、施設内での連絡調整等の役割を担う。 | ||
| (表 |
|
| (図 |
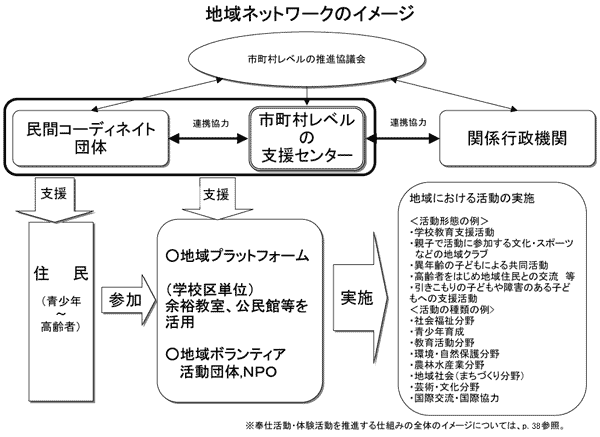
|
| 養成・確保 | |
| コーディネーターには、ボランティア活動、企画・広報、面接技法等に関する専門的知見とともに、関係機関との人的ネットワークやその背景にある豊かな人間性など幅広い素養・経験等が求められる。更には、活動の適正さを確保するため、ボランティア活動に関する情報や団体や人物に対する確かな目利きといった能力も必要である。このため、関係する行政部局や団体等の協力を得つつ、都道府県と市町村が共同して人材の積極的な発掘、計画的な養成が必要である。 | |
| コーディネーターの養成については、社会福祉協議会、ボランティア推進団体、教育委員会、スポーツ団体、青少年団体等関係機関・団体等が連携協力して、養成講座の体系化を図り、養成講座を共同で開設することや、更には関係機関・団体が協力して養成のための各種のモデルプログラムの開発等を行うことも検討する必要がある。また、受講者の経験や知識のレベルに応じた必要事項の補完や、担当する分野の特性に応じた多様なプログラムを用意する必要があることから、基本的には一定人数をまとめ得る都道府県単位で養成講座を行うことが効果的と考えられる。 |
| (4) | 行政機関におけるボランティア活動等を担当する部局の設置・明確化等 |
| ボランティア活動等を効果的に推進していくためには、行政機関とNPO、ボランティア団体などが連携・協力しやすい仕組みを作ることが重要である。また、ボランティア活動等を行おうとする個人にとっても、行政機関の窓口が明確であれば、情報提供や相談対応を求めることができ、活動に気軽に参加しやすくなる。そこで、各行政機関等におけるボランティア活動等を担当する部局を設置(「ボランティア課」等)、又は明確化し、ボランティア活動等の推進に取り組むとともに、国民にアピールするなどの取組も求められる。 |
|