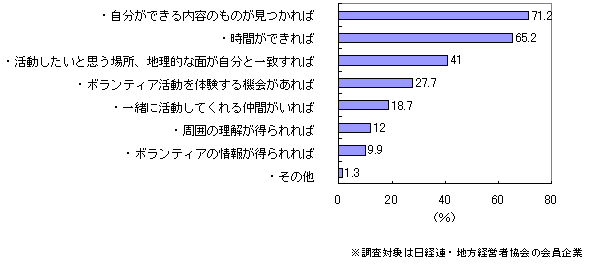| 資料 |
| 奉仕活動・体験活動をどのように推進していくのか |
| 1. | 奉仕活動・体験活動に関する現状 |
|
| (1) | 奉仕活動・体験活動の現状 |
| ○ |
全国で活動するボランティアは、700万人を超えており、環境保護や社会福祉、国際交流等幅広い分野にわたっている。
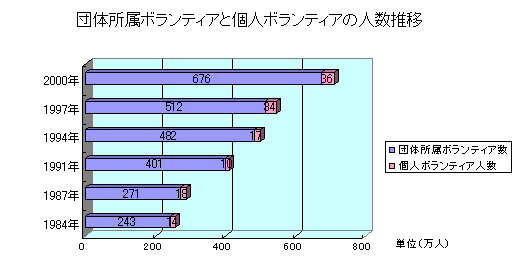
|
| (「ボランティア活動年報2000年」(社会福祉法人全国社会福祉協議会全国ボランティア活動振興センター)) | |
| ○ | 平成10年の特定非営利活動法人(NPO)法の制定で、NPOの活動を支援する基本的な枠組みが構築されたことにより、市民活動が多様な場面で継続的に行われる機会が増大している。(日本におけるNPO法に基づき法人格を取得した団体は5.826団体(平成14年1月18日現在) |
| ○ | 国民の活動状況 | ||
| 諸外国との比較(「国民生活白書(平成12年度)」) | |||
| ・ | 我が国のボランティア活動参加率は諸外国と比較すると低い、特に30代前半までの若い世代で低いという特徴が見られる。 | ||
| ■ | 各国のボランティア活動参加率■ |
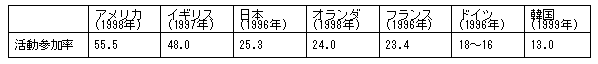
| 国民の活動状況(「国民生活選好度調査(経済企画庁)」(平成12年)) | |||
| ・ | 国民の4人に3人は社会の役に立ちたいと考えており、また、実際にボランティア活動への参加意欲を持つ人は3人に2人の割合となっており、国民のボランティア活動等に対する関心は非常に高いものとなっている。しかしながら、現在活動を行っている、又は過去に活動行ったことがある人は、同調査によれば、3人に1人にすぎない状況にある。 | ||
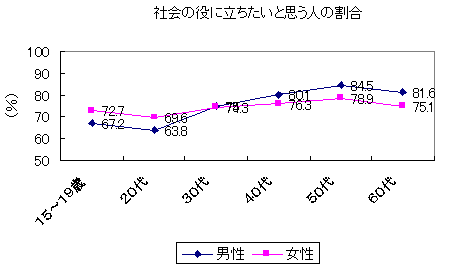 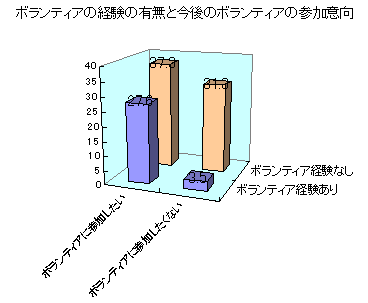 |
|||
| 子どもの活動状況 | |||
| ・ | ふだんの暮らしや地域とのかかわりについても、小学校、中学校、高等学校と学年があがるにつれ、少なくなる傾向にあり、ボランティア活動への参加は、10%に満たない。 | ||
| ・ | ふだん地域の人たちとのふれあいが多い子どもほど、地域活動への関心は高い傾向にある。 | ||
| (「地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査」(速報)(子どもの体験活動研究会)) | |||
| ・ | また、学校における体験活動の実施状況についても、小学校、中学校、高等学校と学年があがるにつれ、活動時間が少なくなっている。(「学校における体験活動の実施状況(平成12年度)」文部科学省調べ) | ||
| ■ | 地域社会とのかかわり■ |
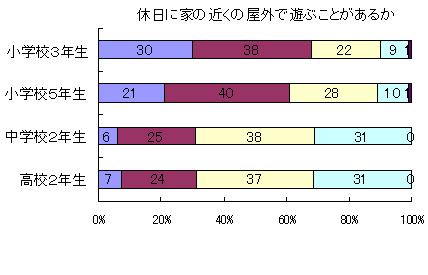
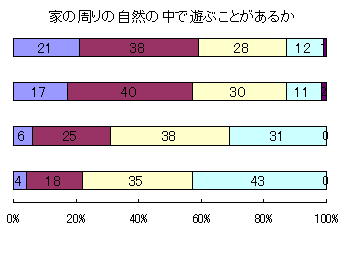
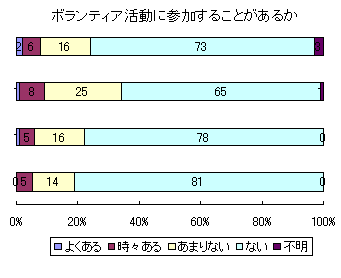
| ■ | 地域の人たちとのふれあいの多少と毎週土日が連休になったときの地域活動への関心■ |
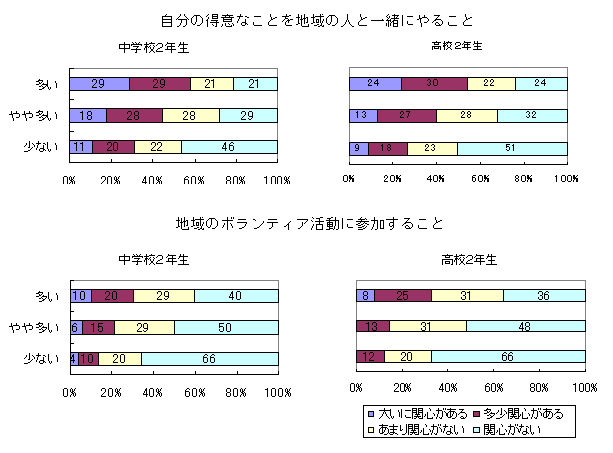 |
| ■ | 学校における体験活動の実施状況(平成12年度)■ |
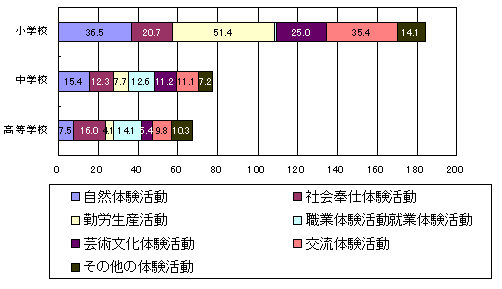 |
|
| 注) | 数字は、小学校は6年間、中、高等学校はそれぞれ3年間で実施されている体験活動の総単位時間 |
| (小学校は1単位時間45分、中、高等学校は1単位時間50分) | |
| (2) | 国民の意識等 | ||
| 国民一般(「国民生活選考度調査(経済企画庁)」(平成12年)) | |||
| ・ | 活動の妨げの要因としては「ボランティア団体に関する情報がないこと」をあげる人が約4割を占め、また、国や地方公共団体に望むこととして、情報提供や相談体制を整備することを上げる人が多い。 | ||
| ■ | ボランティア活動について、国や地方公共団体に望むこと■ | ||
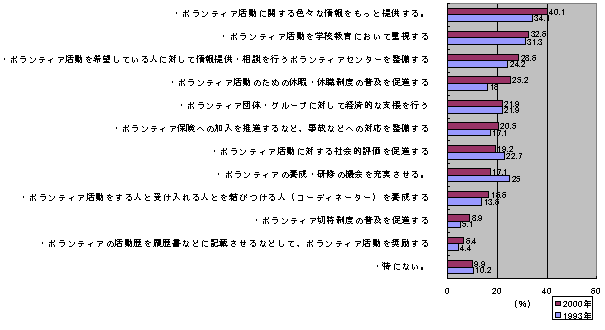 |
|||
| 青少年(「青少年のボランティア活動に関する調査」報告(総務省(平成6年6月)) | |||
| ・ | 青少年のボランティア活動に対するイメージとしては、「やりがいがある」、「勉強になる」といった項目については、肯定的に回答する者が多くいる一方、「遊びよりも面白い」、「かっこいい」といった項目については、否定的に回答する者が多い。 | ||
| ■ | 青少年の抱くボランティア活動に対するイメージ■ |
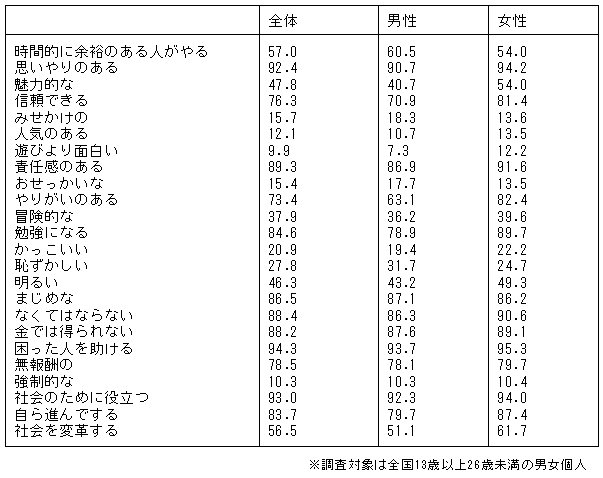
| 大学生(「学生のボランティア活動に関する調査報告書((財)内外学生センター)」 | |||
| (平成10年)) | |||
| ・ | 大学生のボランティア活動については、ボランティア活動の未経験者は59%となっており、活動を始める障害要因については「大学の時間が忙しい」に次いで、「情報不足」「活動のための技術や知識がない」「資金がない」などがあげられている。また、国や市町村、大学に対して望む支援・奨励策として、情報の提供、研修会等の実施、単位認定が上げられている。 | ||
| 社会人・企業(「企業及び勤労者のボランティア活動に関する調査(日本経営者団体連盟・地方経営者協会)」(平成12年)) | |||
| ・ | ほとんどの企業が何らかの地域活動を行っており、何も行っていない企業は約1割程度であり、従業員が行うボランティア活動についても、肯定的に捉えている。 | ||
| ・ | 従業員の活動に対して「支援策あり」の企業は約2割にとどまっており、自主的活動であるため関与しないとする企業が5割を超えている。 | ||
| ・ | 従業員については、約7割がボランティア活動に関心を示しているものの、現在活動を行っている人は16%にすぎない。ボランティア活動を今後やってみたい人については、その条件として、「自分ができる内容のものが見つかれば」「時間ができれば」等をあげている。 | ||
| ■ | 従業員のボランティア活動を始める条件■ |