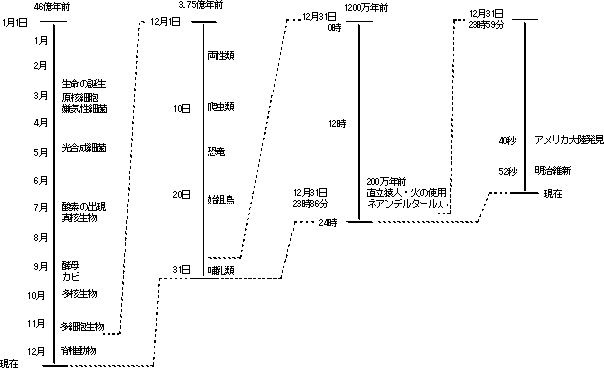資料を適切な環境で保存・保管することは博物館等の主要な役割であるが、夏季に高温多湿の日々が続く日本では、カビ対策は大きな課題となる。表面にあらわれてこないが、カビ対策に頭を悩ませている博物館・図書館等は、数多い。
今回、カビ対策マニュアルを刊行するにいたった背景には、地球規模での環境保全問題がある。日本では1970年代頃から、資料にカビや虫害が発生したときの抜本的な処置として、臭化メチルと酸化エチレンの混合ガスによるガス燻蒸という手法を広く用いてきた。しかし臭化メチルは、オゾン層破壊物質として規制の対象になり、日本を含む先進国では2004年末にその生産が全廃となった。2005年以降は、臭化メチル製剤を、博物館等での殺虫殺菌処理に使用することができなくなったのである。
カビや虫害が発生すればガス燻蒸で対処すればよい、という短絡的な考えが少なからずあった反省をふまえ、近年、総合的有害生物管理(IPM、Integrated Pest Management)の考え方が注目されている。IPMは、農薬を大量に使用してきた農業分野からでてきた生物被害コントロールの方法で、日本の博物館等でも、その導入が始まっている。IPMの目的は、身近なことから防カビ・防虫に対する意識を高めることにある。施設の清掃をこまめに行う、資料への目配りを怠らない、このような基本的事項の大切さを再認識し、カビや虫が発生する環境をつくらないように努める。そして被害が発生すれば、化学的手法になるべく頼らず、被害の状況に応じた処置をひとつずつ、あるいは組み合わせて実施していくという姿勢である。
本マニュアルは、IPMの考え方に基づいたものである。マニュアルの構成は、大きく[基礎編]と[実践編]に分かれる。[基礎編]の1、2、3では、微生物学の見地から、カビの分類学的位置づけ、カビの生理生態と生育環境、カビの簡易同定法、カビ制御方法という、カビに関する専門知識を網羅した。続く[基礎編]の4、5には、カビ被害防止、カビ被害の早期発見、緊急対策など、資料管理の現場で最低限必要となる基礎知識をまとめている。一方、[実践編]は、カビの発生しない環境づくり、カビの発見のしかた、カビ発見後の対策と、より実践に即した内容になっている。多くの人びとが知りたいこと、疑問に思うことは、最後のQ&Aで扱っている。Q&Aから、本文のどの場所に、関連の内容が掲載されているかを逆引きできるようにしてあるので、必要なところだけ読むという使いかたもできる。
カビ対策マニュアルは、このように多彩な内容になっている。博物館・美術館の学芸員、事務職員、施設管理担当者、図書館司書、文書館職員、歴史系の学校職員などを対象とした専門書として、生物・化学について必ずしも十分な知識を持っていない学芸員養成課程初期段階にある学生の教科書として、さらには現場ですぐに使えるマニュアルとして、そのいずれにも対応できるよう書かれたものである。
それでは、まず始めに、カビがどの様な生き物であるのかを理解して頂くために、地球誕生から現在までを1年のスケールとして表示した場合の生命の誕生からカビと人の歴史を眺めてみる(図1)。
地球が誕生してから僅か3ヶ月間(40〜38億年前)で地球最初の生命(原核細胞である嫌気性細菌)が誕生した。続いて5月(約28億年前)に誕生したのが光合成細菌である。この細菌群が太陽光を利用して酸素を10億年間作り続け、7月頃(約18億年前)にやっと現在の大気の酸素濃度と同じ状態になり真核生物が誕生した。さらに、これら真核生物が進化を続け、9月頃(約10億年前)に酵母やカビが誕生し、多細胞生物へと進化した。脊椎動物は12月頃(約4億年前)に誕生している。したがって、人類の歴史に比較して気の遠くなるほどの長い年月を経、地球環境の変化や様々な淘汰を乗り越えて現在まで生き続けてきたのが微生物である。言い換えると、微生物は現在の多様性に富む全ての生物の祖先でもある。細菌やカビは地球上に存在するほとんど全ての有機物や無機物を分解し、栄養源として利用し、これまで生き続けてきた。その結果、現在の美しい地球環境が保たれていると言っても過言でない。さらに、微生物は多種多様の恵み(発酵食品、抗生物質、ビタミン、アミノ酸、医薬品、酵素、各種有機酸および廃水処理等)を人類にもたらしている。
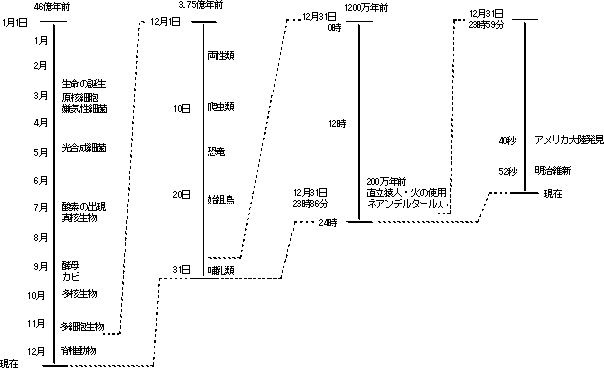
図1 地球と生物の歴史
しかし、微生物の病原性は人類を含めた多くの生物の健康を脅かし、加えて人間の生活の基礎である衣食住の腐敗、変敗、腐朽などの微生物劣化に加え、その分解力は鉄筋コンクリート、金属、ガラス、鉱物に加えて博物館や図書館等資料までにも及んでいる(表1)。
表1 衣食住や工業製品の微生物劣化
| 材料 |
用途 |
劣化原因微生物 |
| アルミニウムおよびその合金 |
飛行機、自動車、窓枠、機器、装置 |
細菌、カビ |
| ステンレス鋼 |
廃水パイプ、キッチンセット、洗濯機 |
細菌、硫酸還元菌 |
| 鉄およびその合金 |
自動車、機械装置、機器、鉄筋 |
細菌、硫酸還元菌 |
| 銅およびその合金 |
熱交換装置、電線、機械器具 |
細菌、硫酸還元菌 |
| 鉄筋コンクリート |
建物、ダム、土木施設 |
細菌、硫酸還元菌 |
| 木材および合板 |
住宅(基礎、床材、柱、天井材)、家具 |
細菌、カビ、木材腐朽菌 |
| プラスチック |
パイプ、タンク、容器、各種器具及び装置、包装材料、 |
細菌、カビ、藻類 |
| ガラス |
光学機器、板硝子 |
カビ |
| 石油 |
ケロシン、ガソリン、灯油、切削油 |
細菌、カビ、藻類 |
| 天然高分子、合成樹脂 |
塗料(天然系・合成系)、接着材(澱粉、膠、漆、エポキシ)、コーキング |
細菌、カビ |
| 天然ゴム・合成ゴム |
ゴムパッキン、ゴムバンド、タイヤ等 |
細菌、カビ |
| コンクリート・モルタル |
柱、床、壁、天井、目地、外壁 |
細菌、カビ、藻類 |
| 医薬品 |
生薬、目薬等 |
細菌、カビ、酵母 |
| 化粧品 |
化粧水、クリーム、乳液等 |
細菌、カビ、酵母 |
| 農水産物 |
生鮮食品、穀物、野菜、魚介類 |
細菌、カビ、酵母 |
| 農水産加工食品 |
缶詰、レトルト、乾燥食品、塩蔵食品 |
細菌、カビ、酵母 |
| 木綿、麻、絹、化学繊維 |
衣料用繊維、インテリア、テント等 |
細菌、カビ |
| 皮革 |
衣類、家具、シート、鞄、ベルト等 |
細菌、カビ |
| 電子材料 |
パソコン、プリント配線、デバイス |
細菌、カビ |
| 麻、雁皮、楮、檀、パルプ |
和紙、洋紙 |
カビ |
| 博物館・図書館等の所蔵資料 |
絵画、彫刻、工芸品、書籍典籍、古文書、考古資料、歴史資料、民族・民俗資料等 |
細菌、カビ |
| 記念物 |
史跡(貝塚、古墳、遺跡)等 |
細菌、カビ |
これら微生物の功罪を踏まえ、博物館・図書館等の資料や記念物のカビ対策マニュアルを作成した。