| (1) |
変化への対応 |
| |
ここ数年来、公共の文化施設は、官から民への大きな流れの中、市場原理の導入等により改めてその在り方が問われている。博物館もその例外ではない。日本博物館協会は、このような変化に対応するために、平成10年以来、わが国の博物館のあるべき姿を求めて検討を続け、博物館活動の基本理念として「対話と連携の博物館」(平成12年12月)、その具体的な行動指針として「博物館の望ましい姿」(平成15年3月)を発表した。そして、望ましい姿の実現を支援するために「手引き」(平成16年3月)を刊行し、ワークショップや意見交換会を行ってきた。
しかし、変化に一層の拍車がかかっている。国立博物館への市場化テスト導入の検討、公立博物館での指定管理者制度の導入開始や市町村合併に伴う博物館の統廃合、そして私立博物館に関係する公益法人改革など、いずれも博物館活動の根幹にかかわる課題である。ここで今一度、博物館のあるべき姿を関係当事者が共有し、状況の変化に対応していくことが求められている。
|
| (2) |
博物館の存在意義 |
| |
博物館活動の根幹は、資料と情報を集積し、展示や学習支援を通して広く活用に供するとともに、人類共有の遺産として次世代に伝えることである。そして、調査研究によって資料の価値を高め、人びとに正確な情報を伝えることが、博物館に対する信頼の礎となる。
このことは、博物館が果たす独自の役割であり、社会情勢の変化に振り回されることなく、その役割を果たすことが人類社会に対する責務である。
|
| (3) |
事業の基盤としての「博物館力」 |
| |
博物館がその役割を果たすには、系統的な集積と調査研究によって価値を高めた資料と、その価値を展示や学習支援を通して人びとに橋渡しをする人材が不可欠である。選び抜かれた資料と専門能力を有する人材、これこそが、博物館が社会から期待される役割を全うする力、「博物館力」の源泉であり、これを強化することが責務を果たす基盤となる。
|
| (4) |
非営利的な公益機関として |
| |
人類共有の財産を集積し、次世代へ引き継ぐには相応の費用がかかり、資金や労力をはじめとする社会的な支援が不可欠となる。経費を入場料収入等の自己収入でまかなえる博物館は限られており、大半の博物館は、公的な資金や税制上の優遇措置などに支えられている。社会からの支持を得るためには、その館にとって適切な入館者数を確保するとともに利用者へのサービスへの努力が求められる。
また、博物館は、公共に資する施設として、社会から直接・間接の支援を受けているからこそ、限られた人材や資金で最大限の効果を得る必要がある。特に国公立館は、多くの公的資金が投入されており、一層経営感覚をもつことが求められている。
|
| (5) |
運営の基軸としての「対話と連携」 |
| |
博物館が社会からの理解と支持を得るには、「博物館はなぜ存在するのか」、「社会にどのように貢献するのか」ということを表明し、具体的な行動で示さなくてはならない。また、限られた資源の中で効果的に事業を行うためには、博物館とその関係者が一致協力するとともに、博物館同士や関係機関、社会との協力体制を築くことが肝要である。
博物館とその関係者の力を結集するためには、博物館の使命と方針を関係者が共有することが必要であり、そのための対話が不可欠である。また、他の博物館や関係機関、地域社会などと連携することよって、一つの博物館だけは困難な事業も実現することが可能となり、さらなる発展につながる。これから迎える成熟社会においては、「対話と連携」を運営の基軸に据えることが博物館力を増大させ、社会に貢献するための鍵となる。
|
| (6) |
博物館活動の共通のイメージとしての「博物館樹」 |
| |
博物館は事業の基盤としての「博物館力」を強化して社会からの信頼に応え、「対話と連携」を運営の基軸とすることで限られた資源を最大限に活用し、社会に貢献することが可能となる。私たち博物館関係者は、一致協力して博物館のあるべき姿の実現に力を尽くさなければならない。
現在、博物館は、事業の根幹に係わる変化を前にしている。関係者が共通の理解を持って変化に対応することが、これほど求められている時はない。博物館の諸活動は、例えば滋賀県立琵琶湖博物館のイラストのように、1本の大きな樹木に例えることができる。
博物館は、地域の自然や文化に根差し、資料の収集や調査研究を通して、展示や教育普及活動といった「果実」を人びとに提供する。人びとが手にする果実は、学芸員による資料収集や調査研究、保管など、樹木の根幹に隠された各種の活動の、最終的な成果である。地中に広く深く根を張らないと存立できないが、より美味しい果実をより多く実らせるためには、人びとの理解と協力が不可欠である。博物館という樹木は、設置者と職員、市民がそれぞれの役割を果たすことで成長し、社会に潤いをもたらすのである。
|
| |
挿入:「琵琶湖博物館の活動イメージ」(滋賀県立琵琶湖博物館『要覧』より)
|
| |
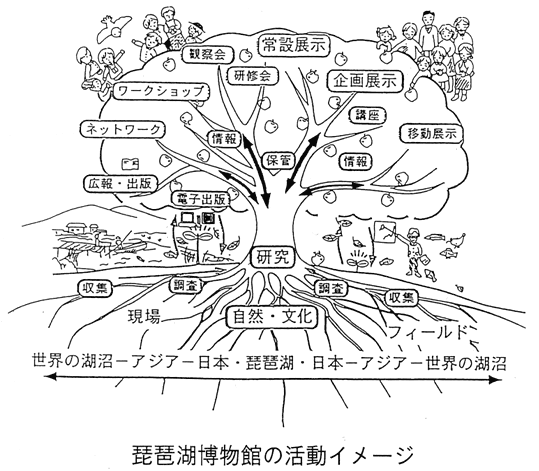 |