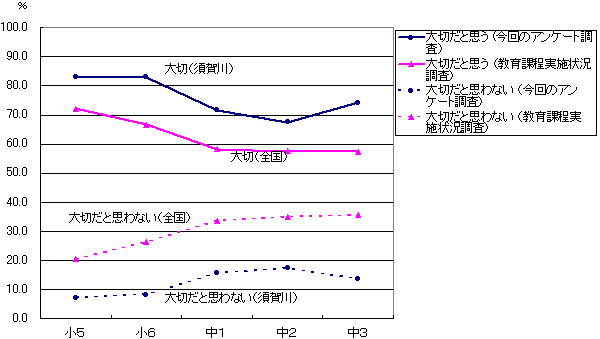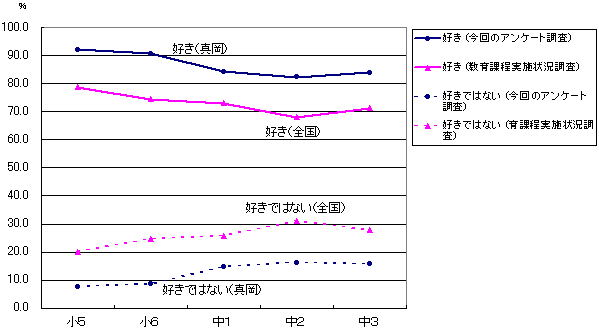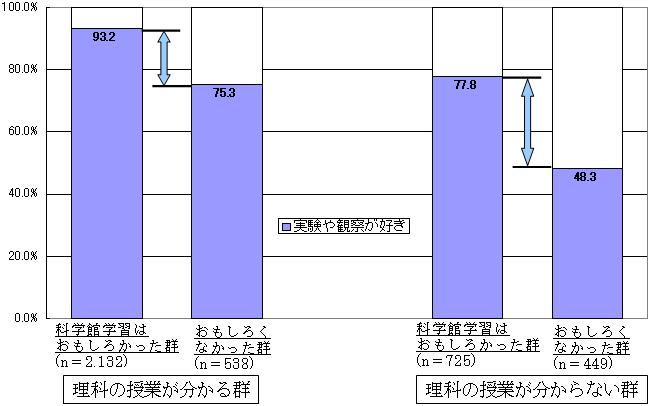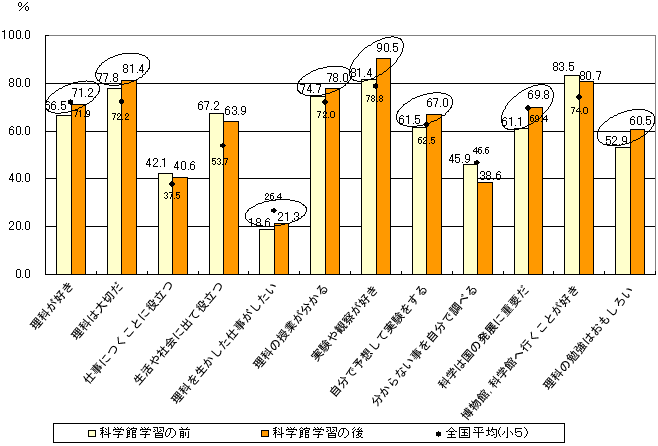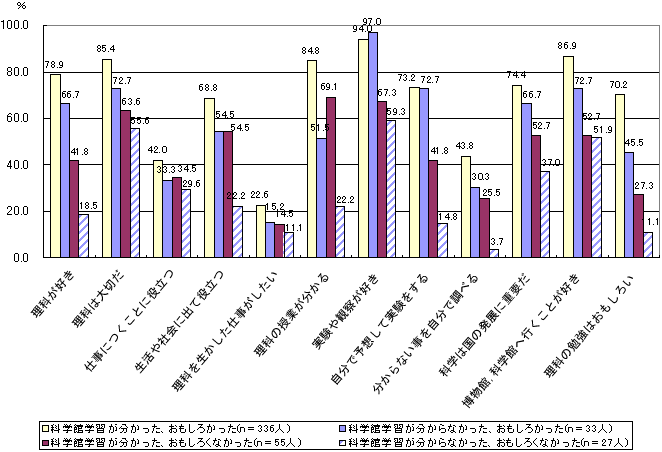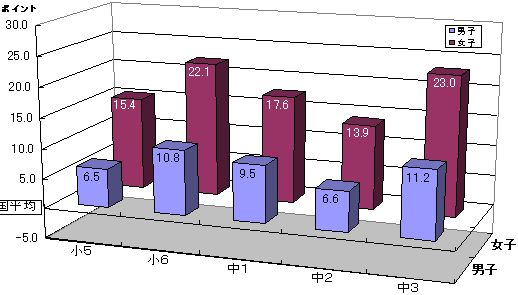《表2》では、今回調査対象となった4つの科学館等の規模や目的、組織体制、科学館学習の対象学年や回数、主な科学館学習の内容等の概要を示している。
また、今回のアンケート票の回収状況は《表3》の通りで、4市とも学校単位では100パーセント回収した。さらに、児童生徒数で見てみると、4市とも90パーセント以上の回収率であった。
《表3》児童生徒に対するアンケートの実施状況
| (1) 科学館学習を受けた4市の児童生徒の理科に関する意識は、全国平均を上回っている。 |
「理科の勉強は好きですか」、「理科の勉強は大切だと思いますか」等、理科に関する意識について、調査した4つの市の児童生徒と全国平均を比較した。この結果、市や設問によりばらつきはあるが、単純に設問と学年別に今回のアンケート結果の肯定的な意見が全国平均を上回ったかどうかを調べてみると、4市それぞれの学年数(須賀川市、真岡市、出雲市は小学校2学年、中学校3学年の計5学年、京都市は小学校2学年、中学校2学年の計4学年)に11(設問数)を掛けた延べ209学年のうち、全国平均を上回っているのは延べ171学年(81.8パーセント)あった《表4》。上回った割合は数ポイントから30ポイントまで様々であるが、この4つの市の児童生徒の理科に関する意識が高いことは明らかであろう。
| 《表4》4市のアンケート結果と全国平均の比較(設問、学年別) |
(単位:延べ学年数) |
| |
須賀川市 |
真岡市 |
京都市 |
出雲市 |
計 |
| 小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
| 全延べ学年数 |
22 |
33 |
55 |
22 |
33 |
55 |
22 |
22 |
44 |
22 |
33 |
55 |
88 |
121 |
209 |
| 全国平均を上回った延べ学年数 |
22 |
28 |
50 |
22 |
29 |
51 |
16 |
15 |
31 |
18 |
21 |
39 |
78 |
93 |
171 |
| 全国平均を下回った延べ学年数 |
0 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
6 |
7 |
13 |
4 |
12 |
16 |
10 |
28 |
38 |
| 注) |
理科に関する意識について質問した11の設問を、学年毎に4市のアンケート結果と全国平均の肯定的な意見の割合で比較した。 |
|
《図1》《図2》は、一例として、須賀川市における「理科の勉強は大切だと思いますか」《図1》と、真岡市の「理科の勉強で実験や観察をすることが好きですか」《図2》の2つの設問についてのアンケート結果を全国平均と比較したグラフである。
|
《図1》理科の勉強は大切だと思いますか<須賀川市>
|
| 注) |
「わからない」、と回答した児童生徒と無回答であった児童生徒を省略したため、各学年のパーセントにはならない。
他の3市は、本文の図7、図8、図9を参照。 |
|
《図2》理科の勉強で、実験や観察をすることが好きですか<真岡市>
|
| 注) |
無回答であった児童生徒を省略したため、各学年のパーセントを合計しても100パーセントにはならない。
他の3市は、本文の図26、図28、図29を参照。 |
|
| (2) 「科学館学習を受けること」と「児童生徒の理科に関する意識が高くなること」との間には相関関係がある。特に、「科学館学習が分かった」と回答した児童生徒よりも「科学館学習はおもしろかった」と回答した児童生徒の方に、より強い相関がある。 |
|
前項の(1)では、単純に今回のアンケート結果と全国平均を比較したものである。しかし、子どもたちの理科に関する意識の向上には様々な要因が考えられ、この結果だけで科学館学習を受けることが児童生徒の理科に関する意識に影響を及ぼしていると、断定することはできない。
そこで、科学館学習を受けることが、児童生徒の理科に関する意識に何らかの影響を与えているのか調べるために、《表5》に示すように、児童生徒を「 理科の授業が分かる」と回答したグループと「 理科の授業が分かる」と回答したグループと「 理科の授業が分からない」と回答したグループに分けてから、 理科の授業が分からない」と回答したグループに分けてから、 と と のそれぞれのグループで、更に「科学館学習がおもしろかった」、「おもしろくなかった」の回答で分け、この中で「理科の勉強が好き」など、理科に関する意識で肯定的な意識を持つ児童生徒がどのくらい存在するのかを比較することとした。つまり、 のそれぞれのグループで、更に「科学館学習がおもしろかった」、「おもしろくなかった」の回答で分け、この中で「理科の勉強が好き」など、理科に関する意識で肯定的な意識を持つ児童生徒がどのくらい存在するのかを比較することとした。つまり、 −1と −1と −2の比較、 −2の比較、 −1と −1と −2の比較を行い、それぞれ −2の比較を行い、それぞれ −1と −1と −1の方が多ければ、「理科の授業が分かる、分からない」に関係なく「科学館学習がおもしろい」と「理科の勉強が好き」との間には相関関係があると推察できる。 −1の方が多ければ、「理科の授業が分かる、分からない」に関係なく「科学館学習がおもしろい」と「理科の勉強が好き」との間には相関関係があると推察できる。
また、「科学館学習が分かった」、「分からなかった」についても、同様の方法で分析を行った。
この結果、「理科の授業が分かる、分からない」に関係なく、「科学館学習はおもしろかった」、「科学館学習が分かった」と回答した児童生徒の方が、「おもしろくなかった」、「分からなかった」と回答した児童生徒より、理科に関する意識が、4つの市の全設問において高くなっている。
さらに、それぞれの設問で(《表1》の 問1〜 問1〜 問11、 問11、 問6は除く)、「科学館学習はおもしろかった」と「おもしろくなかった」との差と、「科学館学習が分かった」と「分からなかった」との差を比較してみると、4市合計での40設問(1市当り10設問 問6は除く)、「科学館学習はおもしろかった」と「おもしろくなかった」との差と、「科学館学習が分かった」と「分からなかった」との差を比較してみると、4市合計での40設問(1市当り10設問 4市 4市 40設問)中、33設問(82.5パーセント)で「科学館学習はおもしろかった」と「おもしろくなかった」の差の方が大きくなっている。このことから、「科学館学習が分かった」ことよりも「科学館学習はおもしろかった」ことの方が、児童生徒の理科に関する意識との間により強い相関があると推察できる。 40設問)中、33設問(82.5パーセント)で「科学館学習はおもしろかった」と「おもしろくなかった」の差の方が大きくなっている。このことから、「科学館学習が分かった」ことよりも「科学館学習はおもしろかった」ことの方が、児童生徒の理科に関する意識との間により強い相関があると推察できる。
|
| 《表5》 |
普段の「理科の授業が分かる、分からない」にかかわらず、「科学館学習がおもしろかった」という意識と、「理科の勉強が好き」という意識との間に相関関係があるかどうかを分析する場合の一例 |
|
| 注) |
 −1、 −1、 −1の方が、それぞれ −1の方が、それぞれ −2、 −2、 −2、よりも多ければ、相関関係があるといえる。 −2、よりも多ければ、相関関係があるといえる。 |
|
《図3》は、京都市の一例として、児童生徒を「理科の授業が分かると回答した群、分からないと回答した群」に分け、「科学館学習がおもしろかったかどうか」別に「実験や観察が好き」な児童生徒の割合を表示したグラフである。なお、その他は、本文の資料7を参照。
|
《図3》実験や観察が好きな児童生徒の割合〈京都市〉
|
| (3)出雲市において、科学館学習を受ける前と受けた後のアンケート結果を比較したところ、科学館学習を受ける前より受けた後の方が、理科に関する意識が高くなっていた。特に、「科学館学習はおもしろかった」と回答した児童の方が、「科学館学習が分かった」と回答した児童よりも、理科に関する意識が高い。 |
|
出雲市では今回のアンケートを実施した時点で、科学館学習を受けていなかった小学校5年生が多数存在した。出雲科学館は平成14年7月(4年生の時)に開館しており、この学年の児童は、平成14年9月に1回科学館学習を受けている。そして、5年生になった後の平成15年10月の今回のアンケートを実施した時点では、一部の児童がまだ5年生での科学館学習を受けていなかった。その後、この一部の児童は平成15年12月と平成16年2月の2回科学館学習を受けた。
そこで、このような児童を対象にして、平成16年4月(6年生に進級後)に平成15年10月と同じアンケートを行った。1回目と2回目のアンケートの間の半年間にあった主な理科に関する行事は2回の科学館学習であり、この2つのアンケートの結果を比較することで、科学館学習が児童へ与える影響をより明確に推察できると考えられる。また、2回目のアンケートの実施が科学館学習の直後でないことから、このアンケートの結果は個別の科学館学習の効果というよりは、科学館学習を続けることによる意識の変化をより大きく表していると思われる。
対象となった児童は8校15クラスの442人で、回答はすべての学校からあり、回答した児童数は451人(1回目のアンケートの回答者数442人よりも多いのは、転校してきた児童や、何らかの理由で回答していなかった児童がわずかながら含まれているためと思われる)であった。
アンケートの結果を、5年生になってからの科学館学習を受ける前と後それぞれと全国平均を比較し、その割合をグラフにすると《図4》のようになった。 |
《図4》科学館学習の前後で、理科に関して肯定的な意識を持つ児童の割合〈出雲市〉
|
この結果、12の設問のうち8問で科学館学習を受ける前よりも受けた後の方が、意識が高くなっている。特に「理科の勉強で、実験や観察をすることが好きですか」の設問が、他の設問に比べより高く伸びていることは、科学館学習の中心が実験や観察であることを鑑みると、科学館学習の効果(学習と意識の因果関係)をより明確に示していると考えられる。
また、科学館学習を受けた後のアンケートの結果を、設問毎に「科学館学習が分かった」と回答した児童と「科学館学習はおもしろかった」と回答した児童を抽出し、その割合をグラフにすると《図5》のようになった。
このグラフの結果だけで明確に言えるものではないが、「科学館学習が分かった」とする児童よりも「科学館学習はおもしろかった」とした児童の方の意識が高くなる傾向がみてとれる。
これは、前述の(2)で述べた「科学館学習が分かった」とする児童よりも「科学館学習はおもしろかった」とした児童の方が、理科に関する意識との間に強い相関関係があるということと同様の結果となった。
このことから、科学館学習は理科の勉強を理解させることもさることながら、理科をおもしろく感じさせて興味を持たせることも重要であると考えられる。 |
《図5》科学館学習の後で、科学館学習が分かったか、おもしろかったかで分類
|
| (4)科学館学習を受けた後の理科に関する意識の変化は、女子の方が男子より全国平均との差が大きく上回っており、より多くの女子が科学館学習の影響を受けていると考えられる。 |
|
今回の調査と全国平均との意識の差を男女別で比較してみると《表6》のように女子の方が男子よりも、全国平均を上回る傾向が見られる。
理科に関する意識について質問した11の設問(《表1》の 問1〜 問1〜 問11)について、全国平均との差を具体的に見てみると、4市それぞれの学年数(須賀川市、真岡市、出雲市は小学校2学年、中学校3学年の計5学年、京都市は小学校2学年、中学校2学年の計4学年)に11(設問数)を掛けた延べ209学年のうち、女子の方が男子より全国平均との差が大きかったのは154学年(73.7パーセント)であった。また、小中学校別に見てみると、小学校では82学年(93.2パーセント)で女子の方が上回っており、中学校では女子の方が上回っていたのが72学年(59.5パーセント)あった。 問11)について、全国平均との差を具体的に見てみると、4市それぞれの学年数(須賀川市、真岡市、出雲市は小学校2学年、中学校3学年の計5学年、京都市は小学校2学年、中学校2学年の計4学年)に11(設問数)を掛けた延べ209学年のうち、女子の方が男子より全国平均との差が大きかったのは154学年(73.7パーセント)であった。また、小中学校別に見てみると、小学校では82学年(93.2パーセント)で女子の方が上回っており、中学校では女子の方が上回っていたのが72学年(59.5パーセント)あった。
|
| 《表6》男女別でみた4市のアンケート結果と全国平均との比較 |
(単位:延べ学年数) |
|
| |
須賀川市 |
真岡市 |
京都市 |
出雲市 |
計 |
| 小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
小学校 |
中学校 |
計 |
| 全延べ学年数 |
22 |
33 |
55 |
22 |
33 |
55 |
22 |
22 |
44 |
22 |
33 |
55 |
88 |
121 |
209 |
| 女子の方が上回った延べ学年数 |
22 |
29 |
51 |
19 |
19 |
38 |
21 |
12 |
33 |
20 |
12 |
32 |
82 |
72 |
154 |
| 男子の方が上回った延べ学年数 |
0 |
4 |
4 |
3 |
13 |
16 |
1 |
9 |
10 |
2 |
20 |
22 |
6 |
46 |
52 |
| 男女が同じだった延べ学年数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
3 |
|
| 注) |
理科に関する意識について質問した11の設問で、学年毎に男女別の4市のアンケート結果を男女別の全国平均と比較し、肯定的な意見の割合が全国平均に対して、より大きく上回っている性別の学年を数えた。また、全国平均よりも下回っている場合は、下回り方が少ない性別の学年を数えた。 |
|
《図6》は、須賀川市を例として、「理科の勉強は大切だと思う」児童生徒の割合の差を、男女別に全国平均と比較したものである。
《図6》男女別で見た今回のアンケート結果と全国平均の差(理科の勉強は大切だと思う)《須賀川市》
| |
小5 |
小6 |
中1 |
中2 |
中3 |
| 女子 |
84.0 68.6 68.6 |
83.8 61.7 61.7 |
68.8 51.2 51.2 |
65.2 51.3 51.3 |
75.0 52.0 52.0 |
| 男子 |
82.2 75.7 75.7 |
82.3 71.5 71.5 |
74.7 65.2 65.2 |
70.2 63.6 63.6 |
73.4 62.2 62.2 |
|
須賀川市( は全国平均)の男女別割合(%) は全国平均)の男女別割合(%) |
| 注) |
その他3市は、本文の図52、図53、図54、図55を参照。 |
|