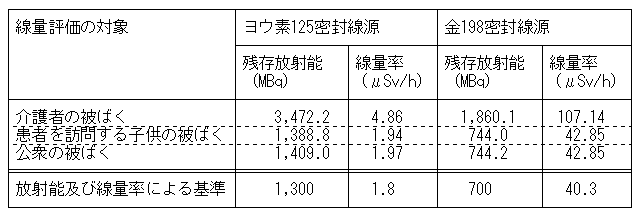(別紙1−参考)
退出基準の具体的内容(平成15年3月の厚生労働省課長通知)
| 放射能及び線量率の基準 医療法に基づいて診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者が病院内の診療用放射線照射器具使用室あるいは放射線治療病室等から退出する場合には、以下のいずれかの基準を満たさなければならない。
|
| 適用量または体内残存放射能(MBq) | 患者の体表面から1メートル離れた地点における1センチメートル線量当量率(μSv/h) | |||||
| ヨウ素125 金198 |
|
|
| 線源脱落の対策 ヨウ素125密封線源が、膀胱や尿道に脱落する症例は1%程度とされている。万一、膀胱や尿道への脱落が術中に確認された場合は、膀胱鏡により回収する。回収せず膀胱や尿道に脱落した線源は、翌日までに尿中(体外)に排出されるため、最低1日入院させ、この間に尿中に排泄された線源の有無を確認した後、帰宅させること。 金198密封線源は、治療部位によっては挿入された線源が脱落することがあるが、アンケート調査によると、全ての線源脱落は挿入後3日以内であった。したがって、線源挿入後少なくとも3日間は入院させ、脱落に十分備えること。 |
|||||||
患者への注意及び指導事項(医師により口頭及び書面による)
|
| ・ | 占有係数(Occupancy factor) 1m離れた地点に無限時間(核種が全て崩壊するまでの時間)滞在したときの積算線量と、実際に第三者が患者から受けると推定される線量との比
|
||||
| ・ | 外部被ばくの線量評価に用いる実効線量率定数 ヨウ素125:0.0014μSv・m2・MBq-1・h-1 (患者の組織・臓器による吸収を考慮し、点線源から1m離れた地点における見掛けの実効線量率定数(ヨウ素125の実効線量率定数は0.0124μSv・m2・MBq-1・h-1)) 金198:0.0576μSv・m2・MBq-1・h-1 (ガンマ線のエネルギーが比較的高く、挿入部位も主に頭頚部であり、組織、臓器による吸収は考慮に入れない) |
||||
| ・ | その他 密封線源であるため、内部被ばくは考慮しない、また、生体において代謝や排泄を受けないので、物理的半減期のみを適用する。 |