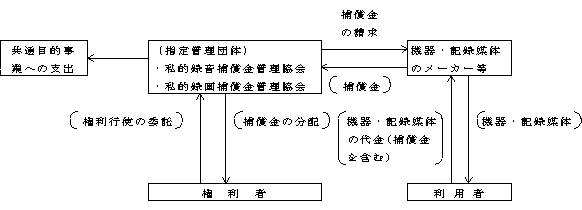ここからサイトの主なメニューです
 |
家庭内等における私的な複製については,例外的に,権利者の許諾なく行うことができるとされている(第30条第1項)。一方,デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い,著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため,平成4年の改正により私的録音録画補償金制度が導入され,家庭内等における私的な「コピー」であっても,デジタル方式による録音・録画を行った者は,著作権者等に対して補償金を支払うこととされた(第30条第2項)。
この場合,補償金の直接の支払義務者は,当該機器・記録媒体の購入者(消費者)であるが,当該機器・記録媒体の製造業者又は輸入業者には,補償金の徴収等についての協力義務が課せられている(第104条の5)。また,補償金の支払いの対象となる特定機器・特定記録媒体は,政令で指定された機器・記録媒体であって,主として録音・録画の用に供するものである(著作権法施行令第1条,第1条の2)。
補償金を受ける権利は,文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは,指定管理団体によってのみ行使することができ,指定管理団体が請求する補償金の額は,指定管理団体が定め,文化庁長官が認可を行い,支払われた補償金は,関係団体を通じて,権利者に分配されている(指定管理団体としては,録音については社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)が,録画については社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)が,それぞれ指定されている)。
指定管理団体が受け取った補償金は,著作権者等に分配されるが,補償金の2割に相当する額については,著作権者等全体の利益を図るため,著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等(共通目的事業)のために支出することとされている。
なお,専ら私的録音・録画以外の用に供することを証明できる場合は,補償金の返還を請求することができる(第104条の4第2項)。
【私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ】
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology