デジタル複製の技術は、元の著作物等の品質と同品質の複製ができること、記録媒体等の破損等の場合を除き何回利用しても品質が劣化しないこと、短時間に大量の複製物が作成できることなど様々な特徴を有する。
我が国で補償金制度が導入された平成4年以降、デジタル化・ネットワーク化の流れは加速し、それに伴ってデジタル複製が行われる機会が多くなってきたことから、権利者側の要求により、様々な著作権保護技術が導入され、無制限な複製等が制限されるようになってきた。
著作権保護技術は、後述するように必ずしも直接的に複製を制限する技術だけを意味しない。本小委員会では、著作権保護技術という用語を、何らかの方法により複製が実質的に制限される技術と捉え使用することとする。
なお、先述したように複製を制限する技術については、著作権法でも技術的保護手段(第2条第1項第20号)を定義し、当該手段を回避して複製することや当該手段を回避する装置等を製造販売等することを規制しているので、必要に応じ、技術的保護手段という用語も用いるが、著作権保護技術は技術的保護手段より広い概念と考え使用していることに留意する必要がある。
著作権保護技術は、技術の特徴によって大きく「フラグ検出型」と「暗号技術利用型」に区分される。
フラグ検出型の著作権保護技術は、基本的には複製等が自由にできるコンテンツ(例えば音楽CD)に複製制御フラグを付加し、複製機器が当該信号を検出し、反応することで複製を制限する方法である。
フラグ検出型の著作権保護技術は、当該技術が施されている複製機器しか複製等の制御ができないのが特徴である。
[フラグ検出型の著作権保護技術の概念図]
 |
| (出所:社団法人電子情報技術産業協会提供資料) |
暗号技術利用型の著作権保護技術は、コンテンツを暗号化し、そのままでは再生、出力、複製等ができないようにした上で、ライセンス契約により、利用者が復号に必要な鍵等を入手することにより、利用者側の機器での再生、出力、複製等を可能にする方法である。
フラグ検出型と異なり、ライセンス契約がないと複製等ができないのが特徴である。
暗号技術利用型の著作権保護技術は、復号鍵のライセンス契約の内容に様々な条件を付すことが可能である。例えば、相手先の機器が著作権保護技術に対応しているものであればデータを出力し、それ以外は出力不可にするなど、複製の制御以外に様々な条件を付加してコンテンツの利用を制御できる。
なお、暗号技術利用型の著作権保護技術は、次のような制限を暗号化してコンテンツに付加することが可能である。
| 制限の種類 | 制限の内容 |
|---|---|
| 複製の制御 |
|
| 転送・出力の制御 |
|
| 再生の制御 |
|
[暗号技術利用型の著作権保護技術の概念図]
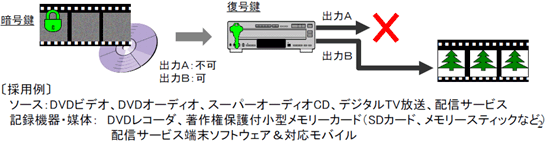 |
| (出所:社団法人電子情報技術産業協会提供資料) |
(参考1)著作権保護技術の例
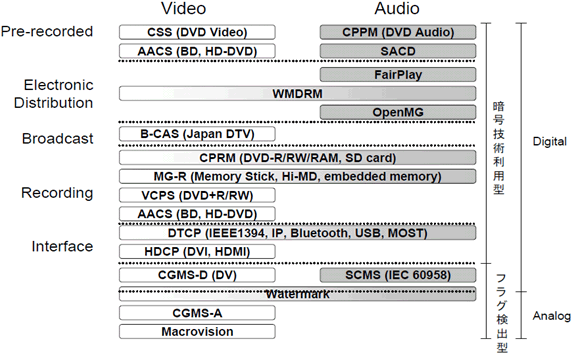 |
| (出所:社団法人電子情報技術産業協会提供資料) |
(参考2)著作権保護技術採用の歴史
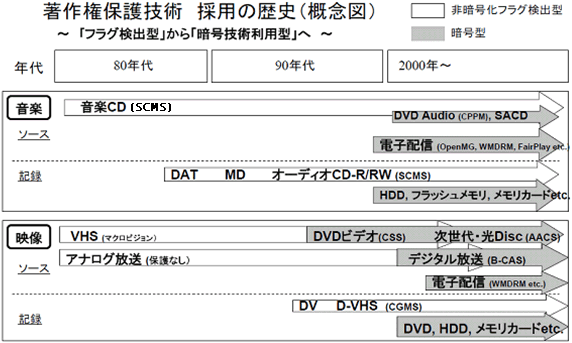 |
| (出所:社団法人電子情報技術産業協会提供資料) |
現在、音楽パッケージとして流通しているもののほとんどは、音楽CD(Compact Disc)であるが、音楽CDにはデジタル録音に係る著作権保護技術として、SCMS(注1)という技術(前述のフラグ検出型)が採用されている。
例えば、この技術が採用されている場合、MDレコーダーでは、音楽CDデータをMDに1世代までコピーすることはできるが、録音したMDデータをさらにMDへ録音することはできない仕組みになっている。
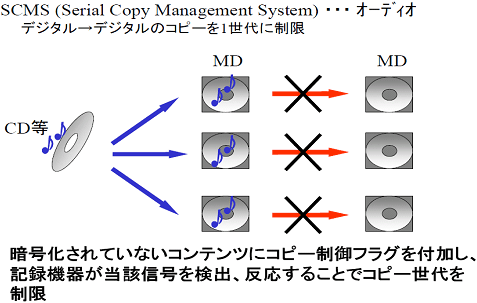 |
| (出所:社団法人電子情報技術産業協会提供資料) |
音楽CDについては、上記のように、DAT、MD、CD−R等の録音機器において一定の複製制限が行われているが、そのような方式が採用されていないパソコンや携帯用オーディオプレーヤー等については、複製制限はなく自由に複製等を行うことができる。
なお、1990年代半ば以降、パソコンの普及により、音楽CDデータ(音楽)をパソコンへ取り込み再生して楽しむことが可能になり、ファイル交換ソフトを経由して音楽CDデータを複製するなどの事例が増加したため、パソコンでの音楽CDデータの複製を制御する技術として、平成14年から一部のレコード会社がコピーコントロールCD(CCCD)(注2)を導入した。
しかし、CCCDは、一部のOSで意図した効果が発揮されなかったことや一部のCDプレーヤー等で正常に再生されない場合があったことなどから、現在では、CCCDを発売しているレコード会社はない。
音楽CDは、現在においても音楽パッケージビジネスの中心的商品であり、平成18年には、約1億8千万枚のアルバムが市場に出荷されている。
このうち、約1億7千万枚の音楽CDがセル用に出荷されており、残りの約1千万枚はレンタル事業者へ提供されている。
<CDアルバムの出荷枚数>
| (単位:百万枚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| (社団法人日本レコード協会提供資料を元に作成) |
音楽CDに続く次世代オーディオとして期待されているスーパーオーディオCDは平成11年から、DVDオーディオは平成12年から発売されている。
このようなパッケージについては、先述の暗号技術利用型の著作権保護技術を採用しているが、現在のところ余り普及しているとは言えない。
<スーパーオーディオCD、DVDオーディオの出荷枚数>
| (単位:千枚) | ||||||||||||||
|
|
| (社団法人日本レコード協会提供資料を元に作成) |
音楽配信ビジネスでは、著作権保護技術を採用していないものも存在するが、主要なサービスにおいてはほとんどの場合、何らかの著作権保護技術を採用している。
代表的な音楽配信の著作権保護技術としては、iTunes Storeで採用されているFairPlay、MORAで採用されているOpenMG、その他多数のサービスで採用されているWMDRMなどがある。
これらの著作権保護技術では、パソコンや携帯用オーディオプレーヤーへの複製回数などがあらかじめ決められているサービスもあるし、コンテンツの提供者が自由に設定することが可能なものもある。
ちなみに、コンテンツホルダーであるレコード会社が配信事業者のサービスで選択している著作権保護技術の内容は次のとおりである。ただし、iTunes Storeについては、選択の幅がほとんどないのが現状である。
<音楽配信事業におけるコピー制限ルールの例>
| (平成18年4月時点) |
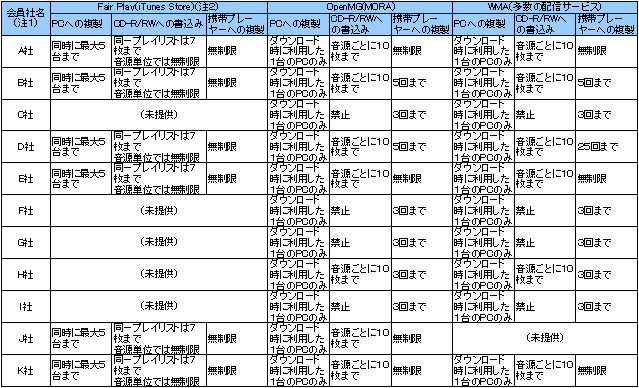 |
|
| (出所:社団法人日本レコード協会) |
我が国の音楽配信ビジネスは、約1,500事業者(注13)が事業展開をしていると言われているが、配信デバイス、課金方法、著作権保護技術などにより様々なサービスが存在する。
配信デバイスとしては、パソコンへの配信、携帯電話への配信、専用機器への配信などがあり、課金方法としては、コンテンツごとの課金モデル、会費制(サブスクリプション)モデル、無料モデルなどがある。
特に、我が国では、「着メロ」「着うた」「着うたフル」に代表される携帯電話への配信が発達している。
<有料音楽配信の売上実績>
| 2005年/2006年 有料音楽配信売上実績(年間) |
| 社団法人 二日本レコード協会 |
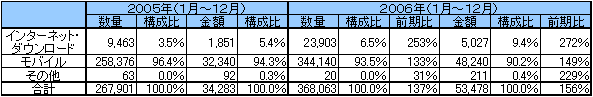 |
現在、映像パッケージとして流通しているものはビデオカセットとDVDがある。
ビデオカセットについては、多くの場合、著作権保護技術としてマクロビジョン(注14)と呼ばれる技術が採用されており、この技術が施された映像を複製し再生した場合、映像が乱れて映し出される仕組みになっている。
一方、DVDには、マクロビジョンのほか、CGMS(注15)やCSS(注16)と呼ばれる著作権保護技術が複数施されている。
CGMSは、映像データの複製世代を管理する技術で、「コピー可」「1世代までコピー可」「コピー不可」のいずれかの信号に機器が反応して録画を制限する技術である。
また、多くのDVDには、CSSと呼ばれる著作権保護技術が施されており、映像信号に暗号がかけられているため、復号に必要な鍵を有する機器しか再生できない仕組みになっている。
現在、販売用の映像ソフトはDVDが主流になっている。レンタル用の映像ソフトについてもDVDが中心になりつつあるが、旧作の映画は現在でもビデオカセットが用いられている。
商業用の映画については、現状では、マクロビジョンやCGMS、CSSなどの著作権保護技術の仕様にかかわらず、多くの場合、複製は禁止で運用されている。
<ビデオカセット・DVD(セル・レンタル)の売上の推移>
(単位:億円) |
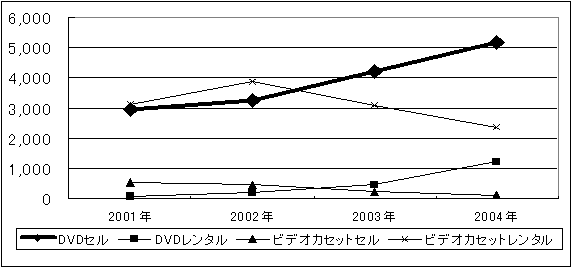 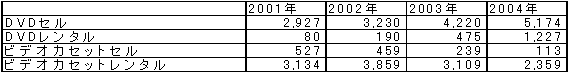 |
出所:財団法人デジタルコンテンツ協会 「デジタルコンテンツ白書2005」
|
映像配信ビジネスは、約400事業者(注17)が事業展開をしていると言われているが、視聴用機器の種類等により著作権保護の特徴が異なっている。
セットトップボックス(STB)を介してテレビで視聴する場合は、マクロビジョンなどのフラグ検出型の著作権保護技術や、デジタル伝送路の規格に対応したHDCP(注18)と呼ばれる暗号型の著作権保護技術が採用されており、STB側で復号する仕組みになっているため、外部機器への録画等は原則禁止されている。
パソコンによる視聴の場合についても、HDCPによる著作権保護技術が採用されており、ソフトウェア側が暗号化された信号を復号して再生する仕組みになっている。
また、モバイル機器による視聴の場合は、現在のところ、選択した機器のみ再生が可能な仕組みであり、当該機器でダウンロードしたものからの録画はできないものがほとんどである。
<映像配信サービスの特徴>
| 視聴用機器 | サービスの特徴 | 外部機器への録画等 |
|---|---|---|
| セットトップボックス(STB)利用型 | ストリーミング配信が中心 | 原則禁止 |
| パソコン | ストリーミング配信が中心
|
原則禁止 |
| モバイル機器 | ダウンロード配信が中心 | 原則禁止 |
映像配信サービスは、STB、パソコン、モバイル機器などの視聴用機器ごとに配信サービスが異なっている。課金方法については、コンテンツごとの課金モデル、会費制(サブスクリプション)モデル、無料モデルなどがある。
現在の映像配信サービスは、ストリーミング配信が中心であるが、最近では、再生期限付きのダウンロード配信も登場している。
一方、携帯電話等のモバイル機器による視聴の場合は、当該機器からパソコンや他のモバイル機器への転送を制限している場合が多く、配信されるコンテンツが複製される可能性が少ないことから、ダウンロード配信のビジネスモデルが発達している。
<映像配信にかかる売上の推移>
| (単位:億円) |
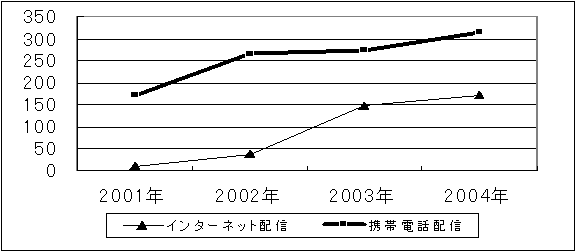 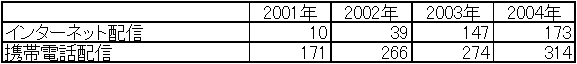 |
| (出所:財団法人デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書2005」) |
地上デジタル放送においては、現在、著作権保護方式として、いわゆる「コピーワンス」ルールが適用されている。
この方式は、BSデジタル放送において、放送番組などの不正コピーを防止するため、平成16年(2004年)4月から導入された著作権保護方式で、録画した放送番組をオリジナルを残したまま複製することはできず、移動(ムーブ)のみ可能とするルールである。
具体的には、放送番組をハードディスクレコーダーに録画し、その後、DVDディスク等の他の記録媒体に複製した場合、オリジナルの番組は消去される仕組みになっている。
また、放送番組をDVD等の記録媒体に録画した場合、直接録画した媒体は再生することはできるが、それをさらにコピーすることはできない。
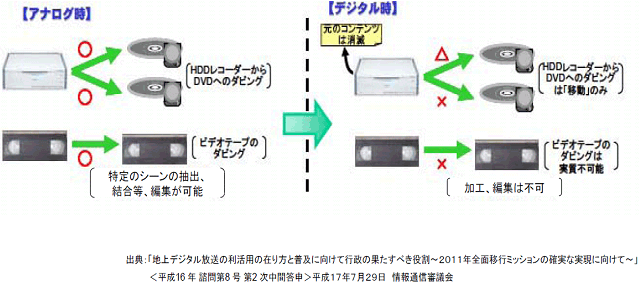
現行の「コピーワンス」ルールについては、録画の制限が厳しすぎる、視聴者が「ムーブ」に失敗すると、オリジナルの放送番組が使用不能になるなどの指摘があったことから、平成18年9月、総務省の情報通信審議会情報通信政策部会に「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(主査:村井純(慶応義塾大学教授))」が設置され、現行のデジタル放送の著作権保護方式である「コピーワンス」の運用改善等について検討が進められ、平成19年8月、当該検討委員会の検討を踏まえ、同審議会が中間答申を行った。
中間答申では、検討委員会の議論の経緯を紹介した上で、審議会としての共通認識を以下のとおり得たとした。
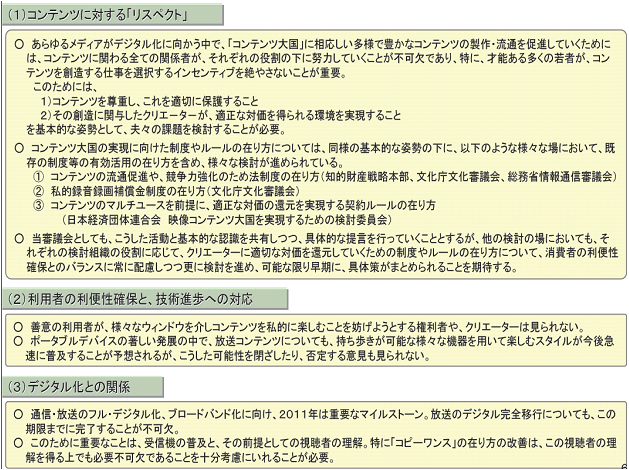
(出所:−デジタル・コンテンツの流通の促進−地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政が果たすべき役割<平成16年諮問第8号 第4次中間答申>(概要版)情報通信審議会)
改善策の方向性としては、「COG(Copy One Generation)の考え方の適用+一定の制限」が適当とし、具体的な回数を決めるにあたっては、次の考え方を考慮すべきとされた。
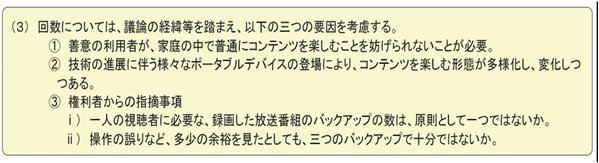
(出所:−デジタル・コンテンツの流通の促進−地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政が果たすべき役割<平成16年諮問第8号 第4次中間答申>(概要版)情報通信審議会)
具体的には、デジタル・チューナーとハードディスク等が同一筐体の場合、ハードディスク等にCOGで録画された放送番組については、同一筐体内のDVD等への出力や、外部機器への出力におけるコピー回数を9回までとし、最後の10回目のコピーを行った場合、ハードディスク内のオリジナルは消去される取り扱いとする考え方である。
今後の取り組みとして、今回の「コピーワンス」の運用改善が、海賊版の違法流通を助長しないよう、行政、放送事業者、受信機メーカー、消費者などの関係者が連携・協力して周知広報活動に努めることや、デジタル技術の急速な進展に対応するため、今回の運用改善を暫定的なルールとすること等を配慮すべき事項としつつ、放送事業者や受信機メーカーなどの関係者においては、同審議会の提言を踏まえた取組を可能な限り早期に実現するよう要請している。
CS放送などの有料放送では、番組ごとに、コピーワンスやCOGなどの著作権保護技術を選択することが可能であるが、現在は、「コピーワンス」ルールが採用されている場合が多い。