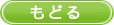| (1) |
著作権侵害の結果を惹起する機械や道具を提供し、直接侵害が行なわれた
場合に、その提供行為が著作権の間接侵害行為として違法であるとの評価は最近の最高裁判決により、わが国の判例法上確立したといえる。
 |
平成13年2月13日 最3小判「ときめきメモリアル事件」 |
 |
平成13年3月 2日 最2小判「ビデオメイツ事件」 |
|
| (2) |
しかしながら、著作権等の侵害行為に対して最も有効でかつ優先的に構ずべき措置は、当該侵害行為の停止または予防であるが、間接侵害者に対する差止請求権を正面から扱った最高裁判決は未だ存在しない。 |
| (3) |
著作権等の侵害事件が日常的に継続している現状に鑑みて、間接侵害者に対しても、差止請求権が認められるべきことを確認的に明らかにする意義は大きいものと考える。 |
| (4) |
本年5月27日に施行された、いわゆる「プロバイダ責任法」もプロバイダに対する差止の可否について規定していないが、総務省の逐条解説によれば「侵害される権利の性質等に応じ、当該権利について規定する法律に則ってそれぞれ個別に判断されることになる」としている。 |
| (5) |
また、東京地裁平成14年6月26日の「2ちゃんねる事件」判決では、電子掲示板の管理者に対して、人格権としての名誉権に基づく削除請求を認容している。 |
| (6) |
なお、「ときめきメモリアル事件」も末端ユーザーによる直接侵害行為を前提としているが、「専ら著作物の改変のみに使用される機器を製造・販売する行為」のような、著作権侵害に直結するような行為については、直接侵害行為を前提としない、独立した間接侵害行為としての規定の創設も必要ではないか。 |