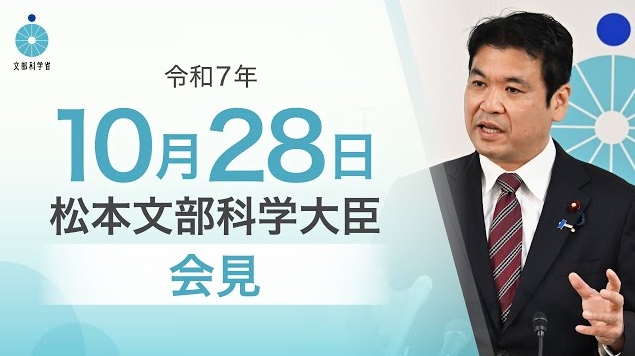- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > 松本洋平 文部科学大臣の会見 > 松本洋平文部科学大臣記者会見録(令和7年10月28日)
松本洋平文部科学大臣記者会見録(令和7年10月28日)
令和7年10月28日(火曜日)
教育、科学技術・学術、文化
キーワード
H3ロケット7号機の打上げ成功、熊に対する児童生徒等の安全対策、理化学研究所における「雇い止め」訴訟、給食費の無償化に向けた対応、文化審議会答申を受けた重要無形文化財の対象における「生活文化関係」の新設、児童生徒の読書時間の確保
松本洋平文部科学大臣記者会見映像版
令和7年10月28日(火曜日)に行われた、松本洋平文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年10月28日松本洋平文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
松本洋平文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件申し上げます。26日、H3ロケット7号機によります新型宇宙ステーション補給1号機「HTV-X1」の打上げに成功をいたしました。今回は、H3ロケットの中でも最も打上げ能力の大きい24形態で初めての打上げとなりました。また、H3ロケットは今回の打上げを持ちまして5機連続での打上げ成功となったところでもあります。今回打上げられたHTV-X1は国際宇宙ステーションへの物資補給を担うとともに、飛行中の技術実証ミッションを実証することによりまして新たな技術の開発などに貢献することを期待しているところであります。今後とも、H3ロケットの打上げ実績を積み重ねまして信頼性向上やコスト低減に向けた着実な開発・運用を進めることで国際的な信頼を獲得し、国際競争力を強化して我が国の宇宙開発利用に、宇宙開発利用の発展に大いに貢献できるように尽力をしてまいりたいと存じます。個人的には大変ほっとしたというところであります。ただ、HTV-X1が今、ミッションを継続中でありますので、こちらのほうの成功をしっかりと実現をするために見守ってまいりたい、サポートしてまいりたいと思います。以上です。
記者)
全国で熊の出現が相次いでいます。先日、秋田県の県立高校の敷地内にも侵入し、他の地域でも保護者に送迎を依頼したり、屋外での部活動を禁止するなど、学校での対応が必要な状況となっていますが、文科省として子供や教員の安全確保のための取組を検討していたら教えてください。
大臣)
今御指摘がありましたとおり、学校敷地内における熊の出没など、児童生徒等の安全を脅かす事案が発生をしていることは承知をしているところでもあります。また、これまで熊が出没をしていた場所とは違うところでこういう事案が起きているということに対しましても、加えて大変憂慮をしているところであります。学校におきましては、児童生徒等の安全確保のための危機管理マニュアル等を、作成をし、これを踏まえて対応することとなっているところでありますけれども、御指摘の秋田県内を含めまして熊の出没が想定される地域におきましては、一般的に危機管理マニュアルにおいても熊の出没に対する対応が記載されていることが既に多くあり、また児童生徒に対する熊が出没した場合の訓練なども行われているというふうに承知をしているところであります。ただ、先ほども申し上げましたようにこれまで出没していた場所とは違う場所で熊の出没があるということであります。獣害による被害が深刻になっているところもありますので、まずはこうしたこれまでそうした経験がある地域の事例、また環境省による熊出没時の対応に対する知見などにつきまして他の地域にも情報提供を行うなどについて検討しているところであります。文部科学省として、引き続き児童生徒等の安全確保に向けた必要な取組を進めてまいりたいと存じます。私からは以上です。
記者)
理化学研究所の研究者の男性の雇い止め訴訟につきまして、10月10日付で理研と男性側で和解が成立しました。理化学研究所も朝日新聞の取材に対して労働契約に際してのコミュニケーションが不十分だったとして遺憾であるというふうなことは示していますが、理化学研究所を所管する文部科学省として本件和解や訴訟に至った経緯についての所感を教えてください。また、学会のアンケートなどでも研究者の安定した雇用環境が重要という指摘がずっと続いています。子供や若い学生がぜひ研究者になりたい、博士課程に進みたいと思える環境づくりについて文部科学省としての施策と意気込みを教えてください。
大臣)
御指摘の件に関しましては、今お話がありましたとおり、和解に至ったものと承知しておりますけれども、当事者ではございませんのでコメントは差し控えさせていただきたいと思います。理化学研究所におきましては、労働関係法令に基づきまして引き続き適切な人事の運用を行っていただきたいと考えております。また、我が国の研究力強化に向けましては優れた人材の育成と確保が極めて重要であります。そのため、具体的には優れた研究者や技術者の活躍促進に向けた研究費や安定的なポストを充実・確保していくということ、また博士課程学生の経済的支援や次世代の科学技術を担う児童・生徒の育成などが挙げられると思っております。文学科学省といたしましては、今後、優れた科学技術人材を育成・確保し、その活躍促進に向けて関係機関と連携をいたしまして全力で取り組んでまいりたいと存じます。
記者)
給食無償化について伺います。現在、詰めの作業をしていることと思いますけれども、物価高が続く中で無償化の予算確保だとか実施方法など、改めて進捗状況ですとか対応策、所感などがあれば教えてください。
大臣)
これもかねてからお答えをさせていただいておりますけれども、今年の春の3党合意、そしてこの度の自民・維新によります連立合意、この中でも来年の4月からの給食の無償化実施ということが書かれているところであります。これに基づきまして、今それぞれの党におきまして議論が進められているというような状況だというふうに承知をしているところでもあります。小学校給食無償化を令和8年4月から実施するため、残る課題を整理し制度設計を確定させるというふうにその合意の中ではされているところでもありますので、その議論というものをしっかりと進めていただきたいと思っておりますし、我々といたしましても党における議論と並行して必要な準備というものはできるように進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。なお、この各政党間によります協議の進捗につきましては、ちょっと私のほうからお答えをすることはできませんので、そちらのほうを我々としてもしっかりと見守りながら、何とかこの合意に書かれている事項を守っていくことができるように我々としても対応をしてまいりたいと思います。
記者)
文化審議会が24日に開催されて、重要無形文化財を対象に生活文化を新設すべきとの方針が出されました。同時に、この分野の技を高度に体得するいわゆる人間国宝の認定基準も示しました。認定されたら一転、関心が高まるのかなと思うのですけれども、料亭などが急激に減っていく中で日本の伝統的な食文化の保護に向けて文科省としてどういうふうに取り組んでいくかお願いします。
大臣)
これまでも「生活文化」分野につきましては、令和3年に新設をされました登録無形文化財制度によりまして、登録を進めてきたところでもありまして、これまでに「書道」、「伝統的酒造り」、「京料理」など計6件を登録いたしまして保護・継承を図ってきたところでありますけれども、今回、24日に文化審議会から重要無形文化財指定制度に「生活文化」を加えるということについて答申をいただいたところであります。この過程におきましても、学術的調査も積み重なり特に優れた「わざ」に関しまして国による強い保護等の措置が必要と思われるケースが散見されてきたということだと承知をしております。こうした状況も踏まえまして、この度の答申が出されたものと承知をしておりまして、今般の指定の対象拡大を通じて文部科学省として食文化を含む生活文化分野のさらなる保護・継承を図ってまいりたいと存じます。指定基準などの改正に向けましては今後、意見公募手続なども踏まえまして改正の作業を進めていくということになります。また、いわゆる「人間国宝」の認定に向けましては生活文化分野の重要無形文化財の指定に相当する「わざ」について調査研究を進めることとしております。ですので、現時点でスケジュールについて確たる時期を申し上げられるものではありませんけれども、こうした答申を踏まえ、また制度を作っていくことによって先人たちが残してきたそうした優れた文化や技というものをこれからも継承していくことができるように文部科学省といたしましても後押しをしてまいりたいと存じます。
記者)
今週から読書週間が始まりました。ベネッセと東京大学の調査で読書をしない子供たちが増えているという結果が出たのですけれども、文科省でも全国学力テストの際に家にある本の冊数とテストの結果に一定の相関があるというような話も出ました。大臣として、子供と読書の関係についてどうお考えになるのか教えてください。
大臣)
今御指摘をいただきましたとおり、今回、ベネッセさんが行った調査によりまして1日の中で読書を「しない」という回答が50%を超えていたということであります。また近年、類似の調査をいたしましても大体同様の結果が得られているということであります。個人的には私、小さいころから本を読むのがものすごい大好きだった人間なので結構衝撃を持ってこの結果というものを受け止めているところであります。今お話がありましたように、子供の読書活動というものは言葉の学びであったり、感性を磨く、また表現力を高める、創造力を豊かなものにしていく、いろいろな意味で大変人生において重要なものだというふうに思っておりますし、また読書に興味や関心を持っていただくような取組を推進するということは大変重要なことだというふうに承知をしているところであります。文部科学省におきましては、第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」、これは令和5年度から令和9年度の5年間でありますけれども、こちらの計画を作り、そしてそれを踏まえて読書活動の先導的なモデル事業や子供の読書活動を推進するための優れた取組の表彰、図書館と学校図書館、書店を含む地域の様々な関係機関の連携、協働による読書を通じたまちづくりを推進する取組、これらを、実施をしているところでもあります。いろいろと調査の結果を見てみますと、やはりスマホだったりにちょっと取られる時間のほうが増えてしまって結果的に読書の時間が減ってしまっているのではないのかというような話もありますけれども、学校での教育現場の中、教育を通じてそうした読書の素晴らしさというものをまずはしっかりと子供たちに知ってもらうということが極めて大切なことではないかと思っておりますので、そうした取組、現場の声をしっかりとお聞きをしながら進めていくことができるようにしていきたい、そのように思っておりますのでどうぞよろしくお願いをいたします。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室