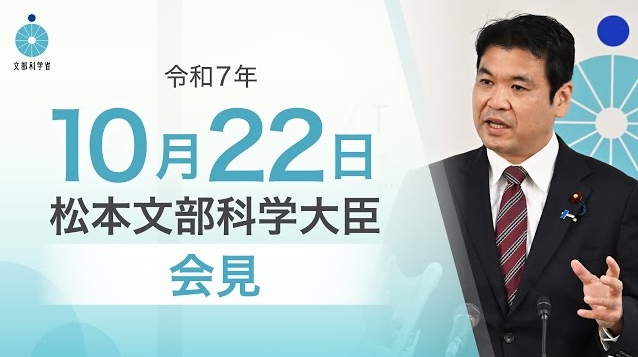- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > 松本洋平 文部科学大臣の会見 > 松本洋平文部科学大臣記者会見録(令和7年10月22日)
松本洋平文部科学大臣記者会見録(令和7年10月22日)
令和7年10月22日(水曜日)
教育、科学技術・学術、スポーツ、文化、その他
キーワード
文部科学大臣就任,大臣としての抱負と特に力を入れたい政策,文部科学行政の喫緊の課題,これまでの人生で印象に残っている教師との出会い及びこれからの教師の在り方,教育勅語に対する見解,給食無償化の進め方,南京事件に対する見解,高校無償化による専門高校を含む公立高校への影響,旧統一教会との関係性及び旧統一教会への今後の対応,科学技術で特に力を入れたい政策、先端技術の研究、基礎研究力の低下に対する見解,原子力をはじめとするエネルギー研究に関する施策の進め方
松本洋平文部科学大臣記者会見映像版
令和7年10月22日(水曜日)に行われた、松本洋平文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年10月22日松本洋平文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
松本洋平文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)、
この度、文部科学大臣を、拝命をいたしました松本洋平です。文部科学省が担う分野というのは大変多岐に渡ります。また、大変重要な分野ばかりであります。教育、科学技術・学術、そしてスポーツ、文化芸術は次世代に向けて豊かな未来を創造し、つないでいく重要な分野であるというふうに認識をしているところであります。それぞれの現場の皆さんのお声というものをしっかりとお聞きをし、そして受け止めながら文部科学行政をしっかりと前に進めていくことができますように全力を尽くしてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いをいたします。
記者)
改めてにはなりますけれども、大臣就任にあたっての抱負と文部科学行政を取り巻く課題意識、また特に力を入れたい政策等についてお願いいたします。
大臣)
先ほども申し上げましたが、文部科学行政は大変重要な分野でありますし、また多岐にわたる分野であります。例えば、教育に関して言えばまさに人づくり、我が国の礎になる分野でもあります。我が国におけるどのような事柄も全ては人が一番の基礎になって行われるものでありますから、そういう意味ではここの部分をしっかりと文部科学行政として後押しをしていくということは極めて重要な部分だと思っております。科学技術分野におきましても、我が国の経済競争力の発展、社会課題の解決、こうした分野の基礎になっていくものでありますから、これらもしっかりとやっていかなければなりません。文化の分野につきましても当然、我が国の、そして国民の皆さん一人一人のアイデンティティの根源でもありますし、また同時に最近は、コンテンツ産業なんかは稼ぐ力にもつながっていくような、そういう分野でもあります。スポーツ分野につきましても、人々に夢や感動を与えるだけではなくてスポーツを身近に触れる環境をしっかりと作っていくということは青少年の健全育成、そして高齢者を始めといたしましたそうした皆さんの健康増進、いろいろな意味で本当に重要なそうした取組でもあります。こうしたところを私自身、しっかり所管をする大臣といたしまして皆様方のお声、特に現場のお声というものをしっかりとお聞きをいたしながら課題の解決を進めていくばかりではなくて、それぞれの皆さんが持てる可能性をしっかりと発揮をされ、そして可能性を広げ、そしてそれぞれの皆さんが豊かに生活をしていくことができるような、そうした環境づくりにぜひ私自身、邁進をしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いを申し上げたいと思います。
記者)
先ほど抱負がございましたが、文部科学行政の喫緊の課題というのをどのように捉えていらっしゃいますか。それに対してどのように対応されていくか、教えてください。
大臣)
この文部科学大臣に就任する以前、と言っても一昨日までということになるわけでありますけれども、政務調査会の副会長兼事務局長というお役目をいただきまして仕事をしてまいりました。また同時に、その中の一つの仕事といたしましていわゆる自公維、三党協議、教育分野における三党協議の現場にも入らせていただいて、そうした様々な協議の過程の中で仕事をさせていただいたところでもあります。そういう意味では、今後、まだまだ議論が今も継続をしているわけでありますけれども、高等学校等就学支援金制度の拡充、また高校改革を推進するための取組というものを一つの大きな柱になるというふうに私自身、考えているところであります。また、先ほどお話をさせていただきましたように教育の分野、また科学技術・学術、文化芸術、スポーツ、それぞれ様々な課題があるというふうに存じているところであります。これから前大臣との引継ぎは今日の午後予定をされているところでもありますので、前大臣が一生懸命やってきた内容、またやり残していると感じているような内容も私自身、これからしっかりと受け止めをしてまいりたいと思いますし、またできる限り私自身の方針として現場に足を運んで皆さんからいろいろとお話を聞かせていただく、そんな取組も通じてぜひ私としてはやはり文部科学行政が進んだことによって国民であったり様々な人々が実感できるというか、手触り感のあるような、そういう文部科学行政を何とか進めていくことができればというふうに思っているところであります。文部科学省の皆さんと一緒になってそんな思いを共有しながらこれから大臣として仕事を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
記者)
大臣にとってこれまでの人生の中で印象に残っている教師との出会いはありますでしょうか。時代の変化が激しい中で働き方を含め、子供や保護者への接し方など、これからの教師の在り方をどのようにお考えになっているのか、全国への教師にメッセージがありましたら合わせてお願いできればと思います。
大臣)
まず、私自身の先生とのエピソード、思い出に残るエピソードでありますけれども、もちろんいくつかの場面で様々な先生方とのエピソードがあります。部活を指導してくださった先生だったりとか、また担任の先生だったりもあるのですけれども、ちょっと私からせっかくなので御紹介をしたいのは私が保育園時代の話になります。当時、保育園の園庭で泥んこになって駆けずり回って、走り回って遊んでいたわけでありますけれども、そのときに思わず園長先生にぶつかってしまって、園長先生が持っているカメラがパタッと落ちてしまった瞬間があったのです。まだ小さい子供ながらにこれは大変なことをしてしまったなというのを自分なりにすごく感じて、やはり園長先生のところに行くのがすごく怖かったときになかなか謝りに素直に行けなかったのですね。もじもじしてしまって。どうしたらいいのだろうという思いもあって、そういうこともあったときにそれこそ先生がずっと寄り添っていただいていろいろとお話を聞かせていただいて、こういうときはきちんと謝りに行きなさいということをすごく丁寧におっしゃっていただいて、園長先生のところに勇気を持って謝りに行ったという経験がすごく印象に残っております。もしあの経験がなければ私は今この場に立っていないだろうなと思うぐらい、実は小さいエピソードかもしれないですけれども、そんなところから自分自身というのはいろいろなことを学ぶことができましたし、自分自身の人間形成にはあのときの一つの、小さい経験かもしれないけれども、それが大きかったなということをすごく感じています。そうした私自身の経験も踏まえまして、やはり教育というものはものすごく重要な役割を持っている、それはもちろん子供の学力という面でももちろん大切な役割を担っているわけでありますけれども、社会生活を学んだり、また人間形成における重要な経験をしたりというのがまさに学校現場でありますし、それらを、指導をしていただいているのが先生ということになるのだと私自身、思っているところであります。そういう意味で、今いろいろと私も地元の学校の先生なんかともお話をする機会がありますが、やはり今は教師が不足をしていてすごく大変だというようなお話、また仕事面でもいろいろな御苦労をされたりというようなお話を聞かせていただいているところでもありまして、ぜひそういう意味では改めて教師という仕事の尊さというものを皆さんが実感をしていただくことができるように、また同時に「働きやすさ」であったり「働きがい」、そういうものを感じていただくことができるような、そうした先生方の環境整備というものも私たちが進めていく上においては極めて大事なことだと思います。そして、それは教師の、先生のための施策ではなくて、それを実現することによって実際に教育を受ける子供たちであったり学生さんたちに結果としてそれはしっかりと伝わっていく、そういうものだと思っておりますので、そうした取組を私自身、邁進して進めてまいりたいと思います。
記者)
高市首相の教育観に関連してお伺いをしたいと思います。高市首相は過去にホームページのコラムで教育勅語を現代においても尊重するべき正しい価値観と記すなど、教育勅語に肯定的な姿勢を示してきました。高市内閣の一員として文部科学大臣に就任されたわけですけれども、こうした姿勢はこれからの文科行政に反映されるのでしょうか。あと、合わせて教育勅語に対する大臣御自身のお考えをお聞かせください。
大臣)
高市総理御自身のホームページにそうした記載があるということは承知をしているところでありますが、その趣旨等について私自身が直接話をしたりして承知をしているわけではありませんのでコメントは控えさせていただきたいと存じます。その上で、教育勅語は日本国憲法及び教育基本法の制定などを持ちまして法制上の効力が喪失しているというふうに考えております。その内容について政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますし、私も文部科学大臣としてそうした形でコメントは差し控え、私自身のコメントというものは差し控えさせていただきたいと思います。いずれにいたしましても、この方針に則ってやってまいりたいと思います。
記者)
給食の無償化について伺いたいのですけれども、連立合意でも令和8年4月から小学校無償化に向けて制度設計を急ぐということですから、自公維の3党合意で中学校も迅速に進めていくというスタンスだったと思うのですけれども、中学校のほうも引き続き進めて行く考えに変わりはないのか、また給食費無償化等に関して総理大臣のほうから何か指示を受けていらっしゃったら教えてください。
大臣)
給食の無償化につきましては、三党合意の中でも述べられているとおりでもありますし、またこの度、自民党また日本維新の会の連立政権の合意書の中におきましても小学校給食無償化を令和8年4月から実施するため残る課題について整理をし、制度設計を確定させるというふうに記述をされているというふうに承知をしているところであります。そういう意味では、これに基づいて与党の中におきましても議論が進んでいくものと承知をしております。それらとしっかりと我々といたしましても連携をしながら、必要な準備というものを進めてまいりたいと思います。また、中学校給食に関しましては三党合意の中ではそうした記述があるということは承知をしているわけでありますけれども、ただそこについての今後の道筋というものは特にまだ示されていないふうに承知をしているところでもあります。そこに関しましては、まずは政党間、与党間で自民、公明、維新の三党協議の枠組みの中でこれからも議論がされていくものというふうに承知をしておりますので、そちらの意見というものも参考にさせていただきながら我々としても考えさせていただきたいと思っております。
記者)
大臣は過去に南京事件はなかったと解釈される映画「南京の真実」の賛同人をされています。政府は過去に閣議決定で南京事件はあったとの立場を取っており、文科省が所管する教科書行政においても閣議決定に沿った内容とするよう検定を行っていることかと思います。南京事件に関する大臣の認識を教えてください。また、教科書認定や現在発行されている教科書についても大臣の御意見があれば教えてください。
大臣)
お尋ねの点につきましては、外務省のホームページに掲載されている見解のとおりであります。その見解というものを歴代内閣で一貫して引き継がれてきた、そうした気持ちというものを私自身引き継いでしっかりとやってまいりたいと思います。また、教科書検定につきましては静謐な環境で、そしてどの教科書がふさわしいのかということは議論をされた上で教科書選定というものは進んでいるというふうに承知をしているところでありまして、こうした環境をしっかりと引き続き守っていくということかと思っております。
記者)
高校無償化について伺いたいのですが、農業高校など地方の高校への影響が懸念されている中で大臣はどのように対応されているのか、教えてください。あと、専門高校の支援で特に力を入れていきたいことや重要性についても教えてください。
大臣)
私が三党協議の実務者として入っていたときからもそのことは大変大きな議論になっておりました。専門高校を含む公立高校というものは大変子供たちの教育にとって、またそれぞれの地域にとって大変重要な役割を果たしているというふうに認識をしているところであります。これはかなり地域差もあるわけでありますけれども、ある県におきましてはこうした専門学校(注)に通う子供たちの割合が非常に高いというようなところもあるわけでありまして、そういう意味では子供たちの学びという観点もそうでありますが、同時にそれぞれの地域経済に人材を、供給をしていくという意味合いにおきましても非常に重要な役割を果たしているというのが私自身の認識であります。そういう意味では、今、三党協議が進んでいるわけでありますけれども、その中でも公立学校や専門学校(注)への支援というものが入っているように伺っておりますし、また同時に文科省におきましても令和8年の概算予算の概算要求におきましても専門高校の機能強化・高度化を含む高等学校教育改革の実現に向けた事項要求、また専門高校の運営モデルの構築や人材の確保、産業教育施設整備の補助に必要な経費を要求しているところでありまして、これらを通じて専門高校等々をしっかりと支援をしてまいりたいと思います。三党協議の場でも実はこんな話がありまして、例えば今、AIであったり、またGPSなんかを使った新しい農業だったりとか新しい水産業だったりとか、いろいろなそういう新しい技術というものを、活用をしたそうした取組というものが進んでいる中で、でも実際の学校にはそれに対応した残念ながら機器が整備をされていないので、そういうものを実際にはやはり学校段階でしっかりと教えてあげたいのだけれども、なかなかそれを教える、そういう施設というか機械がないがためになかなかそれらを教えることができないのだというようなお話があったり、また実際には予算が足りないがためにそうした実習等に必要な機械等が壊れたままに放置をされていて子供たちの実習の機会が失われている場合もあるというようなことも聞いているところであります。今回の議論をきっかけにいたしまして、ぜひ我々といたしましてはしっかりとした予算を確保し、そうした公立高校またそうした専門高校、こうしたところへの支援を、充実をして教育の質を高めていく取組というものをぜひ進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
(注)「専門学校」は、正しくは「専門高校」です。
記者)
旧統一教会の関係でお伺いいたします。2022年に自民党が行った党所属議員と教団との接点に関する調査で、大臣は旧統一教会及び関係団体に対する会費類の支出があり、政治資金規正法上、用途公開の対象議員に含まれていたと思いますが、現状の大臣と教団側との関係性について改めてお教えください。合わせて、解散命令請求や清算を所管する文科大臣として、過去に接点があった旧統一教会に対して今後どのように対応なさるのでしょうか、お考えをお聞かせください。
大臣)
まずは、安倍元総理が銃撃をされ、このように大きな問題になる以前のこととはいえ、私自身に認識の不足があったということかと私自身率直に反省を申し上げたいと思いますし、それによっていろいろな思いを持たれる方がいらっしゃいましたら率直にお詫びを申し上げたいと思います。現在、私自身はもちろん党の指示に基づきまして一切の関わりを絶っているところでありまして、一切そうしたつながりというものは何も持っていないという状況であります。また今後、同様のことが起きないように私自身しっかりとこれから気をつけて対応をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。その上で、解散命令請求についてでありますけれども、今、地裁で判決、解散を命じる旨の決定が本年3月に出され、現在、東京高裁において審理が進められているということであります。今、司法の場でそうした審理が進んでいるということでありますが、それらをしっかりと見守ってまいりたいと思いますし、また、同時にあべ前大臣に引き続きましてその対応方については万全の対応をとってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
記者)
私からは科学技術関連で3点お伺いしたいことがありまして、まず一つは科学技術で特に力を入れたい政策をお聞きしたいのと、もう一つは宇宙やAI、半導体やマテリアルといった先端技術の研究をどう進めていきたいか、もう一つが基礎研究力の低下というのが今、課題となっていますが、大臣の所感を教えてください。
大臣)
3点まとめてお答えをさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたがやはり科学技術の力、そしてイノベーションを生み出していく国づくりというものは我が国の経済、そして国民生活、社会課題の解決、こうしたものを進めていくためには必要不可欠であり、その基礎となるものだと思っておりますので、その重要性というものはますます高まっているというふうに認識をしているところでありますので、それらを進めていくことができるようにしっかりやっていきたいと思います。また、加えて基礎研究についてでありますけれども、先日、本当に嬉しいことに坂口先生、北川先生がノーベル賞を受賞されたわけでありますが、その際に両先生からも基礎研究の充実であったり、また若手研究者への支援、こうしたものをもっとしっかりと進めてほしいというようなお話があったというふうに承知をしているところでありまして、これらの御意見というもの、またそれぞれの現場で携わっている皆様方にもいろいろと御意見をいただきながら抜本的に強化をする施策というものを進めていきたいと思っておりますし、多分、ただ予算をつければいいという話ではなくてそれをどういうふうに使いがってよく、また実際にその資金を使ってそれが具体的な研究に結び付けていくことができるのかということ、また同時に国民の皆さんにもそれをしっかりと理解をしてもらう、こういうことをしっかりとやっていくことが極めて大事だと思っておりますのでやってまいりたいと思います。また、宇宙、AI、半導体、マテリアル、こうした分野もそうでありますし、私自身、本当にこれらの分野というものは国民生活に欠かせない分野でもありますので、これら全力を尽くして進めていきたいと思います。来年度からいよいよ第7期科学技術・イノベーション基本計画ということでありまして、その策定に向けた議論も進んでいるところでもありますので、ぜひ関係府省ともしっかりと連携をしつつこの計画というものをまとめて、これら大切な分野にしっかりと後押しをすることができるように全力を尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
記者)
私からは所管されている原子力をはじめとするエネルギー研究についてお伺いできればと思っております。原子力の基礎研究支援や次世代革新炉、また首相が力を入れて取り組むと言われている新技術、フュージョンエネルギーなどの開発についてどのような施策を進めるか認識をお聞かせください。
大臣)
原子力は発電もそうでありますけれども、例えば医療、材料、こうした様々な分野にも利活用が期待をされる分野でもありますので、文部科学省といたしまして原子力機構や大学などにおける研究を支援するとともに、産官学による人材育成コンソーシアム「ANEC」の活用などを通じて人材基盤の強化に取り組んでいく、こうしたことを進めてまいりたいと思います。また、次世代革新炉やフュージョンエネルギーについては大変重要なこれからの我が国を支える技術というふうにも承知をしているところでもありますので、エネルギー基本計画等々もありますが、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略等に基づいてしっかりと進めてまいりたいと思います。私自身、経済産業委員会の筆頭理事のとき、茨城県の那珂にあるJT-60(注)を、実際に視察をさせていただいて、そこで皆さんとお話をさていただいたときに大変印象深いお話を聞かせていただきました。このフュージョンエネルギー、長く喋って申し訳ないのですけれども、フュージョンエネルギーのお話を聞いているときにその研究者の方がおっしゃっていたのは、これまでエネルギーにおける世界の覇権というものは要するに資源がある国が握っていたのがこれまでの世界の情勢でありますと。有り体に言えば産油国だったりとか、ガスを産出するような国がエネルギー覇権というものを握っていたわけでありますけれども、もし仮にフュージョンエネルギーというものが実用化をすることができれば技術を持つ国こそがエネルギーの覇権を持つことができる国になるのですというお話が私にとってはすごく印象に残っております。これは、我が国における過去の歴史的な脆弱性をむしろ強みに変えることができるような一大、私はそういうプロジェクトなのだということをそのときに大変認識を持ったところであります。ぜひそういう意味では、非常に我が国の将来を左右するような重要な分野だということを私自身、認識をしているところでもありますので、しっかりと文科省としても各省と連携をしながらこれらのプロジェクトを進めていくことができるように全力を尽くしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
(注)「JT-60」は、正しくは「JT-60SA」です
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室