- 現在位置
- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度) > 文部科学省の推進施策(予算・説明会・委託事業等) > コミュニティ・スクールの推進に係るフォーラム、CSマイスター派遣事業等 > コミュニティ・スクールの推進に係るフォーラム等 > コミュニティ・スクール推進協議会 > 平成19年度コミュニティ・スクール推進フォーラム > 平成19年度コミュニティ・スクール推進フォーラム事例発表(福岡県春日市立日の出小学校)
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)
平成19年度コミュニティ・スクール推進フォーラム事例発表(福岡県春日市立日の出小学校)
学校名 福岡県春日市立日の出小学校
所在地 福岡県春日市日の出町3-1-10
電話番号
092-572-4451
1 実践発表のテーマ
『共学・共育』風土を醸成させる地域運営学校(コミュニティスクール)日の出小学校の実践
2 なぜ、「学校運営協議会」制度を導入したのか
(1)春日市「子どもトライアングル21」の推進から
(2)子どもたちに身につけたい生きる力としての学力(生涯学力)の育成の推進から
(3)日の出小学校の開かれた学校づくりの積み上げから(支援型から協働型)
3 日の出小学校のコミュニティスクールの特色は何か
- 教師と保護者、地域住民が責任を共有し参画する学校運営(協働方式)
- 地域・校区における「共に育てる(共育)」風土の醸成(役割分担の明確化・機能化、相互補完・錬磨)
- 地域運営学校における組織体制の確立(学校運営協議会及び実働組織の設置)
4 本校の地域運営学校としての経緯(あゆみ)
(1)ステップ1;地域のニーズに応える学校の方向性(方針策定)を明確にすること
- 実態調査アンケートの実施(第1、2次)
- 保護者・地域住民とのディスカッション(情報交換)
| 共有ビジョン (身につけさせたい力) |
1.学力の向上 2.健康・体力の向上 3.生活力の向上 4.モラルの向上 5.かかわる力の向上 6.安全対応力の向上 |
|---|
(2)ステップ2;地域運営学校の在り方を模索すること
| 学校 | 学校運営協議会 |
|---|---|
|
・学校組織の再編 ・教育支援ボランティアの参画の拡大 ・評価活動の改善 ・学校行事の改善 |
・定期的な協議会の開催 ・2学期制の検討 ・先進校の視察 ・学校・地域行事の改善 |
(3)ステップ3;組織体制づくり(実働組織づくり)をすること
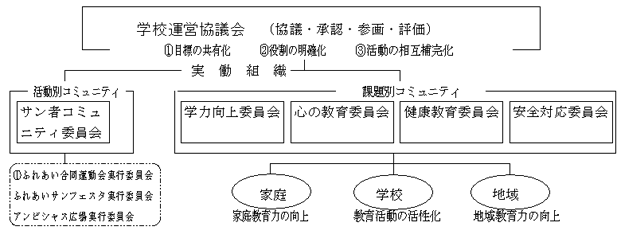
(4)ステップ4;実働組織ごとの活動計画づくりをすること
1.実態調査結果の分析→2.課題別ごとでめざす子ども像の決定→3.実践活動の内容決定→4.三者の役割分担→5.具体的方途の決定→6.活動計画の作成→
(5)ステップ5;実働組織を中心に実践すること
- 学校が中心になった活動
- 地域が中心になった活動
- 家庭が中心になった活動
- 三者が協働して実施する活動
5 本校の地域運営学校としての取り組み
(1)学校が中心になって取り組んでいる活動
- 「共学」の授業の推進
- サンライズ・ティーチャー(教育支援ボランティア)との協同授業
- 学力アップのためのサマースクールの実施
- 学習習慣化を図る「学問のすすめ運動」の推進
- 知のチャレンジ、心のチャレンジ、体のチャレンジの推進
- ペットボトルによる稲づくり
- 開かれた学校保健委員会
- 学校評価、情報公開(学校説明会・報告会、教育モニター会等)の充実
- フリー参観日「日の出の日」の実施
- 日の出小学校公民館の設置 等々
(2)地域が中心になって取り組んでいる活動
- 生き生きサロン(高齢者の福祉活動)の実施
- 日の出アンビシャス広場の充実
- 安全パトロールの強化
- 子ども公民館活動
- 地域読書相談室の推進 等々
(3)家庭が中心になって取り組んでいる活動
- 家庭教育チャレンジ宣言の推進
- 日の出情報メールの作成
- 食育に関する取り組み
- 安全マップづくり
- キラキラノートによる生活習慣づくり(学校と家庭の連携)
- 親子一鉢運動の充実 等々
(4)三者が協働して実施する活動
- ふれあい合同運動会の充実
- ふれあいサンフェスタの充実
- 日の出アンビシャス広場の充実
6 コミュニティスクールによる成果と携わっているものとしての実感(手応え)
(1)地域、保護者(役員、委員)の当事者意識の高揚(学校教育に利害を持つ関係者の拡大)
(2)学校運営協議会及び実働組織「課題別コミュニティ」の機能化(組織体制の整備充実)
(3)学校と家庭、家庭と地域、学校と地域、及び三者の連携した共育活動の充実(地域との協働関係を活性化する共育活動の充実)
(4)教職員の内なる閉鎖性の打破
(5)学校の教育環境の充実、学校施設の有効活用
(6)内外環境からの教育資源の発掘・活用の促進
7 今後に向けて(今後の課題)
(1)地域、保護者の当事者意識の拡大(特に保護者)及び地域社会の成熟度アップ
(2)共育活動の質的な深まり、学校評価とそのシステムの確立(特に第三者評価)
(3)教職員の人事、予算等に関する意見の反映システムの確立
-- 登録:平成23年11月 --