- 現在位置
- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 進路指導・キャリア教育について > 中学校職場体験ガイド > 参考資料 > 地域に学ぶ中学生・体験活動週間「トライやる・ウィーク」
地域に学ぶ中学生・体験活動週間「トライやる・ウィーク」
兵庫県教育委員会
1 事業の概要
(1) 趣旨
中学生が職場体験、福祉体験、勤労生産活動など、地域での様々な体験活動を通じて、働くことの意義、楽しさを実感したり、社会の一員としての自覚を高めるなど、生徒一人一人が自分の生き方を見つけられるよう支援する。
また、「トライやる・ウィーク」への取組を通じて学校・家庭・地域社会の連携を深め、社会全体で子どもたちの人間形成や社会的自立の支援を行うことで、子どもたちを中心とした地域コミュニティの構築へと発展することを期待するものである。
(2) 実施内容
○対象
全県下公立中学校2年生及び市立盲・養護学校中学部2年生等(平成16年実績)48,913人
372校(中学校358校、盲・養護学校13校、県立中等教育学校1校)
○期間
連続した5日間(6月、11月を中心に各中学校ごとに実施)
○活動内容
ア 活動の分野(平成16年)
- 職場体験活動(79.2%)
- ボランティア・福祉体験活動(7.9%)
- 文化・芸術創作活動(5.7%)
- 勤労生産活動(3.5%) 等
イ 活動業種等(平成16年)
- 販売(20.6%)
- 幼児教育(20.2%)
- 役所・消防署等(7.9%)
- 製造・建築(5.8%)
- 社会福祉施設(5.7%)
- 飲食店等(5.2%)
- 文化芸術創作活動(3.9%)
- 病院等(3.3%)
- ホテル・理美容(3.2%)等
(3) 実施に至る経緯
- 平成7年1月
阪神・淡路大震災 - 平成9年6月
神戸市須磨区の事件 - 平成9年
心の教育緊急会議設置 - 平成10年6月
「トライやる・ウィーク」先行実施(県下7地区18校) - 平成10年11月
「トライやる・ウィーク」全県実施(322校) - 平成14年
5年目の検証委員会設置 - 平成16年
-「トライやる・ウィーク」の新展開-
「トライやる」アクション実施
「トライやる・ウィーク」の市立・盲養護学校への拡大
(4) 事業費
1学級あたり300千円(県3分の2補助:平成17年県事業予算 約2億8千万円)
2 「トライやる・ウィーク」の推進体制
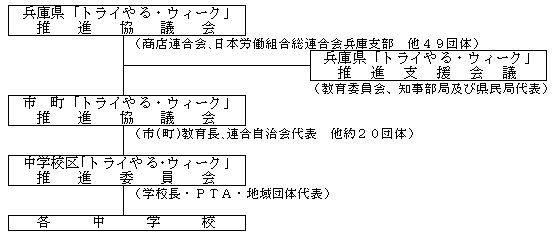
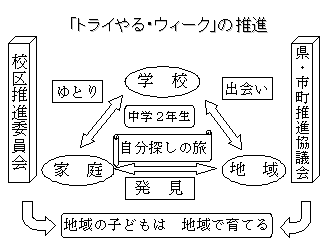
3 成果 (「トライやる・ウィーク」5年目の検証(報告)より)
(1) 生徒
- 自己の確立・生き方の探求がなされた。
- 職業観・勤労観が育成された。
- 社会性が育成された。
- 社会の肯定的な認識・規範意識を醸成する機会となった。
- 不登校生徒の登校改善につながった。
| 調査校 | 在籍生徒数 | 左のうち1年生の時に不登校の生徒数 | 全日参加生徒数 | 実施後1ヶ月の状況 登校率の上昇した生徒 |
実施後2ヶ月の状況 登校率の上昇した生徒 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年 | 359校 | 49,413名 | 1,030名 | 482名 (46.8) |
193名 (40.0) |
192名 (39.8) |
(2)学校・教職員
- 教育活動を見直す契機となった。
- 開かれた学校づくりが推進された。
(3) 家庭
- 家族のコミュニケーションの活性化が図られた。
- 自主的に家事手伝いをするなど家庭の在り方を考える契機となった。
- 親に対する理解が深められた。
(4) 地域社会・受入先
- 学校の教育活動に参画する意識の高揚が図れた。
- 生徒に対する考え方が変わり、地域の子どもを育てようとする気運が高まった。
- 職場が活性化したことや地域社会への貢献による充実感があった。
- 県民運動としての推進体制を確立できた。
4 今後の課題
(1) 体験活動が一過性のもので終わらない工夫
- 中学校の3年間を見通した教育計画の推進(総合的な学習の時間との関係等)
- 事前、事後指導の内容の充実
- 学校、家庭、地域において、日常の教育活動や日々の生活につなぐ創意工夫
(2) 円滑な実施に向けた実行ある推進体制の確立 ―三者の役割の明確化―
(参考)本県におけるその他の体験活動に係る施策
○ 自然学校(昭和63年~)
対象 全公立小学校5年生
内容 5泊6日の自然体験の実施
○ 高校生地域貢献事業(平成17年~)
対象 全県立高等学校の1年生
内容 年間5,6回程度、クラス単位等による地域でのボランティア活動やグープ単位による福祉活動等の実施
○ 高校生就業体験事業(平成17年~)
対象 全県立高等学校の2年生
内容 専門高校等で5日間程度、普通科高校で3日間程度の就業体験等の実施
-- 登録:平成21年以前 --