- 現在位置
- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 進路指導・キャリア教育について > 中学校職場体験ガイド > 第1章 職場体験の基本的な考え方
第1章 職場体験の基本的な考え方
(1)職場体験とは
生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業や仕事の実際について体験したり、働く人々と接したりする学習活動
(2)職場体験が求められる背景と必要性
| 学校から社会への移行をめぐる課題 | 子どもたちの生活・意識の変容 |
|---|---|
1.就職・就業をめぐる環境の激変
|
1.子どもたちの成長・発達上の課題
|
|
|
|
| 学校教育に求められている課題 |
|---|
1.「生きる力」の育成
|
| キャリア教育の推進キャリア教育の推進 |
|---|
|
| 職場体験の一層の充実 |
1.職場体験が求められる背景
職場体験が求められる背景として、子どもたちの生活や意識の変容、学校から社会への移行をめぐる様々な課題、そして、何よりも望ましい勤労観、職業観を育む体験活動等の不足が指摘されています。
物質的な豊かさや生活の利便性の向上、都市化・少子化等の進展に伴って、子どもたちの生活や意識も大きく変容している。また、これまでの子どもたちには見られなかった柔軟な感性や遊び心、ボランティア活動等への高い参加意欲を持っているなどの積極性は見られるものの、社会性の不足、規範意識の低下、人間関係や連帯感の希薄化、集団や社会の一員としての自覚や責任感の低下などが指摘されている。そして、変化の激しい先行き不透明な社会を背景として、若者の世界に漠然とした閉塞感や無力感、あるいは、職業について考えたり、職業の選択・決定を先送りにするモラトリアム傾向やフリーター志向の広がり、高水準で推移する若年者の失業率やいわゆる「753」といわれる就職後の早期離職、また最近ではニート(NEET:Not in Education,Employment,or Training)の問題が指摘される中で、生徒の進路意識や目的意識の低下が懸念されている。
一方、このようなことから、学校段階では、従来から課題となっている不登校や中途退学についても、将来の社会的自立に向けた支援の視点から「進路の問題」として捉えることの重要性が指摘されている。
何よりも、各種報告等によると、日本の子どもたちは、将来に向けて、なぜ、学ばなければならないのか、学び続けなければならないのか、何のために学校で学ぶのか等、学ぶことへの関心や意欲が低下傾向にある等、様々な課題が指摘されている。まさに、「学ぶことの意義」という教育の根幹の部分で問われているのである。
こうした課題の背景には、子どもたちを取り巻く環境の変化等に起因する様々な要因が考えられるが、特に、子どもたちの生活の中で、疑似体験や間接体験が多くなる一方、社会体験や自然体験等の直接体験が著しく不足していることが大きく影響しているとの指摘がある。
自己の将来に夢や希望を抱き、その実現をめざし、職業生活に必要な基礎的な知識や技術・技能の習得への理解や関心、望ましい勤労観、職業観の育成はすべての子どもたちに必要なものである。また、技術革新の進展や経済・産業の変化や構造転換などが急速に進む中で、学校教育を終えた後も、若年者に対して、新たな知識や技術・技能を身に付け、生涯にわたって自己の職業生活をたくましく切り拓いていこうとする意欲や態度、目的意識などを培うことがこれまで以上に大切になってきている。
2.職場体験の必要性
職場体験には、生徒が直接働く人と接することにより、また、実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、生きることの尊さを実感させることが求められています。また、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など培うことのできる教育活動として、重要な意味を持っています。
望ましい勤労観、職業観の育成や、自己の将来に夢や希望を抱き、その実現を目指す意欲の高揚を図る教育は、これまでも行われてきたところであるが、より一層大切になってきている。
職場体験は、こうした課題の解決に向けて、体験を重視した教育の改善・充実を図る取組の一環として大きな役割を担うものである。特に、生徒の進路意識の未成熟や勤労観、職業観の未発達が大きな課題となっている今日、生徒が実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義を理解し主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など、培うことのできる教育活動として重要な意味を持っている。
現行の中学校学習指導要領においては、体験的な学習や問題解決的な学習を重視している。
また、平成11年12月の中央教育審議会の答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」、及び平成16年1月「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書」においても、小学校段階から発達課題に応じて「キャリア教育」を推進することが提言され、その一環として職場体験等の体験活動を促進することが重要であると指摘されている。
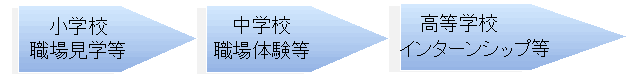
このような職業にかかわる体験は、ともすれば「働くこと」と疎遠になりがちであった学校教育の在り方を見直し、今、教育に求められている学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させる具体的な実践の場である。
特に、中学校における職場体験は、小学校での街探検、職場見学等から、高等学校でのインターンシップ等へと体験活動を系統的につなげていく意味において、重要な役割を持っている。
このため職場体験は、各学校において、事業所や地域との深い連携・協力関係のもとに、生きた学びの場を構築していくという観点に立って、幅広く導入していくことが強く望まれている。あわせて、小学校・中学校・高等学校等の連携を図っていくことも重要である。
(3)職場体験の意義
| 職場体験の教育的意義 |
|---|
|
| 学校にとって |
|---|
|
| 教員にとって |
|
| 生徒にとって |
|---|
|
| 家庭にとって |
|---|
|
| 保護者にとって |
|
| 地域にとって |
|---|
|
| 事業所にとって |
|
1.勤労観、職業観の育成の場
実際に仕事をしている人と接し、自分自身も体験することで、働くことの意義や目的の理解、進んで働こうとする意欲や態度などを育むことができる。職業の意義についての基本的な理解・認識、自己を価値あるものとする自覚、夢や希望を実現しようとする意欲的な態度など、望ましい勤労観、職業観を育むまたとない機会である。
2.新たな自分を発見する場
生徒が自己の個性や適性を把握し自己理解を深めていく上で、様々な体験・経験を積み重ねることは、極めて重要である。自分が役立つ存在であることを知ることができたり、自己の新たな可能性を見い出したりする場合も少なくない。また、それぞれの職業の実像は、実際に仕事を経験し、働くことの厳しさや喜びなどを身をもって体験することを通して、生徒自らが体得していくものである。
3.コミュニケーション能力、社会的スキルを身に付け、人間関係の大切さを体得する場
職場体験は、そこで働いている多くの職業人との触れ合いや交流を通して、異世代とのコミュニケーション能力を高めるとともに、社会人としての基本的マナーや言葉遣いなどを身に付けることができる場でもある。核家族化や都市化が進む中で、異世代との交流が減少し、あいさつができない、言葉づかいを知らない、コミュニケーションがうまく図れないといった若者が増えているという指摘もあり、これが高い離職率の一因となっている場合も考えられる。コミュニケーション能力や社会的スキルを身に付ける上でも、職場体験の果たす役割は大きい。
4.学校と社会をつなぐ場
生徒は、職場体験を通して、学校での学習が社会でなぜ大切なのか、どのように役立つのか、実際に仕事をしていく上でどのように用いられるのかを知ることができる。それは同時に、現在の学習と将来の職業生活との関係を理解し、目的を持って学習に取り組む上での重要な契機ともなる。「働くこと」から疎遠になりがちな今日の子どもたちにとって職場体験は、こうした現状を打開し、体験を通して学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感をもって理解していくという大きな役割がある。
5.職業生活や社会生活に必要な知識、技術・技能を学ぶ場
生徒が職業で実際に用いられている知識、技術・技能を学ぶ貴重な機会である。
また、実際に働いている人たちの生活ぶりを見聞きする絶好の機会でもある。
6.教員の新たな資質・能力の形成の場
教員にとっては、産業界の動きや職場の実情、地域の現状についての認識を深めることができる。そのことから、生徒への適切な助言や生きた情報の提供等が行われるようになり、また、教員のコーディネート能力、カリキュラム開発能力等の向上、さらに、意識改革につながることが大いに期待できる。さらには、これまでには見られなかった生徒の姿やその変化を見たりすることによって、教員の生徒理解が一層深まるのである。
7.親子の会話を促進する場
保護者にとっても子どもたちの働く姿は、その新たな側面を発見することになる。
また、働くということを通して、子どもとの会話を促進する機会にもなり、子どもは保護者との会話を通して、働くことの尊さや感謝の気持ちを持つことになろう。
8.事業所、地域の理解と活性化を図る場
職場体験は、地域の産業やそこに働く人々の素晴らしさや大切さを発見する場合も多く、そのことが地元に対する愛着や誇りを持つことにつながる。また、自分自身に対する自信や可能性の発見と相まって、自己の拠って立つところ=アイデンティティを形成していく上での大きな契機となっていく。
さらに、地域が一体となって生徒を育てていこうとする気運が高まること、事業所も地域に貢献することができるなど、職場体験には広範な教育効果を期待することができる。
(4)職場体験の現状
全国の公立中学校における職場体験の実施率は、年度別に下のグラフのようになっている。
公立中学校の約90パーセントで職場体験が実施されている。今後はその日数、時期、実施内容、生徒の意識の変容、さらには、職場体験の事前・事後指導の在り方等を見直し、職場体験が生徒にとってよりよいものとなるよう、改善していく必要がある。
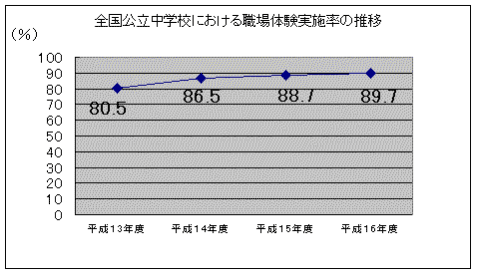
(国立教育政策研究所生徒指導研究センター)
(5)キャリア教育の視点に立った職場体験の在り方
1.児童生徒の発達段階を踏まえた在り方
職場体験を進める上において重要なことは、児童生徒の発達段階を踏まえて、児童生徒の全人的な成長・発達を支援する視点に立って行うことである。
人間の成長・発達の過程には、いくつかの段階(節目)と各段階で取り組まなければならない発達課題がある。これをキャリア発達の視点から見れば、学校段階別に次の図のような段階と課題が考えられる。また、こうした発達には、自己理解、進路への関心・意欲、勤労観、職業観、職業や進路先についての知識や情報、進路選択や意思決定能力、職業生活にかかる習慣や行動様式及び必要な技術・技能などといった様々な側面が考えられる。
2.小学校、中学校、高等学校の連携を図った在り方
今後、各学校において職場体験を進めていく上では、それぞれの学校の状況、子どもたちの実態や発達段階を踏まえ、小・中・高等学校における連携の意義を生かしながら、キャリア教育の視点からしっかりとそのねらいを明確にして取り組む必要がある。例えば、次の図のように整理できる。
小学校・中学校・高等学校におけるキャリア発達と職場体験等の関連(例)
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|
| <キャリア発達段階> | ||
| 進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期 | 現実的探索と暫定的選択の時期 | 現実的探索・試行と社会的移行準備の時期 |
|
|
|
| 体験的活動(例) | ||
|
|
|
| 児童生徒の感想から | ||
|
|
|
3.学校と家庭・保護者との連携を生かした在り方
勤労観、職業観を育成する上で基礎となるのは、家庭における手伝いである。家庭の中での役割分担を通して、子どもたちの役割認識、分担された仕事への責任感、家族としての自分の立場などを体得していくことができる。その意味では、幼児期からの家庭のしつけを含めて、保護者の担う部分が大きい。したがって、保護者が学校生活、職場体験等での子どもの感想を聞いたり、保護者の勤労観、職業観を話したりすることは、非常に有効である。さらに職場体験の前後はもちろんのこと、入学時期から家庭・保護者と学校とが連携を図っていくことが重要である。
4.学校と地域・事業所との連携を図ったシステムづくりとその活用
職場体験を機会に、学校と地域や事業所との連携が図られる。このことは、事業所にとっても、次代を担う人材育成の面から地域における社会的な役割を担うことにもなり、職場の活性化、地域への貢献といった意味においても価値のあることである。
しかしながら、職場体験の一時で連携が終わってしまうことも少なくない。今後は、共に築き上げた連携体制を、職場体験後も引き続き維持していくことにより、キャリア教育をさらに継続的、発展的に推進していくシステムづくりが必要である。職場体験をより効果的に進めていくための協議の場のみならず、社会人講師の招聘等、ここで築いたシステムをさらによりよい地域のシステムとしていくためにも、様々な連携を進めていくための年間を通した、協議の場を設けることが大切である。
このことはまた、その後、地域の自治会の活動やお祭り、ボランティア活動に際し、子どもたちが進んで参加していける地域のシステムづくりにつながっていく。地域や事業所、家庭との連携を図ったシステムづくりは、学校と家庭・地域全体で子どもたちを育てていく気運を高めていくことにもなるのである。
お問合せ先
初等中等教育局児童生徒課
-- 登録:平成21年以前 --