- 現在位置
- トップ > 教育 > 学校等の施設整備 > 調査報告(出版物案内) > 学校施設の防犯対策に係る点検・改善マニュアル作成の取組に関する調査研究 報告書 > 学校施設の防犯対策に係る点検・改善マニュアル作成の取組に関する調査研究 報告書 第2章 点検・改善マニュアルの調査分析3-2
学校施設の防犯対策に係る点検・改善マニュアル作成の取組に関する調査研究 報告書 第2章 点検・改善マニュアルの調査分析3-2
3.点検・改善マニュアル作成のポイント
3‐2 現状の把握、問題点の抽出
キーポイント
- 図面等を活用した現状の把握
- 個々の学校の守り方に基づく問題点の抽出
3‐2‐1 図面等を活用した現状の把握
- (1)図面等を活用して、防犯に関する学校敷地内及び周辺環境の現状について把握することが大切である。
- (2)既存施設・設備の現状把握は、図面や点検用チェックリスト等を使って、学校現場の状況を確認することが重要であるため、学校配置図、周辺地図等に気づいた点をチェックする「学校施設安全マップ」づくりが有効である。
- (3)「学校施設安全マップ」づくりに、学校関係者、保護者等の検討体制メンバーが参画することは多面的な点検、情報の共有化に有効である。
3‐2‐2 個々の学校の守り方に基づく問題点の抽出
- (1)学校の運営方針、周辺環境等を考慮しつつ、防犯に関する基本方針を定め、防犯対策に必要な領域性の確保、視認性の確保、緊急時の対応等の守り方(範囲・方法等)を設定し、現状に対する問題点を抽出する。
- (2)公立の図書館、運動施設等との複合施設は、来校者及び利用者が同一の出入口、建物を利用する場合が多く、領域性・視認性の確保、受付体制の確認等、防犯対策の連携を行うために、施設の現状、問題点等を相互に共有することが重要である。
- (3)多数の来校者が予想される、運動会、授業参観日、学校公開日等は特定または不特定の者を受け入れるため、個々の学校の状況に対応した守り方による不審者の侵入防止対策が必要である。

参考事例
- 防犯施設の点検マニュアルの基本的考え方として
- 児童の安全・安心を第一に確保する。
- 地域住民が利用しやすい開かれた学校とする。
- ゆとりや潤いが感じられる学校とする。
を挙げている。(雲南市立三刀屋小学校:P.36参照)
- 「防犯対策マネジメントシステム」として防犯対策の基本方針を定め、図面により学校内外の施設の点検・評価及び改善を実施している。(群馬大学附属小学校:P.22~25参照)
- 学校配置図及び点検用チェックリストを使って教職員、保護者、児童、地域住民の協力により現場のチェックを行い「学校施設安全マップ」を作成している。(武蔵野市立境南小学校:P.9~10参照)
- 防犯の専門家の協力を得て、防犯に関する施設の問題点を点検し、その内容を学校配置図に整理し、記載している。(群馬大学附属小学校:P.24~25参照)
参考資料 現状把握の主な項目<例>
本調査研究及び学校施設の防犯対策に関する調査研究報告書等の内容により作成
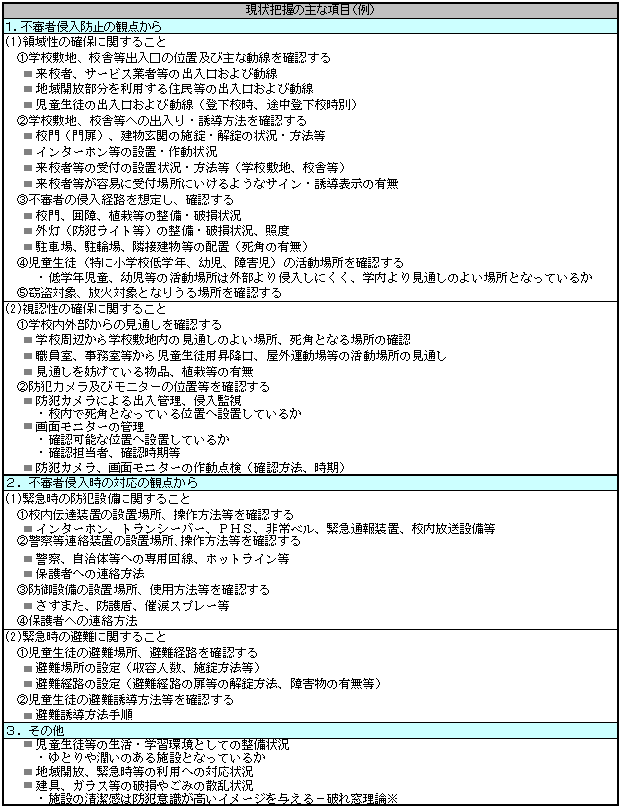
※点検項目は参考として例示した。
学校施設の防犯に対する現状について、児童生徒への安全教育、教職員の役割分担、保護者や地域住民等のボランティアによる協力など、安全対策及び安全管理の実態について把握し、適切な対応を行うことが重要である。
関連資料
既存施設の点検・評価手順の例
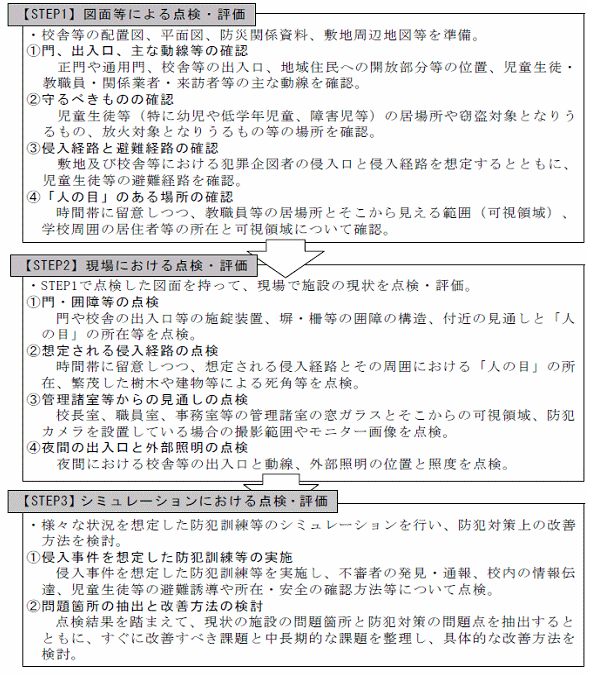
(注)学校施設の防犯対策に関する調査研究報告書1‐3学校施設の防犯対策に係る基本的な考え方
関連情報
破れ窓理論(注)
1982年に米国で提唱された犯罪抑止理論。割れた窓ガラスを放置しておくと、ここは管理・監視されておらず自分も割っても問題ないという印象を与え、模倣的、連鎖的にガラス窓が割られていってしまうように、都市において軽犯罪の取り締まりを放置すると、重大な犯罪を助長するという指摘による理論。
お問合せ先
大臣官房文教施設企画部施設企画課
-- 登録:平成21年以前 --