- 現在位置
- トップ > 文教施設施策 > 調査報告(出版物案内) > 学校施設の防犯対策に関する調査研究報告書 > 3‐1 施設配置
3‐1 施設配置
(1)校舎内や周囲からの見通しがよく、敷地内において死角となる場所がなくなるよう各建物、屋外施設、門等の配置に留意することが重要である。また、建物等を増築する場合は、新たに死角となる場所をつくらないよう既存施設等との関係に十分に留意することが重要である。
(4)建物等の配置上、やむを得ず死角となる場所については、防犯監視システムの導入や定期的なパトロールの実施等の対応をとることが重要である。
(1)見通しの確保
- 「死角となる場所をなくす」ということは、周囲からの見えやすさを確保し、人の目等により離れたところからでも不審者が識別できるようにすることをいう。
- 敷地内の建物、屋外施設、門等の各部位の設計については、敷地内外各部からの見通しを確保するとともに、門や建物の出入口などには周囲からの見通しが確保されるように計画することが重要である。
(2)増築の際の留意点
- 建物等の増築の際には、既存建物や既存建物と増築建物との間に、新たな死角を生むことが多いため、既存建物との関係に十分配慮した計画とするとともに、教職員や地域等の「人の目」を分散した形で配置することが望ましい。
- 見通しが確保されにくい場所には、教師コーナー等に「先生の目」やPTA等が利用するクラブハウス、会議室等に「地域の人の目」を分散する等、「人の目」が確保できる部屋の配置を、増築の際に考慮することが重要である。
- 死角となるところで、「人の目」を配置することができない場所については、防犯カメラやセンサー等の防犯設備の設置や、こまめなパトロールの実施等の対策を行うことが重要である。
(2)職員室、事務室等については、アプローチ部分や屋外運動場等を見渡すことができ、緊急時にも即応できる位置へ配置することが重要である。また、調理室等についてはサービス用車両の進入頻度も高いことから、その配置や動線計画について配慮することが望ましい。
(1)管理部門の位置
- 職員室、事務室等から、アプローチ部分や屋外運動場などが見通せる配置になっていることが望ましい。
- 職員室、事務室等は、迅速な行動がとれるように1階に計画し、それぞれの部屋から直接屋外に出られるような出入口を設けることが望ましい。2階に配置した場合には、接地階につながる階段をこれらの部屋に近い位置に設ける等、計画上配慮することが望ましい。
(2)サービス部門の防犯対策
- 外部からの出入りがしやすく、人の目につきにくい位置にある調理室等のサービス部門における出入口については、バックヤード用の門扉等を設けて単独のセキュリティの領域をつくり、IDカードによる施錠コントロール等、防犯設備による対応や時間による出入管理等を行うことが望ましい。

写真3‐1‐1 サービス部門の防犯対策例
- 給食室への搬入車両用に門扉を設け単独のセキュリティの領域をつくっている。手前が正門、正面が給食室への搬入車両用の門扉。
(3)特に適切な指示・誘導や介助が必要な幼児や低学年の児童等が活動する施設については、防犯上の安全性を確保するため、テラスや遊び場等の屋外スペースを含めその活動範囲を明確にしたり、敷地境界からの距離を十分に確保することや、非常時に即応可能なように、職員室や事務室等の教職員の居場所から近い位置や見通しのきく位置に配置する等の配慮が重要である。
- 低学年の児童や幼児は、遊びに夢中になり、突然先生の目の届かない場所に行ってしまう事なども考えられるため、大人によって守られなければならない対象であり、防犯上特に配慮することが重要である。
- 屋外スペースについては、敷地境界から距離をとり、スペースに余裕を確保すること、行き止まりをつくらないこと等により、非常時に容易に避難ができるように計画することが重要である。さらに、花壇等を設け、子供たちの活動領域を絞りやすいようにしておくことも有効である。
- また、非常時に即応可能なよう、職員室や事務室から近い位置や見通しのきく位置に配置することが重要である。さらに、低学年の教室の直近に教師コーナーを設けるなど、必ず誰かの目が子供たちのすぐ傍にあることがより望ましい。

写真3‐1‐2 低学年の活動領域を絞った例
- 低学年の子供たちの活動領域を絞りやすいよう配慮している。
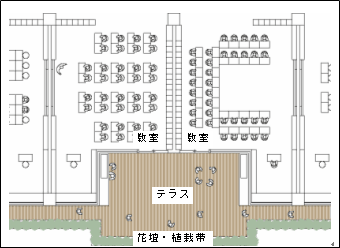
図3‐1‐1 ベランダの活動領域設定の例
- 屋外空間に花壇や植栽帯等を設け、活動領域を設定している。
お問合せ先
文教施設企画部施設企画課
-- 登録:平成21年以前 --