- 現在位置
- トップ > 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 小・中・高校教育に関すること > 私立学校の振興 > 学校法人制度の概要 > 学校法人会計基準の改正 > 学校法人会計問答集(Q&A)第17号 計算書類の注記事項の記載について
学校法人会計問答集(Q&A)第17号 計算書類の注記事項の記載について
学校法人会計問答集(Q&A)第17号
(注)本Q&Aは、日本公認会計士協会から平成17年6月に公表された資料の内容を掲載しております。
最新の情報については、日本公認会計士協会のホームページ(https://jicpa.or.jp/![]() )をご確認ください。
)をご確認ください。
平成17年6月13日
日本公認会計士協会
まえがき
これまで、学校法人会計基準(以下「基準」という。)における注記事項は、1減価償却額の累計額の合計額、2徴収不能引当金の合計額、3担保に供されている資産の種類及び額、4退職給与引当金の額の算定方法、5翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額の5項目とされてきた。これらは学校法人の財政及び経営の状況を判断するに当たり重要な情報であるため注記事項とされてきたものであり、広く実務に定着してきた。
しかしながら、少子化の進展など昨今の学校法人を取り巻く社会経済情勢の変化に伴い、学校法人の諸活動も多様化が進み、学校法人にも財務状況の透明性の確保や説明責任の明確化が求められてきた。このような社会の要請を受け、今般、学校法人会計基準の一部が改正され、注記事項の充実が図られたものである。
そこで本問答集は、基準により明記された注記事項及びこのほか考えられる注記事項をできるだけ網羅的に取り上げることにより、実務の参考となるよう具体的な記載例を取りまとめたものである。
注記事項の内容について
Q1
「学校法人会計基準の一部を改正する省令」(平成17年3月31日 文部科学省令第17号)により、注記すべき重要な会計方針及びその変更並びにその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項は、具体的にはどのような内容でしょうか。
A
計算書類には、基準第34条の規定に従い、次の事項を脚注として記載する。
- (1)重要な会計方針
- (2)重要な会計方針の変更等
- (3)減価償却額の累計額の合計額
- (4)徴収不能引当金の合計額
- (5)担保に供されている資産の種類及び額
- (6)翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
- (7)その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
上記の重要な会計方針及びその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項には、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(平成17年5月13日17高私参第1号以下「第1号通知」という。)に基づき、以下の項目を記載する。なお、具体的に掲げた項目以外にも、重要な会計方針及びその変更並びにその他財政及び経営の状況を判断するために必要な事項については、学校法人の規模等によって一概に金額基準を示すことはできないが、学校法人の資産総額若しくは帰属収入や消費支出又は消費収支差額などに照らして重要な影響を与える場合やその事項に重要性がある場合には、財政及び経営の状況を正確に判断するために記載することとなる。
重要な会計方針
- 引当金の計上基準(徴収不能引当金及び退職給与引当金等)
- その他の重要な会計方針
- 有価証券の評価基準及び評価方法
- たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
- 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
- 食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法、等
その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
- 有価証券の時価情報
- デリバティブ取引
- 学校法人の出資による会社に係る事項
- 主な外貨建資産・負債
- 偶発債務
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 純額で表示した補助活動に係る収支
- 関連当事者との取引
- 後発事象、等
注記事項に関する考え方について
Q2
Q1に掲げた注記事項は、必ず記載しなければならないのでしょうか。
A
基準第34条に規定されている注記事項は、基準第35条に示す第6号様式に事項が定められており、該当がない場合であってもその事項と該当がない旨の記載をしなければならない。
重要な会計方針のうち、引当金の計上基準には、徴収不能引当金及び退職給与引当金に係る計上基準を必ず記載し、これら以外の引当金を設定している場合には併せて必ず記載する。また、その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項のうち、学校法人の出資会社に係る事項は、「学校法人の出資による会社の設立等について(通知)」(平成13年6月8日13高私行第5号)により、該当がある場合に必ず記載しなければならない。
なお、引当金の計上基準以外の重要な会計方針及び学校法人の出資による会社に係る事項以外のその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、重要性がある場合に記載するが、この場合の「重要性」は、注記項目が計算書類に与える影響額又は学校法人の財政及び経営の状況に及ぼす影響により判断する。また、これらは、該当がない場合あるいは重要性がない場合については、項目自体の記載を要しない。
記載場所について
Q3
注記事項は必ず貸借対照表の末尾に記載しなければならないのですか。例えば、収支に関わる注記事項について、資金収支計算書又は消費収支計算書の末尾に記載してもよいですか。
A
注記事項の記載箇所は、基準第34条に規定する事項については、貸借対照表の末尾に一括して記載する。
その他の事項については、関係する計算書類の末尾に記載することが適当であろう。しかし、注記の項目によっては、複数の計算書類に関係するものもあり、これらを一覧できるよう一括して記載する方法が便利な場合もある。どちらに記載するかは、注記事項の種類、数、関係する計算書類などによって判断し、より分かりやすい方法によるべきであろう。
したがって、収支に係る注記項目で、基準34条に規定する事項については、貸借対照表の末尾に一括して記載し、その他の事項については、個別に判断することとなる。
重要な会計方針
Q4
重要な会計方針の注記はなぜ必要なのですか。
A
会計方針とは、計算書類の作成に当たって、その財政及び経営の状況を正確に判断するために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。計算書類の作成に当たって採用する会計方針は、それぞれの学校法人について必ずしも同一ではなく、一つの会計事象や取引について複数の会計処理が認められており、その中から一つの会計処理を選択適用している。したがって、重要な会計方針としてどのような手続等を採用しているかを計算書類に注記することによって、計算書類の信頼性を高め、計算書類の前年度との比較を可能とするものである。
なお、いったん採用した会計方針は毎年度継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
引当金の計上基準
Q5
引当金の計上基準は、具体的にどのようなものですか。
A
引当金とは、将来の特定の消費支出であって、当年度の負担に属する額を当年度の消費支出として計上したときの貸方項目であり、その発生が当年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合に計上される。引当金の計上基準については、金額的重要性のみならず、科目の重要性があるため、計上の理由、計算の基礎その他の設定の根拠を記載することとなる。基準に示されている引当金は、徴収不能引当金及び退職給与引当金であり、具体的記載例は以下のとおりである。なお、会計年度末に引当金残高がない場合においても会計方針として引当金の計上基準を注記することとなる。
その他、学校法人が計上している引当金がある場合には、これらに準じて取り扱うものとする。
記載例
引当金の計上基準
徴収不能引当金
- (例1)金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- (例2)未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金
- (例1)退職金の支給に備えるため、期末要支給額×××円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との組入れ調整額を加減した金額の100パーセントを計上している。
- (例2)退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額×××円の100パーセントを基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。さんかく県○○退職金団体加入者については、期末要支給額×××円から同退職金団体からの交付金を控除した額の100パーセントを計上している。
- (例3)期末要支給額××円は、○○私学退職金団体よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
有価証券の評価基準及び評価方法
Q6
有価証券の評価基準及び評価方法の注記は、どのように記載するのですか。
A
基準第25条において、「資産の評価は、取得価額をもってするものとする。」と規定されており、有価証券の評価基準は原価法である。また、評価方法については定めていないが、先入先出法、総平均法、移動平均法等がある。
このように、評価基準には選択の余地がないが評価方法には選択の余地があるので、有価証券の評価に関する会計方針として、評価基準と評価方法を一体として注記し、その内容を明らかにするものである。なお、学校法人の処理する勘定科目のいかんを問わず、保有するすべての有価証券の帳簿価額を合計した金額に重要性がある場合には、当該事項を注記する。
記載例
有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。
- 有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。
たな卸資産の評価基準及び評価方法
Q7
たな卸資産の評価基準及び評価方法の注記は、どのように記載するのですか。
A
有価証券と同様に基準第25条において、「資産の評価は、取得価額をもってするものとする。」と規定されており、たな卸資産の評価基準は原価法である。また、評価方法については定めていないが、先入先出法、総平均法、移動平均法等がある。
このように、評価基準には選択の余地がないが、評価方法には選択の余地があり、たな卸資産の評価に関する会計方針として、評価基準と評価方法を一体として注記することによりその内容を明らかにするものである。したがって、学校法人が保有するたな卸資産に金額的重要性がある場合には、両者を一体として注記する。
【記載例】
たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 移動平均法に基づく原価法である。
外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準
Q8
外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準の注記は、どのように記載するのですか。
A
外貨建資産・負債は、外貨建を円貨に換算して表示するが、年度末日の為替相場で換算する場合と取得時又は発生時の為替相場で換算する場合とでは計算書類に与える影響が異なる。したがって、外貨建資産・負債等に金額的重要性がある場合には、本邦通貨への換算基準を注記する。
【記載例】
外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準
- 外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。
ファイナンス・リース取引の処理方法
Q9
ファイナンス・リース取引の処理方法の注記は、どのように記載するのですか。
A
学校法人委員会報告第37号「リース取引に関する会計処理及び監査上の取扱い」(平成9年12月8日以下「委員会報告第37号」という。)において、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行い、注記を条件として賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことも認められている。したがって、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合には注記は不要であり、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合にのみ注記が必要とされる。
なお、この注記は学校法人においてリース料総額に重要性がない場合は省略できるので、重要性がある場合に記載されることになり、リースに関する注記が行われる場合には会計処理方法も注記することになる。
【記載例】
ファイナンス・リース取引の処理方法
- リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
Q10
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法の注記は、どのように記載するのですか。
A
基準第5条において、「計算書類に記載する金額は、総額をもって表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出‥‥については、純額をもって表示することができる。」と規定している。このように総額表示と純額表示の双方の表示方法が認められており、どちらの方法を採用するかは勘定科目ごとに任意に選択することができる。
しかし、このような学校法人特有の会計処理については、相殺の有無により収支計算書の合計金額が大きく相違する場合がある。したがって、相殺金額に重要性がある場合にはどのような表示方法を採用しているか注記することに意義がある。
【記載例】
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
- 預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。
食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法
Q11
食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法の注記は、どのように記載するのですか。
A
基準第5条において、「計算書類に記載する金額は、総額をもって表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出‥‥については、純額をもって表示することができる。」と規定されており、さらに学校会計委員会報告第22号「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」(昭和51年3月9日)において、純額表示する場合の収支相殺の範囲もいくつか例示されている。したがって、総額表示する場合と純額表示する場合で資金収支計算書及び消費収支計算書に計上される金額が大きく異なる場合がある。
このように補助活動事業の金額に重要性が認められ、相殺処理を行っている場合には、その処理方法を注記する必要がある。
【記載例】
食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法
- 補助活動に係る収支は純額で表示している。
重要な会計方針の変更等
Q12
重要な会計方針の変更等の注記は、どのように記載するのですか。
A
(1)会計方針の変更等
会計方針の変更とは、従来採用していた会計処理又は表示方法から他の会計処理又は表示方法に変更することをいう。重要な会計方針を変更した場合には、変更の旨、変更理由及び当該変更が計算書類に与える影響額を注記する。ただし、当該変更又は変更による影響が軽微である場合は注記することを要しない。
なお、会計方針の変更に該当するものは以下のとおりである。
- 複数の会計処理が認められている場合の会計処理の変更
一つの会計事象や取引について複数の会計処理が認められており、その中から一つの会計処理を選択適用する場合において、従来から採用している認められた会計処理から他の認められた会計処理への変更は、正当な理由により変更するものである限り、会計方針の変更となる。 - 表示方法の変更と会計方針の変更
表示方法とは、一般に計算書類項目の科目分類、科目配列及び報告様式をいい、表示方法の変更には、貸借対照表の固定資産あるいは流動資産の区分や収支計算書の同一区分内での勘定科目の区分掲記、統合あるいは勘定科目名の変更等を行うものと、当該区分を超えて表示方法を変更するものがある。前者は単なる表示方法の変更であるが、後者の区分を超えての表示方法の変更は会計方針の変更として扱われる。
金額的重要性が高まったことにより、区分掲記する場合などは前者に該当する表示方法の変更であり、合理的根拠又は理由に基づくもので単なる表示形式上の変更にすぎないものは、会計方針の変更として取り扱わない。 - 会計基準等の改正に伴う会計方針の採用又は変更
会計基準等の改正によって特定の会計処理又は表示方法の採用が強制され、他の会計処理又は表示方法を任意に選択する余地がない場合、これに伴って会計方針を採用又は変更する場合も、当該変更の事実を明確にするために、正当な理由による会計方針の変更として取り扱う。この会計基準等の改正には、既存の会計基準の変更のほか、新たな基準の設定、実務指針等の公表・改廃及び法令の改正等が含まれる。 - 会計方針の変更に類似する事項
以下の事項は、会計処理の対象となっていた事実に係る会計上の見積りの変更、あるいは新たな会計処理の採用等であり、会計方針の変更には該当しない。
ア.会計上の見積りの変更
イ.重要性が増したことに伴う本来の会計処理への変更
ウ.新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の採用
(2)会計方針の変更による正当な理由
会計方針は、継続して適用とすることを前提とするが、正当な理由がある場合にはこれを変更することが認められる。
会計方針の変更による正当な理由については、次のとおり判断することが適当である。
- 会計方針の変更は学校法人の事業内容及び学校法人内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること
- 変更後の会計方針が一般に公正妥当と認められる学校法人の基準に照らして妥当であること
- 会計方針の変更は会計事象等を計算書類により適正に反映するために行われるものであること
- 会計方針の変更が財務情報を不当に操作することを目的としていないこと
【記載例】
重要な会計方針の変更等
-
高等学校の教職員の退職給与引当金について、従来、年度末要支給額から私学退職金団体よりの交付金相当額を控除した額の50パーセントを計上していたが、教職員の年齢構成、退職予定者数の実態等を勘案し消費収支計算を適正に行うため、当年度から100パーセント計上する方法に変更した。このため、退職給与引当金繰入額は従来の方法によった場合に比べ、


 円多く計上されている。
円多く計上されている。 - (表示方法の変更)
補助活動事業に係る収支は、従来純額により表示していたが、当年度から総額により表示することに変更した。なお、前年度に純額表示していた補助活動事業に係る収支を総額表示した場合は、補助活動収入

 円、人件費支出
円、人件費支出

 円、管理経費支出
円、管理経費支出

 円である。
円である。
基準第34条第1項第3号ないし第6号の注記
Q13
改正前の基準第34条の注記事項の取扱いはどのようになりますか。
A
従来の規定により記載を要することとされていた「退職給与引当金の額の算定方法」については、重要な会計方針として記載することとなる。「減価償却額の累計額の合計額」、「徴収不能引当金の合計額」、「担保に供されている資産の種類及び額」及び「翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額」については、従来どおりの記載である。
【記載例】
減価償却額の累計額の合計額 ![]()
![]()
![]() 円
円
徴収不能引当金の合計額![]()
![]()
![]() 円
円
担保に供されている資産の種類及び額
担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
土地 ![]()
![]()
![]() 円
円
建物 ![]()
![]()
![]() 円
円
定期預金 ![]()
![]()
![]() 円
円
翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 ![]()
![]()
![]() 円
円
有価証券の時価情報
Q14
有価証券の時価情報の注記は、どのように記載するのですか。
A
学校法人が時価の変動する有価証券を所有している場合、市場変動リスクにさらされており、会計年度末に相当の含み損又は含み益があれば取得価額による表示だけでは実態を表しているとは言い難いので、保有する有価証券の簿価総額あるいは含み損又は含み益に金額的重要性がある場合には有価証券の時価情報を注記する。時価情報の注記として、時価のある有価証券の貸借対照表計上額及びその時価並びにその差額を記載することとなる。なお、国債、地方債、政府保証債、その他の債券を満期まで所有する意思をもって保有する場合には、会計年度末における評価損益が多額であっても実現する可能性が低いことから、時価情報の注記として満期保有目的の債券を内書きして記載することが望ましい。
この時価情報を記載しなければならない有価証券の範囲は、時価のある有価証券のみである。ここでいう時価とは、取引市場が十分に確立している場合は市場価格であり、取引市場が十分に確立されていない場合には市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価格をいう。外貨建有価証券の時価については、外貨建の時価に年度末日の為替相場により円換算した額によることとなる。
【記載例1】
有価証券の時価情報
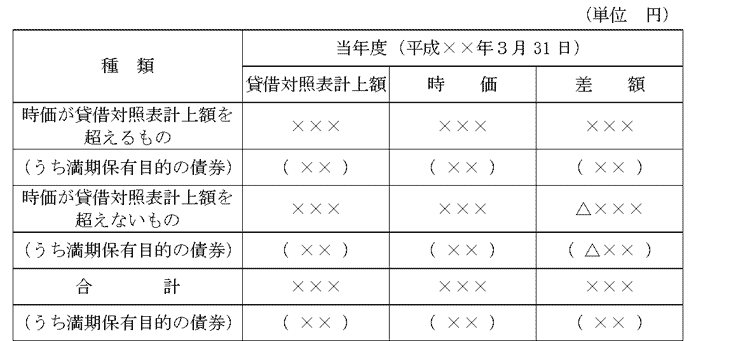
【記載例2】
有価証券の時価情報(貸借対照表の勘定科目ごとの区分によって記載した場合)
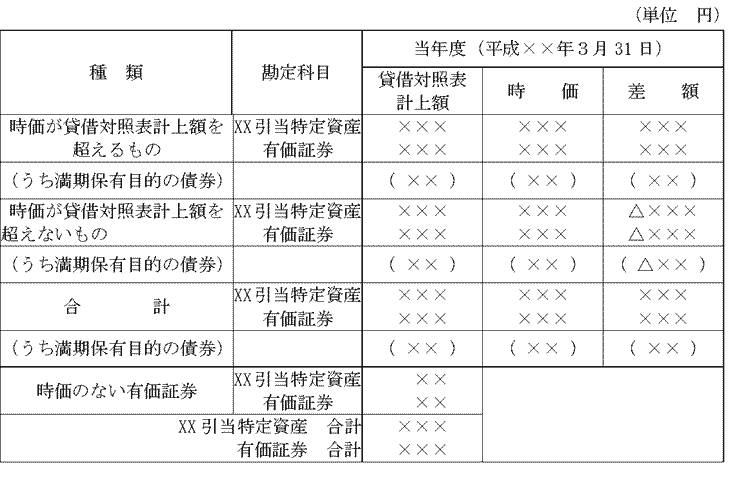
記載上の注意
(1)時価のある有価証券(特定目的の引当資産に含まれる有価証券を含む。)を記載する。なお、時価のない有価証券(特定目的の引当資産に含まれる有価証券を含む。)についても記載する場合には、時価のないものの貸借対照表計上額を明示して記載する。
(2)特定目的引当資産に含まれる預金等については記載を要しない。
このほか各学校法人の実態に応じて、次のように記載することも考えられよう。
- 株式、債券などの種類ごとに記載する。
- 有価証券の運用方針を記載したり、また、満期保有目的の債券の評価損益が多額であっても実現する可能性が低い場合にはその旨を注記する。
満期保有目的の債券
Q15
有価証券の時価情報の注記に記載する、満期保有目的の債券の「満期まで所有する意思をもって保有する」とは、どのようなことをいうのでしょうか。
A
満期まで所有する意思をもって保有するとは、学校法人が償還期限まで所有するという積極的な意思とその能力に基づいて保有することをいう。保有期間が漠然と長期であると想定し保有期間をあらかじめ決めていない場合、又は市場金利や為替相場の変動等の将来の不確定要因の発生いかんにより売却が予測される場合には、満期まで所有する意思があるとは認められない。また、資金繰計画等からみて、満期までの継続的な保有が困難と判断される場合には、満期まで所有する能力があるとは認められない。
満期保有目的の債券を償還前に売却等した場合の注記
Q16
満期保有目的の債券の一部を償還前に売却した場合、あるいは満期まで保有しないこととなった場合、どのように注記するのでしょうか。
A
当初、満期まで所有する意思をもって保有していたが、その一部を償還期限前に売却し、残りについても満期まで所有する意思がない場合には、時価情報の満期保有目的の債券には集計しない。また、会計年度末において満期まで所有する意思がない場合においても、時価情報の満期保有目的の債券には集計しない。企業会計においては、例えば満期保有目的の債券の売買目的への保有区分の変更によって、評価基準を原価法から時価法へ変更しなければならないが、学校法人会計では評価基準は原価法であるため、保有目的を変更しても評価基準に変更はなく、実態に合わせて注記に正しく集計すればよいものと考えられる。
デリバティブ取引の会計処理
Q17
学校法人会計では、デリバティブ取引はどのように会計処理されますか。
A
デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の時価の変動により保有者が利益を得たり、損失を被るものである。例えば、為替予約取引、金利スワップ取引があり、他社株転換社債、日経平均株価連動社債等のいわゆる仕組債もデリバティブが組み込まれた複合金融商品と考えられる。
学校法人会計では、デリバティブ取引を行っていても、デリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失が確定しているか、あるいは確定が見込まれる場合を除いて、契約上の決済時まで会計処理が行われない。ただし、デリバティブ取引の契約金額又は決済金額に重要性がある場合には決済時に多額の損益が計上される可能性があり、会計年度末において時価の変動による影響額を把握するために注記が必要となる。
デリバティブ取引の注記
Q18
デリバティブ取引の注記は、どのように記載するのですか。
A
デリバティブ取引の注記として、デリバティブ取引の対象物、種類、当年度末の契約額等、契約額等のうち1年超の金額、その時価及び評価損益を記載することとなる。当該取引がヘッジ目的であろうと投機目的であろうと注記する。
なお、当該デリバティブ取引の利用目的について、ヘッジ目的あるいは投機目的である旨を注記することが望ましい。また、ヘッジ目的で評価損益が実現する可能性が低い場合には、その旨を注記することも考えられよう。
【記載例】
デリバティブ取引
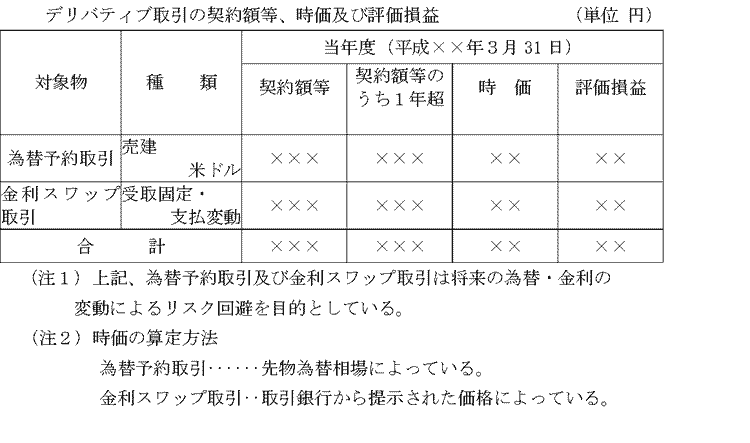
学校法人の出資による会社に係る事項
Q19
学校法人の出資による会社に係る事項の具体的な記載例はどのようなものですか。
A
当該項目は、平成13年6月8日及び平成14年1月7日の文部科学省高等教育局私学部参事官通知により、貸借対照表に学校法人の出資割合が2分の1以上の会社がある場合に、注記として記載するように第1号通知で定められている。また、学校法人委員会報告第38号「学校法人の出資による会社に係る注記に関する監査上の取扱い」(平成14年1月17日)により、その記載例が定められている。当該項目も注記事項の一つであるため、記載内容は従来と変わるところはない。
ア.名称及び事業内容
イ.資本金又は出資金の額
ウ.学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
エ.当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額
オ.当該会社の債務に係る保証債務
【記載例1】
学校法人の出資による会社に係る事項
当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。
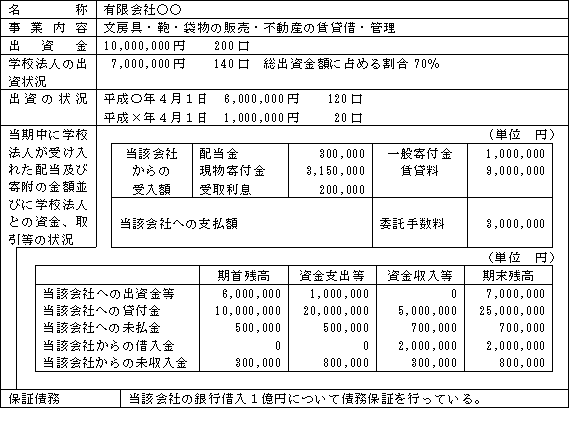
【記載例2】
学校法人の出資による会社に係る事項
当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。
- 名称及び事業内容 株式会社

 清掃・警備・設備関連業務の委託
清掃・警備・設備関連業務の委託 - 資本金の額


 円
円 - 学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日
平成
 年
年
 月
月
 日
日 

 円
円

 株
株
総出資金額に占める割合
 パーセント
パーセント - 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額 受入配当金

 円、寄付金
円、寄付金
 円、当該会社からの長期借入金
円、当該会社からの長期借入金

 円
円 - 当該会社の債務に係る保証債務
学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。
主な外貨建資産・負債
Q20
主な外貨建資産・負債の注記は、どのように記載するのですか。
A
外貨建の預金及び借入金等は、外貨建を円貨に換算して表示するが、これらの外貨建資産・負債等は、為替変動の影響を受けることにより、学校法人の財政及び経営の状況に影響を及ぼすことがある。計算書類上は外貨建であることが表示されないので、主な外貨建資産・負債につき、取得時又は発生時の為替相場で換算している場合には、その旨、年度末日の為替相場による円換算額及び換算差額を注記することとなる。なお、外貨建有価証券については、為替変動の影響が有価証券の時価情報の注記に含まれることになるため、記載を要しない。
【記載例】
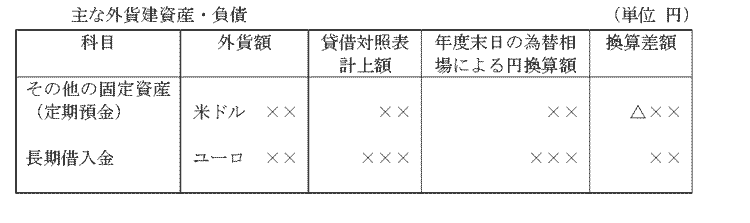
偶発債務
Q21
偶発債務の注記は、どのように記載するのですか。
A
偶発債務は、将来において当該法人の負担となる可能性のあるものをいい、将来債務を負う又は損害を被る可能性が年度末日において既に存在しているため注記が求められるものである。なお、学校法人の出資による会社に係る事項で当該会社の債務による保証債務を注記している場合には、重複することになるため、ここでの記載を要しないと考えられる。
【記載例】
偶発債務
ア.債務保証を行った場合
下記について債務保証を行っている。
教職員の住宅資金借入![]()
![]()
![]() 円
円
役員の銀行借入金![]()
![]()
![]() 円
円
A学校法人(姉妹校)の銀行借入金![]()
![]()
![]() 円
円
B社(食堂業者)の銀行借入金![]()
![]()
![]() 円
円
理事(又は監事)が取締役であるC社の銀行借入金![]()
![]()
![]() 円
円
イ.係争中の事件がある場合
当学校法人を被告とする![]()
![]() 事件について
事件について![]()
![]() と係争中であり、
と係争中であり、![]()
![]()
![]() 円の損害賠償請求を受けている。
円の損害賠償請求を受けている。
ウ.手形の割引又は裏書を行った場合
手形の割引高![]()
![]()
![]() 円
円
手形の裏書譲渡高![]()
![]()
![]() 円
円
所有権移転外ファイナンス・リース取引
Q22
所有権移転外ファイナンス・リース取引の記載例は具体的にどのようなものですか。
A
当該項目は、委員会報告第37号により、貸借対照表に注記すべき場合が定められている。なお、学校法人においてリース料総額に重要性がない場合には当該注記は省略することができる。
【記載例】
所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
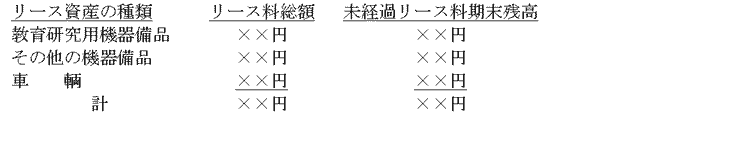
純額で表示した補助活動事業の収支
Q23
純額で表示した補助活動事業の収支の記載例は具体的にどのようなものですか。
A
「1.重要な会計方針」で補助活動事業の収支を純額表示している旨の注記を行った場合には、収支相殺の範囲及び金額を注記する必要がある。
【記載例】
純額で表示した補助活動事業の収支
純額で表示した補助活動事業の収支を相殺した科目及び金額は次のとおりである。
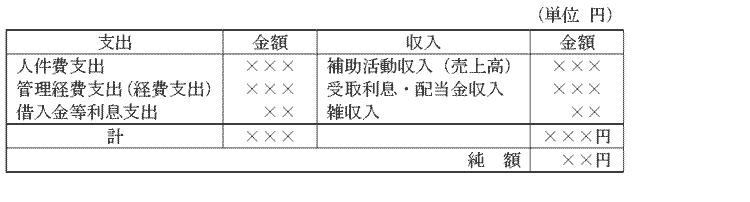
関連当事者との取引の注記
Q24
学校法人における関連当事者との取引を注記することの意義はどのようなことですか。
A
関連当事者との取引は恣意性の介入する余地があるため特に透明性が要求される。したがって、関連当事者が自己又は第三者のために学校法人と取引を行った場合には、取引内容を記載することによって学校法人の計算書類の透明性を高めることとなる。
関連当事者の範囲
Q25
関連当事者の範囲はどこまでですか。
A
第1号通知による関連当事者の範囲は、以下のとおりである。
- 関連当事者とは、次のとおりである。
ア.関係法人
イ.当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人
ウ.当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又はこれらの者が支配している法人 - 関連当事者との取引の注記の対象となる関係法人とは、一定の人的関係、資金関係等を有する法人をいい、具体的には以下の場合に該当することとされている。
ア.一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること
イ.法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること
ウ.法人の意思決定に関する重要な契約等が存在すること
ただし、財務上又は事実上の関係から法人の意思決定に関し重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には、対象外とされている。
関連当事者の注記の対象となる関係法人とは、学校法人の出資割合が2分の1超という形式的な支配のみならず、上記のように一定の人的関係、資金関係等も判断基準となる。なお、学校法人の出資割合が2分の1以上の会社については、別途注記されるため、関係法人であっても関連当事者との取引の注記事項としては扱わないものとされている。
また、役員の出資割合が2分の1以下であり、それだけでは支配しているとはいえない法人であっても、役員の近親者又はこれらの者が支配する法人の出資割合と合計して2分の1超である法人についても、当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又はこれらの者が支配している法人に該当することとなる。
このように注記の対象となる関連当事者とは、例えば学校法人の出資割合が2分の1超という形式的な支配のみならず、実質的に法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めている場合も該当するものと考えられる。
(参考)配偶者又は2親等以内の親族
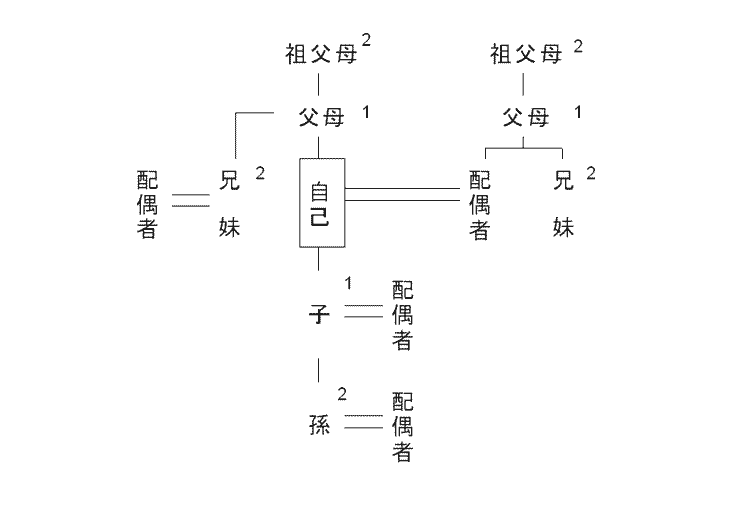
会計年度中の関連当事者の変更
Q26
会計年度中に関連当事者でなくなった場合の取引も注記しなければなりませんか。
A
関連当事者に該当するか否かは、個々の取引の開始時点で判定するものとし、関連当事者が会計年度中に関連当事者に該当しなくなった場合には、関連当事者に該当している間の取引については注記しなければならない。なお、同一会計年度における取引であっても関連当事者に該当しなくなった後の取引については記載を要しない。
関連当事者との取引の記載事項
Q27
注記すべき関連当事者との取引の記載事項はどのようなものですか。
A
取引の内容については、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記することが望ましい。なお、Q19に示したとおり、学校法人の出資による会社に係る事項に注記した事項については重複を避けるため、ここでの注記を要しない。
(1)当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容(及び当該会社等の議決権に対する当該学校法人の所有割合)
(2)当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業
(3)当該学校法人と当該関連当事者との関係
(4)取引の内容
(5)取引の種類別の取引金額
(6)取引条件及び取引条件の決定方針
(7)取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
(8)取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
なお、具体的記載例は以下のとおりである。
【記載例】
関連当事者との取引
関連当事者(関連当事者)との取引の内容は、次のとおりである。
| 属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
| 関係法人 | C社(注1) | 東京都 |
- | 兼任3名 | C社製品の購入 | 機器備品の購入 (注2) |
未払金 | ||||
| 当法人の銀行借入に対する被保証 (注3) |
- | - | |||||||||
| 当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人 | D社 (注4) |
神奈川県 |
清掃請負業 | 10パーセント | - | 清掃委託 | 清掃料の支払 (注5) |
未払金 | |||
| 債務保証 (注6) |
- | - | |||||||||
| 保証料の受入れ (注6) |
- | - | |||||||||
| 理事 | 佐藤 三郎 |
- | - | - | - | - | 設備の賃貸 | 住宅の賃貸料 (注7) |
- | - | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | E社 (注8) |
大阪市 |
食堂等の運営管理 | - | - | 食堂等の委託契約の締結 | 業務委託費の支払 (注9) |
未払金 | |||
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) C社の役員及び職員が当法人の理事の過半数を占めている。
(注2) 機器備品の購入については、C社以外からも複数の見積りを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定している。
(注3) 当法人は銀行借入に対してC社より債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。
(注4) 当法人の関係法人であるC社の子会社である。
(注5) 清掃料の支払については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較の上、交渉により決定している。
(注6) D社の銀行借入(![]()
![]() 円、期限
円、期限![]()
![]() 年)につき、債務保証を行ったものであり、年率
年)につき、債務保証を行ったものであり、年率![]()
![]() パーセントの保証料を受領している。
パーセントの保証料を受領している。
(注7) 設備の賃貸は、近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を締結している。
(注8) 理事長![]()
![]()
![]() 及びその近親者が議決権の80パーセントを直接保有している。
及びその近親者が議決権の80パーセントを直接保有している。
(注9) 食堂等の業務委託費については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。
(1)「属性」の欄には、関連当事者の種類を記載する。具体的には、関係法人、当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人、理事長、理事、監事、役員の近親者、当該学校法人の役員及びその近親者が支配している法人、団体等があげられる。なお、複数の属性をもつ関連当事者については、影響が強いと考えられる属性により重要性を判断することが考えられる。
(2)「住所」の欄には、関連当事者が法人、団体等の場合、市町村(政令指定都市においては区)までを記載する。ただし、役員及びその近親者等、個人である場合には記載を要しない。
(3)「議決権の所有割合」の欄には、当該学校法人の所有割合を記載する。その他は注記で補う。
(4)「役員の兼任等」の欄には、兼任をしている役員のほか、出向、転籍等の形態により派遣されている役員の年度末日現在の人数を記載する。学校法人の職員が出向又は転籍して当該法人の役員の過半数を占め、当該法人の意思決定に関する機関の構成員が過半数を占めることとなった場合についても、兼任の数に含める。
(5)「事業上の関係」の欄には、資金援助、設備の賃貸借、業務委託等の関係内容について簡潔に記載する。
(6)「取引金額」の欄には、会計年度中の関連当事者である期間の取引について、取引の種類ごとに総額で記載する。
(7)「科目」及び「期末残高」の欄には、取引により発生した債権債務に係る主要な科目及びその期末残高を記載する。
(8)取引条件及び取引条件の決定方針を注記することが望ましい。なお、取引条件が、一般の取引に比べ著しく異なる場合には、その条件を具体的に記載する。
(9)役員及びその近親者等、個人である場合には、「資本金又は出資金」及び「関係内容」の欄の記載を要しない。
記載を要しない取引
Q28
記載を要しない取引はどのようなものですか。
A
注記を要しない取引は第1号通知において、次のとおり示されている。
ア.一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
イ.役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払
ウ.当該学校法人に対する寄附金
なお、関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても取引金額が時価に比して著しく低い金額等による場合には、原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断して注記することとされていることに留意しなければならない。
また、その他取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については、省略することが考えられる。その場合の重要性の判断については、学校法人の規模によって異なるため、学校法人が決定し毎年度継続的に採用することが望ましいが、例えば、以下のように決定することが考えられる。
- 役員及びその近親者との取引については、100万円を超える取引についてはすべて注記する。
- その他の関連当事者との取引は、帰属収入の1/100に相当する金額(その額が500万円を超える場合には、500万円)を超える取引についてはすべて注記する。
後発事象
Q29
後発事象の注記は、どのように記載するのですか。
A
監査対象となる後発事象とは、会計年度末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した会計事象で、学校法人の財政及び経営の状況に影響を及ぼすものをいい、修正後発事象と開示後発事象に区分される。
修正後発事象は、会計年度末日後に発生した事象ではあるが、その実質的な原因が会計年度末日現在において既に存在しており、会計年度末日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないしより客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない事象である。したがって、重要な事象については、計算書類の修正を行うものである。開示後発事象は、会計年度末日後において発生し、当該会計年度の計算書類には影響を及ぼさないが、次年度以降の計算書類に影響を及ぼす事象である。したがって、重要な事象については、学校法人の財政及び経営の状況に関する的確な判断に資するため、当該会計年度の計算書類に注記を行うものである。
開示後発事象のうち、次年度以降の計算書類に重要な影響を及ぼすものについては、次年度以降の学校法人の財政及び経営の状況を正確に判断するために後発事象として注記することとなる。
【記載例】
ア.火災により被害を受けた場合
平成![]()
![]() 年5月
年5月![]() 日、
日、![]()
![]() 高等学校本館が火災により焼失した。この火災による損害額及び保険の契約金額は次のとおりである。
高等学校本館が火災により焼失した。この火災による損害額及び保険の契約金額は次のとおりである。
建物![]()
![]()
![]() 円
円![]()
![]()
![]() 円
円
構築物
![]()
![]()
![]() 円
円![]()
![]()
![]() 円
円
なお、機器備品の損害額は調査中である。
イ.係争事件が新たに発生、又は解決した場合
平成![]()
![]() 年4月
年4月![]() 日、本学園を被告とし、
日、本学園を被告とし、![]()
![]() 社から
社から![]()
![]()
![]() 円の賠償請求を受ける
円の賠償請求を受ける![]()
![]() 事件の訴訟が提起された。
ウ.募集の停止又は再開
事件の訴訟が提起された。
ウ.募集の停止又は再開
平成![]()
![]() 年5月
年5月![]() 日の理事会において、新年度より
日の理事会において、新年度より![]()
![]() 学校の募集を停止することを決定した。
学校の募集を停止することを決定した。
その他考えられる注記項目
Q30
その他考えられる注記項目はどのようなものですか。
A
その他考えられる注記項目として、事例を示すと以下のとおりである。
(1)その他の重要な会計方針
- 減価償却の方法等について
減価償却の方法については、基準第26条において、減価償却の方法は定額法と定められており、その他の方法の選択はできない。一方、減価償却額の計算の構成要素である耐用年数については、学校法人が自主的に決定している場合のほか、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省令)による場合又は学校法人委員会第28号「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」(昭和56年1月14日、改正平成13年5月14日)に掲げる「固定資産の耐用年数表」によっている場合も妥当な処理として認められている。さらに残存価額を零として行った場合であっても、妥当な処理として認められている。したがって耐用年数等の相違によって、その減価償却額の金額が異なり、消費収支計算に影響を及ぼすと判断される場合には、どのように算定しているかを注記することが望ましい。
【記載例】
残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
耐用年数は学校法人委員会報告第28号による耐用年数を採用しており、主な耐用年数は以下のとおりである。
建物 50年
構築物 15年
機器備品 10年 - 減価償却資産の計上基準について
基準では減価償却資産の計上基準について何ら規定しておらず、また各都道府県によっては計上基準について定めている場合もあるが、その設定金額の範囲は一定ではない。しかし、減価償却資産は基本金の設定対象となり消費収支差額に影響を及ぼすと判断されるので、当該計上基準を注記することが考えられる。
【記載例】
取得日後1年を超えて使用する有形固定資産(土地、建設仮勘定、図書を除く。)のうち、1個又は1組の金額が10万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生生徒が使用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品に計上している。
(2)その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
- 退職年金制度について
退職給与引当金に記載した退職金制度とは別に退職年金制度に加入している場合には、その制度の概要、年金資産額、退職給付債務(又は年金財政計算上の責任準備金)の額等を注記することが考えられる。 - 継続企業の前提について
いわゆる「継続企業の前提」については、従来、学校法人では該当事例がほとんどなく開示の慣行も成熟していない。また、どのような状態が、いわゆる「継続企業の前提」に重要な疑義を抱かせる場合に該当するのか詳細な検討が行われていない。しかし、学校法人がいわゆる「継続企業の前提」に重要な疑義を抱かせる場合に該当しているという状況を自ら認識し、何らかの対策等を自主的に行っている場合には、自主的に講じている対策等を注記することが望まれる。
適用初年度の留意事項
Q31
適用初年度に留意しなければならないことはありますか。
A
適用初年度となる平成17年度の計算書類に「会計処理及び表示方法の変更」の注記が必要であり、基準の改正に伴い、当会計年度から改正後の基準によっている旨を必ず記載する。また、基準の改正に伴い従来と同一の方法によった場合と比較して変更による影響額を記載する。なお、変更による影響がない場合にも影響がない旨の記載を要する。
【記載例】
(会計処理及び表示方法の変更)
「学校法人会計基準」(昭和46年文部省令第18号)の改正に伴い、当会計年度から改正後の基準によっている。なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して基本金組入額が![]()
![]() 円増加し、当年度消費収入超過額が同額減少している。また、基本金取崩額が
円増加し、当年度消費収入超過額が同額減少している。また、基本金取崩額が![]()
![]() 円増加している。
円増加している。
以上
お問合せ先
高等教育局私学部参事官付
-- 登録:平成21年以前 --