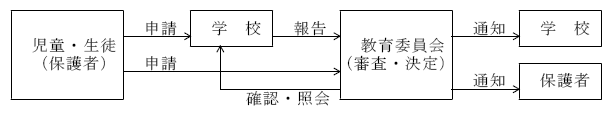| (1)品川区の教育を推進する学校選択制(東京都品川区) |
|
| 1 |
制度の概要等 |
| |
| (1) |
実施の経緯 |
| |
 |
導入前の状況 |
| |
昭和62年5月臨時教育審議会「教育改革に関する第三次答申」や、平成8年の行政改革委員会の提言などにより、文部省(当時)から平成9年に「通学区域制度の弾力的運用」について通知が出されている。これらを踏まえ、品川区では従来からの指定校変更制度の中で、審査基準を明確にしながら積極的に弾力的運用を図ってきた。
指定校変更の状況を見ると、平成5年度は186件であったものが、平成11年度では385件と倍以上に伸びており、その中の65パーセント以上が、学区域の境から約100メートルの範囲であれば他の学校に変更できる「調整区域」を理由とする変更であり、このことからも保護者の学校を選択したいという希望は高まってきていた。 |
 |
品川区教育改革プラン「プラン21」 |
| |
それまでも、学校教育においては「個に応じた指導の徹底」、「特色ある学校の創造」、「教育の質向上」などの諸課題が指摘されるとともに、子どもたちの実態についても、いじめや学校生活の不適応など、教育関係者はもとより地域社会の様々な努力にもかかわらず、他の自治体と同様に、なかなか解決策が見出せない状況があった。
そこで品川区教育委員会では、この閉塞状態を1つでも2つでも克服し、新たな展望を開きたいとの熱い思いから、品川区教育改革「プラン21」をスタートさせた。
「プラン21」の目標は、各学校が特色づくりを進める中で地域、家庭といかに連携して、学校そのものの個性化や持ち味を出していくことにより、学校全体の活性化を図っていくことにある。
その一環として、平成12年度から、小学校の新1年生を対象に、子どもに適した教育を受けさせたいという保護者の希望に添った学校の選択ができる「通学区域のブロック化」を実施し、平成13年度からは、中学校の新1年生を対象に「通学区域制度の弾力化」の実施として自由選択制を導入した。 |
|
| (2) |
制度の枠組み |
| |
| ○ |
中学校【通学区域制度の弾力化(自由選択制)】 |
| |
中学校の新1年生を対象に、従来の通学区域や指定校変更の制度は維持しつつ、区内の全18校の中から選択できる。
各中学校とも、現行の通学区域内の生徒は無条件で入学が可能であり、当該中学校の通学区域以外からの入学希望者について受入枠を設定し、受入枠を超える申請があった場合は抽選を行うことができる。
また、抽選に漏れた場合には補欠順位を設定し、希望校において転出する等による辞退者が出た場合、補欠順位の上位の者から繰り上げて希望申請のあった学校へ就学指定換えを行う。
なお、繰り上げがなかった場合であっても、従来の通学区域以外の学校への指定校変更の申立も可能である。 |
|
| |
(参考)小学校【通学区域のブロック化】
小学校の新1年生を対象に、従来の通学区域や指定校変更の制度は維持しつつ、区内の通学区域を4つにブロック化し、住所地の通学区域が属するブロック内の小学校ならば、どの小学校でも選択できる。区立小学校は全40校であり、選択できる学校数はブロックにより8~12校である。 |
|
| 2 |
事務の流れ(平成18年度入学予定者を対象とした事務の流れ) |
| |
| 時期 |
内容 |
場所等 |
| 9月下旬(小学校・中学校) |
希望申請書・学校案内パンフレット・就学時検診票・他案内文等 |
封書にて各家庭に郵送 |
| 9月26日~10月31日(小学校・中学校) |
希望申請受付期間 |
郵送または学務課窓口 |
| 11月1日~30日(小学校) |
就学時検診実施期間 |
各小学校 |
| 11月10日(中学校) |
抽選通知発送 |
対象家庭に郵送 |
| 11月16日(小学校) |
抽選通知発送 |
対象家庭に郵送 |
| 11月18日(中学校) |
抽選 |
区役所会議室(公開抽選) |
| 11月24日(小学校) |
抽選 |
区役所会議室(公開抽選) |
| 11月25日(中学校) |
抽選結果通知 |
各家庭に郵送 |
| 11月30日(小学校) |
抽選結果通知 |
各家庭に郵送 |
| 12月8日(中学校) |
就学通知発送 |
メールシーラーにて郵送 |
| 12月19日(小学校) |
就学通知発送 |
メールシーラーにて郵送 |
|
| 3 |
実績と傾向 |
| |
| (1) |
学校選択制を導入して |
| |
当区では、小学校は平成12年度から、中学校は1年遅れる平成13年度から学校選択制を導入し、すでに平成18年度の新入生の学校選択希望も含め、それぞれ7年と6年が経過した。
この間、選択制を利用する保護者は、小学校では当初の12.9パーセントから現在は22.9パーセントとなり、同様に中学校では当初22.0パーセントから29.0パーセントとなっている。
このことは、品川区が推進してきた「プラン21」の趣旨に沿った、学校選択の制度・趣旨が区民の方々に理解され、定着してきたものと考えられる。
|
| (2) |
保護者・学校等の変化 |
| |
当初は保護者にとっても学校を選ぶことが出来るということについて、ある意味での戸惑いがあったことと思われる。
各学校は学校選択制の開始にあたり、それぞれ特色を打ち出してきたが、学校・保護者双方の想いが一致するのに多少の時間が必要だったのではないだろうか。
しかし現在においては、アンケートの結果からも「学校の特色ある教育活動を考えて」自分の行きたい学校を選択した方が約19パーセントと年々上昇してきた。
まだまだ満足できる率ではないが、今後も保護者に選択の際重要な基準となるよう努力をしていかなければならない。
一方、学校の現場をみると、選択をされる立場に置かれたことにより、マンネリズムからの脱却を余儀なくされる状況に置かれた。
つまり自分達で学校を変えなければ選んでもらえないという危機感が、広く教職員の中に浸透してきた。
教職員が自分の持っている力を最大限発揮することによって自ずと学校は特色を持つのだという意識を一人一人が持つこととなり、結果、教職員の意識は格段に変わってきたと考える。
また学校とは切り離せない関係にある地域との関係が、学校選択制の導入により希薄になるという質問がよくあるが、保護者が、子どもの行く学校がよりよい学校になることを望む結果、PTA・学校行事への参加率が高くなったとの声も多く聞かれる。
地域の方々においても学校外部評価制度を通じ、さらに学校との結びつきが強くなってきている。
結果的に、学校・地域・保護者が子供の教育を核として、より良い状態を形成している。 |
|
| 4 |
評価等 |
| |
【選択制のメリット・デメリットについて】
選択制のメリットは色々あるが、今回は、7年目を迎えた中で、よく質問のあるデメリットの部分について考察してみたい。
デメリットとしてまず第一によく聞かれるのが、学校間格差が出るのではないかという質問である。
この学校間格差の内容はまず人数的なもの、教育の内容的な意味が含まれていると思う。
人数的なことについては、選択制を行っている以上、人数の偏りが出ることは当然のことと考える。
しかし、多人数・少人数それぞれ、その中で学校の特色を出していくことがまさに品川区が推し進めている「プラン21」のめざしている目的の推進力となるはずである。
また、教育の内容であるが、児童・生徒の人数によって教育の内容に差が出るはずもなく、先ほど述べたようにいかにプラス の教育内容を付加し、これをいかにシステム化していくかが重要であり、単にデメリットとなるとは考えていない。 の教育内容を付加し、これをいかにシステム化していくかが重要であり、単にデメリットとなるとは考えていない。
さらに地域との関係が希薄になるとの意見も聞かれるがこの点については先ほど述べたとおりである。
選択制を導入すれば、事務局としても色々事務も増えるが、学校・保護者に賛同されるように日々さらなる工夫をしていくことが肝要と考える。 |
| (2)尾道市小中学校学校選択制度-夢と志を抱く子どもの育成をめざして-(広島県尾道市) |
|
| 1 |
制度の概要 |
| |
| (1) |
実施の経緯・趣旨 |
| |
人口減少、少子高齢化の進行に伴う児童生徒数の全市的な減少傾向と、地域的な増減の偏りは、従来からの通学区域制度の下で学校の小規模化とともに一方で学校の大規模化の実態を生起させていた。
このような状況の中で、尾道市教育委員会(以下に表記される「教育委員会」は、「尾道市教育委員会」とする。)では、平成13年10月5日、尾道市立学校通学区域審議会に「尾道市立小学校・中学校の適正配置および通学区域について」諮問した。
審議会において、市の教育環境の実態把握や将来予測、市民の意識調査などを行い、審議検討を重ね、平成14年11月29日に、これからの小中学校の在り方や適正規模・適正配置の基本的な考え方、望ましい通学区域等について答申がなされた。
この答申を踏まえ、通学区域制度を弾力化し保護者のニーズに応えるものとして、平成16年度の小中学校入学者から「学校選択制度」を導入した。
一方、本市では、平成14年度に教育計画「尾道教育プラン21」を策定し、特色ある学校づくりを進めており、学校選択制度の実施により、さらに保護者や児童生徒から信頼され選択される学校をめざした各種の取組みを促進した。
また、平成17年度に新たに策定した「尾道教育さくらプラン」においても、市民の願いと信頼に応えるため、特色ある教育システムを確立することを目標として、制度の充実を図っているところである。
|
| (2) |
目的 |
| |
 |
保護者・児童生徒の多様なニーズに応える。 |
 |
保護者の学校への関心、自ら選んだ責任による学校への協力意識を高める。 |
 |
選択による評価で教職員が経営感覚を身につけることにより、教育改革の推進を図る。 |
 |
選択されるための特色ある学校づくりを展開し、学校の活性化を図るとともに、開かれた学校づくりを促進する。 |
|
| (3) |
対象者・条件等 |
| |
 |
対象者 |
| |
小学校、中学校とも新1年生を対象として、各学校が受入可能な範囲で、市内全域からの受入を行う。 |
 |
条件等 |
| |
| ・ |
選択し入学した学校には、原則として、卒業まで通学すること。 |
| ・ |
通学の方法は、各学校の規則に従い、通学途上の安全管理は保護者の責任であることを理解し、通学方法や通学時間、地域活動への参加等を十分考慮したうえで選択すること。 |
|
|
| (4) |
受入可能人数の設定 |
| |
| ・ |
教育委員会は、指定通学区域外からの受入可能人数を、指定通学区域内の入学予定者の人数や各学校の実情等を考慮して決定する。 |
| ・ |
教育委員会は、決定に当たっては各校長の意見を十分に聴取し、考慮する。 |
|
| (5) |
学校選択の方法 |
| |
 |
制度の周知と学校情報の提供 |
| |
| ・ |
市広報誌やホームページ、尾道エフエム放送の行政番組などによる制度の周知 |
| ・ |
学校紹介冊子を教育委員会から対象者に送付 |
| ・ |
尾道ケーブルテレビでの学校紹介番組の放映(1日1校各3分) |
| ・ |
学校公開期間を設けて、各学校でオープンスクール等の実施 |
|
 |
申請方法 |
| |
| ・ |
通学区域以外の学校を希望する者について、教育委員会が定めた期間中、学校選択希望申請書を受付ける。 |
| ・ |
申請受付後、教育委員会が定めた期間中に限り、希望学校の変更申請を受付ける。 |
|
 |
抽選と補欠登録 |
| |
| ・ |
受入可能人数を超えた申請があった場合は、公開抽選により入学者を決定する。 |
| ・ |
抽選において選外となった者で、なお希望する者は補欠登録し、2月末まで繰上げを待つことができる。 |
|
|
|
| 2 |
事務の流れ(平成18年度入学者を対象とした学校選択制度に係る事務) |
| |
| 時期 |
内容 |
備考 |
| 8月26日 |
各学校の受入可能人数等実施内容決定 |
教育委員会議 |
| 9月上旬 |
募集概要を市広報誌9月号・市ホームページに掲載 |
|
| 9月15日~11月11日 |
学校紹介番組の放映 |
尾道ケーブルテレビ |
| 10月上旬 |
学校紹介冊子・募集要項・申請書の配付 |
小・中入学予定者 |
| 学校公開日程の市広報誌10月号への掲載 |
|
| 学校紹介番組の放送 |
尾道エフエム放送 |
| 11月1日~11月21日 |
学校選択希望申請受付 |
尾道市教育会館 |
| 11月24日~11月30日 |
学校選択希望申請変更届の受付 |
尾道市教育会館 |
| 12月1日 |
申請件数(抽選の有無)の公表(抽選対象者へは12月2日に通知書発送) |
市役所・支所・学校に掲示、ホームページ |
| 12月9日 |
公開抽選 |
|
| 12月9日~12月16日 |
補欠登録申請受付 |
登録は2月末まで有効 |
| 1月中旬 |
入学通知書発送 |
|
|
| 3 |
実績と傾向 |
| |
| 年度(入学年度) |
対象/全体学校数 |
受入可能人数 |
申請のあった学校数 |
申請者数 |
抽選校数 |
選外者数 |
| 16年度 |
小学校 12/20校 |
155人 |
6校 |
60人 |
1校 |
17人 |
| 中学校 8/11校 |
55人 |
4校 |
31人 |
1校 |
5人 |
| 17年度 |
小学校 20/20校 |
182人 |
16校 |
95人 |
2校 |
19人 |
| 中学校 11/11校 |
85人 |
7校 |
34人 |
1校 |
1人 |
| 18年度 |
小学校 25/26校 |
215人 |
15校 |
79人 |
2校 |
9人 |
| 中学校 13/13校 |
100人 |
9校 |
40人 |
2校 |
7人 |
|
| |
| ※1 |
平成17年3月28日御調町と向島町が尾道市に編入合併。旧御調町、旧向島町の小中学校について、平成18年度から対象とした。 |
| 2 |
平成18年度小学校1校が統廃合の予定である。 |
|
| |
平成16年度入学者を対象にした制度運用に当たっては、初年度ということもあり、募集は小学校20校中12校、中学校11校中8校に留まった。選択希望申請者数は小中学校各1校で受入可能人数を超え、公開抽選を実施した。
制度運用2年目からは、制度の趣旨に則り、保護者・児童生徒に、できるだけ選択の機会を提供するため全校で募集することに努め、平成17年度は小学校2校、中学校1校で申請が受入可能人数を超え公開抽選を実施した。
平成18年度入学者を対象とした制度運用に当たっては、市町村合併により増加した学校についても募集を行い、抽選は小中学校各2校で実施した。
小中学校とも通学手段の利便性が高い市街地に立地する学校、特に文部科学省の研究指定を受けて特徴的な教育課程、学校経営を行っている学校への選択希望申請が多い傾向が続いている。
|
| 4 |
評価等 |
| |
平成16年度、平成17年度学校選択制度の実施後、小中学校新1年生の保護者全員に対してアンケートを実施している。この結果からは、保護者の概ね8割程度が当該制度に肯定的な意見であると判断している。
また、アンケートでは、より多くの選択・入学の機会を求める意見が多く見受けられたことから、全ての学校で受入可能人数の設定を行い選択の機会を確保するように努めている。
学校の施設や設備などの面から受入枠を設けなければならず、抽選を実施する状況であり、全ての希望には沿えていないが、通学区域制度を維持する中で、可能な限り保護者・児童生徒のニーズに応える制度として、学校選択制度は有効に機能していると考える。 |
| (3)学校活性化を目指した「学校選択制」の導入(福岡県穂波町) |
|
| 1 |
制度の概要 |
| |
本町では、それぞれの学校の活性化・特色化を目指し、学校選択制を導入した。
平成12年10月、通学区域に関する規則を改正し、町内で一番小さな学校「高田小学校」について、13年度から通学区域を全町に拡大した。結果は、4名が従来の通学区域外から転入学した。その時穂波町全小学校・中学校の通学区域の弾力的運営が検討され、平成14年度から町内すべての小中学校について、町内全域からの学校選択制を実施している。
今日の教育改革は新しい学校づくり(開かれた・特色ある・信頼できる学校)を目指しているが、学校が活性化しているかどうかは、子どもたちや保護者等による外部評価が有効である。
学校選択制は学校(校長・教職員)の外部評価であり、外部評価を受け、よいところは伸ばし、悪いところは改善することは学校活性化への手段になると考えた。
近年、子どもたちの問題行動が多発し深刻化しているが、まだまだ学校の危機感は少ないといえる。学校選択制の導入は、学校・教職員が選ばれる立場にたつという、今までの学校に逆転の発想を期待したものである。学校活性化に必要な職員の意識の変革も大きなねらいである。
|
| |
| ○ |
対象となる学校・児童生徒数(平成17年4月1日現在) |
| |
| ・ |
楽市小学校: |
390名 |
|
学級数13 |
|
うち特学1 |
| ・ |
平恒小学校: |
207名 |
学級数7 |
うち特学1 |
| ・ |
若菜小学校: |
415名 |
学級数14 |
うち特学2 |
| ・ |
椋本小学校: |
345名 |
学級数12 |
|
| ・ |
高田小学校: |
72名 |
学級数6 |
|
| ・ |
穂波東中学校: |
306名 |
学級数10 |
うち特学1 |
| ・ |
穂波西中学校: |
410名 |
学級数14 |
うち特学2 |
|
|
| 2 |
事務の流れ |
| |
| ・ |
学校紹介パンフレット及び入学・転学希望書の配付 |
|
10月中旬 |
| ・ |
希望申込み締切り |
2学期末(現実には3月中まで可)転入・転居他特別の事情については随時 |
| ・ |
学校を選ぶに当たって |
選ぶのは自由だが通学(方法・経費)は自己責任 |
| ・ |
受入数 |
各学校・学年で異なる |
| ・ |
通学期間 |
学級編制上、転入学後は原則一年間学校の変更はできない。 |
| ・ |
学校見学 |
各学校で日時を設定 |
| ・ |
受付 |
各学校及び教育委員会 |
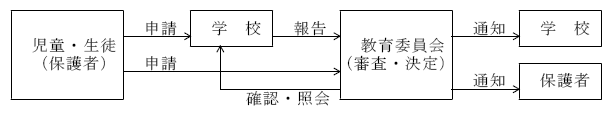
|
| 3 |
実績と傾向 |
| |
| 平成13年度(高田小学校のみ実施):申込者数 4名(新規申請4名) |
| 平成14年度:申込者数 35名 |
|
| 新規申請31名 |
〈内新入学5名〉 |
| 前年度からの継続4名 |
|
|
|
| 平成15年度:申込者数 53名 |
| 新規申請26名 |
〈内新入学8名〉 |
| 前年度からの継続27名 |
|
|
|
| 平成16年度:申込者数 72名 |
| 新規申請31名 |
〈内新入学9名〉 |
| 前年度からの継続41名 |
|
|
|
| 平成17年度:申込者数 73名 |
| 新規申請17名 |
〈内新入学17名〉 |
| 前年度からの継続56名 |
|
|
|
| (4月1日現在) |
|
| 4 |
評価等 |
| |
学校を選択してもらうために不可欠な学校紹介パンフレットを作成し、各学校の特色や取組を掲載したことにより、保護者に「学校選択制」の趣旨や町内各学校の様子を周知することになった。一方でこのパンフレットは、学校から保護者住民への公約ともいえるものであり、説明責任を果たすものであると考えている。
具体的数値目標を提示し、それに向かって努力する教職員の姿が見えるようになれば、保護者や地域の協力の支援が得やすくなる。保護者や地域と学校との関係は従来よりよくなり学社連携がすすんできたと評価している。
自ら学校を選んで通わせるということは、当然保護者にも選んだという責任が伴うことになる。学校には選ばれたという責任があり、初めて両者に責任の共有が始まる。その意味で「学校選択制」は、学校と保護者に責任を伴うことの自覚を促す意味からも重要と考えている。また、学校を選ぶに当たっては、保護者と子どもの十分な話し合いも不可欠になるはずである。「学校選択制」の付加価値と思う。
穂波町では5年目を迎えた「学校選択制」であるが、町民にもかなり周知され、保護者からの質問や苦情もほとんどなく、また学校活性化や特色化、開かれた学校づくりに向けての学校管理職、教職員の意識が変化してきていると感じている。本町での「学校選択制」は定着したと考えている。 |