- 実践授業例
- 情報Ⅰで生成AIの上手な活用を探究的に考える
生成AIの回答の真偽や利用上の留意点、活用の可能性を考える
| カテゴリー | 生成AIを活用する |
|---|---|
| 校種・学年 | 高等学校 |
| 活動概要 |
【概要】 生成AIが社会にもたらす影響について学習したのち、生成AIとよりよく付き合うために課題となることについて考える。(単元:情報Ⅰ「情報社会の問題解決」) 【学習活動】 〇第1時:「情報収集・情報整理の技法を用いた、生成AI活用の効果的な点と問題点の整理」 ①教師による生成AIの説明 ②ブレーンストーミングとテキストマイニングを用いて生成AIの効果的な点と問題点を整理 ③教師の生成AIの実演による問題意識の検証 ④生成AIを上手に活用するための目標設定 〇第2時:「生成AIを上手に活用するための課題設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現」 ①生成AIを上手に活用するための留意点(※)をテーマとして選択 ②テーマに対する解決案をネット等を使って調査、まとめる ③教師の生成AIの実演による生徒が考えた解決案の検証 【気づき・学び】
|
| 経緯・効果 等 |
【経緯】 生成AIの話題は世界的に注目を集めており、日夜進歩している。一方で、その進歩に伴い問題も生じており、対応が急がれている。このような中、学校現場での適切な対応を行ったうえで、生徒の生成AIに対する意識を向上させるとともに、将来的にこうした高度なAIと共存していく姿勢を養うことは重要である。 【効果】 生徒の多くは実際に生成AIを見たことや使ったことはないという状態であったため、教師が実際に使っている場面を見ることで、生徒の認識を改めた。その結果、生成AIに対して漠然とした不安を抱く生徒が減少した。 |
| 準備するもの |
生成AIの教師用アカウント 生徒の思考を支援するためのワークシート 生徒の調査活動の結果をまとめるワークシート |
ブレーンストーミングやKJ法で生成AIの問題意識を見つける。

既習事項の「問題解決のための手法」を用いて活動する。生成AIについて漠然と知っている人の問題意識を洗い出す。
興味をもとにグループを作り、調査活動を行う。

調査した情報をまとめるためにワークシートを利用したり、思考ツールを活用する。
調査したことをまとめ、利用法や留意点を提案・検証する。
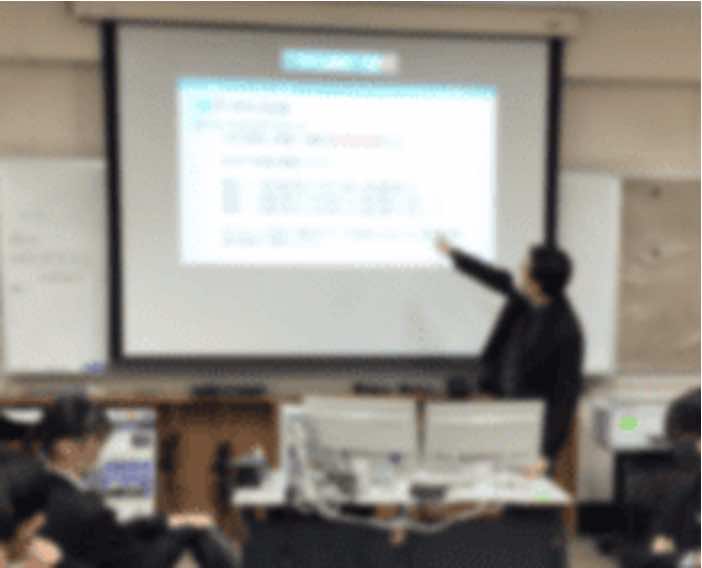
調査活動の結果をワークシートにまとめ、クラスに提案して共有する。教師が生成AIを用いて、調査結果を検証する。

有識者からのコメント
本事例は、問題解決の過程を踏まえたうえで、生徒が生成AIに対して漠然と抱いている情報を洗い出し、その情報を分析し、生成AIの便利な点と不安な点を整理しています。そして、グループごとに生成AIの身近な問題を解決するための目標を設定し、そのためには何が必要かを調査して、解決策を提案しています。問題を発見・解決する一連の活動を通して、生成AIのより良い活用について主体的に考える内容となっていることがポイントだと思います。また、解決策の中で、情報の真偽を確かめる方法についても学ぶ機会となっています。 愛知教育大学 教授
梅田 恭子
トップページに戻る